アフリカでのビジネス事例愛媛からアフリカへ、不透明な地方経済を切り拓く好奇心と実行力
2025年11月6日
2025年8月に横浜市で開催された第9回アフリカ開発会議(TICAD9)で、ジェトロはテーマ別イベント「TICAD Business EXPO & Conference(TBEC)」を主催した。出展者194社・団体を本社所在地別にみると、東京都が100社以上、大阪府と神奈川県、兵庫県がそれぞれ10社以上(注)と、都市圏からの出展者が多くを占めたが、高い技術力を有する地方の中小企業も、アフリカ市場の開拓に取り組んでいる。本稿では、愛媛県を例に対アフリカ輸出の状況を解説し、TBECに出展した愛媛県企業2社の取り組みを基に、地方の中小企業がアフリカ市場を開拓するヒントについて考察する。
愛媛のアフリカ輸出はリベリア向けが多い
愛媛県全体の輸出額は、2000年ごろから2022年の間で、約3,000億円から倍以上に増加している。主な輸出先はアジア、次いで中南米、アフリカ、北米の順で多い。アフリカへの輸出額は年によって大きく変動しているが、輸出全体に占める割合は2016年から2022年の間は全体のおおむね5%以上で推移し、2022年は約9%だった(図参照)。
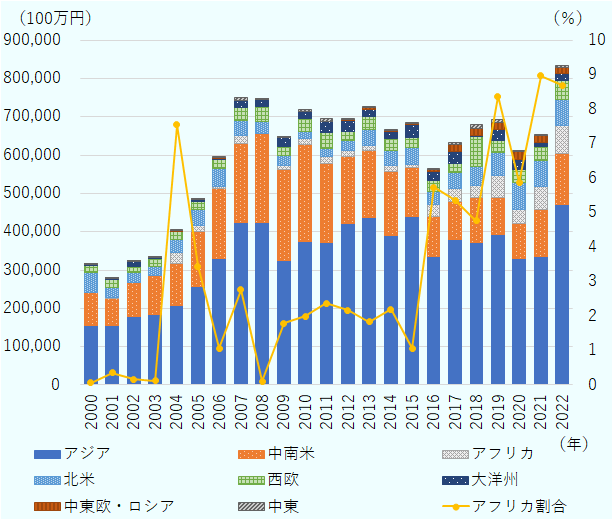
出所:「愛媛県統計年鑑」からジェトロ作成
主要港(宇和島、松山、今治、新居浜、三島川之江)別に、2021年から2024年の輸出額をみると、化学製品や鉄鋼製品の製造が盛んな地域にある新居浜港が最も多く、造船業で有名な今治港が2番目に多い。日本全体からのアフリカ向け輸出は、比較的経済発展が進んで自動車分野の集積が進む南アフリカ共和国と、税制優遇のあるリベリアへの輸出が多いが、愛媛のアフリカ向け輸出は特にリベリアに集中しているのが特徴だ。リベリアは税制などの優遇を受けることができる便宜船籍国であることから、リベリアに置籍するケースが多く、造船業が盛んな愛媛県の貿易統計上では、リベリア向けが多くなるとみられる(表参照)。
| 港名 | 輸出先 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島 | 全体 | 7,658 | 8,456 | 5,324 | 6,703 |
| アフリカ | 2,375 | — | — | — | |
| リベリア | 2,375 | — | — | — | |
| 松山 | 全体 | 173,934 | 195,191 | 187,146 | 137,827 |
| アフリカ | 55 | 0 | 13 | 609 | |
| リベリア | — | — | — | — | |
| 今治 | 全体 | 211,056 | 285,141 | 283,663 | 286,638 |
| アフリカ | 16,283 | 10,630 | 18,960 | 13,880 | |
| リベリア | 16,283 | 10,630 | 18,960 | 13,880 | |
| 新居浜 | 全体 | 226,531 | 304,938 | 259,114 | 304,230 |
| アフリカ | 40,022 | 61,845 | 66,858 | 14,817 | |
| リベリア | 37,156 | 58,018 | 64,721 | 9,802 | |
| 三島川之江 | 全体 | 35,624 | 40,455 | 37,311 | 44,216 |
| アフリカ | 28 | 3 | — | — | |
| リベリア | — | — | — | — |
注1:松山は松山空港を含む。
注2:2021~2023年は確報値、2024年は確々値。
出所:神戸税関からジェトロ作成
好奇心と現場主義で、先行き見えない未来を勝ち抜く
愛媛県松山市に本社を置く愛亀(あいき)は、建設業を中心にリサイクル事業や農業など、グループ12社で多様なビジネスを展開しており、「エクセル・パッチ」という道路の穴(ポットホール)を簡単に埋めることのできる道路補修材が主な商材だ。ジェトロは2023年に同社を取材している(2023年11月14日付地域・分析レポート参照)。2025年2月にナイジェリアに製造工場が完成し、現在は同国をストック拠点として、ガーナを含む西アフリカ諸国への展開を考えているという。同社技術試験事業部(海外企画チーム)の安部拓朗氏に話を聞いた(取材日:2025年8月20日)。
- 質問:
- ナイジェリアに製造拠点を持つなど、アフリカへ積極的にビジネス展開しているが、アフリカビジネスの難しさは何か。また、どのように課題を乗り越えてきたのか。
- 答え:
- 日本から海外事業に関わっているのは、社長を含めて4人だ。アフリカで実現可能性調査(FS)をしようとすると、往復航空券代だけでもエコノミーで40万円、ビジネスクラスで渡航するとなると、100万円ほどかかることもある。中小企業は、さまざまな支援サービスや補助金を活用しなければ、アフリカを含めた海外ビジネスに目を向けられない。そこで、各省庁の補助金を活用している。弊社はジェトロのラゴス国際見本市などの展示会出展支援や、各国のビジネス情報、国際協力機構(JICA)のカンボジアでの技術協力プロジェクトやウクライナでのビジネス支援などを活用している。
- 2~3カ月に1度の頻度で渡航することもあり、実際に現場を目で見ることがいかに重要かを日々痛感している。工場の完成に当たっても、ナイジェリア人の「できる」基準と日本人の「できる」基準は異なるので、作業マニュアルの作成など、互いの目線をそろえつつ、パートナーの協力も得ながら進めてきた。
- 質問:
- 今回のTICAD9への出展目的は。
- 答え:
- 官公庁向けビジネスがメインなので、いかに現地政府に伝えるか、伝わるかが重要だ。体験に勝る感動はないので、実際に穴を「エクセル・パッチ」で埋め、踏み固める体験してもらいたいと思った。


- 質問:
- アフリカを目指す中小企業が持つべきマインドセットや、いま中小企業がアフリカを目指す意味とは。
- 答え:
- 社長の言葉を借りると、「好奇心こそが、中小企業が先行きの見えない未来を勝ち抜く術」。事業がうまく行ったときに面白そうかを考えるのが経営層の仕事で、それを実現可能なかたちに落とし込んでいくのが部下の仕事だと思っている。英語が話せないことなどを心配するよりも、ためらって行動しないことの方がマイナスだと思う。失敗を恐れないことが何よりも大事だ。
- 日本や愛媛の経済が縮小していくのは間違いなく、大企業も中小企業も限られたパイの奪い合いになり、中小企業はますます入っていける隙間がなくなってしまう。国内で市場を奪い合っても仕方がないので、国外のニッチな市場へ潜り込んでいく。社長自らが現地に足を運び、わくわくするような可能性を感じられれば、その土地で価値あるものを適正な価格で提供して勝負していく。衰退する未来が見える中で、いかに地方にいる企業がそうならないための未来をつくっていけるのかが試されていると思う。
人との出会いから生まれた南部アフリカでのものづくり
次に、愛媛県伊予市に本社を置くオンリーワン愛媛代表の仲井利明氏に話を聞いた。同社は食品加工機械の海外向け輸出入を行っている。従業員数3人とマンパワーが限られる中で、仲井氏自らが海外事業を担う(取材日:2025年8月20日)。
- 質問:
- 会社概要とアフリカでのビジネスを考えたきっかけは。
- 答え:
- 食品加工機械をマラウイやその周辺国を含む南部アフリカや、欧州、米国に輸出入している実績があり、販売拠点が中国、韓国、タイ、バングラデシュ、インドネシア、マラウイの計6拠点ある。2010年代にマラウイから愛媛大学に留学してきた学生が「母国で仕事をしたいが、そもそも事業がない」と話すのを聞いて、愛媛県内の企業からも出資してもらい、マラウイで事業を開始した。マラウイでは、ピーナッツなど多くの農作物が生産されているが、加工技術や機械が限られている。そこで、マラウイの工業大学と覚書(MOU)を結び、食品加工機械の現地製造やマラウイ人技術者の育成にも寄与してきた。
- 質問:
- 限られたリソースの中でどのように事業展開する国を選び、展開してきたのか。
- 答え:
- 中国や韓国をはじめとする海外展示会で出会ったバイヤーから開拓していった。TICADに出展したきっかけも、2019年に横浜で開催されたTICAD7が、出展していたほかの食品工業関連の展示会の日程と重なり、マダガスカルなどアフリカのバイヤーがTICAD会場から見に来て、関心を寄せてくれたことだった。6つの拠点にスタッフを送り、現地で起業してもらい、メンテナンスと営業を任せている。成功報酬を払うことで管理コストもかからず、コストとマンパワーを抑えながら事業展開ができている。
- 質問:
- アフリカを目指す中小企業にメッセージを。
- 答え:
- 何事にも興味を持つこと、そして、日本のものづくりを大切にすることだ。現在のアフリカは日本の戦後と重なるものがある。日本も援助を受けながら、ものづくりを続けてきた。アフリカの企業に日本が成長してきた過程を伝えるのが役目だと思っている。
-

オンリーワン愛媛の仲井氏(ジェトロ撮影)
「好奇心」と「実行力」でアフリカ市場開拓
ジェトロが愛媛県内の貿易・投資などの実態を調査した愛媛県国際取引企業リスト2025のエリア別輸出取引状況によると、アジア46.0%、北米21.8%、欧州13.5%と続き、アフリカは最も少なく、1.2%だった。今回インタビューを行った2社は、愛媛県内でアフリカ市場に取り組む数少ない企業だ。2社に共通して印象的だった点は、「ヒトとカネ」の不足と、そういった状況でも現場に足を運ぶ「好奇心」と「実行力」だ。
「ヒトとカネ」の不足は、多くの中小企業に共通する課題だ。高度外国人材の受け入れや補助金事業の活用などで対応する企業も多い。世界の数ある競争市場の中で、自社が勝ち残っていけるニッチな市場をアフリカに見いだす経営者の「好奇心」と、それを着実にビジネスに落とし込んでいくチームの柔軟かつ粘り強い「実行力」こそが、日本の中小企業330万社の中に埋もれない強い企業を作るのだろう。
一方で、アフリカ市場は、自社の資金面や人材面といった経営基盤の安定のみならず、財政、汚職、治安などさまざまな課題とリスクへの対応力が求められるハードルの高い市場だ(本特集「アフリカにおけるビジネス上の課題を再考する」参照)。こうした課題やリスクを踏まえながら、人口増加と経済成長が続く見込みのあるアフリカ市場にポテンシャルを見いだし、実行していく中小企業が今後さらに増えていくことを期待したい。
- 注:
- 当該所在地を含め、本社機能を2拠点持っている企業数も含む。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ愛媛
数実 奈々(かずみ なな) - 2021年、ジェトロ入構。ビジネス展開・人材支援部新興国ビジネス開発課、海外展開支援部フロンティア開拓課、ジェトロ・アクラ事務所を経て現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部中東アフリカ課
坂根 咲花(さかね さきか) - 2024年、ジェトロ入構。中東アフリカ課で主にアフリカ関係の調査を担当。




 閉じる
閉じる






