多国間主義に瓦解の兆し―試されるグローバルビジネスの耐性世界で競争が激化
EV取り巻く環境変化、政策の見直し進む(前編)
2025年10月21日
2021年から世界での販売台数を大きく伸ばし始めた電気自動車(EV)だが、2024年から2025年初めにかけて、EVの貿易や投資を取り巻く状況や政策は大きく転換した。本稿では、2024年以降の世界のEV販売と貿易の現状を報告し、同時期における主要国のEV政策の変更を取り上げる。
世界のEV販売は増加続く、特に中国で大きな伸び
国際エネルギー機関(IEA)の「世界EV見通し」2025年版![]() によると、2024年の世界のEV(注1)新車販売台数(乗用車のみ)は前年比25%超増え、1,750万台となった(図1参照)。伸び率は前年(35%増)を下回ったが、全新車販売台数に占めるEV比率は22%と、前年(18%)から拡大した。2024年のEV販売台数を主要国・地域別に見ると、中国が前年比約40%増の1,130 万台と最も多く、欧州が前年比ほぼ横ばいの318万台、米国が約10%増の152万台だった(図2参照)。
によると、2024年の世界のEV(注1)新車販売台数(乗用車のみ)は前年比25%超増え、1,750万台となった(図1参照)。伸び率は前年(35%増)を下回ったが、全新車販売台数に占めるEV比率は22%と、前年(18%)から拡大した。2024年のEV販売台数を主要国・地域別に見ると、中国が前年比約40%増の1,130 万台と最も多く、欧州が前年比ほぼ横ばいの318万台、米国が約10%増の152万台だった(図2参照)。
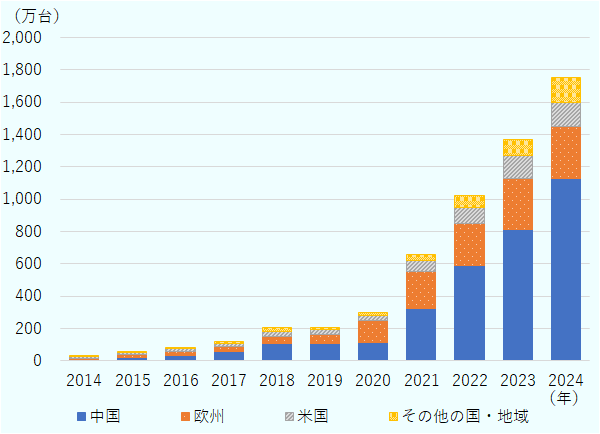
出所:IEA 世界 EV見通し(2025年5月)
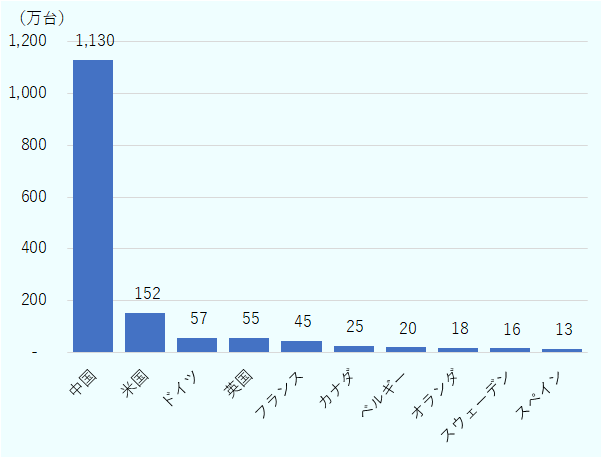
出所:IEA 世界 EV見通し(2025年5月)
中国が引き続き世界のEV市場の牽引役となっている。IEAは、欧州でのEV販売の伸びの停滞は、購入補助金の段階的な廃止と、EUの自動車の二酸化炭素(CO2)排出目標(後述、注2)が2024年まで据え置かれていたことが要因と分析する。 中国は、EVの巨大市場としてのみならず、EV製造でも世界をリードしている。同レポートによると、世界のEV製造の70%を中国が占め、2024年には約125万台を他国に輸出した。それに対し、米国、カナダ、EUなどが中国製EVの過剰生産を指摘し、中国製EVに対する追加関税を課した。
このような状況の中でも、2025年もEV販売台数は増加し、世界で2,000万台を超えると予測する。EV販売台数は拡大の一途をたどり、同見通しによると、2030年には世界のEV販売台数はさらに増え、4,000万台との予測となっている。
世界に進出する中国企業のEV、各国で競争が激化
中国のEVについては、前述のとおり、欧米諸国を中心に追加関税が賦課されており、障壁を避けるようにして東南アジアや中南米といった新興国向けの輸出が増加している。また、中国のEVメーカーが中国以外の輸出拠点を獲得するため、東南アジアに生産工場を構える動きも活発化している。タイでは2024年に複数社が現地生産工場を稼働させた。しかし、タイをはじめとするASEAN各国も、現地の国内需要を大幅に上回る生産能力を有し、中国国内と同様の厳しい競争環境が再現されるかたちとなっている。既に現地に進出している日系企業は、既存の自動車市場シェアを徐々に侵食され、値下げ競争にも巻き込まれて、事業収益が悪化するなど、中国企業との競争激化に直面している。
前述のIEAによる世界EV見通しは、2024年以降の注目すべき点として、ブラジル、タイ、インドネシア、マレーシアなどの国で中国の完成車EVメーカーが現地生産の開始を発表したことを指摘する。これらの国でEVに対する輸入関税の減免措置が数年のうちに終了することや、EV購入補助金の適用条件として国内での一定数の製造を義務付けていることなどが中国企業の主な進出要因と考えられる(表参照)。
| 国名 | EV減税政策など | 進出している中国EVメーカー |
|---|---|---|
| ブラジル |
EV輸入関税減免措置 (2026年半ばまでに段階的廃止予定) |
進出:長城汽車(GWM)、比亜迪(BYD) 計画:零跑汽車(リープモーター)、ジーカー、広州汽車集団(GAC) |
| タイ |
EV3.5(EV補助金) (補助金を受けた車数に応じた2027年末までの国内生産の条件あり) |
進出:上海汽車(SAIC)、長城汽車(GWM)、比亜迪(BYD)、広汽アイオン(AION)、長安汽車(Changan)、奇瑞汽車(チェリー)など |
| インドネシア |
BEVの付加価値税の減税(国産化率40%以上の条件あり) 輸入税の免除(2027年末までに国内生産開始の条件あり) |
進出:上汽通用五菱汽車(SGMW)、奇瑞汽車(チェリー)など 計画:比亜迪(BYD)、広汽アイオン(AION) |
| マレーシア | 輸入関税免除 (2025年12月末まで) | 進出:吉利汽車(Geely)など |
出所:ジェトロ「中国EV・車載電池企業のグローバル戦略」『地域・分析レポート』特集
ブラジルでは、2024年のEV販売台数は2倍以上に増加し、12万5,000台となった。ブラジルの新車EVの85%以上を中国からの輸入車が占める。EV完成車への関税減免措置が徐々に縮小され、2026年半ばに撤廃予定となる中、それまでに比亜迪(BYD)と長城汽車(GWM)がブラジルで生産を開始する予定とされる(2024年12月13日付地域・分析レポート参照)。
また、タイやインドネシアでは、補助金や免税に絡んで、国内でバッテリー式電気自動車(BEV)製造を義務付ける条件があり、これによって両国での製造が拡大している。タイは、2024年の新車EVの販売の85%を中国からの輸入車が占めるが、タイでの生産も拡大している。EV3.5というBEV補助金支給の条件として、補助金を受けて輸入したBEV完成車の台数に応じて、タイ国内で一定数のBEV生産が義務付けられる。具体的には、2026年までに国内でBEV生産を開始する場合は、当該補助金を受けて輸入したBEV完成車の台数の2倍以上、2027年に生産を始める場合は3倍以上の国内生産を義務付けられる。こうした政策により、2024年12月時点で上海汽車(SAIC)、長城汽車、BYD、広州汽車(AION)、長安汽車(Changan)、奇瑞汽車(チェリー)などがタイに投資し、製造を始めている。しかし、2024年に入り、景況感や消費者マインドの悪化などもあり、タイの自動車市場は低迷した。中国EV企業が現地生産を本格化する中、タイ市場でも中国市場と同様に供給過剰が起きており、在庫過多による値下げ競争が行われている(2024年12月16日付地域・分析レポート参照)。こういった現状もあり、多くの中国企業がタイを市場としてではなく、生産・輸出拠点と位置付け、ASEAN、オーストラリア、中東などへの輸出を目指している。
インドネシアでは、BEVの付加価値税の減税制度があり、これを受けるためには国産化率40%以上を満たす必要がある。これが、中国EV企業が現地生産を進める背景の1つとなっている。2022年から中国企業の上汽通用五菱汽車(SGMW)と韓国企業の現代自動車がEVの現地生産を行ってきたが、2024年からは特に中国系自動車メーカーによる生産が目立つようになった。特に2024年にチェリーはインドネシアで5,762台生産し、上汽通用五菱汽車(1万4,034台)に次ぐ生産台数で、現地で以前からEVを生産してきた韓国の現代自動車の生産台数(3,865台)を上回った(注3)。付加価値税の減税制度だけでなく、インドネシアでは現地で自動車を製造することを約束することで輸入税を免税する制度を導入した。前述のIEAのEV見通しによると、BYDやAIONといった中国メーカーや欧州のステランティスなどがこの制度を利用した。その結果、インドネシアでの中国製EV輸入は2024年末までに前年の18倍の3万4,000台に増加した。これらのEV完成車メーカーは、2027年末までにインドネシアで生産を開始しなくてはならない。また、中国企業はニッケルなどの採掘・精錬から、車載電池の開発、BEVの製造・販売まで、サプライチェーン全体でインドネシアに進出する動きも見せている。
マレーシアでは、2025年末までEVの関税と物品税を免除している。中国の自動車メーカー吉利汽車(Geely)と地場メーカーのプロトンが2024年12月に販売したBEV「e-MAS7」は中国で生産しているが、2025年末までにマレーシアで生産開始する予定だ。
このように、各国のEV関連税減免の撤廃と現地生産誘致により、中国企業の海外進出が拡大し、相次いで現地生産を開始している。既に進出している日本や韓国などの自動車メーカーの内燃機関車、ハイブリッド車(HEV)やBEVとの競合だけでなく、東南アジアなどで中国EVメーカー同士の競争も激化している。実際に、2025年6月にはタイやインドネシアに進出していた哪咤汽車(NETA)が中国で破産申請した。
後編では、EV導入の先駆者だった欧州でのEV販売の伸び悩みと、それに関連する政策の見直し、米国のトランプ政権下でのEV推進政策の取りやめの状況を取り上げる。
- 注1:
- プラグインハイブリッド車(PHEV)とバッテリー式電気自動車(BEV)の合計。
- 注2:
- 1キロメートル当たり95.0グラム(2020-2024)欧州委員会。
- 注3:
- インドネシア自動車製造業者協会(ガイキンド)自動車販売台数。
EV取り巻く環境変化、政策の見直し進む
シリーズの次の記事も読む

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部国際経済課
板谷 幸歩(いただに ゆきほ) - 民間企業などを経て、2023年4月ジェトロ入構。






 閉じる
閉じる





