日本の対中輸入、2年連続で減少
2024年の日中貿易(後編)
2025年7月2日
連載後編の本編では、電気機器、機械類など日本の対中輸入の上位品目の分析と、日本の財務省貿易統計に基づく貿易額、輸出額、輸入額の中国の構成比の推移について報告する。
電気機器と衣類で3年連続の減少
2024年の日本の中国からの輸入は前年比3.9%減の1,671億1,943万ドルと、過去最高を記録した2022年から減少に転じた2023年以来、2年連続で減少した。
品目別にみると、HSコード2桁で輸入額上位5品目では、第1位の電気機器(第85類)と第3位の衣類および同付属品(第61類)でともに3年連続で減少した。電気機器では、主要品目のスマートフォン(851713号)が前年から微増したものの、その他の主要品目の減少が響いた。前年に最大の押し上げ要因となった蓄電池(8507項)も、輸入単価の下落を受け減少に転じた。衣類および同付属品は、国内市場の低迷や生産国の多元化の進展もあって、対中輸入の減少が続いている(注1)。
他方、第2位の機械類(第84類)、第5位のプラスチックおよび同製品(第39類)は前年から微増したほか、第4位の車両(第87類)は4年連続で増加した。機械類では、自動データ処理機械(8471項)が4年ぶりに増加に転じ、HSコード4桁ベースで最大の押し上げ要因となった。車両(第87類)は、最大品目の自動車部品が微増し、3年連続で過去最高額を更新した。
また、主要な対中輸入品目について、日本の輸入額全体に占める中国の構成比の変化をみると、衣類(第61類、第62類)や印刷機など(8443項)で低下が続いているほか、依然として中国が9割前後の構成比を占めるノートパソコン(847130号)や、スマートフォン(851713号)といった品目でも低下傾向がみられる。他方で、蓄電池(8507項)や自動車部品(8708項)などでは、中国の構成比が上昇している。
| HSコード 品目 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| 総額 | 167,119,434 | △ 3.9 | 100.0 | — |
| 第85類 電気機器およびその部分品 | 47,952,146 | △ 5.8 | 28.7 | △ 1.7 |
 8517 電話機およびその他の機器 8517 電話機およびその他の機器
|
19,365,784 | △ 2.5 | 11.6 | △ 0.3 |
 8507 蓄電池 8507 蓄電池
|
2,489,824 | △ 4.6 | 1.5 | △ 0.1 |
 8528 モニター、プロジェクターおよび受像機器 8528 モニター、プロジェクターおよび受像機器
|
2,387,114 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
 8504 トランスフォーマー、スタティックコンバーターおよびインダクター 8504 トランスフォーマー、スタティックコンバーターおよびインダクター
|
2,359,129 | △ 10.1 | 1.4 | △ 0.2 |
 8544 電気絶縁をした線、ケーブルおよび光ファイバーケーブル 8544 電気絶縁をした線、ケーブルおよび光ファイバーケーブル
|
2,108,189 | △ 8.3 | 1.3 | △ 0.1 |
| 第84類 原子炉、ボイラーおよび機械類 | 30,558,393 | 0.3 | 18.3 | 0.1 |
 8471 自動データ処理機械 8471 自動データ処理機械
|
11,955,552 | 4.9 | 7.2 | 0.3 |
 8415 エアコンディショナー 8415 エアコンディショナー
|
1,996,500 | 2.6 | 1.2 | 0.0 |
 8443 印刷機、その他のプリンター、複写機およびファクシ ミリ 8443 印刷機、その他のプリンター、複写機およびファクシ ミリ
|
1,748,400 | △ 3.6 | 1.0 | △ 0.0 |
| 第61類 衣類および衣類附属品(メリヤス編みまたはクロセ編みのものに限る) | 6,286,328 | △ 4.4 | 3.8 | △ 0.2 |
 6110 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベ ストその他これらに類する製品 6110 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベ ストその他これらに類する製品
|
2,375,623 | △ 3.4 | 1.4 | △ 0.0 |
| 第87類 鉄道用および軌道用以外の車両 | 5,979,582 | 4.9 | 3.6 | 0.2 |
 8708 自動車の部分品および付属品 8708 自動車の部分品および付属品
|
3,821,521 | 1.3 | 2.3 | 0.0 |
| 第39類 プラスチックおよびその製品 | 5,362,063 | 2.3 | 3.2 | 0.1 |
 3926 その他のプラスチック製品およびHSコード3901~3914の材料から成る製品 3926 その他のプラスチック製品およびHSコード3901~3914の材料から成る製品
|
2,014,975 | 2.5 | 1.2 | 0.0 |
| 第94類 家具、寝具 | 5,130,548 | △ 1.1 | 3.1 | △ 0.0 |
 940 腰掛けおよびその部分品 940 腰掛けおよびその部分品
|
1,893,500 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 第90類 光学機器精密機器および医療用機器 | 5,013,907 | △ 3.1 | 3.0 | △ 0.1 |
| 第62類 衣類および衣類附属品(メリヤス編みまたはクロセ編みのものを除く) | 4,946,420 | △ 11.4 | 3.0 | △ 0.4 |
| 第95類 玩具、遊戯用具および運動用具 | 4,914,480 | △ 15.4 | 2.9 | △ 0.5 |
 9503 三輪車、その他車輪付き玩具、人形、縮尺模型およびパズル等 9503 三輪車、その他車輪付き玩具、人形、縮尺模型およびパズル等
|
2,200,863 | 1.7 | 1.3 | 0.0 |
 9504 ビデオゲーム用のコンソールおよび機器等 9504 ビデオゲーム用のコンソールおよび機器等
|
1,749,067 | △ 31.2 | 1.0 | △ 0.5 |
| 第73類 鉄鋼製品 | 4,179,089 | △ 2.2 | 2.5 | △ 0.1 |
| 第29類 有機化学品 | 3,942,023 | △ 4.2 | 2.4 | △ 0.1 |
| 第28類 無機化学品および貴金属、希土類金属 | 2,804,366 | △ 32.9 | 1.7 | △ 0.8 |
| 第63類 紡織用繊維のその他の製品 | 2,651,119 | △ 8.4 | 1.6 | △ 0.1 |
| 第16類 肉、魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 | 2,252,673 | 2.5 | 1.3 | 0.0 |
| 第42類 革製品、ハンドバッグ | 2,158,247 | △ 1.9 | 1.3 | △ 0.0 |
 4202 バッグ、財布、ケース等 4202 バッグ、財布、ケース等
|
2,029,429 | △ 1.7 | 1.2 | △ 0.0 |
| 第64類 履物およびゲートル | 2,021,916 | △ 7.3 | 1.2 | △ 0.1 |
| 第76類 アルミニウムおよびその製品 | 1,746,013 | △ 4.8 | 1.0 | △ 0.1 |
注1:輸入額は日本の財務省貿易統計による対中輸入額。貿易データベースGlobal Trade Atlas(ドルベース)を基に作成。
注2:HSコード2桁、4桁分類で構成比1.0%以上の品目を抽出し、金額降順。
注3:太字は二桁分類の金額ベースで上位5位
出所:Global Trade Atlasからジェトロ作成 (データ抽出日:2025年4月1日)
品目別ハイライト
-
電気機器(第85類)
金額:479億5,215万ドル、構成比:28.7%
伸び率:マイナス5.8%、寄与度:マイナス1.7 - 同品目全体の40.4%を占める電話機およびその他データ送受信機器(8517項)が、前年比2.5%減の193億6,578万ドルとなり、3年連続で減少した。うち、HSコードの改正により2022年から新設された品目であるスマートフォン(851713号)は同品目(8517項)の81.9%を占め、前年から1.7%増と微増した。IT専門調査会社のIDC Japanの統計によると、2024年の日本国内のスマートフォンの出荷台数は前年比0.6%増の3,021万台だった。なお、日本のスマートフォンの輸入額全体に占める中国の構成比は87.7%を占めた。ただし、2位のベトナム(構成比8.7%)と3位のインド(構成比2.3%)からの輸入額がそれぞれ16.4%増、約6.3倍となったことを受け、中国の構成比は前年から1.8ポイント低下した。
- スマートフォンおよび後述するノートパソコン(847130号)といった品目では、リスク分散の観点から米国のブランド企業が生産地分散の意向を示しており、台湾系EMS(電子機器製造受託)などがインドやベトナムなどで生産能力を拡大する動きがみられている(2025年5月14日付地域・分析レポート参照)。このほか、8517項を構成する主要品目のうち、音声、画像などデータ送受信・再生機械(851762号)は13.5%減、5G(第5世代移動通信システム)などの基地局の整備に使用される基地局通信装置(851761号)は65.8%減となり、それぞれ3年連続および4年連続で減少した。
- 蓄電池(8507項)も、前年比4.6%減の24億8,982万ドルと、過去最高額を記録した前年から減少に転じた。同品目全体の81.7%を占めるリチウム・イオン蓄電池(850760号)が4.0%減と、2014年以来10年ぶりに前年比で減少した。ただし、数量(個数ベース)は12.5%増と増加したことから、輸入単価の減少が輸入額の減少につながったものとみられる。ブルームバーグのリサーチ部門であるブルームバーグNEFによると、2024年のリチウム・イオン電池パックの世界市場における平均価格は2023年から20%下落し、1キロワット時(kWh)当たり115ドルと過去最低を記録した。要因として、主な用途である電気自動車(EV)向けで電池メーカー各社が生産能力を増強させたことや、中国メーカーによる希少金属の使用が少なく生産コストが抑えられるLFP電池の生産増などが指摘される。なお、中国国家統計局によると2024年の中国におけるリチウム・イオン電池の生産量は前年比13.7%増だった。伸び率は前年(3.5%増)から10ポイント以上拡大した。日本のリチウム・イオン電池の国別の輸入額をみると、中国からの輸入額は5年前の2019年比で2.6倍に拡大。構成比も55.0%から76.8%に拡大し、中国に対する輸入依存度が高まっている。
- このほか、トランスフォーマー、スタティックコンバーター(8504項)も10.1%減の23億5,913万ドルと減少したほか、電気絶縁をしたケーブルおよび光ファイバーケーブル(8544項)も8.3%減の21億819万ドルとなった。
- 他方、モニター、プロジェクターおよび受像機器(8528項)は、前年に2桁減(12.3%減)となった反動もあり、前年比1.4%増の23億8,711万ドルと微増した。
-
機械類(第84類)
金額:305億5,839万ドル、構成比:18.3%
伸び率:0.3%増、寄与度:0.1 - 同品目全体の39.1%を占める自動データ処理機械(8471項)が、前年比4.9%増の119億5,555万ドルと、4年ぶりに増加に転じた。日本の対中輸入の全品目(HSコード4桁ベース)の中で、最大の輸入押し上げ要因となった(寄与度0.3)。
- このうち、主要品目であるノートパソコン(847130号)は11.6%増だった。日本のノートパソコンの輸入先として、中国の構成比は94.4%を占める。ただし、2位のベトナムからの輸入額が10.5倍と激増。構成比も前年の0.5%から4.7%に上昇したことを受け、中国の構成比は前年から4.3ポイント低下した。
- エアコンディショナー(8415項)も、2.6%増の19億9,650万ドルと微増ながら3年ぶりに増加に転じた。日本の同品目の輸入額全体に占める中国の構成比は80.1%に上り、2009年(81.1%)に初めて8割を超えて以降、おおむね7~8割の水準で推移している。
- 他方、印刷機など(8443項)は3.6%減の17億4,840万ドルと2年連続で減少した。輸入額は過去最高額を記録した2012年(36億6,642万ドル)から約半減した。また、中国の構成比は過去最高となった2011年(67.2%)から減少傾向が続いており、2024年には52.8%となった。第2位のタイ、第3位のベトナムの構成比はそれぞれ16.7%、9.8%だった。
-
衣類・同付属品/メリヤス編みまたはクロセ編みのもの(第61類)
金額:62億8,633万ドル、構成比:3.8%
伸び率:マイナス4.4%、寄与度:マイナス0.2
衣類・同付属品/メリヤス編みまたはクロセ編み以外のもの(第62類)
金額:49億4,642万ドル、構成比:3.0%
伸び率:マイナス11.4%、寄与度:マイナス0.4
- 第61類(メリヤス編みまたはクロセ編みのもの)、第62類(メリヤス編みまたはクロセ編み以外のもの)は、ともに3年連続の減少となった。両品目の日本の世界からの輸入額もそれぞれ0.9%減、6.0%減と減少した。また、日本の輸入額全体に占める中国の構成比は、第61類が52.8%、第62類が44.9%といずれも3年連続で過去最低を更新。それぞれ第61類が2008年(88.3%)、第62類が2006年(80.8%)にピークを迎えて以降、低下傾向が続いており、ベトナムをはじめ、カンボジア、バングラデシュ、ミャンマーなどの構成比が上昇傾向にある。
-
車両(第87類)
金額:59億7,958万ドル、構成比:3.6
伸び率:4.9%、寄与度:0.2 - 同品目全体の63.9%を占める自動車部品(8708項)は、前年比1.3%増の38億2,152万ドルと4年連続で増加し、3年連続で過去最高額を更新した。同品目(8708項)の輸入額のうち、約4分の1を占める車輪および同部品が2.5%減と減少した一方、ハンドル・同部品、懸架装置・同部品、駆動軸および非駆動軸・同部品が2桁増となったことなどを受けて、全体では微増した。日本の自動車部品(8708項)の輸入額全体では、10年前の2014年比で7.9%増となっており、その中で中国の構成比の上昇傾向が続いている。2024年には46.1%と2014年から8.9ポイント上昇した。他方、2014年時点で輸入先第2位だったドイツの構成比は9.9%から5.2%に、第3位だった韓国は9.4%から4.8%に、タイに次いで第5位だった米国は6.6%から4.4%にシェアが低下し、またそれぞれ順位も4位、5位、6位に下落している。なお、2024年時点の第2位、第3位はそれぞれタイとベトナムだが、構成比は11.1%、6.3%と、2014年比で2.0ポイント、1.2ポイントの上昇にとどまる。
- また、乗用自動車(8703項)は、同品目(8703項)の構成比42.2%を占めるハイブリッド車(870340号)が前年比で3.3倍と急増した。日本メーカーの一部モデルにおいて、日本での生産終了後に、中国工場で生産した完成車を正規モデルとして輸入販売する動きが報じられている。同品目(8703項)で第2位の構成比(39.0%)を占める電気自動車(HS870380)は1.0%減となり、前年までの3年連続2桁増から減少に転じた。
-
プラスチック・同製品(第39類)
金額53億6,206万ドル、構成比3.2%
伸び率2.3%、寄与度0.1 - 多くの品目で金額、数量ともに増加し、数量の伸びが金額の伸びを上回る品目が目立った。プラスチック製品の主要原材料である石油やナフサの価格が下落したことなどが影響したとみられる。
日本の輸出額に占める中国の構成比は前年に続き米国を下回り2位に
財務省の貿易統計によると、2024年の日本の輸出額に占める中国の構成比は17.6%となり、前年から横ばいで推移した。過去最高の構成比を占めた2020年(22.1%)以降、2021年から3年連続で低下が続いていた(表2、図1参照、注2)。
一方で、輸入額に占める構成比は22.5%となり、前年から0.4ポイント上昇した(表2、図2参照)。ただし、過去最高の構成比を占めた2020年(25.8%)や2021年(24.1%)などと比較すると構成比が低下している。その結果、貿易総額に占める構成比は20.1%と、2014年(20.4%)以来の低水準だった2022年(20.2%)、2023年(20.0%)とほぼ横ばいで推移した(表2、図3参照)。
日本の対世界貿易で、中国は引き続き大きな存在感を示している。その国・地域別順位は、貿易総額で2007年以降18年連続、輸入額で2002年以降23年連続、1位だった。輸出額でも2020年から2022年まで3年連続で1位だったが、2023年に引き続き2024年も米国を下回り2位となった。
表2:2024年の日本の貿易相手国上位5カ国・地域とASEAN、EU(財務省統計)
| 国・地域名 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| 総額 | 706,963 | △ 1.4 | 100.0 | — |
| 米国 | 140,542 | △ 2.3 | 19.9 | △ 0.5 |
| 中国 | 124,481 | △ 1.3 | 17.6 | △ 0.2 |
| 韓国 | 46,436 | △ 1.0 | 6.6 | △ 0.1 |
| 台湾 | 45,312 | 5.6 | 6.4 | 0.3 |
| 香港 | 35,946 | 10.6 | 5.1 | 0.5 |
| ASEAN | 101,340 | △ 3.3 | 14.3 | △ 0.5 |
| EU | 65,837 | △ 10.8 | 9.3 | △ 1.1 |
| 国・地域名 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| 総額 | 742,538 | △ 5.5 | 100.0 | — |
| 中国 | 167,119 | △ 3.9 | 22.5 | △ 0.9 |
| 米国 | 83,498 | 1.5 | 11.2 | 0.2 |
| オーストラリア | 52,875 | △ 18.9 | 7.1 | △ 1.6 |
| アラブ首長国連邦 | 36,845 | △ 0.4 | 5.0 | △ 0.0 |
| 韓国 | 31,426 | 1.4 | 4.2 | 0.1 |
| ASEAN | 116,310 | △ 3.6 | 15.7 | △ 0.5 |
| EU | 78,329 | △ 2.7 | 10.5 | △ 0.3 |
| 国・地域名 | 金額 | 伸び率 | 構成比 | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| 総額 | 1,449,501 | △ 3.6 | 100.0 | — |
| 中国 | 291,600 | △ 2.8 | 20.1 | △ 0.6 |
| 米国 | 224,039 | △ 0.9 | 15.5 | △ 0.1 |
| 韓国 | 77,862 | △ 0.1 | 5.4 | △ 0.0 |
| 台湾 | 75,802 | △ 3.5 | 5.2 | △ 0.2 |
| オーストラリア | 68,846 | △ 16.0 | 4.7 | △ 0.9 |
| ASEAN | 217,650 | △ 3.4 | 15.0 | △ 0.5 |
| EU | 144,166 | △ 6.6 | 9.9 | △ 0.7 |
注1:EUは27カ国。
注2:伸び率は前年比。
出所:前編の表1に同じ
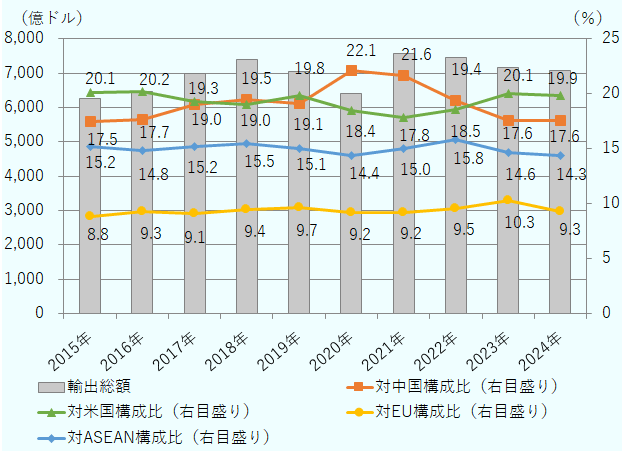
注:EUは27カ国の値。
出所:前編の表1に同じ。
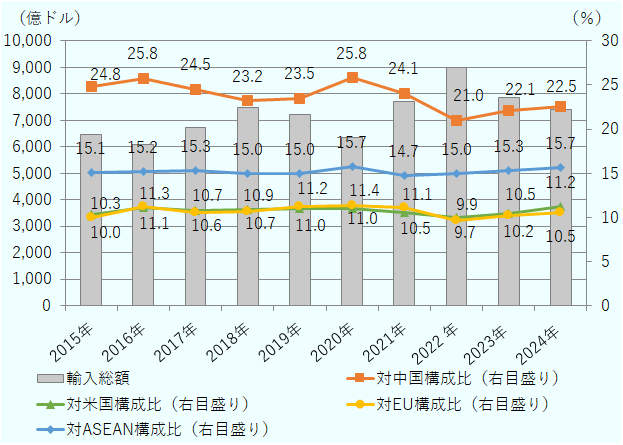
注:EUは27カ国の値。
出所:表1に同じ
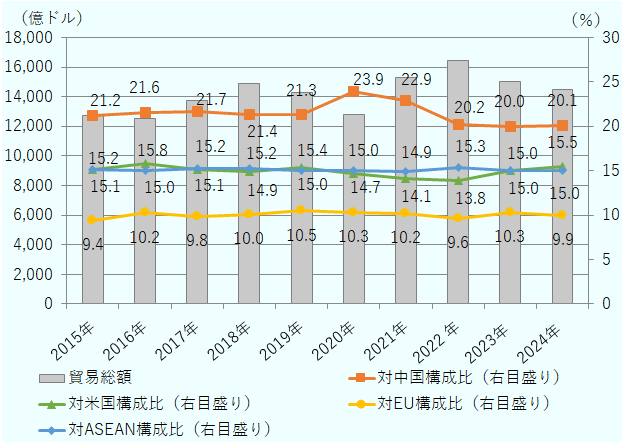
注:EUは27カ国の値。
出所:前編の表1に同じ
- 注1:
- HS分類では、上2桁の分類のことを「類」、上4桁を「項」、上6桁を「号」と呼ぶことがある。
- 注2:
- この分析では、貿易総額、輸出額(日本の対中輸出額)、輸入額は全て財務省貿易統計に基づき貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を用いている。同記述以前で使用している「双方輸入ベース」の分析とは異なるため注意が必要。「双方輸入ベース」については、「2024年の日中貿易(前編)日本の対中輸出、3年連続減少」をご参照。
2024年の日中貿易
シリーズの前の記事も読む

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部中国北アジア課 課長代理
小林 伶(こばやし れい) - 2010年、ジェトロ入構。海外調査部中国北アジア課、企画部企画課事業推進班(北東アジア)、ジェトロ名古屋などを経て2019年6月から現職。




 閉じる
閉じる






