ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応通商環境の揺らぎとASEAN
サプライチェーン潮流を見る視点(中編)
2025年10月6日
混乱する通商秩序の下でも、ASEANは依然としてグローバルサプライチェーンの重要拠点としての可能性を秘めている。本稿は特集総論の中編で、世界経済の不確実性と分断リスクが高まる中、ASEAN各国が採用する戦略、産業政策・外国企業誘致の政策に加え、米国トランプ政権以降の関税政策が在ASEAN日系企業に与える影響を整理する。また、ASEANの競争環境の変化についても論じる。
混乱する世界の通商秩序とASEANの「中心性」
ASEAN地域のサプライチェーンを考察する上で、世界の通商秩序の変化の中でのASEANの位置づけと、各国が目指すポジションを把握することが重要だ。米中競争の激化、ウクライナ紛争、中東情勢などを背景に、世界経済の不確実性や分断リスクは高まっている。国際ビジネスを展開する企業は、地政学リスク、サステナビリティー、デジタル化、人材不足といった課題に対応する必要がある。その中でも地政学リスクは、グローバルサプライチェーンに重大な影響を及ぼす。従来のように「低コスト・短納期・集約化による効率的な生産」を前提とした時代は転換期を迎えつつあり、企業には途絶リスクを踏まえたレジリエンシー(回復力)確保のためのサプライチェーン再構築が求められている。
米中対立の長期化が想定される中、中国に集中していたサプライチェーンがリスクとして再認識され、東南アジアは既存の生産・流通ネットワークを基盤に、主要な移管先候補地としての地位を維持している。地政学的バランスの観点からも、ASEANの各国政府は、米中いずれか一方に偏ることなく、中立を保持しながら外資誘致を進めている。ASEAN各国の産業政策や投資誘致戦略は、混乱する世界経済の中で「サプライチェーン再構築」の受け皿となることを目指し、西側諸国と中国の双方から外国企業を誘致している。ASEANは、中国との経済的結びつきを維持しながら、西側諸国との関係も深める戦略を採用している(2025年7月14日付地域・分析レポート参照)。
通商戦略でも、2国間協定に加え、多国間協定〔地域的な包括的経済連携(RCEP)や、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)〕の拡大を通じて、ASEANは自由貿易協定(FTA)網の結節点としての重要性を高めるとともに、「中心性」を維持している。近年、地政学的緊張が高まる状況下では、先進国や中国を中心に保護主義的な貿易制限措置が拡大し、「ルールに基づく国際貿易秩序」の弱体化が進行している。しかし、ASEANは、これまで域内生産・流通ネットワークの構築で従来大きなメリットを享受してきたため、通商秩序の維持に強いインセンティブを持っている。
供給網の要衝狙う各国の産業政策と投資誘致戦略
ASEANの各国政府による産業政策や投資誘致戦略はどういったものか。ASEANは長年にわたり、外国直接投資(FDI)の誘致と輸出拡大を成長エンジンとして発展してきた。近年、米中貿易戦争などの地政学的変化により、世界のサプライチェーンが再編される中、各国は自国の発展段階に応じた戦略を策定し、産業政策やFDI誘致を通じて、新たな製造拠点となるべく競争を展開している〔ジェトロの調査レポート「ASEAN地域における2025年地政学的展望」(2025年3月)参照![]() (682KB)、2025年7月14日付地域・分析レポート参照〕。
(682KB)、2025年7月14日付地域・分析レポート参照〕。
ベトナムはグローバルサプライチェーン再編の主要な受益国で、2030年までに上中位所得国を目指す中で、ハイテク・高付加価値製造業の拡大を推進している。政府は投資支援基金を設立し、ハイテク産業に重点を置いて、特定基準を満たす企業に助成金や補助金を提供する方針だ。タイは「タイランド4.0」の下、東部経済回廊(EEC)で自動車や航空宇宙、デジタル技術分野への投資を誘致しており、インフラ整備や税制優遇、非課税インセンティブも導入している。マレーシアは半導体、デジタル分野で優位性を持ち、税制優遇や輸入関税免除、国家半導体戦略などの施策により、高付加価値産業の成長を促進している。インドネシアは重要鉱物資源の国内精錬を義務付ける下流化政策などで保護主義的傾向が強いものの、世界第4位の人口と成長する消費市場を背景に、FDIの積極的誘致を続けている。フィリピンはルソン経済回廊などのインフラ整備を進めるとともに、法人税引き下げなど新たな経済政策で投資環境を強化している。2024年 11月、法人税率の引き下げや企業へのさらなる税制優遇措置を認める法案(クリエートモア法)に署名した。
このように、ASEAN各国はそれぞれの強みや政策を生かし、グローバル企業の誘致競争を繰り広げている。共通課題として、デジタル化やグリーン成長、人材高度化という課題が浮上する中、各国は国際競争力の確保に向けて多角的政策を展開している。こうした取り組みを通じて、ASEANはグローバル企業を引き付け、グローバルサプライチェーンの重要拠点として存在感を高めようとしている。
米国相互関税でASEANは「漁夫の利」を封じられるか?
2017年に米国で第1期トランプ政権が発足して以降、特に2018年7月に始まった米中間の関税戦争は、中国からASEANへの生産移管を促す契機となった。それまで中国で生産されていた品目に米国が関税を課したため、中国や台湾の企業などがグローバル向け生産拠点をASEANに移したことで、ASEANから米国向けに輸出が増加した。投資を受けたASEAN諸国にとっては、この動きは「プラス効果」となった。一方、それまで米国市場向けに出荷された中国製品は行き場を失い、地理的に近いASEAN諸国に大量に流入するなど、「マイナス効果」も生じた。 第2期トランプ政権下では、2025年4月に公表した「相互関税」がASEAN諸国にも適用され、これまでの「漁夫の利」は封じられた。具体的には、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、カンボジアでは19%、ベトナムでは20%、ラオス、ミャンマーでは40%という高関税が課された。2025年9月末時点では、米国による中国向け相互関税の「上乗せ税率」(24%)の賦課停止は11月10日まで延長されているが、今後の交渉次第では、ASEAN諸国が競争上の優位性を得る可能性がある。
米国向け輸出企業にとって業績悪化要因に、「迂回輸出」への対応も重要
米国による相互関税措置は、在ASEANの日系企業に対して一定の影響を及ぼしているものの、その範囲は限定的だ。ジェトロのアンケート調査によると、米国向けに輸出するASEAN進出日系企業は5.0%にとどまる(2025年7月10日付地域・分析レポート参照)ため、直接的な影響を受ける企業は比較的少ない。とはいえ、関税対象となる企業にとっては、コスト上昇や、関税率が低い国に所在する企業に取引が移るリスクがあり、業績悪化やビジネス機会の減少につながる可能性がある(図1)。
また、企業にとっては、関税率だけではなく、その適用ルールや税率の不透明性も頭の痛い問題だ。各社は米国やASEAN各国政府から公表される情報を正確に理解・把握するとともに、自社に与える影響をシミュレーションすることに注力している。例えば、米国政府は、中国原産品が関税回避のために十分な付加価値を加えられずにASEANを経由して米国向けに輸出される「迂回輸出」や原産地偽装に対し、強い警戒を示している(図2)。これを受け、ASEAN各国は原産地証明書の発行審査の厳格化や取り締まりの強化を提案している。米国とASEAN各国による交渉の結果次第では、審査の厳格化で進出日本企業が巻き込まれる可能性もある。ASEANでの組み立てに際して中国から部品・素材などを調達する場合、製品が「ASEAN製」と見なされるのか、「中国製」と見なされるのかによって、関税率が異なるため、その基準は企業にとって非常に重要だ。
図1:米国相互関税がASEAN進出日系企業に与える影響・
サプライチェーン再編の検討
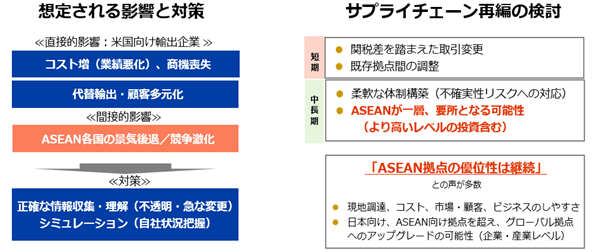
出所:企業ヒアリングなどに基づきジェトロ作成
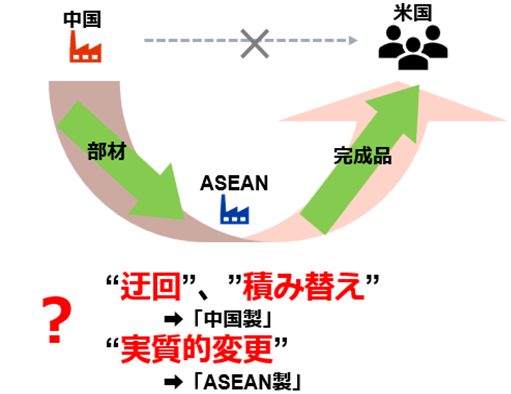
出所:ジェトロ作成
ASEAN生産拠点の優位性は継続、アップグレードも視野に入れる企業も
米国の相互関税による間接的な影響として、短期的にはASEAN全体の景気悪化や競争の激化といった影響が懸念される。一方、ASEANの各国間の税率差については、前述のとおり、主要国では19%、ベトナムでは20%などと小さいため、域内での生産移管など大幅なサプライチェーン変更を検討するような声で目立ったものはない。また、中長期的には米国を中心に政策の不確実性が高く、「半年後にどのような状況になるか予測が困難」といった声もあり、企業には柔軟にサプライチェーンを再構築していなかければならないという問題意識がある。
全体として、多くの日系企業にとってASEANの事業拠点としての重要性と優位性は継続するとしている。ASEAN以外の地域への生産移管や抜本的な再編を計画している企業の声は多くない。その理由として、これまでの進出経緯やASEAN地域でのビジネスのしやすさが挙げられる。一部の企業は、今後ASEAN拠点をグローバル拠点としてアップグレードする可能性を検討している。米国の相互関税の直接的な影響は限定的だが、サプライチェーン戦略やリスク管理を再検討する契機となっている。
中国・米国の積極攻勢と相対化される日本の優位性
前述のように、米国相互関税の間接的な影響として、ASEANでは中国製品の流入が急増し、日本企業の競争環境は大きく変化している。ジェトロのアンケート調査では、ASEAN進出日系企業のうち26.5%が「現地市場での競争相手」として中国企業を挙げ、特にタイ、マレーシア、シンガポールで高い水準だった(図3)。中国企業はコスト競争力や意思決定の迅速さで脅威とされ、米国関税の影響で製造業分野でのASEAN進出も活発化している。一方、米国企業もデータセンター、再生可能エネルギー、半導体など先端分野で投資を拡大しており、工業用地や人材の獲得競争が一層激化している。こうした状況下、日本企業は多様な競争相手に対し、コスト、スピード、技術力で戦うことが求められている。
図3:進出日系企業にとっての現地競争相手
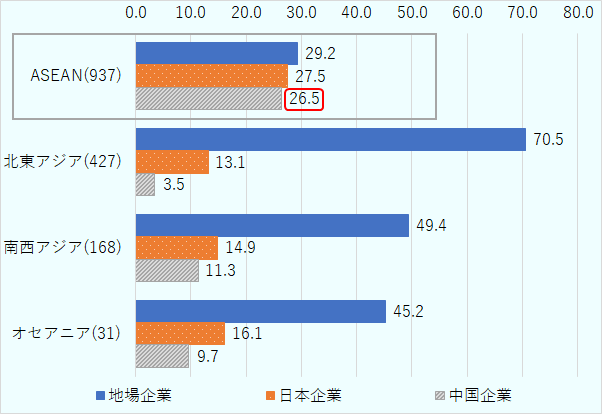
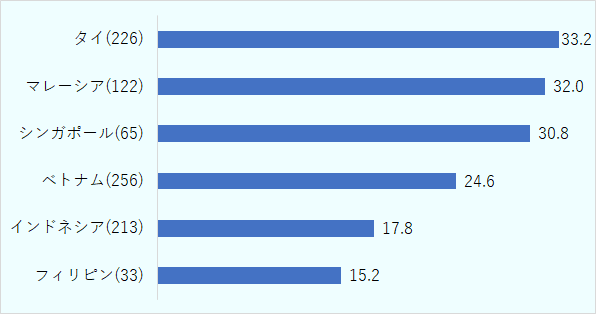
注:在中国日系企業による「中国企業」の回答は、「地場企業」としてカウントしている。
出所:ジェトロ「2024年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」
サプライチェーン潮流を見る視点

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課長
藤江 秀樹(ふじえ ひでき) - 2003年、ジェトロ入構。ジェトロ・ジャカルタ事務所(10~15年)、海外調査部アジア大洋州課(15~18年)、シンガポール事務所(18~22年)などを経て、2024年9月から現職。編著に「インドネシア経済の基礎知識」(ジェトロ、2014年)、「分業するアジア」(ジェトロ、2016年)がある。




 閉じる
閉じる






