ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応縫製輸出で台頭、裾野拡充とFTAが繊維産業の追い風に
ベトナム(4)
2025年10月28日
ベトナムは、中国、バングラデシュに次ぐ世界第3位の繊維製品輸出国で、多数の縫製工場と膨大な労働者を抱えている。そのため、縫製品の輸出動向は労働市場や経済に大きな影響を与える。
縫製原料の多くは、依然として輸入に依存しているが、近年では素材メーカーの進出などで国内サプライチェーンの強化が進みつつある。
本稿では、輸出入の推移や投資、企業動向から、ベトナムの繊維産業について考察する(注1)。
米国向け衣類輸出が牽引
ベトナムの繊維・同製品(HS50~63)の輸出額は、ほぼ毎年増加している。2000年の約20億ドルから2022年には約450億ドルへと大幅に拡大した。2023年は、米国や欧州など主要市場の需要低迷で一時減少したが、2024年には再び回復している。
その大半を占めるのが、最終製品の衣類(HS61~62)だ。国・地域別にみると、2001年までは日本向けが最大だったが、2002年以降は米国が首位になっている(図1参照)。その背景には、2001年12月に発効した米国・ベトナム通商協定がある。当該協定を受け、米国は輸入関税を最恵国待遇の水準に引き下げた。その結果、米国のスポーツ・アパレルブランドなどからの受注が増加し、ベトナムの米国向け衣類輸出額は2000年から2022年にかけて約351倍に拡大した。
(上位5カ国・地域)
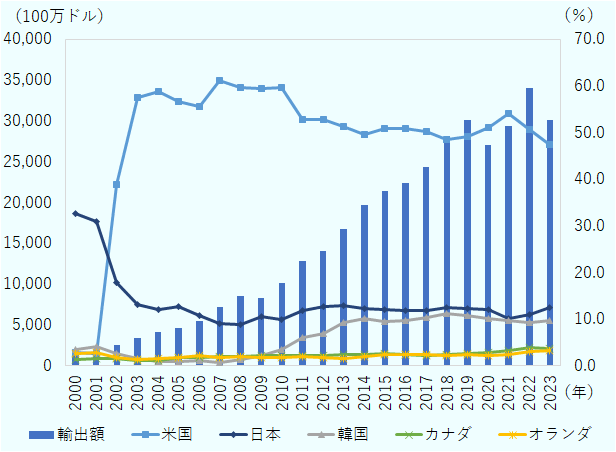
注:2023年時点の上位5カ国・地域を表示。
出所:Global Trade Atlas(GTA)に基づきジェトロ作成
繊維原料の輸入が増加も、綿糸と綿織物は国内生産拡大
繊維・同製品(HS50~63)の輸入額も、概ね右肩上がりで推移している。大部分は繊維原料(HS50~60)で、衣類輸出の拡大に伴い、素材や部材の輸入も増加している。
輸入元は、2000年時点では台湾、韓国、日本が中心だったが、中国が大幅に伸び、2006年以降は首位を維持している(図2参照)。
(上位6カ国・地域)
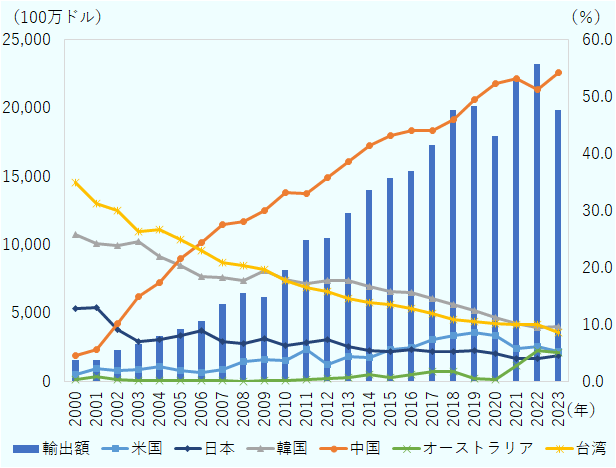
注:2023年時点の上位6カ国・地域を表示。
出所:GTAに基づきジェトロ作成
輸入される繊維原料は、編物や織物といった生地関連品が中心を占めている。
一方、綿・綿織物(HS52)では、傾向が異なる。綿糸や綿織物の輸入は小幅増にとどまるのに対し、実綿・繰綿(HS5201)が2000年代後半から急増している。原材料としての綿花は安定した国内調達が難しく、輸入依存が続く。しかし、綿糸は輸出が飛躍的に増え、現在ではベトナムの繊維原料輸出を牽引している。これは、綿花から綿糸へ、付加価値を高めて国外供給する産業構造に転換したことを表す。また、綿糸の国内生産は、綿織物をはじめとする裾野産業全体の成長を促している。
ベトナムは衣類の縫製だけでなく、繊維原料の生産でも競争力を高めている。日系の繊維関連企業へのヒアリングでは、国内で調達可能な糸や副資材、さらには一部の生地などが徐々に増えているとの声が多い。国としても、綿糸や綿織物を中心に、中国や縫製業が盛んなカンボジア、インドネシアなどの近隣国へ安定的に輸出できるようになった(図3参照)。ベトナムは、衣類・繊維原料の生産・輸出国として着実に成長を遂げている。
(上位5カ国・地域)
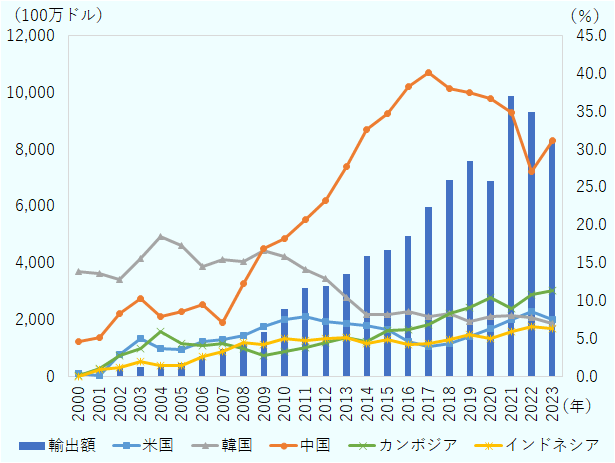
注:2023年時点の上位5カ国・地域を表示。
出所:GTAに基づきジェトロ作成
外資による投資がベトナム繊維産業を強化
ベトナムはグローバルアパレルブランド向けOEMで衣類輸出を拡大してきた。地場企業では、国営のVINATEXや大手のTNG Investment and Tradingのほか、多くの中小規模企業が産業基盤を支えている。
ベトナム繊維協会(VITAS)は、ベトナムの繊維・アパレル部門における累計外国直接投資は約3,500件、投資額は370億ドル超と発表、「外資系企業が、ベトナムの繊維製品輸出額の約65%を占める」とした(2024年5月の複数の現地報道)。
主な投資元は、韓国が最大で、台湾、香港、中国が続いている。外資企業は、縫製工場設立から始まり、糸や生地、副資材など、一部の繊維原料企業も進出している。特に2018年ごろから、第1次トランプ政権発足以降の米中貿易摩擦に伴い、再編の動きが加速した。日系繊維商社は、「中国産を使用しない動きが広がる中、まず縫製工場のベトナム進出が増加した。その後、現地調達の流れに伴い、新型コロナウイルス収束後に副資材や生地メーカーの進出も続いた」と話す。
日系企業もベトナムを繊維産業の重要拠点に位置付け
日系の繊維企業も、ベトナムを重要な生産拠点と位置づけ、投資を拡大している。ユニクロを展開するファーストリテイリングは、ベトナム国内で縫製事業を拡充しており、2025年9月時点で契約している縫製工場は73カ所にのぼる(注2)。これは中国に次ぐ規模だ。さらに、素材工場や副資材工場も23カ所と契約し、グローバルな供給体制の中で、ベトナムの役割を強化している。
生地関連では近年、東レのグループ会社が2024年7月に北部ナムディン省(現ニンビン省、注3)で繊維・染色工場を開所した。また、三井物産と日鉄物産が出資する繊維商社のMNインターファッションは、韓国と米国の繊維企業と3社合弁で、中部ニントゥアン省(現カインホア省)にエコファー(人工毛皮)生地工場を2025年7月に稼働すると発表している。
日系の繊維・縫製関連事業では、生産だけでなく営業や開発などの機能をベトナムに集約する動きがある。代表例は、ファスナーなどの副資材を製造・販売するYKKだ。同社は2023年、営業本部の機能を日本からベトナムへ移管した。背景には、ベトナム国内でスポーツやアウトドア、カジュアルウェアなどのアパレル縫製が増えたことがあり、営業担当者がグローバルに供給する縫製工場との連携や提案をしやすい体制にした。なお同社は、2012年に南部ドンナイ省のニョンチャックで、2019年に北部ハナム省で、新工場を立ち上げていた。さらに2024年にはハナム省の第2期工場を増築、2025年6月にはニョンチャック工場の第3期増築を発表している。これにより、生産と開発機能を強化し、ASEANにおける技術の中核拠点としての役割を一層高める方針だ。
繊維産業のカギ握るベトナム人材
ベトナムへの繊維投資が拡大する背景には、人材面での魅力がある。安価な人件費や豊富で質の高い労働力は、ジェトロの調査でも投資環境上の主要メリットとして上位に挙がる。縫製管理を担う日系商社は、「ベトナム人材は真面目で、アジアの中でも相対的に生産性が高い」と評価する。
一方、人件費上昇や一部地域での労働者不足といったリスクも顕在化している。「現地通貨ベースでは、賃金上昇幅が大きいが、ドル換算ではまだ安価」との日系企業の指摘もあるが、最低賃金の上昇や周辺企業との人材獲得競争の激化で、賃金を上げざるを得ない場合もある。特に、近隣に大規模工場が進出すると、労働者が流出するリスクがある。
現在のところ、人材確保に問題はないという声もあるが、採用が以前ほど容易ではなくなることは、今後の事業展開に当たって無視できない。
縫製の高付加価値化と地方展開に活路
このように縫製業界で、今後の人件費上昇や労働力不足への懸念が広がる中、新たな事業展開も進んでいる。ある日系企業は、「都市部近郊の既存工場では賃金が高い。一方で、ワーカーの技術力が上がっており、中高級ラインの少量多品種生産を強化している」という。高付加価値化によって、単なるコスト競争から脱却し、品質やデザイン性を重視した製品展開を目指す動きが進んでいる。
また、ある日系企業は「地方部では都市部より人件費が安く、豊富な労働力の確保が期待できる」とし、地方の縫製委託先を拡充している。都市部での高付加価値化と地方部での量産体制の両立は、ベトナムにおける縫製産業の競争力を確保する重要な戦略になり得る。
自由貿易協定の活用、新市場開拓に可能性
ベトナムの縫製業にとっては、自由貿易協定も重要なツールになる。ベトナム政府は、積極的に自由貿易協定を締結しており、現在、世界の国・地域との間で16の協定が発効している。米国が「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)」に加盟しなかったため、米国向け輸出での関税率引き下げはないが、日本、韓国、中国との間では関税率の減免があり、「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」の累積規定のメリットも享受できる。さらに、2020年8月には欧州ベトナム自由貿易協定(EVFTA)が発効し、欧州市場への販路開拓のチャンスも広がっている。ある日系繊維商社は、日本以外の新たな市場として欧州市場向けにも注力していくという。
東南アジアのアパレル市場の規模は小さいものの、人口増加と所得水準向上で今後の成長を見込める。日系企業では、素材の品質や機能性と価格のバランスを考慮しながら、現地で自社アパレルブランドの展開を進める動きがある。ただし、現地商流や価格競争での難しさもあり、参入方針は企業によって分かれる。
今後10年に向けたベトナムの競争力
繊維産業全体では、中国一極集中から、ASEANや南アジアなどの複数地域へのサプライチェーン移行が進む。日系企業もベトナムを重視し、日本向け衣類輸出は安定したシェアを維持している。日系繊維商社は、距離の近さ、リードタイム短縮、人件費水準、労働力確保、生産効率などのバランスを評価し、日本市場向けの安定的かつ迅速な供給体制を実現している。日本向けの多品種少量生産は、欧米市場向けの大口受注を抱えるベトナム縫製工場にとって優先順位が低いとも指摘されるものの、これらの強みを踏まえると当面、日本向け輸出拠点としての競争力は維持されるだろう。
加えて、裾野産業の成長が進んできたことで、川下の縫製工程だけでなく、川上の素材調達を含めて供給体制の幅が拡大している点もベトナムの強みになる。日系企業の多くは、「今後10年程度は縫製ビジネスが十分に成り立つ」と見る一方、人口ボーナス終了後の事業環境には不透明感があり、「10年後の予測は難しい」との声も少なくない。こうした状況下、ベトナム国内外の事業環境の変化を的確に見極め、柔軟に対応していく姿勢が求められている。
- 注1:
- 輸出入統計の分析では、HS50~63(繊維・同製品)を繊維産業として扱い、そのうちHS50~60を材料となる繊維原料、HS61~63を最終製品となる縫製品とする。なお、縫製品のうち、ほとんどはHS61~62の衣類だ(HS63はその他縫製品)。
- 注2:
-
ファーストリテイリングの関与する工場は、2025年9月1日時点で次のとおり(ファーストリテイリングウェブサイト参照
 )。
)。
- 縫製・一部工程外注先:73工場。うち、衣類の縫製が69工場。その他4工場。
- 主要素材や副資材の製造:23工場。
- 注3:
- 地方行政の再編が2025年7月から実施され、省名が統合によって変わった。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理(執筆当時)
庄 浩充(しょう ひろみつ) - 2010年、ジェトロ入構。海外事務所運営課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ビエンチャン事務所(ラオス)、広報課、ジェトロ・ハノイ事務所(ベトナム)を経て、現職。




 閉じる
閉じる






