ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応裾野産業の育成と産業基盤の強化が急務
フィリピン(3)
2025年10月31日
本シリーズの前編と中編では、フィリピンの貿易・投資構造や外資誘致政策の経緯、エレクトロニクス産業の発展と企業動向について概観してきた。後編にあたる本稿では、内需向け製造の代表例である自動車産業のサプライチェーンや産業政策の現状を整理する(注)。
そのうえで、フィリピンの産業高度化とサプライチェーンの展望、現地政府が取り組むべき政策や運用、さらに日系企業の既存拠点の競争力強化や地政学リスク対応の観点から、フィリピン拠点発展の在り方を考察する。
好調な自動車販売市場、国内生産台数との差が30万台超に
フィリピンのサプライチェーンでは、エレクトロニクス産業に加え、内需向け製造も注目されており、自動車産業がその代表例だ。
フィリピン自動車工業会(CAMPI)とトラック製造者協会(TMA)によれば、2024年の新車販売台数は前年比8.7%増の46万7,252台だった(図参照)。過去10年間、販売台数は堅調に推移し、2015年の28万8,000台から2024年には46万7,000台超に増え、過去最高を記録した。特に2022年以降は内需拡大で急増した。一方、生産台数は2015年の10万1,000台に対して2024年は11万7,000台にとどまっている。その結果、販売台数との差は30万台以上に広がっている。国内需要の高まりに対し、生産が伸びず輸入への依存が続いていることを示している。
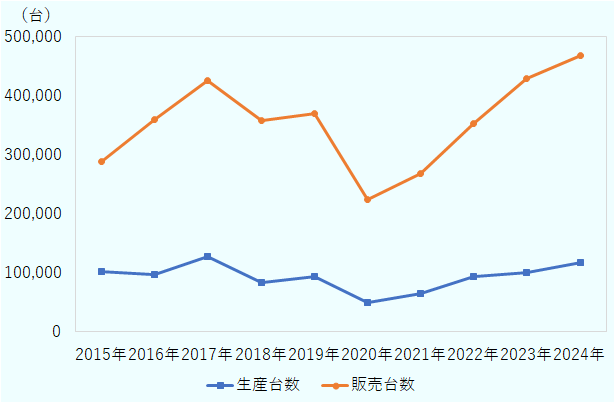
注:販売台数は、バスを除く。
出所:生産台数はマークラインズ、販売台数はフィリピン自動車工業会(CAMPI)とトラック製造業者協会(TMA)を基にジェトロ作成
フィリピンの自動車市場は、人口増加と所得向上のほか、在外フィリピン人労働者(OFW)からの送金による消費意欲の高まりもあり、拡大傾向にある。中古車の輸入規制で新車販売が伸びており、日系ブランドのシェアが約8割と高い。近年では、比亜迪(BYD)などの中国ブランドや韓国ブランドもシェア拡大を狙っている。電気自動車(EV)も政策支援で需要が伸びているが、電気料金の高さや充電インフラ整備の遅れなどから、バッテリーEV(BEV)よりも、プラグインハイブリッド車(PHEV)やハイブリッド車(HV)の販売拡大も期待されている。なお、二輪車(バイク)の販売も好調で、2024年にはASEANで4番目に多い168万2,000台が販売された〔フィリピン自動二輪開発計画参加社協会(MDPPA)〕。バイクの所有率は他の東南アジアの国と比較して低く、今後の市場の伸びが期待されている。
一方、新車市場では輸入車の販売が好調で、日系ブランドも多くをタイやインドネシアで製造した車種に依存している。フィリピンにも自動車部品サプライヤーが進出しているが、その生産規模は小さい。自動車関連企業へのヒアリングによると、フィリピンでの生産は人件費や物流コストで有利だが、他国での生産規模や部品調達環境、さらにFTA(自由貿易協定)を活用したASEAN域内での関税減免を考慮すると、完成車輸入とのコスト差は小さく、現地生産による競争力の優位性は限定的とされる。
自動車の産業政策、運用の改善に期待
同国での自動車生産にあたって、企業からは政策支援の強化が求められている。フィリピンの代表的な自動車政策として、2015年に導入された「包括的自動車産業振興戦略(CARS)」がある。CARSは、国内生産の強化と雇用創出を目的とし、自動車産業に対して税還付などの恩典を提供する制度だ。支援は、車両導入や関連設備など初期投資向け固定投資支援と、生産目標台数10万台以上を達成した場合に付与される生産台数インセンティブの2段階で構成される。直近では、2025年に「自動車産業における競争力強化のための再活性化プログラム(RACE)」が適用予定だ。RACEは、固定資産支援のみだが、CARSよりも適用条件が緩和されている。
企業ヒアリングでは、両制度とも魅力があるものの、運用面に不安があるとの声があった。CARSでは、一部の恩典が実行されないケースがある。これは政権交代による政策の引き継ぎ不足や、十分な予算が確保されなかったことが一因だ。新政権として、歳出抑制と歳入増加を意図していることも背景にあるようだ。RACEは、予算規模がCARSの3分の1程度と縮小していることへの懸念がある一方、固定投資支援額はCARSよりも大きい点が評価されている。これらの支援策は魅力的だが、実際の運用が伴うかが課題で、政府には政策立案から運用まで一貫した実施が求められる。
中長期的な成長に向け、投資環境の魅力を生かした製造業振興を
前編・中編を通じ、フィリピンの貿易構造は輸出が米国向け、輸入が中国依存であること、半導体・電気機器産業は米国企業と日本企業の投資で成長してきたことが確認された。1990年代以降、日系製造業はエレクトロニクスや自動車を中心に進出・拡張投資を継続しており、政府の外資誘致策が活用されている。一方、制度運用の不透明さや部品輸入依存など課題も指摘されている。以下では、政府が取るべき産業高度化政策とその運用、企業にとってのビジネス環境の魅力と課題、日系企業にとっての製造拠点としての位置づけと今後の展望を考察したい。
フィリピン政府、一貫性・透明性のある政策運営が重要
まず、裾野産業の育成が急務だ。素材・部品産業が全般的に脆弱(ぜいじゃく)で輸入に依存せざるを得ないことから、人件費の優位性があってもコストを十分に低減できない。一方、プリンター産業などでは、セットメーカーとともに進出したサプライヤーが長年にわたり連携を維持している。中長期的な経済成長を見据えると、製造業基盤の整備と輸入依存からの脱却が不可欠だ。
また、産業基盤強化にはインフラ整備が欠かせない。停電が頻発する地域では、半導体や精密電子部品の生産にあたって非常用発電機の導入が必要となり、生産コストの上昇を招いている。電気料金も相対的に高水準で、企業の競争力や投資判断に影響を及ぼす。さらに、道路損傷への修繕要望に対する行政の対応の遅延や、港湾が民間主導のため開発が遅れること、高い利用料が調達コストや物流効率に直結することも課題だ。企業からは「政府は産業誘致を掲げながら、物流などのビジネス環境を十分に整備できていない」と指摘されている。政府はこうした課題の改善に向け、インフラ開発政策「ビルド・ベター・モア」を推進している。
一方、製造業振興策は限定的で、内需向けサービス産業の成功を背景に、一部企業からは「輸入依存では国内産業が育たない」との懸念も聞かれる。アジア周辺国と比較して競争力のある政策が求められる中、前述の自動車関連政策は一定の進展を見せており、今後の運用に注目が集まる。
また、6年おきの大統領選挙期間には、公共投資や規制緩和が停滞し、企業向け優遇措置の遅延も生じやすいという。法規制により、選挙期間中に規制対象の化学物質や原材料へのアクセスが制限されるため、企業は在庫の積み増しなどの対応を迫られることもある。税務調査や追加徴税も依然として多く、行政の一貫性や透明性が不十分なことも課題だ。CREATE MORE法など法整備で税務リスクの改善が期待されている(本特集「フィリピン(1)エコゾーンによる外資誘致、製造業は拡張投資が中心」参照)。
日系企業、コスト競争力と日本との高い親和性を活用
日系企業にとって、フィリピン拠点は既存工場への追加投資による生産拡大や設備増強の有力拠点となっている。小型・軽量の電子部品は物流コストを抑えつつ販路拡大が可能で、米中対立の影響で中国依存を減らす調達先としても注目される。エレクトロニクス産業では組み立てや最終検査など、豊富な労働力を必要とする工程の移管先としても有力で、企業からは「米国顧客の移管にあわせ、半導体用メッキ剤の展開を狙っている」「チャイナリスクの受け皿になる需要は大きい」との声が聞かれた。
フィリピンでの製造では、コスト競争力の高さや日本との親和性など投資環境のメリットが大きい。東南アジア全域で賃金の上昇が進む中、フィリピンでは上昇が比較的穏やかで若年労働力も豊富だ。企業からは、「人件費の価格競争力が量産モデルの収益性を支える」「ワーカークラスの人材確保にほとんど苦慮しない」という意見もみられた。大量オペレーションを要する電子部品の組み立てや検査工程でコストを抑えて品質を維持できるため、フィリピン拠点は重要な位置を占めている。ある企業では、現地法人で10年以上勤務している中核スタッフが、日本側の人手不足を補うため派遣されるケースもある。
また、フィリピンは東南アジアで最も日本に近く、時差は1時間で、日本本社との連携やエンジニア、管理者の現地出張による立ち会いが容易で、生産調整や品質トラブルへの即応性が高い。日本時間に合わせて稼働したり、リアルタイムの開発会議や技術指導を行ったりする体制を整備している日系企業もある。また、公用語の1つが英語のため、現地従業員とのコミュニケーションが円滑に進められる。各種文書やマニュアル類の表記を統一でき、翻訳や通訳を介さずに業務指示や技術指導できることは、運営効率の向上につながる。
総じて、フィリピンは独自の魅力と潜在的な課題を併せ持つ。適切なリスク管理を行い、既存拠点の競争力を強化し、地政学的優位性を生かすことで、サプライチェーンにおける役割拡大が期待される。
- 注:
- 本調査では2025年8~9月に、エレクトロニクス、OA機器、自動車などのメーカー、物流、メッキ加工、銀行、商社など、合計15社にヒアリングを実施。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理(執筆当時)
庄 浩充(しょう ひろみつ) - 2010年、ジェトロ入構。海外事務所運営課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ビエンチャン事務所(ラオス)、広報課、ジェトロ・ハノイ事務所(ベトナム)を経て現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課
西村 公伽(にしむら きみか) - 2024年、ジェトロ入構。アジア大洋州課でASEANおよびオセアニア関係の調査を担当。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・マニラ事務所
西岡 絵里奈(にしおか えりな) - 2016年、ジェトロ入構。途上国ビジネス開発課、ジェトロ・プノンペン事務所、ビジネス展開支援課、対日投資課DX推進チーム、ジェトロ島根を経て、2023年9月から現職。




 閉じる
閉じる






