ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応EMS企業が中国から生産移管、コンピュータ輸出が急拡大
ベトナム(3)
2025年10月27日
ベトナムのエレクトロニクス産業は、スマートフォンを中心に発展してきた。しかし、近年、輸出額を急増させているのはコンピュータ関連分野だ。米中貿易摩擦の影響を受け、中国からベトナムに生産移管が進んだことが背景として考えられる。
本稿では、ベトナムのエレクトロニクス産業の中でもコンピュータ関連分野に焦点を当て、輸出入の推移、投資の変遷、主要企業の動向などから、その成長要因と今後の展望を考察する。
コンピュータ関連の輸出が2020年以降に急拡大
ベトナムの輸出額は近年、スマートフォンをはじめとする電気機器(HS85類)に次いで、一般機械(HS84類)が大きな割合を占めている。HSコード4桁ベースでみると、特にコンピュータ(HS8471)、コンピュータ部品(HS8473)、印刷機(HS8443)の割合が大きい(図1参照)。印刷機は2008年以降、輸出額を堅調に伸ばし、安定した成長を続けている。一方、コンピュータおよびその部品の輸出は、2020年以降に急速に拡大し、近年の輸出全体の成長を牽引する主要な要因になっている。とりわけコンピュータでは、ノートパソコン(PC)やタブレットなどの携帯用自動データ処理機器(HS847130)の輸出が大半を占めている。
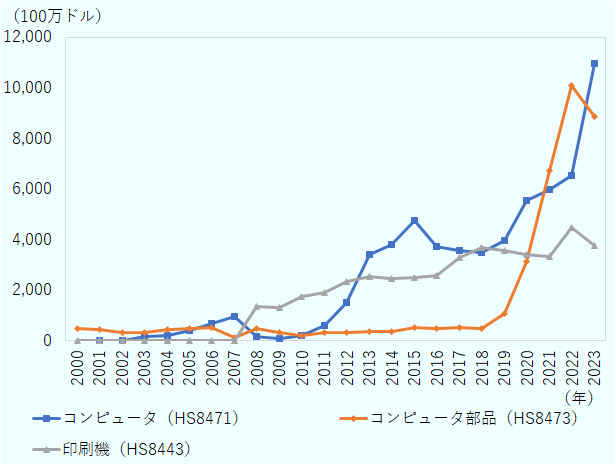
注:2023年時点の上位3品目を表示。
出所:Global Trade Atlas(GTA)に基づきジェトロ作成
コンピュータの輸出先を国・地域別にみると、米国向けが最大で、2018年から2023年にかけて5.3 倍に増加した。背景には、台湾や中国の電子機器製造受託(EMS)企業がベトナムで米国向けノートPCなどの生産を拡大したことがある。
米国に次ぐのが、中国だ。2021年までは少額だったものの、同年から2023年にかけて12.8倍に増加した。これは、中国市場向けコンピュータの一部をベトナムでも生産するようになったことを示唆している。
続く韓国向けも、2010年代後半から増加した。サムスンがベトナムでタブレット端末などの生産を開始した影響とみられる。
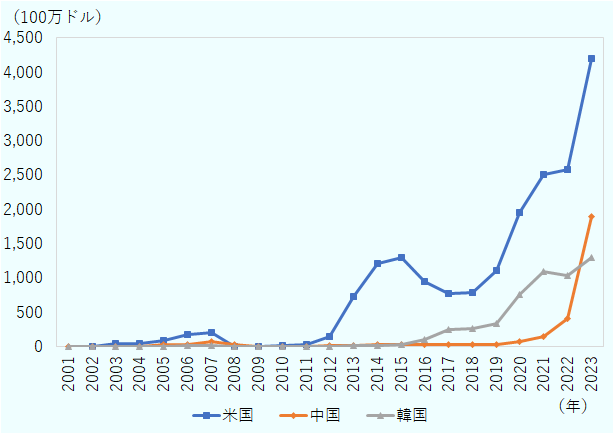
注:2023年時点の上位3国・地域を表示。
出所:Global Trade Atlas(GTA)に基づきジェトロ作成
コンピュータ部品も2019年以降、米国や中国、香港向けを中心に輸出が拡大している。完成品と同様、米中貿易摩擦を受けて、中国からベトナムへの生産移管が進んだことが背景にある。
台湾・中国系のEMSが投資、ノートPCなどの輸出拠点に
コンピュータ関連の輸出拡大を牽引しているのは、台湾・中国系のEMS・ODMだ(注1)。ベトナム北部には、台湾系のホンハイ(フォックスコン)、ウィストロン、コンパル、ペガトロン、クアンタ、中国系のラックスシェア、ゴアテック、BYDなどが製造拠点を構えている(表参照)。2010年代後半以降の米中貿易摩擦を受けて、ベトナムへの投資を加速し、2020年以降も工場の新設・拡張が相次いでいる。日系のエレクトロニクス関連企業によると、「EMSは当初、ベトナムを中国の補完的な生産拠点として位置づけていた。中国でのコスト競争力が高く、中国以外での生産拡大に消極的だったが、顧客のブランド企業による脱中国志向が強まる中、ベトナムでの生産を増やしている」という。
| 台湾系/中国系 | 企業名 | 投資先(注1) | 主な製造品目 | アップルのサプライヤー(注2) |
|---|---|---|---|---|
| 台湾系 | ホンハイ(Foxconn) | 北部バクニン省(旧バクザン省)、クアンニン省 | ノートPCなどの電子機器 | ○ |
| ウィストロン(Wistron) | 北部ニンビン省(旧ハナム省) | ノートPCなどの電子機器 | ||
| コンパル(Compal) | 北部ビンフック省、タイビン省 | ノートPC、スマートフォンなどの電子機器 | ||
| ペガトロン(Pegatron) | 北部ハイフォン市 | ノートPCなどの電子機器 | ||
| クアンタ(Quanta) | 北部ナムディン省 | ノートPCなどの電子機器 | ○ | |
| 中国系 | ラックスシェア(Luxshare) | 北部バクニン省(旧バクザン省)、北中部ゲアン省 | イヤホンなどの電子機器 | ○ |
| ゴアテック(GoerTek) | 北部バクニン省、北中部ゲアン省 | イヤホンなどの電子機器 | ○ | |
| BYD | 北部フート省 | タブレットなどの電子機器 | ○ |
注1:2025年7月に地方行政が再編されたため、投資先の省・市の名称にも一部変更が生じている。
注2:○はアップル公表の2023年度サプライヤーリストに掲載のある企業。
出所:各社ウェブサイトや各種報道などを基にジェトロ作成
この動きは、特に米国を中心とするブランド企業の意向を反映したものだ。米国政府は、中国からの輸入品に対して高関税を課す方針を継続しており、米国系PCブランドのデルやHPは中国での生産を縮小し、とりわけHPは主力移管先としてベトナムを選択した。これにより、ノートPCなどの生産を受託する台湾系EMSは、ベトナムへの投資をさらに強化し、米国向けを中心に輸出が急拡大している。米国ブランド以外では、台湾のAcerとASUSも、米国市場向け製品の生産をベトナムのEMSに移管している。
また、米国のアップルも、スマートフォン以外のワイヤレスイヤホンやスマートウォッチをはじめ、タブレット、ノートPCの一部生産もベトナムに移管している。
プリンターメーカーは中国からベトナムに生産移管加速
一般機械(HS84)の中でも、印刷機(HS8443)の輸出は2008年以降、堅調に増加している。輸出先は米国、EU、中国などで、グローバル供給体制を構築している。
この背景には、日系プリンターメーカーが相次いでベトナム北部に進出したことがある。キヤノン、ブラザー工業、京セラ、富士フイルムなどがベトナムで生産・輸出している。
日系の関連企業によると、中国における人件費の上昇や米中貿易摩擦の影響などを受け、2017年ごろから中国からの生産移管が加速した。その過程で、多くの部品サプライヤーも中国からベトナムへ生産移管し、後方連関効果(注2)でベトナムの工業化が進展している。一部のサプライヤーはプリンター部品以外の製品にも事業を拡大し、ベトナムの産業基盤強化に貢献している。
米国通商政策に注視も、中国からの生産移管は継続
近年、コンピュータや印刷機関連の輸出が拡大している背景には、米中貿易摩擦がある。2018年に米国が中国製品に高関税を課したことで、米国向けのエレクトロニクスブランドが脱中国を加速させ、その代替拠点として注目されたのがベトナムだ。日系の関連企業へのヒアリングを踏まえると、ベトナムは、中国よりも人件費が安価で、労働力の確保が容易なほか、電力・水道などのインフラ整備、政治・社会の安定など、投資先としてのバランスの良さが評価されている。さらに、サムスンがベトナム北部での生産・輸出に成功したことも、後押しになっている。
地理的にもベトナム北部は中国と隣接し、中国から部品を輸入する上でリードタイムや物流コスト面で優位性がある。あるEMS企業へのヒアリングによれば、中国側のサプライヤーからベトナム国境近くの都市〔ランソン省に隣接する中国・凭祥(ピンシャン)など〕にある倉庫に納品し、北部工場へ陸送しているという。ベトナム国内で調達できる原材料・部品が限られる中、中国のサプライチェーンを活用しやすい環境にある。米国が今後さらに脱中国の動きを強めると、HPやアップル以外のブランド企業が当地で生産を拡大する可能性が高まる。
米国は2025年4月、相互関税措置を発表したものの、短期的には中国からベトナムへの生産移管に大きな変化は見えてこない。日系のエレクトロニクス企業によると、ベトナム当局の迂回貿易対策とみられる措置として、中国からベトナムに電子部品を輸入する際の通関が厳格化し、一時的に物流のリードタイムが延びる事例はあったが、米国向けの輸出が多いEMSで目立った影響は確認されていないという。ただし、今後ベトナムを含む東南アジアからの輸出に高関税が課されると、ベトナムでの生産拡大計画にも見直しのリスクが生じる。複数企業へのヒアリングでは、米中対立を踏まえたリスクヘッジの方針は顧客企業ごとに異なる傾向がある。
組み立て以外の付加価値創出が今後の課題
印刷機関連では、部品サプライヤーのベトナム進出が進む一方、EMS企業が生産受託するノートPCなどでは、依然として多くの電子部品を輸入に依存している。
EMS向けに部品などを納品する日系企業によると、「現場での緊急対応や将来的な現地購買への切り替えを見据え、ベトナムに自社拠点を構える意義は大きい」との声がある。一方、「EMSは購買を一極集中管理しており、本国側で電子部品を注文の上、キットにして仕向け地別に分配している。ベトナム国内で完結するようなサプライチェーンの構築は時期尚早」「小型・軽量の電子部品を特定地域に集積する必要性が低く、新たにベトナムに生産拠点を設ける動きは限られる」との見方もある。
EMS関連のベトナムへの投資は今後、組み立て中心にとどまるのか。それとも、当地の裾野産業拡大や開発機能の新設などが進み、付加価値創出につながるのか。ベトナムの産業高度化における重要な分岐点となり得る。
- 注1:
- ODM は、Original Design Manufacturingの略。受託者が顧客の要望に応じて、製品の製造だけでなく、設計・開発の段階から引き受ける。
- 注2:
- 最終製品の需要増加が原材料や部品などの上流産業に波及する経済効果。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理(執筆当時)
庄 浩充(しょう ひろみつ) - 2010年、ジェトロ入構。海外事務所運営課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ビエンチャン事務所(ラオス)、広報課、ジェトロ・ハノイ事務所(ベトナム)を経て、現職。




 閉じる
閉じる






