ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応エレクトロニクス、量産型の輸出拠点で差別化
フィリピン(2)
2025年10月31日
フィリピンのエレクトロニクス産業は、米国企業の投資や日系企業の進出に支えられ、着実に成長してきた。輸出では、電気機器(HS85)が約4割前後を、集積回路(HS8542)はその約6割を占める。半導体企業では米国企業による進出が主体で、米国企業がフィリピンの半導体産業の発展を主導している。一般機械(HS84)では、印刷機(HS8443)が主要品目の1つで、日系プリンターメーカーが主要生産拠点の1つとして進出している。
中編の本稿では、米国半導体企業による投資動向や増産の背景、日系電機企業の進出・拡張の経緯、現地での部品調達の状況、プリンターを中心とした輸出動向を最新事例とともに考察する(注)。
集積回路が輸出を牽引、グローバル市場向け
フィリピンの輸出額に占める電気機器の割合は約3~4割で、特に集積回路(HS8542)がその成長を牽引している。図表にはないが、2005年以降の電気機器に占める集積回路の割合をみると、特に2010年代後半から2020年代初頭にかけて顕著な伸びが確認できる。2005年のシェアは約40%だったが、2015年には約55%、2020年には約60%にまで上昇した。集積回路の輸出額は、2010年の6億4,300万ドルから2022年には22億2,400万ドルへと約3.5倍に拡大した(図1参照)。世界的な半導体需要の波はあるものの、集積回路を中心とした電気機器がフィリピンの輸出を牽引している。
(上位5品目、HSコード4桁ベース、2005~2024年)
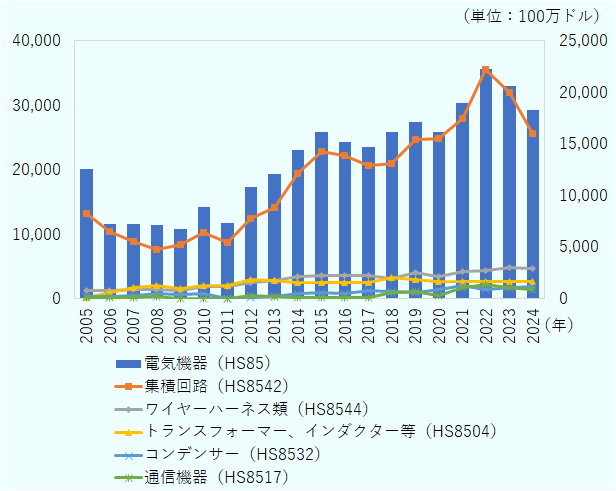
注:2006年にHS98類(再輸出品目)を導入し、輸出品生産にかかわる輸入原材料の関税免税措置を利用した品目をHS1~97類の貿易品目と区別して分類するようになったため、HS85類の品目がHS98類に分類されている場合がある。
出所:Global Trade Atlas(GTA)を基にジェトロ作成
電気機器の輸出先を国・地域別にみると、2012年以降に香港向けが増加し、2015年以降は首位を維持している(図2参照)。背景には、電子部品を一度香港の倉庫に集約し、そこからグローバルに再輸出するサプライチェーンの仕組みがあるとみられる。フィリピンで電子部品を製造する日系企業は「香港に輸出した後、日本、中国、ASEAN、米国、欧州など、幅広い地域に供給されている」と話す。香港に次ぐ輸出先は、米国、日本、中国で、特に米国向けは2021年から2023年にかけて顕著に伸びた。これは、米国の半導体企業による集積回路の生産拡大の影響とみられる。
(上位5カ国・地域、2005~2024年)
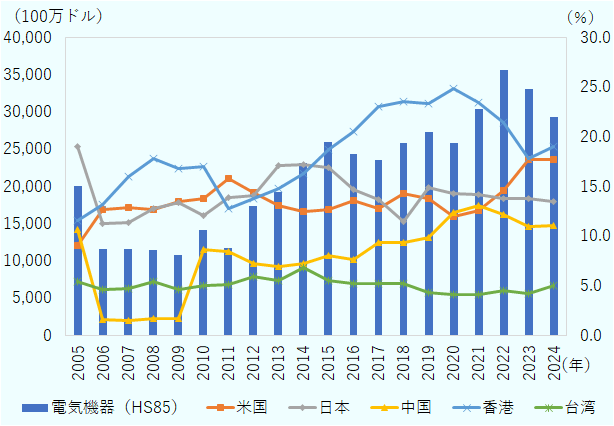
出所:GTAを基にジェトロ作成
米国企業が半導体産業で大きな役割
フィリピンの半導体産業の発展には、インテルやテキサス・インスツルメンツ(TI)など米国企業が大きな役割を果たしてきた。
米国のシンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)によれば、2014年から2023年にかけて、米国企業によるコンピュータ・電子製造への投資額は約79億1,000万ドルに上る。インテルは、フィリピンで5,000人の直接雇用者と約3万6,000人の間接雇用者を抱えていたが、2008年の世界的な景気後退に伴う事業再構築の一環として、同国のチップ組み立て・テスト・パッケージ拠点を閉鎖した。それでも、現在も半導体企業では米国企業による進出が主体で、組み立て・テスト・パッケージ部門に特化した工場が13カ所ある。また、産業全体では約250万人のフィリピン人が雇用されている(2023年4月時点)。
米国では、ジョー・バイデン前政権下の2022年8月、地政学リスクを背景に、米国内の半導体製造能力を強化する目的で「CHIPSおよび科学法(CHIPSプラス法)」(2023年8月10日付ビジネス短信参照)が成立した。さらに、同法のもとで半導体サプライチェーンの安全性・多様性を確保するため、「国際技術安全保障・イノベーション(ITSI)基金」が設立された。フィリピンは友好国の1つとして、米国との関係強化を進めている。半導体分野では、「フレンドショアリング」(信頼できる同盟国やパートナー国との連携)を通じた生産が加速しており、フィリピンはその受け皿とみなされている。2023年5月には、アナログ・デバイセズはカビテに研究開発施設を設置するために2億ドルを投資すると発表した。また、2023年8月、テキサス・インスツルメンツがクラークとバギオ市で最大10億ドルの施設拡張投資を行うと発表した。
日系の電子部品商社は「米国企業にとって、同盟国のフィリピンはサプライチェーンにおけるリスク管理をしやすいのではないか」との見方を示した。また、日系電機メーカーも「米国企業との取引ではカントリーリスクが問題となるが、フィリピンはその対象にはならない」と指摘した。
日系電機企業は2010年代前半までに進出、近年は拡張が中心
エレクトロニクスおよびOA機器関連の日系企業は、1980~1990年代と2010年代前半にフィリピンへ進出した事例が多い。
1980~1990年代には、多くの日系企業がフィリピン経済特区庁(PEZA)登録企業としての優遇措置や、1985年のプラザ合意後の円高で、日本電産コパル、ローム、クラリオンなどが生産拠点を立ち上げた。1990年代には日立、東芝、日本電気(NEC)、富士通といったハードディスクドライブ(HDD)メーカーや、プリンターメーカーのセイコーエプソン、磁気ヘッド・ガラス基板などの部品サプライヤーも進出した。2000年以降は、HDD分野の再編に伴い撤退が相次いだ。2010年代前半には、タイのアユタヤでの洪水被害や周辺国での人件費高騰を背景に、2012年に村田製作所、ブラザー工業、キヤノンなどが新規投資を行った。
近年は、新規進出が減少し、既存拠点の拡張が中心となっている。各社プレスリリースや報道によれば、村田製作所は2025年10月に約112億円(建屋のみ)を投じて建設を進めていた積層セラミックコンデンサーの新生産棟が完成した。さらに、ブラザー工業は2024年にプリンター・複合機の生産能力拡大のための第3工場の建設を、ミネベアミツミは2025年に半導体薄型パッケージ用高生産性ライン構築に向けたセブ工場の新棟建設を発表している。
日系電機メーカー、量産拠点として位置づけ
新規進出は限定的であるものの、既に進出しているエレクトロニクス産業の日系メーカーは、フィリピンをグローバル向けの主要輸出拠点として活用している。ジェトロが実施したヒアリングから、次の事例が浮かび上がった。
日系電機メーカーA社は、車載用電子部品の工場を日本とフィリピン、中国に展開している。中国国内向けは中国、グローバル市場向けは日本とフィリピンで生産している。日本では最先端品、フィリピンでは準先端かつ大量生産品を手掛けているが、人件費の安価なフィリピンへ生産移管を進めている製品もあるという。
日系電機メーカーB社は、フィリピンとマレーシアに半導体デバイスの生産拠点を有する。マレーシアでは大型機器向けの製品、フィリピンでは小型・軽量製品を量産している。フィリピンはマレーシアと比べて人件費が安価なため、生産コストの競争力が高い。また、中国向けの販売も多いものの、中国国内での製造だと価格競争が厳しく、他の国・地域に販売する際のリスクにもなり得るため、フィリピンでの量産が成果を上げているという。
日系電機メーカーC社は、日本やフィリピン、マレーシアなどで電子部品を生産している。日本工場ではサーバーや車載向けの高付加価値品を、フィリピン工場ではコア材からの一貫生産体制を築き、PC(パソコン)向けなどの製品を量産し、それぞれの輸出拠点としている。フィリピンは依然として安価な人件費が魅力だが、長年の設備投資と人材育成を背景に、今後は日本からの高付加価値品の生産移管も検討している。なお、マレーシアへの一部生産移管も検討したが、エンジニアの人件費高騰が課題になったという。
日系電機メーカーD社は、フィリピン生産の電子部品を日本やアジア諸国に販売している。近年は中国の景気低迷を受けて、生産調整している製品がある一方、フィリピンで拡大する二輪車(バイク)市場向けに、これまで海外自社工場から輸出していた製品を現地生産へと切り替える検討を進めているという。
ヒアリングによると、電子部品の多くは依然として輸入に依存しており、調達は顧客の指定や手配に基づくのが一般的だ。品質や納期を確保するため、商社を介して調達するケースも多い。現地で調達可能な原材料・部品は、外資企業が製造する一部の電子部品や樹脂成形品などに限られ、地場企業からの調達は、梱包(こんぽう)材などの間接材に限られるとの指摘が多数を占めた。
裾野産業が広がるプリンター業界、堅調な輸出を支える
フィリピンの輸出額では、電気機器(HS85)に次いで一般機械(HS84)が多く、特にコンピュータ(HS8471)と印刷機(HS8443)のOA機器が中心だ。このうち、印刷機は日系プリンターメーカーの生産が寄与しており、米中貿易摩擦を背景に2017年ごろから、フィリピンでの増産が輸出額を押し上げたとみられる(図3参照)。2021年はコロナ後の巣ごもり需要の影響もあり、輸出額は2010年以降最高額となる25億4,100万ドルを記録した。2022年と2023年は停滞したが、2024年は前年比42.4%増の21億5,500万ドルまで回復した。
印刷機の輸出先を国・地域別にみると、2018年以降、米国が首位で近年は20%以上のシェアを占める。米国に次いで、ドイツ、中国、日本などが10%前後、メキシコも3~6%程度で安定している。
(上位5カ国・地域、2010~2024年)
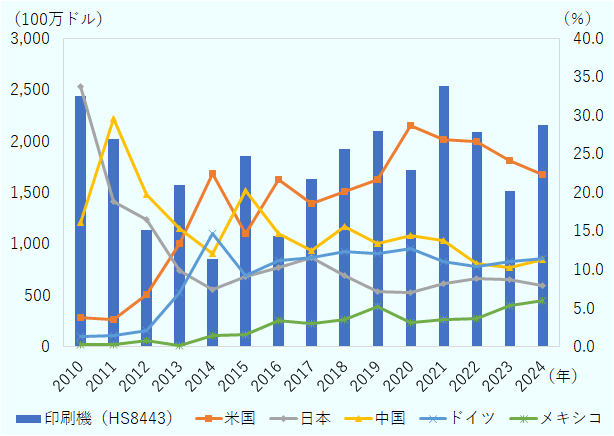
出所:ASEAN statsを基にジェトロ作成
日系プリンターメーカーは、2010年代前半までにフィリピンへ進出し、ページプリンターやインクジェットプリンターなどを生産している。部品サプライヤーの進出も相次いだことで裾野産業が広がっている。関係者によると、台湾や中国系のサプライヤーから調達するケースもあるようだ。業界全体としては、中国からベトナムへの生産移管が進む一方、メーカーによってはフィリピンを主要な生産地に位置づけている。
このように、フィリピンのエレクトロニクス産業は、米国企業や日本企業に支えられてきた。米国企業は特に、半導体の労働集約的工程で雇用を創出し、近年では経済安全保障上の観点からもフィリピンでの生産拡大を進めている。日本企業は1980年代以降、進出・拡張をしている。部品の多くは輸入依存で地場企業からの調達は間接的な材料などに限られるが、プリンター製造では労働集約的拠点としての利点から、グローバル生産拠点として活用されている。
後編では、国内市場の拡大に期待して内需向けに製造する自動車産業のサプライチェーンの現状を考察する。さらに、フィリピンの中長期的な成長を見据え、投資環境の魅力と課題、製造業振興に向けた施策などを整理する。
- 注:
- 本調査では2025年8~9月に、エレクトロニクス、OA機器、自動車などのメーカー、物流、メッキ加工、銀行、商社など、合計15社にヒアリングを実施。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理(執筆当時)
庄 浩充(しょう ひろみつ) - 2010年、ジェトロ入構。海外事務所運営課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ビエンチャン事務所(ラオス)、広報課、ジェトロ・ハノイ事務所(ベトナム)を経て現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課
西村 公伽(にしむら きみか) - 2024年、ジェトロ入構。アジア大洋州課でASEANおよびオセアニア関係の調査を担当。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・マニラ事務所
西岡 絵里奈(にしおか えりな) - 2016年、ジェトロ入構。途上国ビジネス開発課、ジェトロ・プノンペン事務所、ビジネス展開支援課、対日投資課DX推進チーム、ジェトロ島根を経て、2023年9月から現職。




 閉じる
閉じる






