ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応エコゾーンによる外資誘致、製造業は拡張投資が中心
フィリピン(1)
2025年10月31日
1990年代から2010年代前半にかけて、エレクトロニクス、OA機器、自動車産業を中心に、日系製造業はフィリピンへの進出を積極的に進め、現在も拡張投資を続けている。アジア周辺諸国との連携でサプライチェーンを構築し、フィリピンの投資環境を活用しながら、産業や企業方針によって輸出向けや内需向けなど、生産拠点の位置づけを分化している。一方で、税制やインフラ整備など、国内の製造業振興に向けた課題は依然として多い。
本稿では、フィリピンに進出している日系製造業へのヒアリング結果を基に、同国のサプライチェーンの現状を3回に分けて整理する(注)。前編では、2005~2024年の約20年間におけるフィリピンの貿易・投資構造を概観するとともに、同国の製造業に対する外資誘致政策を振り返る。
輸出入ともに電気機器が上位に
フィリピンにおける2024年の対世界輸出額は729億8,400万ドル、輸入額は1,273億8,150万ドルだった(図1参照)。2005年と比較すると、輸出額は78.0%増、輸入額は2.9倍に拡大した。貿易収支は20年間、赤字が続いている。2020年の新型コロナウイルス禍以降も赤字は拡大傾向にあり、2022年には590億4,700ドルと過去最大の赤字幅を記録した。
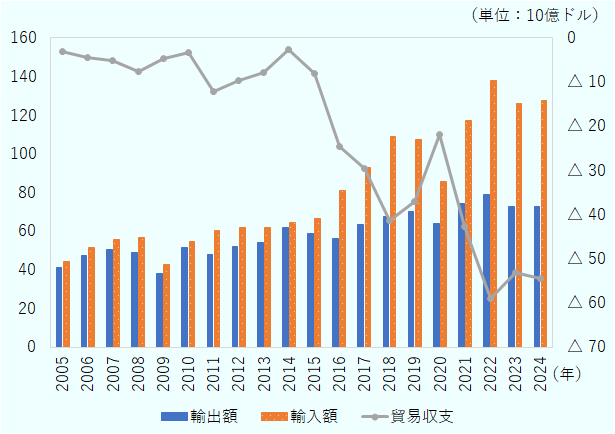
出所:Global Trade Atlas(GTA)を基にジェトロ作成
輸出額を品目別(図2参照)でみると、2024年は電気機器(HS85)が293億4,700万ドル(構成比40.2%)と、過去20年間を通じて緩やかに上昇傾向を示す。同品目は、輸出総額の3~4割を占め、主要品目となっている。その他の品目では、OA機器(複合機、PC)などを含む一般機械(HS84)が61億490万ドル(8.4%)で、近年は横ばいで推移している。
国・地域別では、2024年の最大輸出先は米国で120億6,800万ドル(16.5%)、2位は日本で102億5,400万ドル(14.1%)、次いで近隣のアジア諸国が続く。過去20年間では米国と日本が首位を競い、2010~2017年には日本が最大の輸出相手国だった。2021年ごろからは香港や中国向けの輸出額が100億ドルに迫り、存在感を増している。
米国向けの輸出を直近10年間の推移でみると、電気機器が一貫して首位を維持し、輸出全体の3~4割を占めている。特に、2021~2022年には世界的な半導体不足による価格高騰などの影響を受け、輸出額が38億ドルから52億ドルへ急増した。また、一般機械やゴム製品(HS40)などの輸出額も緩やかに増加しており、対米貿易では黒字が続いている。
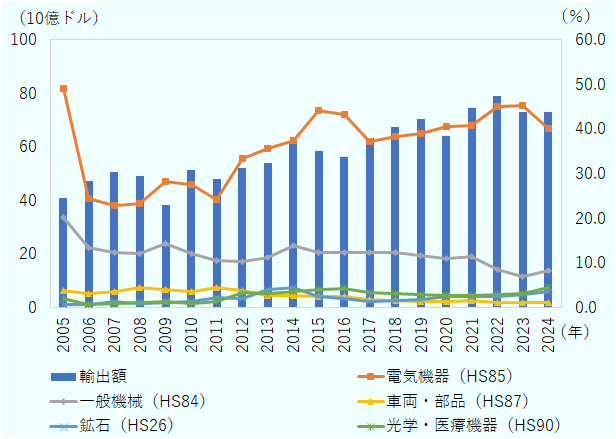
出所:GTAを基にジェトロ作成
一方、輸入を品目別(図3参照)にみると、2024年は輸出と同様に電気機器が193億9,100万ドル(構成比15.2%)と首位だった。過去20年間では、2014年ごろから右肩上がりの傾向が続いている。次いで、鉱物燃料(HS27)が190億9,500万ドル(15.0%)で2位、そのほか一般機械などが上位を占める。
国・地域別では、2024年に中国が328億1,900万ドル(25.8%)と輸入総額の大きな割合を占めた。2位はインドネシア(105億4,100ドル、8.3%)、3位は日本(100億6,800万ドル、7.9%)だった。2005年当時は米国と日本がそれぞれ16~17%台のシェアを占めていたが、2013年に中国が首位となって以降、そのシェアは緩やかに拡大している。中国からの輸入品目をみると、電気機器が最も多く、全体の1割強を占め、近年右肩上がりで上昇している。加えて、一般機械、鉱物燃料、プラスチック製品(HS39)、車両・部品(HS87)、紙(HS48)など、多様な品目を輸入しており、対中貿易では赤字が続いている。
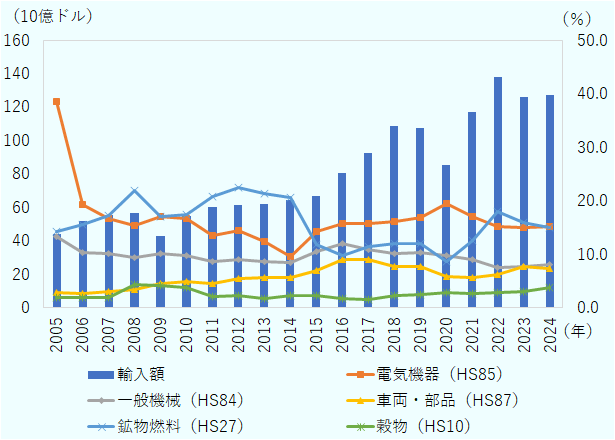
出所:GTAを基にジェトロ作成
近年は新規投資よりも、拡張投資での生産能力強化が中心
フィリピン統計庁(PSA)によると、2024年の海外直接投資認可額のうち、製造業は1,261億800万ペソ(3,278億8,000万円、約1ペソ=約2.6円)で、全体の23.1%を占めた(図4参照)。PSAの入手可能なデータによれば、2010年には製造業が全体の83.1%と、圧倒的なシェアを占めていた。国・地域別では、2010年代を通じて日系および米国系のエレクトロニクス企業による投資が相次ぎ、製造業を含む全体の投資額においても上位を維持していた。
海外直接投資認可額に占める製造業の割合は、2010年代はおおむね約5割の水準で推移したが、2016~18年には製造業投資が伸び悩んだ。アキノ政権からドゥテルテ政権への政権交代に伴う経済政策の先行き不透明感や、世界経済の減速による需要の低迷などが影響したものとみられる。一方、ドゥテルテ政権は国内インフラ整備計画「ビルド・ビルド・ビルド」を推進し、これが投資誘致の一因となった側面もある。
2019年以降は欧州からの再生可能エネルギー分野への巨額投資が相次いだ影響で、製造業比率は1~2割に低下した。それでも、コロナ禍以降は金額ベースで300億ペソから1,000億ペソ超へと増加し、フィリピン向け海外直接投資を下支えしている。
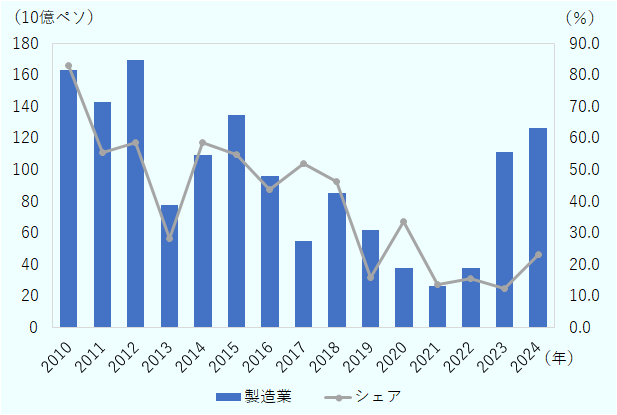
出所:フィリピン統計庁(PSA)を基にジェトロ作成
直近の製造業投資では、日系企業による既存拠点の拡張投資が中心となっている。各社のプレスリリースや報道などによると、セイコーエプソンは2017年に約1億4,300万ドルを投じ、インクジェットプリンター関連の第3工場を新設するとともに、既存工場のプロジェクター生産ラインを増設し、輸出拠点の拡大を図っている。また、トヨタ自動車は2023年にラグナ州サンタロサ工場へ総額約55億ペソを投資するほか、三菱自動車も2030年までの今後5年間で70億ペソを投資する計画を発表している。
日系企業へのヒアリングによれば、進出理由として「フィリピン経済特区庁(PEZA)の積極的な外資誘致活動と税優遇の魅力」「ASEAN諸国と比較して低コストの人件費」「駐在員が暮らしやすい環境」「日本との時差が1時間で距離も近く、英語が広く通じるため、日本との連携が容易であること」などが挙げられた。
さらに、フィリピン経済は堅調な成長を続けており、2024年の実質GDP成長率は5.7%と、ASEAN諸国ではベトナムに次いで2番目に高い水準を示した。近年は6~7%台に近い水準で推移している。需要項目別の構成(表参照)を5年ごとにみると、財・サービスの輸出は27%前後と横ばいだが、財・サービスの輸入は増加傾向にある。また、民間最終消費支出が全体の7割を超え、国内消費が経済成長を支えていることがうかがえる。近年では、内需向け製品の製造拠点拡張も目立っている。例えば、味の素はプレスリリースで、2025年9月に約91億ペソを投資し、風味調味料などを製造する第3工場を新設することを発表した。
| 項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間最終消費支出 | 77.7 | 73.5 | 73.6 | 73.6 | 72.5 |
| 政府最終消費支出 | 9.8 | 10.8 | 11.1 | 15.1 | 14.5 |
| 国内資本形成 | 16.8 | 19.9 | 22.2 | 19.2 | 23.7 |
| 財・サービスの輸出 | 27.1 | 26.4 | 25.7 | 27.1 | 26.8 |
| 財・サービスの輸入 | △ 31.5 | △ 30.5 | △ 32.6 | △ 35.1 | △ 37.4 |
| 国内総生産(GDP) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
出所:PSAを基にジェトロ作成
「エコゾーン」による外資誘致政策、魅力と課題
フィリピンでは、貿易産業省(DTI)傘下のPEZAが中心となり、輸出志向型の製造業に対して、税制優遇や手続き簡素化などのインセンティブを提供してきた。これらの優遇措置は外資企業の進出を促す大きな要因となり、同国の産業発展に寄与してきた。
その歴史は、1972年にさかのぼる。当時設立された輸出加工区庁(EPZA)は、フィリピン初の輸出加工区「バターン輸出加工区」を開設し、地方税の免除、建設資材・製造資源の輸入関税の免除、固定資産の加速償却など、外資系製造業向けの優遇措置を導入した。その後、マニラ近郊にも輸出加工区が広がり、1980年代後半から1990年代には、フィデル・ラモス政権の積極的な外資誘致政策で、集積回路やハードディスクドライブ(HDD)などのエレクトロニクス分野に、日系を含む多くの外資系製造業が進出した。
1995年にはEPZAが改組され、PEZAが新たに設立された。リリア・デ・リマ長官(当時)の下、PEZAは製造業に加えてIT-BPO産業なども対象に含め、投資奨励分野の多様化を進めた。また、経済特区の総称である「エコゾーン」については、民間主導での開発を認め、地方分散型開発を促進した。さらに、PEZA管轄のエコゾーン内では、ビザ申請や建設許可などの行政手続きを一括で受け付けるワンストップショップおよび24時間対応可能なノンストップショップなどのサービスを導入し、外資企業にとって利便性の高い投資環境を整えた。
2021年には企業復興税優遇法(CREATE法)が成立し、法人所得税率の引き下げ(30%から25%)や投資インセンティブの合理化が実施された。さらに、2024年には改正法であるCREATE MORE法が成立し、条件を満たす一部企業への法人税率の再引き下げ(25%から20%)や所得税優遇期間の延長(最長17年間から27年間)などがなされた。これらの政策は外資企業から一定の評価を受けている。ただし、この過程でCREATE法での税制改革や内国歳入庁(BIR)によるVAT(付加価値税)関連の歳入規則により、PEZA登録企業に対するインセンティブ取り扱いが不透明になった。BIRによる徴税圧力が強まり、VAT還付の遅延や税務調査による追加徴税などの課題が顕在化した。企業へのヒアリングからも、このような税務リスクは追加投資を検討する際の障壁となっているとの指摘がある。
以上のことから、フィリピン貿易構造の特徴には、輸出は米国向け、輸入は中国からという傾向がみられ、いずれも電気機器が多くを占めていることが確認された。日系企業は、言語や人材などの投資環境の魅力を理由に進出し、拡張投資を続けている。フィリピン政府はPEZAを中心に、CREATE MORE法やエコゾーンを活用して製造業への外資誘致に積極的で、企業は制度内容には大きな魅力を感じるものの、運用方法の不透明さに対して課題を抱えている。
中編では、フィリピンの輸出入で最も大きな割合を占めるエレクトロニクス産業と日系企業が進出するOA機器産業に注目し、日系製造業のヒアリングを基に輸出拠点としてのフィリピンのサプライチェーンの現状を明らかにする。
- 注:
- 本調査では2025年8~9月に、エレクトロニクス、OA機器、自動車などのメーカー、物流、メッキ加工、銀行、商社など、合計15社にヒアリングを実施。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理(執筆当時)
庄 浩充(しょう ひろみつ) - 2010年、ジェトロ入構。海外事務所運営課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ビエンチャン事務所(ラオス)、広報課、ジェトロ・ハノイ事務所(ベトナム)を経て現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課
西村 公伽(にしむら きみか) - 2024年、ジェトロ入構。アジア大洋州課でASEANおよびオセアニア関係の調査を担当。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・マニラ事務所
西岡 絵里奈(にしおか えりな) - 2016年、ジェトロ入構。途上国ビジネス開発課、ジェトロ・プノンペン事務所、ビジネス展開支援課、対日投資課DX推進チーム、ジェトロ島根を経て、2023年9月から現職。




 閉じる
閉じる






