ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応存在感を高めるASEAN
サプライチェーン潮流を見る視点(前編)
2025年10月6日
日本企業は長年にわたり、ASEANにおいて生産・流通ネットワークを築いてきた。一方、各国のビジネス環境や産業政策の変化、リスク対応の必要性から、企業は中長期的な再編を模索している。新型コロナウイルス禍によってサプライチェーンの脆弱(ぜいじゃく)性が浮き彫りとなり、米中摩擦による地政学リスクも高まっている。さらに、サステナビリティーやデジタル化への対応も急務であるほか、中国や欧米の企業の投資拡大による競争激化も進んでいる。
本特集は、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピンなどの主要産業に焦点を当て、過去20年間の貿易投資構造や主要産業の変化を整理し、各国の産業政策や企業によるサプライチェーン対応の方向性と課題を考察する。調査に当たっては、2025年7~8月に上記5カ国への現地出張と、日本本社への企業ヒアリング(約70社)を通じて実施した。
本稿は、特集総論(前編、中編、後編)として、「ASEANサプライチェーンの潮流」を見る上での視点を提示する。前編では、過去20年間でASEANが貿易・投資においてどのように存在感を高めてきたか、日本企業によるASEAN進出や現地での生産・流通ネットワーク構築の経緯を概観する。
世界の貿易投資に占めるASEANの存在感拡大
2005年以降の20年間の貿易・投資構造の変化を確認すると、輸出額、輸入額はともに大幅に増加し、貿易総額は2005年に1兆2,260億ドルから2015年には1.9倍の2兆2,730億ドル、2024年には3.1倍の3兆8,450億ドルに拡大した(表1)。
| 項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貿易額 | 1,226 | 2,001 | 2,273 | 2,670 | 3,845 |
| 輸出額 | 649 | 1,049 | 1,172 | 1,397 | 1,953 |
| 輸入額 | 577 | 952 | 1,101 | 1,273 | 1,891 |
| 貿易収支 | 71 | 97 | 71 | 124 | 62 |
出所:ASEANstatsから作成
HS2桁ベースで品目別の輸出入構成をみると、電気機器(HS85)、一般機械(HS84)、鉱物資源(HS27)が輸出入全体の約5割を占める(図1)。特に電気機器と一般機械を合わせた割合は、2010年代には輸出入ともに約3割だったが、2020年代に約4割へ拡大した。鉱物資源については、インドネシアやマレーシアを中心に、石炭、天然ガス、液化天然ガス(LNG)などを輸出する一方、国内で精製能力が十分でない国では石油製品を輸入しており、ASEANの輸出では約1割、輸入は約2割を占める貿易構造となっている。世界的な資源価格や需要の変動によって輸出入額が大きく左右する傾向がある。
図1:ASEANの品目別シェア(HS2桁ベース、上位10位)
![ASEAN輸出の品目別シェア(HS2桁ベース、上位10位)、電気機器([85])が、2005年は28%、2010年は23%、2015年は25%、2020年は29%、2024年は28%。一般機械([84])が、2005年は16%、2010年は13%、2015年は11%、2020年は11%、2024年は12%。鉱物燃料([27])が、2005年は14%、2010年は16%、2015年は12%、2020年は7%、2024年は10%。](/ext_images/biz/special/2025/1001/bb9986b33b569738/g01a.gif)
![ASEAN輸入の品目別シェア(HS2桁ベース、上位10位)、電気機器([85])は、2005年は28%、2010年は22%、2015年は23%、2020年は28%、2024年は26%。鉱物燃料([27])は、2005年は16%、2010年は19%、2015年は15%、2020年は11%、2024年は15%。一般機械([84])は、2005年は15%、2010年は14%、2015年は13%、2020年は12%、2024年は13%。](/ext_images/biz/special/2025/1001/bb9986b33b569738/g01b.gif)
出所:ASEANstatsから作成
貿易相手国・地域では、過去10年はASEANが輸出入ともに20%~25%で推移してきた(表2)。一方、対中貿易依存度は、ASEANの輸出で2005年の8.1%から2024年に14.9%へと急伸した。さらに、輸入先としては同期間に10.6%から25.4%へ急伸した。中国からの輸入額の約5割を占める電気機器(HS85)、一般機械(HS84)には家電、コンピュータ、エレクトロニクスなどの完成品に加え、部品や資本財なども含まれる。ASEAN各国の産業化の進行と現地生産の拡大に伴い、中国からの部品・資本財輸入が増加していると考えられる。
また、注目すべき点として、ASEAN輸出に占める米国の割合は、2010年代に10%以下に落ち込んだが、2019年以降再び上昇し、2024年には16.0%に達した。これは中国向け(14.9%)を上回る水準で、ASEANにとって、近年の米国との貿易関係は大幅な輸出超過の傾向が強まっている。特に米国向け輸出額の約3割超を電気機器が占めるなど全体を牽引している。一方、日本やEUは貿易相手国として引き続き重要なパートナーだが、輸出入シェアは低下している。
表2:ASEANの国・地域別貿易依存度推移 (ーは値なし)
| 国・地域名 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN | 25.3 | 25.2 | 24.5 | 21.3 | 22.5 |
| 米国 | 14.3 | 9.5 | 10.7 | 15.1 | 16.0 |
| 中国 | 8.1 | 10.7 | 12.4 | 15.7 | 14.9 |
| EU27 | — | — | 9.4 | 9.3 | 8.5 |
| 日本 | 11.2 | 9.8 | 8.7 | 7.4 | 6.2 |
| 香港 | 5.5 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 5.7 |
| 韓国 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.1 |
| 合計(10億ドル) | 649 | 1,049 | 1,172 | 1,397 | 1,953 |
| 国・地域名 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 10.6 | 12.9 | 19.8 | 23.5 | 25.4 |
| ASEAN | 24.5 | 25.0 | 22.5 | 21.1 | 20.3 |
| 米国 | 10.6 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| 韓国 | 4.1 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 6.8 |
| EU27 | — | — | 8.3 | 7.6 | 6.7 |
| 日本 | 14.0 | 12.2 | 9.2 | 8.0 | 6.1 |
| 香港 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
| 合計(10億ドル) | 577 | 952 | 1,101 | 1,273 | 1,891 |
出所:ASEANstatsから作成
ASEAN10カ国の外国直接投資(FDI)の受入額(ネット、フロー)は順調に拡大し、2024年には 2,260億ドルに達した。2017年に1,500億ドルを超えて以降、ASEAN向け投資は顕著な増加傾向を示している。世界的に地政学的リスクや不確実性が高まる中でも、海外直接投資においてASEANは存在感を高めている。
投資元の国・地域別では、米国、EU、中国からの投資が急増している(図2)。2021年から2024年の米国投資では、金融・保険分野が約7割を占め、製造業も2割を占めている(図3)。投資案件としては、データセンター、再生可能エネルギー、半導体といった先端分野での進出が目立つ。中国企業による投資拡大も顕著で、従来中心だった不動産や建設に加え、製造業への進出が増加しており、特に自動車やエレクトロニクス分野で積極的な動きが見られる。
このように、ASEANは低コストの生産拠点から、グローバルな供給先として多様な生産ハブへと発展するほか、高付加価値を生み出す供給拠点としての地位を確立しようとしている。
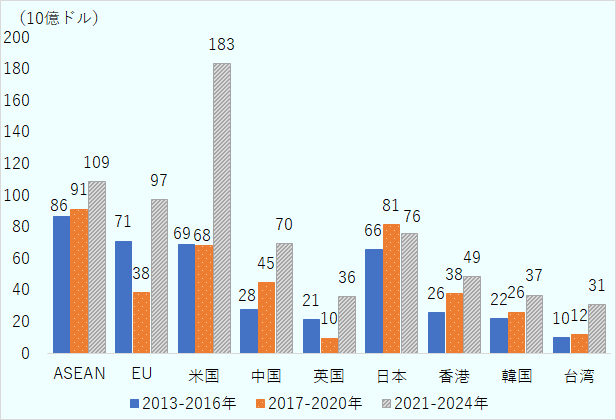
出所:ASEANstats
図3:日本・米国・中国企業によるASEAN向け投資の業種別内訳(10億ドル)
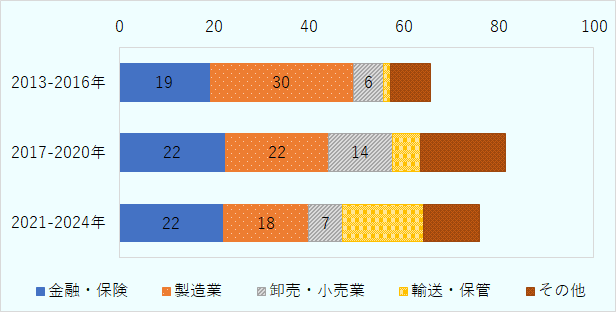
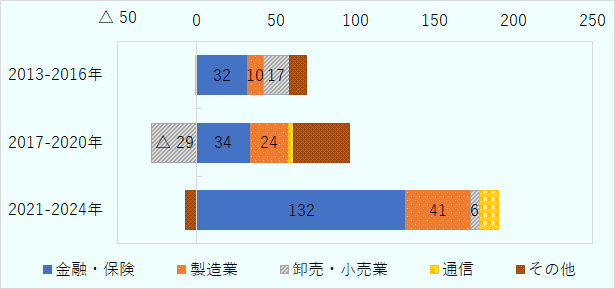
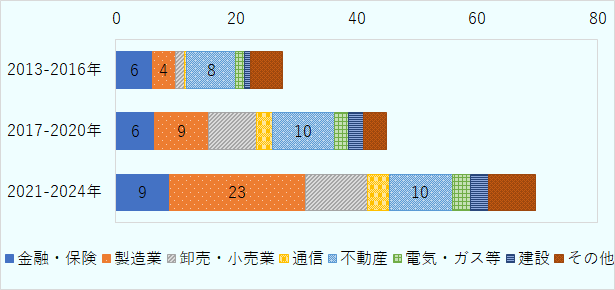
出所:ASEANstats
ASEANで深化する日本企業の生産・流通ネットワーク
日本企業は製造拠点、または消費市場として、長年にわたってASEANに進出し、生産・流通ネットワークを構築してきた(図4)。1985年のプラザ合意以降、日本企業はASEANで生産拠点進出を加速させ、現地の製造業振興や人材育成に貢献してきた。1990年代後半から2000年代にかけては、中国が「世界の工場」として台頭することで、相対的に存在感が薄れていた時期もあった。しかし、2000年代中盤から後半にかけて、中国での人件費上昇や中国一極集中へのリスク分散の必要性から、ASEANを中心とした東アジア地域での生産・流通ネットワークの再構築が進んだ。2015年末のASEAN経済共同体(AEC)の発足や周辺国との自由貿易協定(FTA)の締結も生産・流通ネットワークの再編を加速させた。
この過程で、日本企業は、中国一極集中を回避する「チャイナ・プラスワン」戦略やタイでの労働力不足・賃金上昇に対応して、カンボジアやラオスなどで垂直的分業を促進する「タイ・プラスワン」戦略なども採用した。また、ASEANの経済発展や消費市場の拡大により、それまでの安価で豊富な労働力を生かした労働集約型拠点としての役割から、消費市場としての魅力も増し、現地での消費需要に応えることを目的とした生産拠点設立も進んだ。このように、外部要因や国際情勢の変化に対応するかたちで、ASEAN進出企業は域内での生産・流通ネットワークの再編を進めてきた。
2018年以降、ASEANを取り巻く事業環境は、さらに大きく変化している。米中貿易摩擦の影響で地政学的緊張が顕在化し、サプライチェーンの強靭(きょうじん)化や多角化への意識が高まった。米国の対中関税を回避するため、中国拠点からASEAN拠点への輸出向け生産シフトも鮮明となった。これは、中国市場向けには国内生産を維持しつつ、ASEANへの進出を含む海外拠点を活用する「チャイナ・フォー・チャイナ」の動きだ。主に中国、台湾や欧米のグローバル企業などによるものだが、日本企業でも東アジア地域で既存の複数拠点間での生産調整やリスクヘッジを進める動きが見られる。
図4:ASEANへの日系企業進出経緯と取り巻く環境の変化
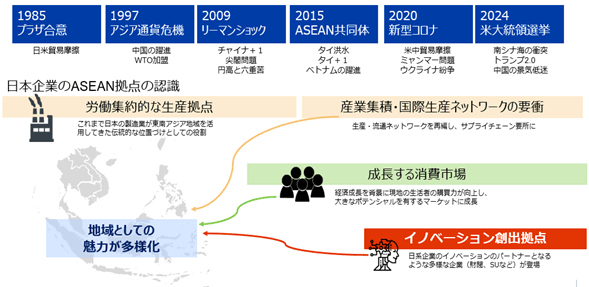
出所:ジェトロ作成
国境を越えた細かな分業体制と多様なリスク
東南アジアでの日本企業の生産・流通ネットワークの構築は、過去数十年にわたって進化・深化してきた。特に注目すべきは、生産工程レベルでの極めて細かい国際分業体制が形成されてきたことにある。ASEAN各国や中国も含めた東アジア広域で、各国の生産コスト、技術力、産業集積などの比較優位に基づき、国境を越えて生産を分担する体制が整備されてきた(図5)。
「垂直分業」では、上流工程では部品や中間財が生産され、国境を越えて移動した後、下流工程で加工・組み立てが繰り返され、最終製品として完成する。例えば、高度な技術を必要とする部品生産は日本や韓国が担い、中国で製造された部品と合わせて、労働集約的な組み立て工程をタイ、ラオスなど新興国が担うといったものだ。一方、同一工程を複数地域に配置する「水平分業」は、市場ニーズや所得水準に応じ、高価格帯製品は中国で、廉価品はベトナムで生産するなど、すみ分けを行うものだ。従来、このような分業体制は、企業が最適な拠点立地を追求し、効率的な生産・販売ネットワークの構築を模索して構築されてきた。企業は、物流コストや人件費、技術水準、市場アクセスといった要素を検討し、各国の産業政策とも連動しながら、地域全体のサプライチェーンが形作られた。
しかし、こうした国境を越え、細分化された分業ネットワークは、多様なリスクにさらされている。地政学的緊張や政変、感染症の世界的流行、自然災害、さらには、米国をはじめとする主要国の通商・関税政策といった要因が供給網の分断や遮断を引き起こす可能性がある。ASEANの進出企業は、これまで効率性を重視してネットワークを構築してきたが、近年はリスク分散や強靱性の確保といった課題への対応が求められている。企業によるサプライチェーン強靭化・多元化の対応事例は後編で紹介する。
図5:リスク回避のため柔軟なサプライチェーン構築を模索
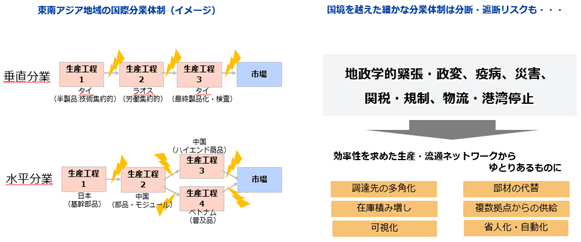
出所:ジェトロ作成
主要産業でのサプライチェーンの変化
ASEAN各国では、外国企業の投資や政策的誘導を背景に、主要産業の生産が進展し、グローバル拠点として世界市場への輸出が展開されている。本特集では、その中から以下の主要産業を取り上げる。
(1) エレクトロニクス・ICT(情報通信技術)部品
スマートフォンをはじめとするエレクトロニクス製品の生産が拡大している。例えば、ベトナムでは2010年ごろから韓国のサムスンが携帯電話の生産と輸出を拡大するとともに、部品サプライヤーの進出で部品輸出も増加した。また、2010年代後半からはEMS(受託製造)企業がパソコンなどの輸出主導型生産を強化してきた。半導体・電子部品では、PCBやモジュールの生産拠点の設立が顕著だ。タイでは、中国や台湾の企業がPCBや電子部品分野での投資を拡大している。
(2) 自動車・EV
ASEANでの自動車産業の集積では、タイとインドネシアが2大拠点として生産体制を整えてきた。自動車サプライヤーまでを含めた産業基盤では、タイが圧倒的な集積を誇り、その中心的な担い手は日本の自動車・同部品メーカーだ。近年、ASEANで電気自動車(EV)の市場が徐々に立ち上がる中、EV生産・バッテリー関連の誘致競争が進み、中国のBYD、長城汽車(MD)などが現地生産を開始するなど、競争環境に変化が見られる。
(3) 繊維・アパレル
労働集約型産業の繊維産業では、2000年代以降、中国の生産基地が強化されてきたが、東南アジアでもベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシアなどを中心に、低コストの人件費や各国が締結するFTAを活用し、生産拠点を拡大してきた。日本企業は主に日本市場向けに製品を供給する一方、欧米系アパレルは世界市場向けに輸出している。近年では、各ブランドによる中国依存からの脱却を目指し、縫製工場や副資材メーカーがベトナム等に進出するとともに、台湾や韓国の合繊メーカーも参入している。
(4) 鉱物資源
インドネシアは世界最大規模のニッケル埋蔵量を持ち、「下流化政策」の一環として鉱物資源を国内で加工・精錬し、付加価値を高めるために、ニッケルの未加工品の輸出を禁止している。これに対応するかたちで、中国企業が精錬工場へ投資をして、稼働させた結果、ニッケル製品の輸出が拡大している。
サプライチェーン潮流を見る視点

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課長
藤江 秀樹(ふじえ ひでき) - 2003年、ジェトロ入構。ジェトロ・ジャカルタ事務所(10~15年)、海外調査部アジア大洋州課(15~18年)、シンガポール事務所(18~22年)などを経て、2024年9月から現職。編著に「インドネシア経済の基礎知識」(ジェトロ、2014年)、「分業するアジア」(ジェトロ、2016年)がある。




 閉じる
閉じる






