ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応自動車産業の現在地、グローバル供給網と日系の対応
タイ(2)
2025年11月12日
タイの自動車産業は、域内分業を進めながら、世界に向けて完成車輸出を拡大してきた。しかし、国内市場の低迷や中国企業の台頭、輸出先での炭素排出規制の導入などにより、事業環境は変化している。
日系企業へのヒアリングも踏まえ、タイの自動車産業の変化と日本企業の対応を含めた今後の展望を考察する。
世界的な自動車部品供給拠点へ
Global Trade Atlas(GTA、注1)によると、2024年のタイの自動車部品(HSコード8708)の貿易額は1兆5,257億ドルだ。2004~2024年に年平均3%ほどで拡大した。また、2014年以降は貿易黒字も拡大している。タイは国境を越えた自動車サプライチェーンに組み込まれ、輸出競争力を高めてきたと言えよう。
2024年の同品目の輸出先を見ると、米国、マレーシア、日本、南アフリカ共和国、インドネシア、アルゼンチン、メキシコ、ベトナムの順に多い。過去20年を通じ、いずれの国への輸出額も拡大している。
このうち、2010年代から米国への輸出拡大が目覚ましい。米国向けの主な品目には、車輪のほか、ギヤボックスや駆動軸などを含む。自動車用ゴムタイヤ(注2)も2015年以降、拡大している。
一方、2004~2024年、ASEANを以上に輸出の伸びが大きかったのは、アルゼンチン(約77倍)とメキシコ(約340倍)だ。メキシコとの当該品目貿易で、2000年代はタイの輸入超過が続いた。しかし、2014年からタイの輸出超過に転じた。これら中南米には、ギヤボックス、ハンドル、エアバッグなどの輸出が拡大している(図1参照)。
タイは、東アジアを越えて、グローバルな自動車部品の生産・供給拠点に発展してきたと言える。
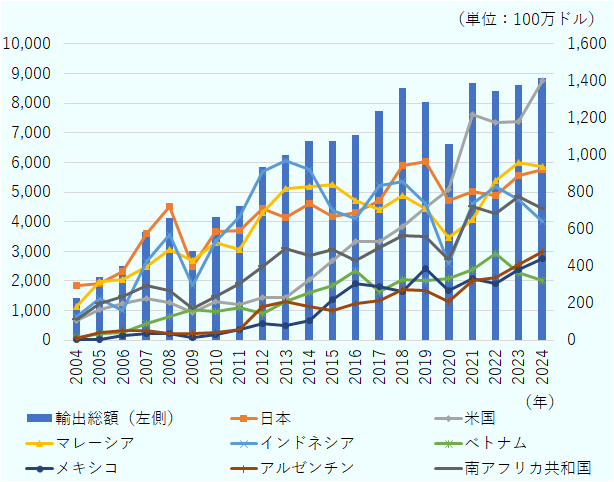
出所:GTAからジェトロ作成
しかし、2013年以降、中国からの輸入が増加。特に2021年以降、同国との間で貿易赤字が拡大している(図2参照)。
タイでは、上海汽車(SAIC)が2013年、長城汽車(GWM)が2021年、当地に工場を設立。その後も、複数の中資系の電気自動車(EV)メーカーが追随した。中国からの部品輸入が拡大した背景には、こうした中国企業のタイ進出がある。貿易均衡の改善や地場サプライヤーの高度化に向けて、進出済み中資系企業による部品現地調達率の向上が必要だ。
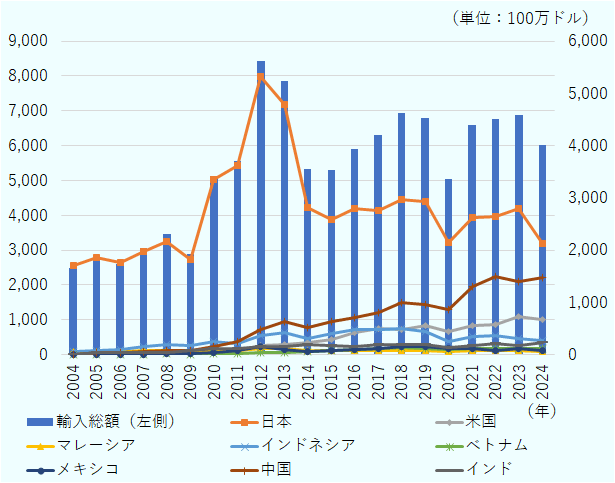
出所:GTAからジェトロ作成
完成車輸出が拡大
タイの2024年の主要輸出品目(HS4桁)で、(1)乗用車の輸出額は第2位、(2)ピックアップトラックは第7位だ。2004~2024年の期間(1)の輸出は年平均13.2%増、(2)は6.2%増だった。特に乗用車の成長が顕著なことがわかる。主な輸出先の国・地域はオーストラリア、ASEAN、中東となっている。
輸出拡大の背景には、タイの産業振興策がある。エンジン国産化の奨励は、国産エンジン搭載の輸出拡大につながった。2003年にはタクシン・チナワトラ首相(当時)が「アジアのデトロイト」構想を発表し、自動車生産台数の拡大を表明した。
一方、政府は2017年以降、それまで生産を強化してきたピックアップトラックやエコカー(注3)に加え、EVを次の主力輸出品目と位置づけた。同政策の下、補助金や税制優遇措置を付与し、複数の中国EVメーカーがタイに進出した(既述)。
HEV生産拠点化を目指す日系企業
日系自動車メーカーは総じて、タイを自動車・部品の重要な生産・輸出拠点と位置付けている。ある日系自動車メーカーは「当地拠点では、エンジンのほか、電動化部品を含む多種多様な品目を生産し、グローバルに供給している」と述べる(注4)。
また、完成車については、2030年ごろまでは販売を見込めるガソリン車(ICE)とハイブリッド車(HEV)で利益を確保しつつ、バッテリー式電気自動車(BEV)市場への本格参入のタイミングを見極めている。複数の日系自動車メーカーが実際、HEV生産拠点としてのタイの重要性に言及した。
状況は各社で異なる。それでも、タイは海外拠点の中で既にHEVの一大生産拠点となりつつあるという。その理由の1つは、HEV販売の好調だ。タイでのHEV販売台数は2024年、約13万台(前年比49.9%増)。BEVの約7万台、プラグインハイブリッド車(PHEV)約9,000台と比べ、明らかに市場が大きい。当地からのHEV輸出台数も2024年は前年比で約3.3倍と好調だ。台頭する中国企業に対しても、HEVは日本企業にとって対抗馬になる。ある日系自動車サプライヤーは「エンジンの燃焼効率など、HEV技術では引き続き日系に強みがある」と指摘。中国企業はバッテリー管理システムに強みを持ち、PHEVやBEVに注力すると推測する。
では、BEVへの対応はどうか。日系企業は総じて、市場動向を見極めタイ政府との連携を保ちつつ、品質やアフターサービスを強みに対応しようとしている。タイのBEV新規登録台数は、2024年にいったん落ち着いた。それが、2025年上半期には前年同期比52.0%増。再拡大に転じたかたちだ。特に中国ブランド車は、タイ政府の補助金を活用しつつ、価格競争力とデザイン性を兼ね備える。その結果、都市部の若い世代を中心に支持を集め、シェアを伸ばしている。日系OEMの中でも、「タイで戦えるBEVモデルの投入が必要」という議論が従前より広まりつつある。しかし、中国メーカーとの価格競争や、充電設備の不足、相対的に高価なBEV向け自動車保険料など、懸念事項は多い。また、周辺国に自国でのBEV生産を企業に求める動きがあることも、念頭に置く必要があるだろう。効率的な生産分業体制の確立が大きな課題になる。
サプライチェーンリスク対応が分業の足かせに
在タイ日系自動車メーカーやサプライヤーは、 (1)在庫の積み増し、(2)調達先の多元化(複数購買)、(3)現地調達の向上など、事業継続計画(BCP)対策を講じてきた。例えば(2)としては、部品ごとに調達先を分散し、常に代替供給できるようにしておく例が見られた(注4)。
このような対策を講じるようになった背景には、2011年のアユタヤ大洪水や東日本大震災を経て得た教訓がある。加えて、新型コロナウイルス禍が企業のBCP対応を加速した。ある日系企業は新型コロナ禍以降、「取引先を慎重に審査し、安定した供給網の確立などの基準を満たす相手と取引するようにした」と述べる。その他、「調達先を複数確保できない場合、在庫を積み増して途絶リスクに備える」という声もあった。
さらに2025年には、米国が世界69カ国・地域に対する相互関税や、自動車・部品への追加関税を打ち出した。在タイ日系企業には、その懸念もなくはない。もっとも、当地日系自動車企業の対米輸出額は多くない。そのため、影響は比較的間接的だ(注5)。主な対応は、拠点の新設や再編ではなく、既存サプライチェーン内の調整にとどまっているようだ。
いずれにせよ、同一品目を複数購買したり、複数拠点で生産したりする動きが進んできたと言えるだろう。換言すると、リスクヘッジ型の「ジャストインケース」対応を志向するようになってきた。
一方で、従来は「ジャストインタイム」の生産体制を構築。生産拠点の最適配置に基づいて、効率的な域内分業を追求してきた。換言すると、ASEANで自動車部品の水平分業が拡大してきた。その背景には、自動車部品相互補完スキーム(BBCスキーム、1988年)がある。同スキームにより、日系自動車メーカーは国境を越えて工程ごとに細かく分業する体制を長年とってきた。その帰結として、「タイではディーゼルエンジン」「フィリピンではトランスミッション」「マレーシアではステアリング部品」など、複数国にわたる補完体制を確立するに至った(注6)。さらに、その後のASEAN物品貿易協定(ATIGA)などを通じて、域内分業の発展と商品価格の低下に貢献してきた。
(1)従来の「ジャストインタイム」と、(2)新たな「ジャストインケース」は、相反する面もある。(1)は、従来のコスト重視で効率性の良い分業を実現しやすいものの、分断・途絶リスクに脆弱(ぜいじゃく)だ。一方で、昨今の不透明なビジネス環境では、(2)のリスクヘッジ型サプライチェーンが意味することも大きい。両者の間で、柔軟かつバランスの取れた対応こそが必要と言えそうだ。
国内市場の縮小が懸念材料
在タイ日系企業が共通して懸念するのは、タイの自動車市場の先行きだ。
タイの自動車販売は2024年、約57万台(前年比26.2%減)だった。家計債務上昇に伴って、自動車ローンの審査が厳格化した影響が大きい。今年に入ってからも、足元の低迷が続いている。中長期的にも、既に人口ボーナスを過ぎつつあるタイは、少子高齢化によって国内市場が縮小していく見込みだ。成熟市場だけに、タイ市場の成長性はインドネシアやベトナムと比べて劣る。
タイが自動車の生産・輸出・研究開発の拠点であり続けるためには、輸送コストがかかる大型部品を多く扱い、地産地消型の産業を展開する必要がある。つまり、十分な現地市場の確保が不可欠だ。
もちろん、タイが日系企業にとって依然として魅力的な投資先ということは間違いない。まず、自動車産業の集積があるため、地場サプライヤーを育成済み。圧倒的な現地調達率の高さを誇る。この点は、周辺国と比べて大きな強みだ。また、タイ政府が日系産業界の要望を真摯(しんし)に聞き入れる姿勢に対する評価も、高い。
実際、ジェトロのヒアリングによると、タイ工業省やタイ投資委員会(BOI)の担当者は、日系企業と意見交換している。また、今後もHEV向けの新たな支援策を公表する可能性に言及した(2024年12月聴取)。
しかし、こうしたタイの投資環境上のメリットは、日系企業を中心に裾野の広い自動車産業の集積があるが故に享受できる。国内市場が縮小したり、非日系ブランドが市場シェアを拡大したりすると、日系企業の現地プレゼンスや、サプライチェーンに影響を与える可能性がある。
日系企業には、これまで蓄積してきたストック(産業集積)を生かし、いかにサプライチェーンを守り強化するかが問われている。
新たなソリューション提供に期待
日系企業は、数十年にわたって自動車の組み立て実績を積み重ねてきた。その結果、技術移転から管理・監督まで、基本的な領域で対応がほぼ完了済みと思われる(注7)。今後一層の高度化に向けた課題は、(1)基幹部品の国産化、(2)研究開発機能の拡大、(3)エンジニアの育成などだろう。また、輸出先の多様化に向け、タイ政府が自由貿易協定(FTA)を充実していくことも、重要な戦略になる。
一方で、国内市場の低迷や非日系企業との競合など、日系企業を取り巻く事業環境は依然として厳しい。しかし、日系企業が蓄積してきた技術・ノウハウは、タイの産業高度化に大きく貢献できる可能性がある。今後は完成車や部品の供給だけでなく、環境対応や社会課題へのソリューション提供、人材育成など、産業全体への多様な貢献に期待が集まるだろう。日系企業にとっては、技術力と現地ネットワークを生かした戦略的対応が、今後のカギになる。
- 注1:
- GTAは、商用の貿易統計データベース。出所は、各国の通関統計。
- 注2:
- 自動車ゴムタイヤ(HSコード:4011)は、自動車部品(同:8708)には含まれない。しかし、実績の変動が大きい品目ため、本稿で特別に言及した。
- 注3:
- エコカーの支援は、低価格、低燃費、低公害の小型車の生産・輸出を促進することが目的。トヨタのヤリス、ホンダのブリオ、三菱自動車のミラージュなどを対象にしている。欧州の排気ガス規制に呼応し、認可にあたっては排気量の大きさで対象モデルを選定した。
- 注4:
- 在タイ日系自動車産業のサプライチェーン対応を調査するため、ジェトロは現地日系企業にヒアリングした(2025年8月)。
- 注5:
- ジェトロによる日系企業へのヒアリング調査による(2025年8月)。
- 注6:
-
トヨタ自動車ウェブサイト「75年史(東南アジア)
 」参照。
」参照。
- 注7:
- 「タイ国経済概況(2024/25年版)」(バンコク日本人商工会議所、2024)所載の『自動車産業』章(293~308ページ)参照。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理
田口 裕介(たぐち ゆうすけ) - 2007年、ジェトロ入構。アジア大洋州課、ジェトロ・バンコク事務所を経て現職。






 閉じる
閉じる





