ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応変化する貿易投資構造と、求められる製造業の高度化
タイ(1)
2025年11月12日
タイは、外資奨励政策によって経済・産業を発展させてきた。しかし、地政学リスクの変化や中国企業の台頭などがそのサプライチェーン構造に変化をもたらしている。貿易統計を軸に、タイの経済産業の変遷を振り返る。
米中との貿易が拡大
タイの貿易総額と主要国・地域別シェアの推移を見てみよう(図1参照)。貿易総額は2000年から2024年にかけて年平均6.5%で成長し続け、世界との貿易が拡大してきた。2002年以降は、国・地域別でASEANのシェアが一貫して最も高く、2割前後を占めている。しかし、伸びが目覚ましいのは中国だ。2000年の4.7%から、2024年の19.1%に拡大。また、米国も、2018~2024年に8.6%から12.2%に拡大した。一方、日本は、2000年には19.5%と最も高かったのに対し、その後は減少傾向にある。2024年は8.6%で、2000年比で約6割減少した。
輸出に限ると、米国のシェアは2024年に18.3%を占めた。やはり、2018年以降に急増している。ASEANを除く国・地域の中では最も高い。輸入では、2000年時点でわずか5.5%だった中国のシェアがその後一貫して拡大し、2024年には全体の3割弱を占めるまでに至った。2000年代以降、タイは輸入超過が続き、この傾向は2019年以降さらに顕著になった。その結果、タイの世界との貿易収支は2022年以降、貿易赤字になっている。
米国と中国との存在感が高まった背景の1つには、地政学リスクへの対応がある。米国では2017年、ドナルド・トランプ第1次政権が発足し、両国の対立が激化した。それ以降、中国や台湾企業が主に北米市場向け製品の生産などを念頭に、中国からASEANへ生産拠点を設置する動きを見せている。これらの動きが中国からの輸入や、米国への輸出拡大を後押ししたと考えられる。
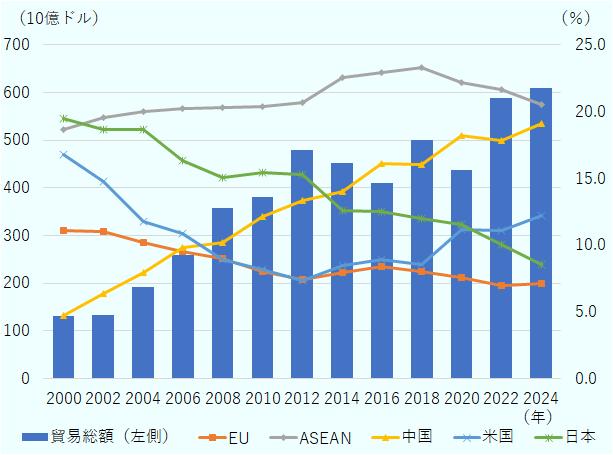
出所:貿易統計データベース「グローバル・トレード・アトラス(GTA)」からジェトロ作成
主要貿易品目の輸送機器とエレクトロニクス
2024年の輸出総額に占めるシェアが高い上位品目(HS2桁ベース)は、電気機械(17.1%)、一般機械(15.9%)、輸送機器(11.2%)だ(図2参照)。特に輸送機器は2000年時点でわずか3.6%だった。それが、2024年に11.2%まで拡大した。2016年のピーク(12.7%)以降は横ばいながら、依然として輸出全体の約1割を占めている。電気機械も注目される。2013年まで減少傾向だったものの、その後2014年から拡大に転じた。2020年以降は成長がさらに加速。2022年には、それまで首位だった一般機械を抜いて、輸出シェアでトップになった。
輸入については、2000~2024年の間、一般機械が微減、輸送機器が横ばいで推移する。一方、電気機械は異なる動きを示した(図3参照)。電気機械は2000年(25.3%)から減少傾向を示していたが、2013年(14.8%)に底を打つと、2014年から再び拡大に転じた。2024年は21.2%までシェアを戻している。
これらの動きから、輸送機器は長期的に、電気機械は2010年代以降、世界との貿易を拡大させてきたことがわかる。例えば、輸送機器では、東アジアを越えて北米、中南米、南アフリカ共和国まで自動車部品の輸出が拡大した。タイは国際的な部品供給拠点としての役割を担っている。一方、近年は中国自動車メーカーのタイ進出などを背景に、中国からの自動車部品の輸入も拡大している。
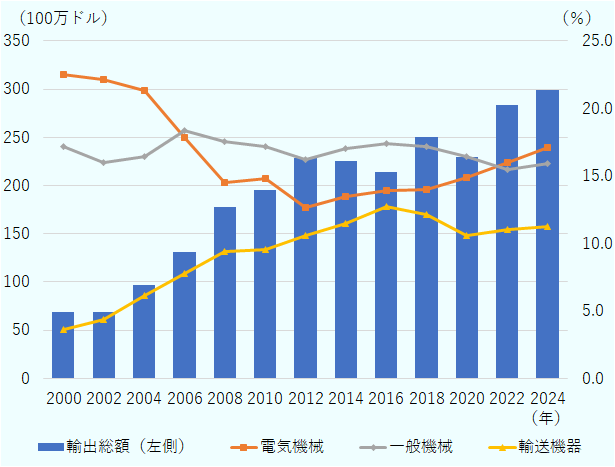
出所:GTAからジェトロ作成
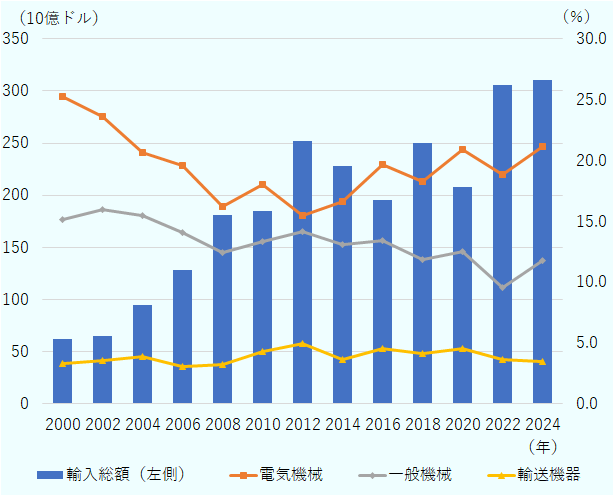
出所:GTAからジェトロ作成
中国・台湾の製造業投資が拡大
タイ投資委員会(BOI)によると、2024年のタイへの外国直接投資(FDI)認可額は、7,271億500万バーツ(約3兆4,174億円、1バーツ=約4.7円)。前年比30.1%増だった。この金額はデータをさかのぼることができる1995年以来、最も多い(表参照)。
国・地域別にシェアの推移を見るが。2014年時点では、日本が37.6%で最大だった。2024年は8.6%で、大幅に縮小している。一方、同期間に最もシェアを拡大させたのは台湾だ。2014年の0.7%から2024年の7.1%へと拡大した。また、2024年に国・地域別で最も高いシェアを占めたのは、ASEAN(32.4%)になる。もっとも、そのほとんどがシンガポールからのため、国別ではシンガポール(30.9%)、次いで中国(24.0%)が高くなる。特に2019年以降、中国からの投資が急増し、2023年に初めて金額とシェアともに、日本を上回った。なお、タイ政府によると、シンガポール経由の投資には同国に拠点を置く中資系企業を含む。そのため、実質の中国のシェアは、さらに大きくなる。
輸送機器とエレクトロニクスで、サプライチェーンに変化
日本によるタイへの投資は、1980年代以降に本格化。エアコンや冷蔵庫、自動車電装部品などの製造拠点が集積してきた。特に自動車の電化や現地調達ニーズの高まりを背景に、電気・電子部品産業の集積が進展した。また、自由貿易協定(FTA)の活用により、ASEANやインド向け輸出でも競争優位性を維持。タイは依然として日本企業の主要な製造・輸出拠点としての地位を保っている。
こうした中、昨今拡大する中国や台湾の投資は、どの産業に向かっているのだろうか。2024年の産業別投資認可額を見ると、中国と台湾はいずれも「機械・輸送機器」と「エレクトロニクス」向けが最も多い。この2分野への投資額合計では、中国からのFDIの48.3%、台湾の85.0%を占める。具体的には、米中対立などの地政学リスクが高まる中、中国や台湾の大手プリント回路基板(PCB)メーカーがタイへの分散投資を決断し、タイがPCBの新たなグローバルハブへとなりつつある。BOIによると、特に2023年以降、PCB関連のタイへの投資申請が飛躍的に拡大した。また、自動車分野では、タイ政府の産業振興策などを背景に、中国の大手自動車メーカーがタイで電気自動車(EV)を生産している。
従来、タイの製造業には、日本企業が多く投資していた。現在では、中国や台湾と投資領域が重複する。日本企業にとっては、製品価格や人材獲得での競争対応が課題になるだろう。
| 国・地域名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 484 | 494 | 358 | 227 | 256 | 282 | 252 | 281 | 314 | 559 | 727 |
| 日本 | 37.6 | 30.2 | 22.2 | 39.5 | 36.6 | 31.2 | 25.5 | 26.2 | 15.9 | 11.7 | 8.6 |
| EU | 15.4 | 9.6 | 10.8 | 18.6 | 12.5 | 10.1 | 11.8 | 12.0 | 10.0 | 8.1 | 11.8 |
| 米国 | 10.4 | 6.5 | 7.1 | 2.4 | 7.1 | 5.2 | 5.4 | 12.2 | 10.4 | 15.7 | 4.2 |
| 香港 | 3.9 | 5.6 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 7.3 | 3.6 | 9.8 |
| ASEAN | 3.8 | 22.3 | 9.0 | 15.8 | 25.7 | 10.6 | 8.6 | 11.8 | 11.8 | 18.2 | 32.4 |
| 台湾 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 10.1 | 6.2 | 6.4 | 14.5 | 8.5 | 7.1 |
| 中国 | 7.9 | 5.7 | 15.0 | 5.0 | 12.8 | 26.2 | 22.1 | 17.0 | 12.8 | 22.3 | 24.0 |
注:投資認可ベース
出所:タイ投資委員会(BOI)からジェトロ作成
産業高度化に向けた外資誘致と産業政策
前段では、統計からタイの貿易投資構造の変化を確認した。では、タイ政府はいかにして産業を誘致しようとしてきたのか。
まず、タイの外資誘致政策を担ってきた中心機関は、首相府傘下のタイ投資委員会(BOI)だ。BOIは投資戦略の策定や、投資案件の認可、恩典の付与を担う。特に外資企業のタイ進出が拡大したのは、ドル高是正のための「プラザ合意」(1985年)や、東部臨海工業地帯の開発を本格的に開始した1980年代後半だ。重工業・輸出志向型企業が進出し、タイは同時期に平均9%以上の高い成長率を遂げた。その後、レムチャバン港が1991年に開港すると、電気・電子産業を中心に工業化がさらに進展した。そして、アジア通貨危機(1997年)を経て、外資流出を抑制するため、外資規制の緩和(外資による出資比率の拡大など)を加速した。
一方、2000年代以降は、リーマン・ショック(2008年)、アユタヤ大洪水(2011年)、政府の自動車購入支援策(2012年)による需要の先食いが成長を押し下げた。成長率は鈍化し、政府は産業高度化にかじを切る。いわゆる「中所得国のわな」からの脱却が意識され始めた。そして、少子高齢化による労働力減少、周辺国との投資誘致競争、気候変動への対応など、さまざまな課題に対応すべく、政府は「20カ年国家戦略(2018~2037年)」を制定。安全・繁栄・持続可能な社会の実現と、2036年の先進国入りを目標にした。
このような状況下、政府はさまざまな構想を打ち出してきた。イノベーションや産業高度化を目指す方向性をビジョン化したのが、「タイランド4.0」構想になる。この構想の下、EVや半導体を含む先端産業の誘致を奨励している。また、サステナビリティーや外的要因への強靭(きょうじん)化を目指す戦略が「バイオ・循環型・グリーン(BCG)経済モデル」だ。これがタイの最上段の国家戦略で、近年の産業政策の方向性を示している。BOIも、同戦略の下で「新5カ年投資奨励戦略(2023~2027年)」を公表している(参考参照)。この戦略では、(1)サプライチェーン強靭化に資する新産業の誘致や既存産業の高度化、(2)産業のスマート化・サステナブル化、 (3)地域統括拠点としてのタイの機能強化に焦点を当てている(参考参照)。
参考:「新5カ年投資奨励戦略(2023~2027年)」7つの投資奨励方針
- サプライチェーン強靭化に資する新産業の構築/既存産業を高度化
- 産業のスマート化/サステナブル化
- 国際ビジネス拠点/地域の貿易投資のゲートウェーとしてのタイの機能強化
- 中小企業/スタートアップの競争力強化
- タイ国内各地域の特性を踏まえた投資の奨励と均衡ある発展
- 地域社会(コミュニティー)発展につながる投資の奨励
- 競争力のあるタイ企業の海外投資支援"
出所:BOIの資料からジェトロ作成
製造業の強化と、新たな懸念への対応
サプライチェーンの変化を議論する上で、タイの経済構造における製造業の位置づけについても触れたい。
世界銀行によると、製造業がタイのGDP(生産側)に占める割合は、1960年の調査開始以降、年平均1.78%で増加。2010年に30.9%でピークに達した。農業や軽工業中心の経済から、工業・輸出主導型経済へと転換したことがうかがえる。
その後は低下傾向に転じ、2024年は24.3%になった。また、GDPでの製造業の成長率も、1988年の17.9%をピークに減少傾向にある。アユタヤ大洪水や新型コロナウイルス禍など、サプライチェーン途絶に関わる危機的状況で大きくマイナス成長を経験した。さらに、2023~2024年も、新型コロナ禍で高騰した家計債務の高止まりで、自動車などの耐久財の消費不振に陥った(2023年に2.7%減、2024年0.5%減)。サプライチェーンの強靭化と、製造業の高付加価値化が不可欠だ。
しかし、2025年1月に誕生した米国のトランプ第2次政権は、69カ国・地域に対する相互関税、また、自動車・同部品への追加関税を打ち出している。先述のとおり、米国は2024年時点で、タイの国・地域別の輸出先として約2割を占める。また同年、タイは最も多く自動車部品(HSコード8708)を輸出する国で、新型コロナ禍以降、米国への同品目の輸出が拡大している。国内の自動車消費が低迷する中、米国の関税政策は、タイの輸送機器関連企業の生産や輸出に深刻な影響を与える可能性がある。
まとめ
本稿では、地政学リスクやタイ政府の産業振興策などを背景に、外国企業が半導体やEV、デジタルなどの分野でタイ進出を強めていることを確認した。主な投資元は中国、台湾、米国で、これは、産業高度化を目指す政府方針とも合致している。
一方、タイでは従来、日本企業が圧倒的なプレゼンスを発揮してきた。新たなプレーヤーの台頭は、競争環境の大きな変化を意味する。日本企業が自らの強みを再確認し、戦略を練る必要がある。また、タイにとっても、米国の追加関税政策や、中国からの安価な製品流入による国内産業への影響は大きな懸念材料になる。製造業の高付加価値化、強靭(きょうじん)なサプライチェーンを構築するため、政府と企業、双方の対応が不可欠だ。
この点については、本シリーズの第2弾以降で触れる。特に、貿易投資が拡大する「輸送機器」と「エレクトロニクス」に絞り、日系企業へのヒアリングも踏まえて概説する予定だ。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理
田口 裕介(たぐち ゆうすけ) - 2007年、ジェトロ入構。アジア大洋州課、ジェトロ・バンコク事務所を経て現職。






 閉じる
閉じる





