多国間主義に瓦解の兆し―試されるグローバルビジネスの耐性どう向き合う?世界揺るがす中国EVの「過剰生産能力」と「競争力」
2025年10月22日
国際通商秩序が大きく揺らぐ中、米国の追加関税政策と並んで注目を集めるのが、中国企業による過剰生産能力の問題だ。電気自動車(EV)や半導体など先端産業にまで広がるこの構造的な課題は、価格競争を伴って世界市場に波紋を広げ、日系企業が優位だった市場を脅かしている。特にASEANでは、中国メーカーのEVの急速な普及が進み、かつての「日系の牙城」が崩れつつある現実が浮き彫りとなっている。本稿では、通商摩擦の背景にある中国企業の技術革新と戦略、日本企業が直面する課題と対応の方向性を多角的に分析する。
中国企業の攻勢が日系企業の脅威に
2025年に歴史的な転換期を迎えた国際通商秩序の中で、世界各国に大きな衝撃を与えているのは、米国の第2次トランプ政権による一連の追加関税政策だが、もう1つの大きなトピックは、中国企業の過剰生産能力の問題だ(2025年9月29日付地域・分析レポート参照)。2025年版不公正貿易報告書では、「中国で生産されたにもかかわらず、国内で消費されない余剰分が他国への安価な輸出に振り向けられる状況が4年間以上も続いていると考えられ、その背景には構造的な問題がある」と指摘されている(注1)。
過剰生産能力の何が問題かといえば、同報告書によると、経済性を考慮しないかたちで生産能力の拡張が進むことで、過剰生産状態が発生し、これに伴う市況低迷が企業の収益悪化を招き、貿易救済措置の増加など世界各地で通商摩擦を引き起こすことだ。この問題は最近になって初めて表面化したわけではない。2014年ごろから鉄鋼や造船、化学繊維などの産業で顕在化し、国際市場に影響を与え始めた。2024年からはこうした従来の産業に加えて、電気自動車(EV)や半導体といった先端産業でも、同様の傾向がみられるという。
近年、特に日本の自動車関連企業から動向が注視されているのは、中国のEVだ。世界のEV生産の約7割を中国が占める(注2)中、同国内で「構造的な生産能力過剰」「過当競争」が起きている(2025年7月25日付地域・分析レポート参照)。中国市場での競争が激しさを増す中、中国資本の完成車メーカー(以下、中資系OEM)は海外市場に活路を求めるようになっている。
中資系OEMの価格引き下げ競争は海外でも激化する傾向にあり、例えば、タイでは、現地自動車市場にも大きな影響を与えている(2024年10月3日付地域・分析レポート参照)。もともとは日系ブランドの牙城だったタイの自動車市場では、特に乗用車市場で進出日系企業も強烈な価格攻勢にさらされ、シェアを奪われており、「デフレが中国から輸出されている」とやゆされる状況にある(注3)。
各国は関税引き上げ、中国は過剰生産の指摘に反論
こうした中資系OEMのEV攻勢に対して、一部の国では貿易制限措置を活発化させている。中国EVの主要な輸出市場のEUでは、2023年10月から反補助金調査を開始した。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、中国では明らかに過剰生産能力が存在し、輸出に流れること、中国政府による直接・間接の補助金でその傾向は強まり市場をゆがめることを説明した(注4)。また、米国やカナダは「製造業サプライチェーンに損害を与えている」として、2024年に追加関税措置を発表した。
国際エネルギー機関(IEA)の「世界EV見通し2025」では、2024年1月以降の中国からの輸入EVにかかる関税率の変化を紹介している。中国EVの仕向け地として全世界の3割を占めるEUや、カナダ、米国、インド、トルコでは、関税率が大幅に引き上げられた(図1参照)。他方、日本、オーストラリア、タイでは0%となっている。インドネシアでも将来的な現地生産を約束している場合は0%だ(注5)。メキシコ、ブラジルでは20%前後に引き上げられた。
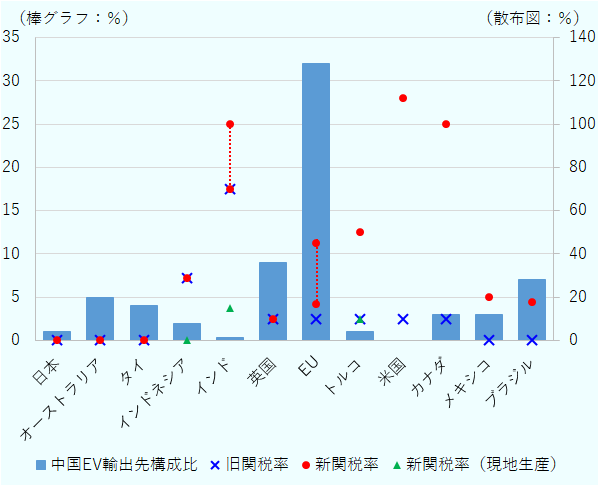
注:赤色点線(インド、EU)は品目等により幅があることを示す。新関税率(現地生産)は、(一定の投資を行い)将来的な現地生産等を約束した企業に対する優遇制度を活用して輸入した場合の関税率である。
出所:IEA「世界EV見通し2025」
日本、英国、カナダ、オーストラリアなどは、貿易歪曲(わいきょく)的な補助金が過剰生産能力を引き起こしていることや、中国の過剰生産能力は鉄鋼などの特定セクターの問題ではなく、構造的な問題になっていることなどを指摘し、新興経済国の企業の競争力喪失につながり得ることに懸念を表明している(注6)。
一方、中国政府からは強い反論が表明されている。主張としては、(1)「過剰生産能力」には明確な定義はない、(2)中国の生産設備稼働率は通常の範囲内で、「余剰」や「過剰」は存在しない、(3)中国EVには国内外ともに莫大(ばくだい)な潜在需要があり、需要に比して供給能力が過剰といえない、(4)中国の産業優位性は高品質と急速なイノベーション、長期的な企業努力の結果として、完全な市場競争によって形成されている、(5)中国の手頃で高品質な製品は消費者の生活の質向上にも役立っている、(6)一部の国は、中国に気候変動対策の責任を求める一方で、中国のグリーン製品の自由な流通を妨げており、ダブルスタンダードだ、といったものだ(注7)。
EVの低価格化と普及もたらした中国の技術革新
実際、新型コロナウイルス禍以降のASEANの産業政策では、EVメーカーの誘致合戦の様相を呈しており、ASEAN各国側のEV産業の早期誘致と産業育成の要望に応えるかたちで、中資系OEMが進出しているという事情もある。例えば、タイでは、EV産業の育成を進める上で、まずは国内市場を形成するためのEV普及策が採用された。将来的な現地生産などを条件にして、輸入EVに対する関税を減免する措置を打ち出した。これに応えるかたちで、中資系OEMは生産拠点を設けるために進出し、同時に当初は輸入EVを中心に販売促進を進めた。2024年から本格的にタイで現地生産を始めた中資系OEMも複数ある。
その結果、タイやインドネシアでは、2022年~2023年ごろからバッテリー式電気自動車(BEV)の普及が飛躍的に高まった(図2参照)。また、ベトナム、マレーシア、インドでも、BEVの販売台数が拡大している。この背景に、中国企業の持つEVやバッテリーの技術革新が寄与している点は否めない。以前はBEV普及の課題として価格の高さが挙げられており、潜在的な顧客は一部の富裕層に限られていた。しかし、BEVを構成する部品・原材料の中で大きな割合を占めるバッテリーコストが大幅に下がったことで、各国でエンジン車との価格差が縮小した(あるいは下回った)。
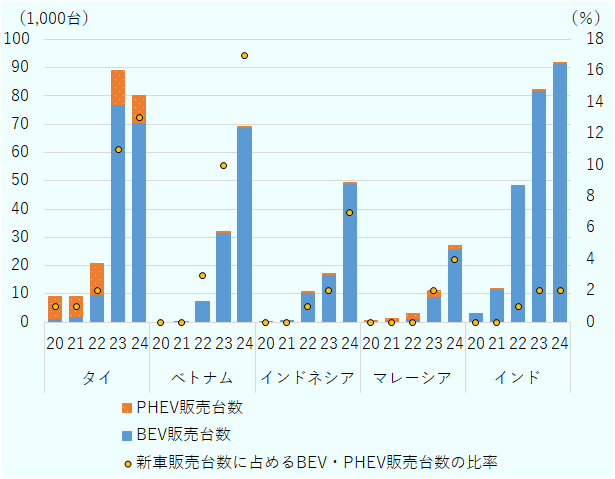
出所:IEA「世界EV見通し2025」
調査会社ブルームバーグNEF(BNEF)によると、2024年のEV向け電池パックの世界平均価格は、前年比2割減の1キロワット時(kWh)当たり115ドルと、2013年の調査開始以来最安値となった(注8)。この要因としてBNEFは、リン酸鉄系リチウムイオン電池(LFP)の普及を挙げている。LFP電池は寧徳時代新能源科技(CATL)、BYD、国軒高科(ゴーション)などが世界市場で圧倒的なシェアを持っている製品だ。安価なLFP電池の性能を三元系電池並みに引き上げることに成功し、それが中資系OEMのEVに実装されていることが価格面でのインパクトを与えている(2024年12月18日付地域・分析レポート参照)。
IEAの「各国での内燃機関(ICE)車とBEV、中資系OEMのBEVの価格比較」(図3参照)をみると、タイで中資系OEMのBEVは、平均価格でICE車を下回っている。その他の国でも、1~3割程度の価格差となっている。ガソリン価格が世界的に上昇する中でランニングコストを考慮に入れた場合、トータルではBEVの方が安くなると考えるユーザーもあり、BEVを選択する消費者が増えた。BEVは富裕層に限らず、中間層の選択肢にも並ぶ状況となっている。
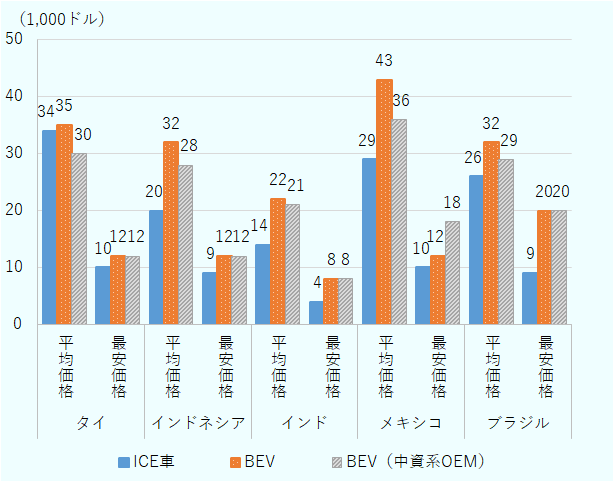
出所:IEA「世界EV見通し2025」
一方で、価格競争力のあるBEVが各国市場に流入したことで、EV市場で中国からの輸入割合が2023年から2024年にかけて大幅に上昇し、中国EVへの輸入依存度、中資系OEMのシェアが高まっている(図4参照)。タイのほか、インドネシアやマレーシアでも、中国からの輸入EVがEV市場全体に占める比率は約7~8割に上っており、ブラジルやコロンビア、メキシコといった中南米地域、エジプトでも、中国からの輸入比率が高くなっている。ベトナムでは現地ブランド(ビンファスト)がほぼ100%を占めるが、バッテリー技術自体はゴーションなどを頼っている状況だ。
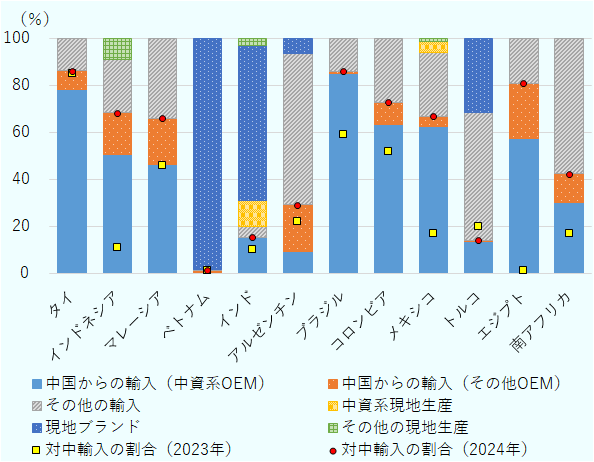
出所:IEA「世界EV見通し2025」
競争力を高める中国企業にどう対抗し、どう連携するか
前述したとおり、中国OEMのEVが世界中に流入しており、通商摩擦を起こしている側面もあるが、「中国の産業優位性は、高品質と急速なイノベーション、長期的な企業努力の結果」とする中国側の主張について、中国OEMが急速に技術革新を起こし、関連技術を発展させていることも事実だ。2025年4月23日から5月2日まで開催された「上海モーターショー」では、36万平方メートル超(東京ドーム8個分)という広大な面積に、26以上の国・地域から約1,000社が出展し、100台以上の新車や新技術が公開された(2025年5月2日付ビジネス短信参照)。

モーターショーでは、東南アジアなど中国国外にも今後展開が見込まれる新型モデルや、AI搭載型の先進運転支援システム(ADAS)、自動運転技術が展示された。5分間の充電で520キロの航続を可能とする高性能バッテリーや、急速充電システム、交換型の板チョコ状のバッテリーなど、最新のEV関連技術が紹介された。トヨタ、ホンダ、日産などと先進運転支援技術の共同開発を行っている新興企業のモメンタや、中国の技術を取り入れたトヨタの「bZ3X」が関心を引いており、日本企業でも中国発の技術を取り入れ、連携しているモデルが好評を得ていることが見て取れた。

(ジェトロ撮影)

65%以上を中国で調達(ジェトロ撮影)
中国企業が持つ競争力については、しばしば、多額の補助金が供給されている点が強調して言及されることもある。しかし、それだけでは中国企業の競争力を十分に説明しているとは言い難い。現地の日系自動車業界関係者等にヒアリングした(注9)ところ、以下のような多面的な強みがあるという。
- 人材組織:若い人的資源が豊富。給与水準が高くない。組織がフラットで、意思決定が迅速。長時間労働をいとわない働き手が多く、人的リソースの大規模投入が可能。
- 経営戦略:垂直統合戦略でバッテリーや半導体を自社生産できる。1モデル当たりの仕様類別を少なく設定できる。
- 開発設計:コンピュータ支援エンジニアリング(CAE)、数値流体力学(CFD)、AI設計を駆使し、仮想環境でテストできる。「X-in-1」設計(電気駆動の3-in-1など)で部材の点数を削減している。
- 生産物流:工場のデジタルトランスフォーメーション(DX)化で生産効率が向上。物流のDX化で、在庫管理時間や物流コストを削減している。
- アフターサービス:修理アプリを開発し、整備士の修理効率・精度を向上させている。AI技術を用いてメンテ部品の需要予測と最適化を行っている。
- 新規事業:車両から生成されるビッグデータを販売している。BYDでは仮想通貨をサプライチェーン上で流通させることで、手数料を削減している。
- 政府支援:地方省政府などが産業パーク内の工場用地を安価に提供。新型エネルギー車(NEV)にさまざまな優遇を付与している。研究開発に税制控除を提供している。
また、短期開発を実現している秘訣(ひけつ)として、大規模な研究開発費と人員を投入しているほか、アジャイル開発(注10)、仮想現実(VR)技術の活用、コンカレントエンジニアリング(注11)、プラットフォームのモジュール設計化、部品共用戦略、車両スペックの適切化(オーバースペックの回避)、サプライヤーへの情報や判断権限、開発業務の委譲(サプライヤーの開発リソースの活用)といったさまざまな工夫がなされている。
本稿では、中国OEMの攻勢で、各地で通商摩擦が起こっており、市場歪曲的な措置が取られている可能性に触れつつも、中国OEMが技術革新で競争力を高めている実態についても触れた。今後、中資系OEMもプラグインハイブリッド車(PHEV)やレンジエクステンダー(REEV)車(注12)にも力点を置く流れとなっており、東南アジアなどの新興国市場で、日系企業のハイブリッド車(HEV)との競争が一段と激しくなっていくことは避けられそうもない。
中国企業が強大な競争相手となりつつある半面、既に日本企業が、優れた中国サプライヤーからの調達や技術面での連携を試みる動きもみられている。地政学リスクや経済安全保障の観点から、中国企業との向き合い方については各企業によってスタンスが異なる面もあるが、「補助金で価格が安いだけ」と軽視する、あるいは「一過性のもの」と楽観視すべきでないだろう。特に中資系OEMの投資を歓迎している新興国では、中国企業のEVに対して貿易障壁を設ける見込みも薄いことから、革新的な中国モデルや技術に対抗していく方法を考える、あるいは、協業関係を構築していくといったことも検討の余地がありそうだ。
- 注1:
-
2025年版不公正貿易報告書
 (2.03MB)363ページ参照。
(2.03MB)363ページ参照。 - 注2:
-
IEAによる。本特集の「EV取り巻く環境変化、政策の見直し進む(前編)世界で競争が激化」参照。
- 注3:
-
日本総研「トランプ政策が助長する中国の「デフレ輸出」
 」『Research Focus』(2024年12月23日)、三菱UFJリサーチ&コンサルティング「米中対立激化で中国の「デフレ輸出」加速の懸念
」『Research Focus』(2024年12月23日)、三菱UFJリサーチ&コンサルティング「米中対立激化で中国の「デフレ輸出」加速の懸念 (856KB)」(2025年5月23日)ほか。
(856KB)」(2025年5月23日)ほか。 - 注4:
-
2025年版不公正貿易報告書
 (2.03MB)364~365ページ参照。
(2.03MB)364~365ページ参照。 - 注5:
-
今後引き上げられる可能性もある。日本経済新聞「インドネシア、EV輸入免税を終了へ、国内工場の稼働率悪化に危機感」(2025年9月3日)。
- 注6:
-
2025年版不公正貿易報告書
 (2.03MB)368ページ参照。
(2.03MB)368ページ参照。 - 注7:
-
2025年版不公正貿易報告書
 (2.03MB)368~369ページ参照。
(2.03MB)368~369ページ参照。 - 注8:
-
「Lithium-Ion Battery Pack Prices See Largest Drop Since 2017, Falling to $115 per Kilowatt-Hour
 」(2024年12月10日付、ブルームバーグNEF)
」(2024年12月10日付、ブルームバーグNEF) - 注9:
-
2025年4月22~27日に行ったヒアリングによる。
- 注10:
-
「素早い」「機敏な」開発を意味する。小規模な計画・実行・評価のサイクルを短期間で繰り返し、各サイクルの終了後に成果を評価し、次のサイクルに反映させる手法。短期間で実装とテストを繰り返すことで、素早く開発を進める狙いがある。
- 注11:
-
製造業の製品開発工程において、複数の業務を同時進行させることで、開発の効率化や期間短縮を図る手法。
- 注12:
-
ハイブリッド車の一種で、電気モーターとエンジンを交互に使用するPHEVとは異なり、動力は電気モーターのみで、エンジンは発電機として機能する。主にバッテリーで動くが、航行距離を延ばすための補助動力装置としてエンジンによる発電がおこなわれ、電気モーターでの更なる走行が可能になる。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部国際経済課 課長代理
北見 創(きたみ そう) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部アジア大洋州課、大阪本部、カラチ事務所、アジア大洋州課リサーチ・マネージャーを経て、2020年11月からジェトロ・バンコク事務所で広域調査員(アジア)として勤務。2024年10月から現職。






 閉じる
閉じる





