多国間主義に瓦解の兆し―試されるグローバルビジネスの耐性価格競争から価値競争へ、越境ECの新時代(世界)
2025年11月4日
国境を越えた電子商取引(越境EC)の市場が急速に拡大している。成長を牽引しているのは、中国系ECプラットフォームだ。Temu(テム)やSHEIN(シーイン)などの企業が、安価な商品を消費者に直接届けるビジネスモデルを武器に、米国やEUで存在感を高めてきた。
しかし政策変更が進み、これまでの優位が揺らぎつつある。例えば米国では、デミニミスルールを廃止し、EUでオンラインプラットフォームの監視を強化している。各国・地域の制度改革は、越境ECの構造そのものに影響を与え、中国系プラットフォームに新たな対応を迫っている。 本稿では、米国とEUでの制度変更の背景と影響を整理。今後の越境ECの展望を探る。
拡大する越境EC市場、中国系ECプラットフォームが牽引
越境ECの市場は、大きく成長してきた。英国の調査会社ユーロモニターインターナショナルによると、世界の越境EC小売市場規模(売上高)は2024年、5,210億ドルに達した(注1)。2015年比で約5倍という急成長だ。
特に目立つのは、中国からの購入の増加だ。ECに関して国際郵便機構(IPC)が実施した調査の2024年版(注2)には、直近の越境EC取引で購入した商品の発送元について設問がある。結果を見ると、2024年は中国から購入したと回答した割合が40%。過去8年間で最大だった(図1参照)。2023年から3ポイント増加した。
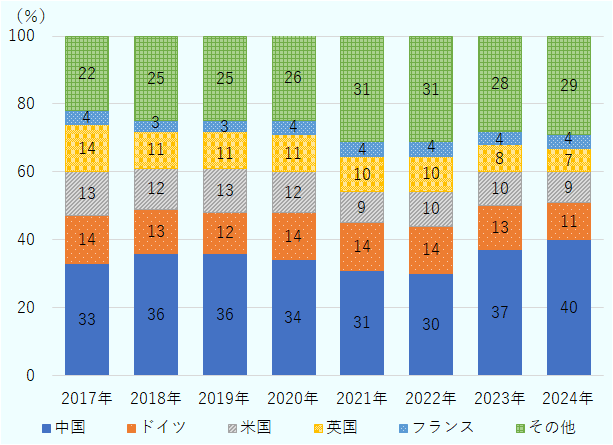
注1:直近の越境 EC取引でどの国から商品を購入したかを尋ねた設問への回答。
注2:調査の概要は記事末注2を参照。
出所:国際郵便機構(IPC)「Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2024」
中国からの購入が増加している背景には、中国系越境ECプラットフォームの台頭がある。IPCの調査では、直近の越境EC取引で利用したプラットフォームについても尋ねている。米国のアマゾン(24%)が中国系のテム(21%)と競り合う結果になった(図2参照)。
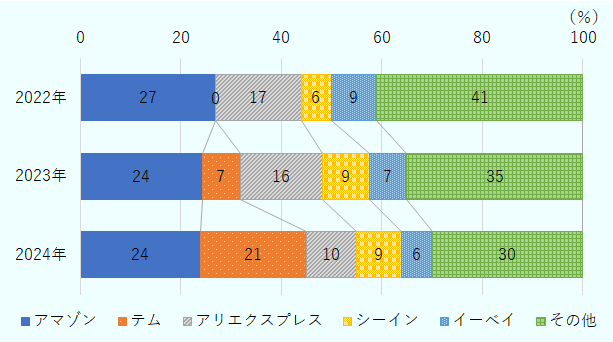
注1:直近の越境 ECでの購入で利用したプラットフォームを尋ねた設問への回答。
注2:図2では、2024年版の上位5つのプラットフォームを取り上げた。6位以下は、「その他」にまとめた。
注3:端数処理の関係で、2023年版は合計が100%とならない。
注4:調査の概要は文末注2、3、4参照。
出所:国際郵便機構(IPC)「Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2022」「Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2023」「Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2024」
図2で取り上げたうち、アマゾンは周知の企業だ。残る4社の概要は次のとおり。
- テム:
本社は、米国ボストン。ただし、親会社は中国のPDDホールディングスだ。
2022年9月に創業したため、IPC調査の2022年版(注3)では、シェア0%。しかし、2023年版(注4)時点で7%。2024年版では、そこからさらに14ポイント増。わずかな期間に急成長を遂げたことがわかる。 - アリエクスプレス(AliExpress):
中国のアリババグループが国際市場向けに構築して運営する越境ECプラットフォーム。シェア10%。 - シーイン:
本社はシンガポールに所在するものの、創業地は中国。シェア9%。 - イーベイ(eBay):
米国の越境ECプラットフォーム。シェア6%
このように、「テム」「アリエクスプレス」「シーイン」は、中国にルーツを持つ越境ECプラットフォームと言える。2024年版調査では、この3社あわせて、シェア4割。世界的に人気を博していることが、ここから読み取れる。
中国系プラットフォームでは多くの場合、中国の工場から商品を消費者に直接配送する「D2C越境モデル」(注5)を採用している。安価な商品を注文ごとに小口配送するため、各国・地域の設定している少額輸入貨物に対する免税措置の恩恵を受け、現地で価格優位に立ってきた。しかし、昨今の保護貿易主義の流れの中で、この前提が崩れつつある。
以降で、制度変更がとりわけ大きい米国とEUでの動きを整理する。
米国:全世界向けにデミニミスルール適用停止
少額輸入貨物に対する免税措置を敷く国・地域の中でも、最も非課税基準額が高かったのが米国だ。「デミニミス(de minimis)ルール」の下、800ドル以下の少額輸入貨物に対して、関税などの支払いを免除するほか、簡易通関を認めていた。
中国系ECプラットフォームは、これを活用。米国の消費者に安価な商品を直接届けてきた。2023年には、1日に米国に輸入されるデミニミスルール対象貨物のうち、テムとシーインだけで3割以上を占めた(注6)。
しかし第2次トランプ政権下で、米国はデミニミスルールの全面的な廃止にかじを切った。まず2025年5月2日以降、中国・香港原産品に対して適用を停止。その後、8月29日以降、全世界向けに停止している(2025年8月1日付ビジネス短信参照)。当政権が制度廃止に踏み切った背景には、複数の政策的要因がある。まずは、安全保障上の懸念だ。デミニミスルールの対象貨物には、簡易通関を認めていた。この場合、原産地証明やHTSコード(品目分類コード)の提出などが不要になる。その結果、麻薬や偽造品、強制労働に依拠した製品などの違法品がデミニミス貨物として流入することが多かった。制度が「抜け穴」になっていると、議会や報道などで批判があった。特にフェンタニルなどの合成麻薬がこの制度を通じて米国内に流入していることが問題になっていた。また、大量の安価な中国製品が米国の小売業や製造業に打撃を与えているとの懸念や、税収機会の損失なども絡み、議会や業界団体からは制度の見直しを求める声が高まっていた。
これらの課題は最近になって提起されたものばかりではない。デミニミスルールを取り巻く幾つかの懸念は2022年ごろから議会で議論が始まり、報道も取り上げるようになった。バイデン前政権下でも、具体的に規則改正案が出ていたのだ。この流れをくみながら、第2次トランプ政権下で制度の廃止まで大きくかじを切ったかたちだ。
トランプ政権は「米国第一主義(America First)」を強調し、国内産業の保護や、貿易赤字の是正、国家安全保障の強化を柱に包括的な通商政策を掲げてきた。その中で、デミニミスルールの廃止は「合成麻薬の流入対策」「国内産業保護」「財政健全化」といった複数の政策目標が交差する地点にある。重点課題に対応する1つの実効手段として、トランプ氏が廃止に踏み切ったと考えられる。
逆境に立ち向かう中国系ECプラットフォーム
テムやシーインをはじめとした中国系ECプラットフォームは、米国のデミニミスルールの撤廃と関税措置によって逆風にさらされることになった。特に中国・香港原産品に対するデミニミスルールの適用停止を発表・開始した4~5月には、デジタル広告支出の大幅カットや商品の値上げ、ユーザー数や売り上げの減退など、ネガティブな影響の報道が相次いだ(注7)。
こうした中でも、テム、シーインの両社とも、米国市場での売上高は2025年もプラス成長の予測だ。米国の調査会社eMarketer(イーマーケター)によると、テムは前年比13.5%増、シーインは10.0%増の見込み。米国での小売事業者として、大手のウォルマート(16.1%)に次いで、2位、3位の座を占めている(注8)。この発表に当たり、イーマーケターは「テムやシーインは依然として、値引きを求める米国の消費者を引き付け続けている」との見立てを示した。デミニミスルールの適用は、中国からの輸入だけでなく全世界向けに停止中だ。また関税コスト上昇の影響は、ほぼ全ての小売業者に及ぶ。こうしたことが相まって、提示する価格で依然として優位が維持できていると分析している。
しかし、売上高の成長を見込めるとはいえ、米国の政策変更は利益率を圧迫するはずだ。これまでデミニミスルールを活用して免税で売れていた商品に関税がかかるようになり、コスト増は否めない。そうした中、テムやシーインはD2C越境モデルから、「現地フルフィルメントモデル」にビジネスモデルを転換し、コスト最適化を図っている。現地フルフィルメントモデルでは、商品を米国内の倉庫に一括輸入し、フルフィルメント業者を通じて国内配送する。受注処理やピッキング、梱包(こんぽう)、発送などを代行するのは現地の業者だ。これによって個別通関の負担や1件当たりのコストを軽減しながら、素早い配送を実現できる。テムの米国サイトで最も売れている商品(Best-Selling Items)カテゴリーにアクセスすると実際、ほぼ全てが国内配送商品だ。ページ上部にも「Local Warehouse(国内配送)」のカテゴリーがあり、国内配送商品だけを閲覧できる仕様にもしている。ちなみに、日本サイトにはそのようなカテゴリーがない(執筆時点)。テムが米国向けで特に、国内倉庫からの配送に注力していることがわかる。また、シーインはアマゾンと連携し、アマゾンの倉庫で在庫を保管して配送できるようにする見込みだ(注9)。
EU:中国系プラットフォームの監視強化、さらなる制度改革案も
EUでは、150ユーロ未満の商品について関税を免除している。また、少額輸入貨物が急増しているという点では、米国同様だ。
背景にはやはり、テムやシーインなど中国系ECプラットフォームの台頭がある。テムがEUで確保している月間アクティブユーザー数(2025年上半期平均)は、域内人口の25%超(約1億1,570万人)に上った(注10)。シーインは、さらに多い。同じく月間(2024年2月~2025年7月の平均)で、実に人口の32%超(約1億4,570万人)に及ぶ(注11)。
なお、EUの低価格商品輸入(150ユーロ未満)は2024年、46億個に達した。これは、前年の2倍に当たる。また、その91%が中国からの輸入だった(注12)。2025年に入り、米国で政策変更のあおりを受けた両社が米国の代わりに、欧州でのマーケティングを強化したとの報告もある(注13)。
存在感を増す中国系ECプラットフォームに対して、EUは監視を強めている(2025年2月7日付ビジネス短信参照)。まず、シーインとテムをデジタルサービス法(DSA、注13)に基づいて「非常に大規模なオンラインプラットフォーム(VLOP)」として指定。厳格な規制の対象になった。シーインには、2025年7月には不当な価格表示を理由に、9月には個人情報保護違反で、それぞれ罰金を科している(2025年9月9日付、2025年9月22日付ビジネス短信参照)。テムに対しては2025年7月、DSA違反の可能性があるとの予備的見解を発表。乳児用玩具や小型家電について、消費者がテムで不適合商品を見つける可能性が非常に高いことが判明した。違反が確定すると、罰金(最大で年間全世界売上高の6%)や是正命令を科す可能性がある。
さらに、より厳しい対策を求める声も根強い。例えば、欧州繊維産業連盟(EURATEX)など欧州の主要な繊維・衣料品団体は、急速に台頭するウルトラファストファッションに警戒感を持つ。対抗するため、EUに対し小口小包への課税の導入や150ユーロ未満の輸入品の関税免除廃止など、迅速な対応を強く求めている(2025年9月24日付ビジネス短信参照)。EU各国の税関当局が苦慮するのは、ECプラットフォームが大量の商品を消費者に直接配送していることだ。そのため、商品の安全性や環境基準の監視が困難で、消費者保護や国内産業への影響を懸念している。また、少額輸入貨物の免税制度に対しては、関税を回避するための過少申告や税収損失も問題視してきた。
EURATEXなどが求めている対策については、欧州委員会が2023年5月に発表したEU関税同盟の改革案に基づき、導入に向けて議論が進行している。改革案では、少額輸入貨物に対する関税免除制度を撤廃する方針を示している。一部のEU加盟国は2028年から、早期に施行するよう要望している。ECプラットフォームを通じた購入の場合、(消費者ではなく)プラットフォーム企業に対して、「みなし輸入者(deemed importer)」としての責任を課す。これにより、アマゾンやテムなどのプラットフォームが関税・付加価値税(VAT)の徴収と申告、製品安全性の責任を担うことになる。そのほかにも、加盟国間の税関業務の一本化や、データベースを活用した効率化など、複数の提案が挙がっている(2023年5月18日付ビジネス短信参照)。2024年3月に、欧州議会が立法報告書を支持。2025年6月には、EU理事会(閣僚理事会)内で妥協案に合意している。理事会は、EU域内へ輸入される小口小包に対する税関当局による取扱手数料の導入を追加提案した。7月からは、三者協議(欧州委員会・欧州議会・EU理事会)を開始。この改革案が成立すると、EU域外のECプラットフォームは関税コスト増や、「みなし輸入者」としての対応に向き合う必要が出てくる。
それだけでなく、トランプ米大統領がEUに対し、中国に100%の関税を課すよう求めたとの報道もある。地政学的な緊張が、中国系プラットフォームの欧州事業に一層の不確実性をもたらしている。
これからの越境ECは多面的な価値の追求を
このように、米国とEUでの制度変更は、中国系ECプラットフォームのビジネスモデルに大きな影響を与えている。これまでのD2C越境モデルによる価格優位性が揺らいでいる。各社は、現地フルフィルメントモデルへの転換など対応を迫られている。
さらに、少額輸入貨物への優遇措置を見直す動きは、欧米以外でも進んでいる。この変化が示すのは、越境EC市場が単なる「安さ」だけでは成り立たなくなってきているということだ。プラットフォーム企業は単に安価な商品を届けるだけではなく、制度順守、品質管理、環境配慮、消費者保護といった多面的な価値を提供する必要がある。そして、プラットフォームに出品するセラー(販売者)もまた、こうした価値基準に対応する責任を負う(注14)。製品の安全性や表示の正確性、輸出入規制への理解、環境や社会への配慮などを通し、「信頼される商品」を提供する姿勢が不可欠になろう。
- 注1:
-
ユーロモニターインターナショナル「What Tariff Turbulence Means for Global Retail E-Commerce: Winners and Losers
 」(2025年5月12日)。
」(2025年5月12日)。
- 注2:
- 国際郵便機構(IPC)「Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2024」(2025年1月9日)。IPC調査のターゲットグループは、過去3カ月以内に国内外を問わずオンラインショッピングで購入実績があり、かつ過去1年以内に越境ECで購入した消費者。2024年版は、世界37カ国を対象に同年9月に調査を実施し、3万1,000人から回答を得た。
- 注3:
- 国際郵便機構(IPC)「Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2022」(2023年1月26日)。2022年版は、世界39カ国を対象に同年10月に調査を実施し、3万3,009人から回答を得た。
- 注4:
- 国際郵便機構(IPC)「Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2023」(2024年1月11日)。2023年版は、世界41カ国を対象に同年9月に調査を実施し、3万2,510人から回答を得た。
- 注5:
- D2CはDirect-to-Consumerを指す。
- 注6:
-
米国連邦議会下院の「米国と中国共産党間の戦略的競争に関する特別委員会(中国特別委)」による発表(2023年6月22日付プレスリリース
 )に基づく。
)に基づく。
- 注7:
-
「ジェトロ世界貿易投資報告 2025年版」第Ⅰ章
 (1.91MB)第2節(3)p.34参照。
(1.91MB)第2節(3)p.34参照。
- 注8:
- イーマーケターの予測(2025年5月時点)に基づく。
- 注9:
-
アマゾンによる発表(2025年9月18日付プレスリリース
 )に基づく。
)に基づく。
- 注10:
-
「Temu Transparency Report
 (314KB)」(2025年8月31日)。
(314KB)」(2025年8月31日)。
- 注11:
-
シーインのウェブサイト
 (2025年10月21日閲覧)に基づく。
(2025年10月21日閲覧)に基づく。
- 注12:
-
欧州委員会「“E-commerce communication: A comprehensive EU toolbox for safe and sustainable e-commerce
 」(2025年2月5日)。
」(2025年2月5日)。
- 注13:
-
イーマーケター「“Shein and Temu increase European ad spend as tariffs upend US strategy
 」(2025年5月6日)。
」(2025年5月6日)。
- 注14:
- 米国のデミニミスルール廃止に伴う実務的な影響と対応については、連載記事「米国デミニミス制度廃止の衝撃」で解説している。連載1本目「越境ECビジネスにもたらす変化」、2本目「コンプライアンス対応の必要性」、3本目「品質やブランド力がカギ」参照。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部国際経済課
宮島 菫(みやじま すみれ) - 2022年、ジェトロ入構。調査部調査企画課を経て、2023年6月から現職。




 閉じる
閉じる






