越境ECビジネスにもたらす変化
米国デミニミス制度廃止の衝撃(1)
2025年10月27日
世界の電子商取引(EC)市場は、パンデミックを契機に急拡大し、2024年には約6兆ドルに達した。中でも市場を牽引したのが、中国と米国だった。
一方、米国は、制度の抜け穴として少額貨物の免税制度「デミニミス」を問題視し、2025年8月末に廃止した。制度の恩恵を受けていた越境EC事業者は、通関手続きの複雑化や関税負担の増加に直面し、ビジネスモデルの再構築が求められている。
本レポートは、現在の世界のEC市場を概観し、越境EC市場拡大を支えたデミニミス制度の歴史的背景や制度変更の経緯などについて深掘りする3本シリーズの1本目。
拡大し続ける世界のEC市場
世界のEC市場(国・地域内取引と越境ECの合計)は、2019年以降、右肩上がりだ。米市場調査会社イ―マーケター(eMarketer)によると、2019年に約3兆ドルだった世界市場は、新型コロナ禍の2020年に一気に4兆ドルに拡大し、パンデミックが続いた2022年には、5兆ドルに達した。世界的な感染が収束した2023年以降も市場は伸び続け、2024年には約6兆ドルになった。同年の国・地域別のEC小売総額では、中国市場が3兆420億ドルで、全世界市場の約半分を占めた。2~10位は、米国(1兆1,923億ドル)、英国(2,284億ドル)、日本(1,348億ドル)、韓国(1,285億ドル)、インド(1,147億ドル)、ドイツ(994億ドル)、フランス(864億ドル)、インドネシア(839億ドル)、カナダ(790億ドル)だった(表1参照)。
世界の小売総額に占めるEC販売の割合は、パンデミック前の2019年に13.6%だったが、それ以降は18~20%で推移している。この傾向は今後も続くとされ、2026年には21.6%に増加すると予測されている。
国別では、中国の割合が約50%超と、他国に比べ非常に高い。オンラインでの購入慣習が根付いていることが分かる。EC小売総額で2位の米国と3位の英国の割合は、それぞれ2020年から約15%と30%で推移している(表2参照)。
一般的に、EC市場が拡大する国・地域の特徴として次の要因が関係していると考えられる。(1)購買力(可処分所得)、(2)インターネットとスマートフォンの普及率、(3)有力なプラットフォーマーの存在、(4)デジタル決済インフラの存在、(5)物流網の整備(特に地方・農村部への配送)、(6)政府の支援・規制緩和、などだ。
| 順位 | 国・地域名 | 売上総額 | シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 30,420 | 50.8 |
| 2 | 米国 | 11,923 | 19.9 |
| 3 | 英国 | 2,284 | 3.8 |
| 4 | 日本 | 1,348 | 2.3 |
| 5 | 韓国 | 1,285 | 2.1 |
| 6 | インド | 1,147 | 1.9 |
| 7 | ドイツ | 994 | 1.7 |
| 8 | フランス | 864 | 1.4 |
| 9 | インドネシア | 839 | 1.4 |
| 10 | カナダ | 790 | 1.3 |
| ー | 世界 | 59,888 | 100.0 |
出所:eMarketer (Retail Ecommerce Sales by Country)
| 順位 | 国・地域名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 34.1 | 42.4 | 43.2 | 45.6 | 48.1 | 50.4 | 52.9 | 54.7 |
| 2 | 英国 | 21.8 | 33.1 | 34.4 | 30.1 | 30.5 | 31.0 | 31.1 | 31.2 |
| 3 | インドネシア | 7.1 | 13.6 | 22.6 | 26.3 | 26.3 | 28.3 | 29.1 | 30.0 |
| 4 | 韓国 | 18.6 | 22.9 | 24.1 | 24.3 | 25.8 | 27.4 | 28.8 | 29.9 |
| 5 | 米国 | 10.6 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 15.3 | 16.1 | 16.7 | 17.0 |
| 6 | カナダ | 6.6 | 11.4 | 12.1 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
| 7 | 日本 | 9.6 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 12.9 |
| 8 | フランス | 9.2 | 10.6 | 11.2 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
| 9 | インド | 3.7 | 5.8 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.2 |
| 10 | ドイツ | 8.4 | 9.6 | 10.7 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.0 |
| ー | 世界 | 13.6 | 18.0 | 18.6 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.6 |
注:2025~2026年は予測値。
出所:eMarketer (Retail Ecommerce Sales by Country)
越境EC市場拡大を支える世界のデミニミス制度
デミニミス(De Minimis)とは、ラテン語で「わずかで無視をしても構わないもの」という意味が起源という説がある。貿易では、少額貨物の通関時や、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)などの品目別原産地規則(PSR)の対象品目の付加価値の計算に利用することが多い。特に越境ECでは、各国・地域が独自に設定する一定金額以下の輸入品に対して関税などの税金を免除し、通関に係る書類も簡素化する仕組みを指すのが一般的だ。この制度は、先進国・地域だけでなく、新興国・地域や発展途上国・地域も導入している。
2025年7月時点で、デミニミス制度で輸入時に免税になる上限額の上位3カ国は、(1)米国(800米ドル)、(2)豪州(1,000オーストラリア・ドル、約650米ドル)、(3)ニュージーランド(1,000ニュージーランド・ドル、約580米ドル)だ。日本では、課税価格合計額1万円以下の設定になっている。課税価格は海外小売価格に0.6を乗じて算出するため、例えば、海外小売価格が1万6,666円以下ならば、課税価格が1万円以下になり、デミニミスの適用範囲内になる。米国の800ドルと日本の1万6,666円(約111ドル、1ドル=約150円)を比較すると、約7倍の差がある。
米国の免税輸入については、1930年米国関税法第321条に規定がある。デミニミスの考え方は、税関の業務効率化のため1938年に導入され、当時の上限額は1ドルだった。これまでに上限額を3回引き上げている。1978年にインフレ対応のために5ドルに、1993年には翌年発効する北米自由貿易協定(NAFTA)に合わせて200ドルに、直近の800ドルには2015年に引き上げた(米国貿易円滑化および権利行使に関する法律:TFTEA法)。
もっとも、名目額としては800ドルで変わりないものの、実質的な免税可能額は2024年時点で、2015年比で約3割目減りしている〔米国労働省労働統計局(BLS)によると、2015年の米国の期中平均物価インデックスを100としたとき、2024年は132.7〕。デミニミス適用上限額の名目値は頻繁に変更しないため、実質的に安価な商品が米国市場に流入する要因の1つになった。
デミニミス制度の限界と抜け穴の拡大
既述の通り、米国のデミニミス適用上限額は世界で最も高く、また米国は中国に次ぐ世界2位のEC市場でもある。このことから、近年は企業戦略として、デミニミス制度を利用した米国への輸出が急増していた。
中国系のグローバル越境ECプラットフォーマーは、特にパンデミック期に米国などの巨大市場で巨額の予算を投じてSNSで広告を行い、ユーザー数(米国側の輸入者)を急拡大させて、個人輸入者数を底上げした。また、それらプラットフォームを通じて、関税を回避して個人向けに直接商品を発送できるようになったため、競争力のある価格設定が可能になり、それが米国市場への安価な中国原産品流入につながった。
米国税関・国境保護局(CBP)によると、デミニミス制度を利用して通関した件数は、2022年の約6億8,500万件から2024年には約13億6,000万件へと倍増した。一方で、輸入額は2022年の約4,650億ドルから2024年の約6,460億ドルへと約1.4倍の伸びにとどまった。その結果、1回の平均輸入額は、2022年の678ドルから2024年には475ドルに、さらに2025年は205ドルになり、3年で約7割下落した(図参照)。
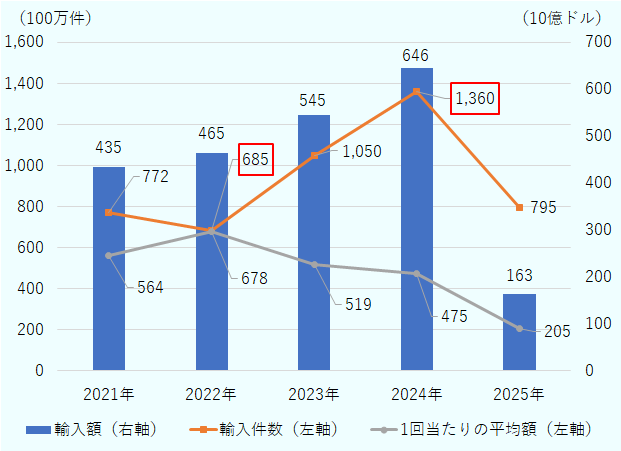
注:2025年は5月20日時点。
出所:米国税関国境保護局(CBP)
通関件数の急増に対して、米国政府は複数の懸念を表明した。第1に、国内産業への打撃だ。安価な中国製品が大量に流入することで、米国企業の競争力が低下する可能性を指摘した。第2に、安全保障上の懸念だ。CBPはデミニミス制度を悪用したフェンタニルなどの違法薬物の輸入が増加していると報告しており、制度の見直しを急務とした。
米国では、デミニミス制度の見直しに向けて複数の法案が提出された。2023年には、「Import Security and Fairness Act」が連邦議会に提出され、中国やロシアなどの特定国からのデミニミス通関を制限する内容が盛り込まれた。この背景には、米中貿易摩擦の激化、国内製造業の保護、そして安全保障上のリスクへの対応がある。特にフェンタニルの流入問題は、制度変更の直接的な契機になった。
デミニミス制度廃止に動いたトランプ政権
トランプ政権は2025年5月2日、中国と香港を原産とする輸入品に対してデミニミス制度の適用を廃止した(2025年4月4日付ビジネス短信参照)。これにより米国での通関のリードタイムが顕著に伸びた。関税評価額が800ドル以下の場合、廃止前、貨物の平均通関時間は数時間だったが、廃止後は複数営業日を要していると複数の米国メディアが報じている。
デミニミス制度は、免税輸入という金銭面のメリットだけでなく、少額貨物の輸出入手続き書類を簡素化する面でも重要な意味を持っていた。しかし廃止後は、少額貨物でも一般商業貨物と同等に格上げされた手続き書類が必要になり、輸出者と輸入者の双方に求められるコンプライアンスが強化された。例えば、廃止前は不要だった10桁のHTSコード(米国の関税分類番号)や品目の原産国の表示などが求められる。輸出者にとっては、特段気にする必要がなかったHTSコードを10桁まで把握し、かつ誤りがないことを確認しなければならない。
また、米国政府は7月30日付の大統領令で、「『大きく美しい1つの法』(2025年7月4日成立)で2027年7月末と定めていた全世界を対象としたデミニミス制度の廃止時期を、2025年8月29日に早める」と発表した(2025年7月8日付、2025年8月1日付ビジネス短信参照)。米国の越境EC市場をめぐるビジネス環境はパラダイムシフトを迎えた。シリーズ(2)(3)では、具体的な変更点やビジネス環境への影響、さらに日本企業に求められる対応策と今後の展望について考察する。
米国デミニミス制度廃止の衝撃

- 執筆者紹介
-
ジェトロデジタルマーケティング部ECビジネス課
志賀 大祐(しが だいすけ) - 2011年、ジェトロ入構。展示事業部展示事業課、ジェトロ・メキシコ事務所海外実習、お客様サポート部貿易投資相談課、海外調査部米州課、ジェトロ・メキシコ事務所などを経て2024年10月から現職。






 閉じる
閉じる





