多国間主義に瓦解の兆し―試されるグローバルビジネスの耐性歴史的転換点を迎える国際通商秩序、日本の役割に期待高まる
2025年9月29日
2025年において、第2次トランプ新政権の発足と米国第一の通商政策、米中対立の激化、世界的な保護主義の台頭により、国際通商秩序は大きな転換期を迎えている。通商政策の不確実性が、企業のグローバル戦略に深刻な影響を及ぼしている。米国の強硬な通商政策、米中対立激化の結果としての第三国での中国の輸出増大、そしてグローバルサウスを巡る競争の激化など、戦後の多国間貿易体制とは不連続の大きな潮流が生じている。日本やEUといった同志国は、世界の通商秩序の擁護に向けて連携を深めつつ、今後、世界貿易で存在感を高めていくグローバルサウス諸国との協力関係を強化していく必要がある。自由貿易体制を主導する日本に対し、期待が高まっている。
貿易政策の不確実性が過去最高水準に
2025年の世界の通商環境について、経済産業省は同年6月に公表した「通商戦略2025」の中で、新自由主義の時代から保護主義が台頭する時代へと変化する「国際経済秩序の歴史的な転換期」と位置づけている。また、情勢認識として、(1)格差拡大を背景とした保護主義・国際経済秩序の揺らぎ、(2)過剰供給・過剰依存による脅威の顕在化、(3)グローバルサウスを巡る競争の激化、(4)デジタル化がすべてをのみ込む時代、(5)競争力強化策としての環境エネルギー政策、という5つの大きな潮流を挙げている。
世界貿易機関(WTO)を中心とした通商ルールに基づく自由貿易に逆風が吹く中で、各国における通商政策の不確実性はかつてないほど高まっている。通商政策の不確実性を測る指標である「貿易政策不確実性指数(TPU)」をみると、米国、日本、中国では第 2 次トランプ政権が発足した2025年1月から徐々に上昇がはじまり、4月には過去最高水準に達している(図1参照)。
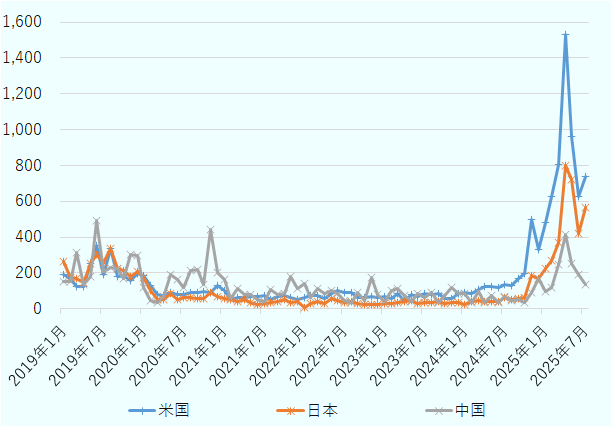
注:TPUは、主要新聞などでの貿易政策と不確実性に関連する用語の同時出現頻度をカウントすることで算出される。数値が高いほど不確実性が高い。日本は通商政策不確実性指数(経済産業研究所)、米国はTPU(Caldara, Iacoviello, Molligo, Prestipino, and Raffo)、中国はThe Chinese Mainland TPU(Davis, Liu and Sheng)に基づく。
出所:Economic Policy Uncertainty
2025年の大きな潮流の1つは「格差拡大を背景とした保護主義・国際経済秩序の揺らぎ」だ。世界各国・地域で保護主義的な動きが散見されるが、最も影響が大きいのは米国の通商政策である。第2次トランプ政権が誕生した2025年1月以降、同政権は従前の通商秩序を根底から覆す政策を矢継ぎ早に打ち出し、世界経済と国際通商秩序に衝撃を与えている。「米国の労働者と農民を不公正貿易から守る」という方針の下、貿易政策であるはずの関税措置が、国内の格差拡大などに不満を持つ市民層に対する政治的なパフォーマンスとして用いられている(注1)。
2025年4月に発表された「米国第一の通商政策(America First Trade Policy:AFTP)」においては、「外国の非相互的かつ歪曲(わいきょく)的な通商慣行により、米国では年間1.2兆ドルに及ぶ巨額の貿易赤字が生じている」と記載されている。貿易相手国による不公正で不平等な貿易慣行によって、米国が著しく不利益を被っているとしており、米国市民の不満の矛先を貿易パートナーに仕向けている。
また、第1次トランプ政権との違いとして、中国などの特定国のみならず、友好国や懸念国を区別せずに追加関税を賦課しており、貿易赤字の解消に加えて、米国への投資や米国内への生産シフトを個別交渉で要求している。これらは、従来は米国自身が推進してきたGATT、WTOを中心に据えた「ルールに基づく自由で公平な貿易体制」を否定する動きであるともいえよう。
〔米国の通商政策についての詳細は、ジェトロ世界貿易投資報告2025年版第Ⅲ章![]() (11.6MB)の第1節「世界の通商政策を巡る最新動向」(2)主要国・地域の通商政策「米国の通商政策」を参照〕
(11.6MB)の第1節「世界の通商政策を巡る最新動向」(2)主要国・地域の通商政策「米国の通商政策」を参照〕
貿易摩擦の多角化を起こす中国製品
もう1つの大きな潮流である「過剰供給・過剰依存による脅威の顕在化」は、中国に関連する部分が大きい。中国は多国間主義や自由貿易の重要性を訴える立場をとっており、国際通商ルールを無視した措置を乱発する米国を非難している。2025年8月末の上海協力機構(SCO)では、多国間貿易体制を支持する「天津宣言」を発表したほか、BRICS、ASEAN、湾岸協力会議(GCC)などとの各種会合においても、自由貿易擁護の主張を繰り返している。
他方、中国は、新たに重要鉱物(レアアース、レアメタル)の輸出管理を強化している実態があり(2025年4月7日付ビジネス短信参照)、日本企業を含めて各国に大きな影響を及ぼしており、貿易制限的措置も散見されている。また、中国の主要な輸出市場である米国において、追加関税をはじめとする貿易障壁がさらに厚みを増した結果、中国からの輸出は第三国に向かう傾向が顕著となっている。米国以外の輸出先との間で貿易摩擦を引き起こす「貿易摩擦の多角化」が起きているといえよう。
中国国家統計局によると、同国の2024年の実質GDP成長率は5.0%だった。中国の経済成長は減速傾向にあり、特に2020~2022年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、ブレーキがかかった(注2)。2023年も5.4%と十分な回復には至らず、2024年も消費の停滞感が継続した。そうした中でも、財・サービスの純輸出は経済成長を1.5ポイント押し上げており、中国経済を下支えする格好になっている。国内消費の停滞感がある中で、国内生産を拡大し、製品の需要地を海外市場に求めている。
中国の2025年上半期の輸出をみると(注3)、米国向けの輸出は前年同期比10.7%減の2,156億ドルと減少する一方、ベトナム、インド、ドイツ、タイ、インドネシア、スペイン、サウジアラビア、チリ、ナイジェリアといった、東南アジアや南西アジア、欧州、中東、アフリカ、中南米向けが伸びている(表参照)。中国の輸出先の構成比をみても、第1次トランプ政権がスタートした2017~2018年時点では米国は約2割を占めていたが、2025年上半期には12%まで縮小し、代わりに新興国市場のポートフォリオが増大し、輸出先の多角化がみられている。
| 国名 | 輸出総額 | 貿易収支 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2024年 | 2025年1~6月 | 2025年1~6月 | |||||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 金額 | 構成比 |
前年同期 伸び率 |
金額 |
前年同期 増減額 |
|
| 米国 | 478.4 | 19.2 | 524.3 | 215.6 | 11.9 | △ 10.7 | 165.4 | △ 25.5 |
| ベトナム | 83.9 | 3.4 | 162.3 | 93.3 | 5.2 | 19.4 | 59.5 | 21.9 |
| インド | 76.7 | 3.1 | 120.6 | 65.3 | 3.6 | 14.0 | 66.7 | 10.0 |
| ドイツ | 77.5 | 3.1 | 107.1 | 56.7 | 3.1 | 10.6 | 14.7 | 9.6 |
| タイ | 42.9 | 1.7 | 86.1 | 50.6 | 2.8 | 22.0 | 29.1 | 8.5 |
| インドネシア | 43.2 | 1.7 | 76.8 | 40.6 | 2.2 | 15.1 | 5.3 | 2.7 |
| サウジアラビア | 17.4 | 0.7 | 50.0 | 27.0 | 1.5 | 13.2 | △ 0.3 | 7.0 |
| スペイン | 25.0 | 1.0 | 40.8 | 22.0 | 1.2 | 11.2 | 20.7 | 2.7 |
| チリ | 15.9 | 0.6 | 20.6 | 11.8 | 0.7 | 25.6 | △ 9.4 | 3.4 |
| ナイジェリア | 13.4 | 0.5 | 19.0 | 11.6 | 0.6 | 34.1 | 12.3 | 3.9 |
| 全世界 | 2,486.7 | 100.0 | 3,580.3 | 1,810.9 | 100.0 | 5.9 | 685.6 | 163.2 |
出所:グローバル・トレード・アトラスから作成
中国の貿易収支をみると、2025年上半期での対米黒字は前年同期比で255億ドル減少したが、対ベトナム貿易黒字は219億ドル増、対インドは100億ドル増、対ドイツは96億ドル増、対タイは85億ドル増と黒字幅が増大している。その半面、仕向け地側からみると対中貿易赤字が急拡大していることとなる。中国製品の流入増で摩擦が生じているのだ。
中国製の安価な製品が流入することを懸念する各国は、中国製品に対してアンチダンピング(AD)や相殺関税(CVD)の調査を開始している。WTO貿易救済ポータルによると、2024年の中国に対するAD調査の件数は前年比2.4倍の152件と過去最大に上った。CVD調査の件数も、2.1倍の25件と2018年に次ぐ水準となった(図2参照)。
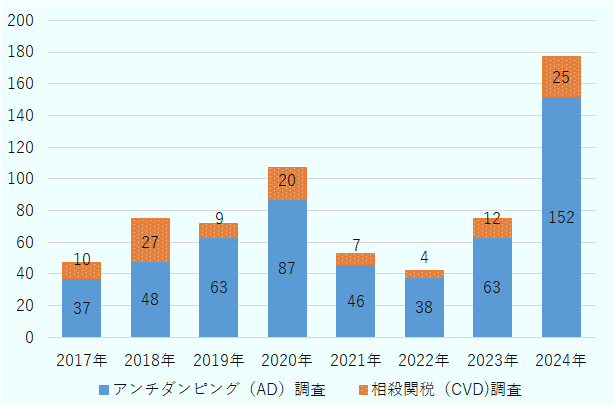
出所:WTO貿易救済ポータルから作成
なお、これらのグローバルサウス市場においては、既に進出している日本企業にとって競争の激化を意味しており、これが3つ目の潮流「グローバルサウスを巡る競争の激化」にもつながっている。
(ほかの潮流としてのデジタル政策や環境エネルギー政策の傾向については、ジェトロ世界貿易投資報告2025年版第Ⅲ章![]() (11.6MB)の第3節「世界の新たなルール形成の動き」を参照)
(11.6MB)の第3節「世界の新たなルール形成の動き」を参照)
共通の価値観を持つ同志国やグローバルサウスと連携し通商秩序を擁護へ
米国、中国の双方により、世界の貿易環境には大きな変化が生じている。特に第2次トランプ政権の登場により国際通商秩序は混乱の渦中にある。しかし、世界貿易総額のシェアを改めて見てみると、米国は11%に過ぎず、中国も15%となっており、合計しても26%と全体の4分の1程度である点には留意すべきだ(図3参照)。企業の観点からは、米国市場と中国市場への対応に関心やリソースが集中しがちだが、残りの4分の3のプレーヤーと、いかに貿易取引していくかは重要である。特にグローバルサウス諸国は今後30年間で約20億人の人口増が見込まれ(図4参照)、世界貿易におけるプレーヤーとしても、日本企業のパートナーとしても存在感を高めていくことが予想される。
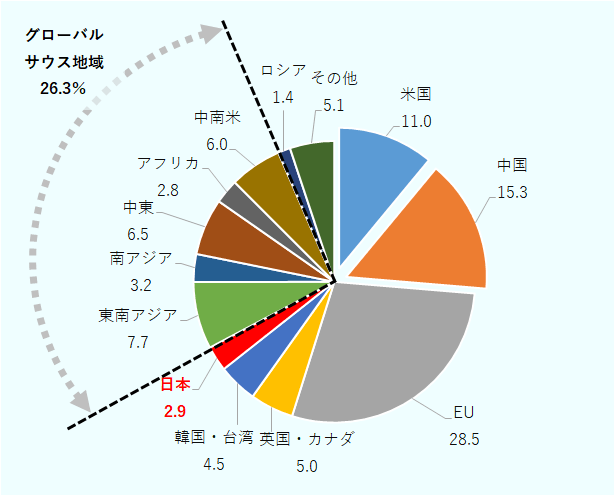
注:中国は香港を含む。
出所:UNCTADから作成
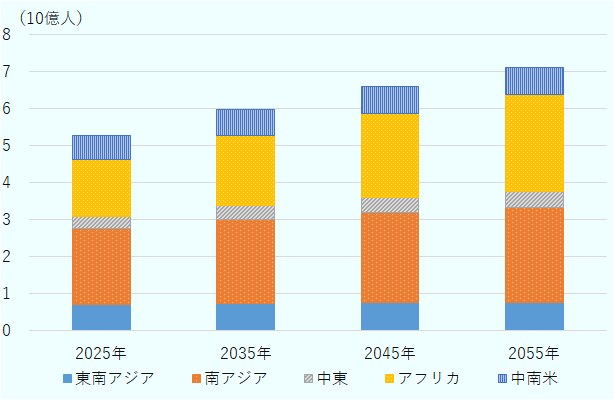
出所:国連人口統計から作成
また、それらの4分の3の国々が連携して、国際通商秩序、ルールベースでの自由貿易体制を擁護する多数派を形成し、イニシアチブをとることも可能だ。日本をはじめ資源・エネルギーや食糧などの輸入依存度が高い国々が多く存在する中、各国が平和的に経済成長するためには、安定的な通商環境と自由貿易体制の維持が必要となってくる。
現行では、米国を含まない広域自由貿易ブロックとして、世界から関心を集めているのが「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)」であり、なおかつ、米国が抜けた後の同協定をまとめて実現させた日本の役割に期待が高まっている。石破茂首相は2025年5月の日経フォーラムにおいて、自由貿易体制下でのさらなる経済成長に向け、CPTPPの枠組みの拡大に取り組む考えを示した。また、ASEANやEUとの対話を模索すると表明した。
EUも、米国が含まれない自由貿易の枠組みを拡大させつつある。2024年12月には、メルコスールとのFTA(自由貿易協定)交渉に最終合意した(2024年12月10日付ビジネス短信参照)。難航していた広域経済圏間でのメガFTA締結に向けて弾みがついた。停滞していたタイやマレーシアといったASEAN加盟国とのFTA交渉にも進展がみられている。2025年6月には、フォン・デア・ライエン欧州委員長がCPTPPとの連携を強化したいとの考えを示した(図5参照)。同委員長は7月の訪日の際、経団連との懇談会において「EUはCPTPPに関して構造的な協力を進めることで、ルールに基づく自由貿易が機能することを示したい」と述べている(経団連ウェブサイト参照![]() )。
)。
図5:連携を模索するCPTPPとEU、ASEAN
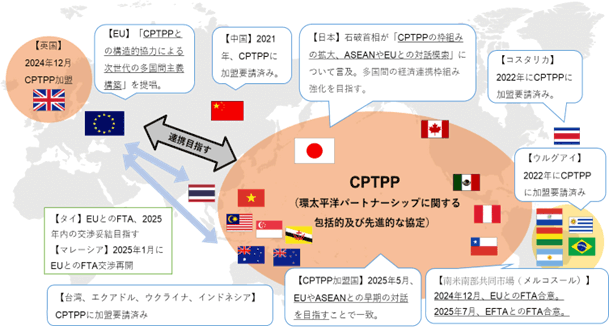
出所:内閣府・経済産業省資料、ロイター、ポリティコ、日本経済新聞など各種報道から作成
またEUは、米国を除く形で、機能不全に陥っているWTOの紛争解決制度を代替する枠組み「多国間暫定上訴仲裁アレンジメント(MPIA)」を主導している。WTOの第二審である上級委員会では、米国が委員選任を拒否しており、2019年12月から審理が行われなくなっている。そうした中、MPIAの参加国・地域間での紛争は、機能不全の上級委に上訴(いわゆる「空上訴」)して塩漬けにするのではなく、MPIAによる仲裁を通じて解決を図るという仕組みがとられており、これが機能し始めている。MPIAに参加する国・地域は拡大する傾向にあり、2025年5月にパラグアイとマレーシア、6月に英国が新たに加わった。2025年7月現在、EUとその27加盟国、日本や中国を含む57カ国・地域が参加している(2025年7月24日付ビジネス短信参照)。
世界貿易の割合では、日本は約3%と限定的だ。しかし、CPTPPや、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定などの広域経済圏において、中心的な役割を担っている。また、2024年7月に大きく進展したWTO電子商取引交渉においても、主導的な立場を担っている(注4)。米国や中国によって世界の通商秩序が混乱する中でも、EUなどの同志国やグローバルサウス諸国との連携を深めている。日本に対し自由貿易の擁護者としての役割に期待が高まっていると同時に、日本企業に対しても、信頼できる安定した貿易・ビジネスパートナーとして、追い風が吹いているとも言えるかもしれない。
(FTAや経済連携の動向については、ジェトロ世界貿易投資報告2025年版第Ⅲ章![]() (11.6MB)の第2節「多国間貿易体制の現状と課題」を参照)
(11.6MB)の第2節「多国間貿易体制の現状と課題」を参照)
- 注1:
- Richard Baldwin (2025) “The great trade hack: how Trump’s tariffs are rewriting the rules for global business”, “The Great Trade Hack: How Trump's trade war fails and global trade moves on”
- 注2:
- ジェトロ「中国の貿易投資年報」を参照。
- 注3:
- グローバル・トレード・アトラス(原典は各国通関統計)。
- 注4:
-
経済産業省プレスリリース(2024年7月26日付)
 。
。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部国際経済課 課長代理
北見 創(きたみ そう) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部アジア大洋州課、大阪本部、カラチ事務所、アジア大洋州課リサーチ・マネージャーを経て、2020年11月からジェトロ・バンコク事務所で広域調査員(アジア)として勤務。2024年10月から現職。






 閉じる
閉じる





