多国間主義に瓦解の兆し―試されるグローバルビジネスの耐性再編される世界投資―地政学リスクと補助金競争が導く新潮流
2025年9月29日
2024年から2025年上半期にかけて、世界の直接投資(FDI)は、地政学的緊張や保護主義的な政策、米中間の貿易摩擦の影響を受けて、減少傾向にある。その一方で、2024年は米国のインフレ削減法(IRA)やCHIPSおよび科学法(CHIPSプラス法、注1)、EUのグリーン・ディール産業計画(注2)、インドの生産連動型優遇策(PLI、注3)など、各国の産業支援策や補助金を追い風に、再生可能エネルギー分野や半導体分野へのFDIが活発化した。本レポートでは、世界投資の現状、地域別・分野別動向、今後の見通しについて分析する。
2024年の世界の直接投資は停滞
国連貿易開発会議(UNCTAD)が2025年6月に発表したレポート「World Investment Report 2025![]() 」によると、2024年の世界のFDI流入額は1兆5,088億ドルと、前年から3.7%増加した(図1参照)。しかし、オランダやルクセンブルクといった導管(conduit)国・地域(注4)を除外すれば、世界の対内直接投資は前年比11%減と推計され、実態としては減速基調が鮮明だ。
」によると、2024年の世界のFDI流入額は1兆5,088億ドルと、前年から3.7%増加した(図1参照)。しかし、オランダやルクセンブルクといった導管(conduit)国・地域(注4)を除外すれば、世界の対内直接投資は前年比11%減と推計され、実態としては減速基調が鮮明だ。
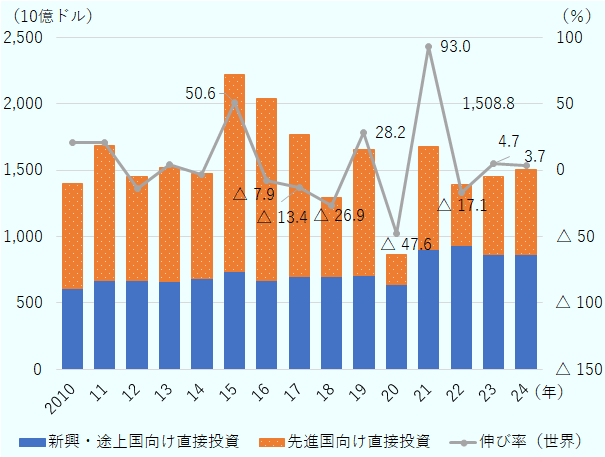
注:先進国・地域、新興・途上国・地域の定義はUNCTADの区分に基づく。
出所:UNCTAD「World Investment Report 2025」から作成
背景には、米中対立をはじめとする通商面での緊張や政策の不確実性と、インフレ圧力の持続、高水準で推移した金利や為替の変動といった複合要因がある。特に長期金利の上昇は大規模インフラ案件やエネルギー開発の資金調達コストを押し上げ、投資家のリスク許容度を低下させた。結果として、投資家は不確実性下で案件の選別を一層厳格化し、戦略的重要性の高いプロジェクトに集中する傾向を強めている。
投資形態別にみると(注5)、インフラ関連などの国際プロジェクトファイナンス(IPF、注6)は、2024年に金額ベースでは前年比26.2%減、件数も26.7%減と大幅に減少した。世界のクロスボーダーM&Aは、欧米を中心とした大規模取引が牽引し、実行額ベースで前年比14.5%増と上向いた。2023年に記録した10年ぶりの低水準から回復基調にあるが、依然として過去10年間の平均を下回る水準にとどまる。一方、グリーンフィールド投資(外国に投資する際に新たに法人を設立し、設備や従業員の確保、チャネルの構築を一から行う投資の方式)の発表件数は2024年に1万7,573件(過去最高)、金額ベースでは1兆3,053億ドル(過去2番目)に達した(注7)。
産業政策が呼び水に、産業別では明暗分かれる
好調なグリーンフィールド型の対外投資の背景には、主要国の産業政策と補助金支援がある。米国のCHIPSプラス法、IRA、EUのグリーン・ディール産業計画、インドのPLI制度などが投資の呼び水となった。生成AIの普及に伴うデータセンター投資も拡大し、クラウドサイバーセキュリティーなどデジタル経済分野が世界投資の新たな牽引役となった。
とりわけ、再生可能エネルギー分野は2024年も金額ベースで世界最大のFDI受け入れ先となり、全体の投資額のうち20.7%を占める(図2参照)。さらに、デジタル経済を支える通信インフラへの投資は全体の12.8%を占め、前年比83.2%増と急増している。クラウド需要を背景に、世界各地でデータセンター建設が加速している。
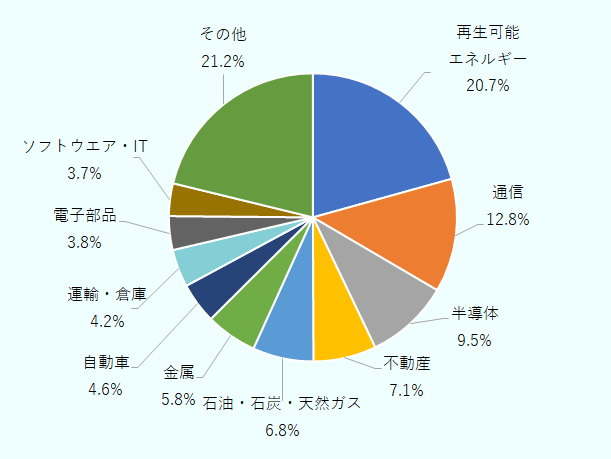
注:2025年7月4日時点。
出所:fDi Markets(Financial Times)から作成
さらに、半導体産業も、UNCTADによると、大型投資が相次いだ年となり、2024年の関連FDI額は前年比2.6倍と、全体の9.5%を占めた。2024年に発表されたグリーンフィールド投資(金額ベース)の上位10件のうち、4件が半導体製造に関するもので、うち3件が米国での半導体プロジェクトだった。これは、台湾や韓国の半導体大手が欧米やアジア各国で相次いで新工場計画を進めた結果で、各国政府の巨額補助金が追い風となった。実際、台湾積体電路製造(TSMC)は2024年4月、CHIPSプラス法に基づく最大66億ドルの補助金を受け、アリゾナ州に第3の先端半導体工場を建設することを発表した。また、インドに対する半導体関連の対内直接投資も大幅に増加しており、2024年の受け入れ件数は、米国(28件)に次ぐ第2位(13件)だった。インド政府は「セミコン・インディア・プログラム」の下、大型プロジェクトに補助金を支給しており、中央政府がプロジェクト費用の最大50%に相当する補助金を拠出する(2023年6月5日付ビジネス短信参照)。
世界の投資地図に変化の兆し、注目される新興地域
新型コロナ禍以前のトレンドとしては、FDI受け入れはEUや米国に集中していたが、近年は分散が見られる。2019年に世界FDIの約半分を占めていたEUと米国は、2024年には4割未満に縮小した。特にEUの構成比は34.3%から17.7%と半減し、減少が顕著だ。一方、アジア(中東を含む)のシェアは3割から4割へ拡大した(図3参照)。
図3:2019年および2024年の対内直接投資(フロー、主要国・地域別)
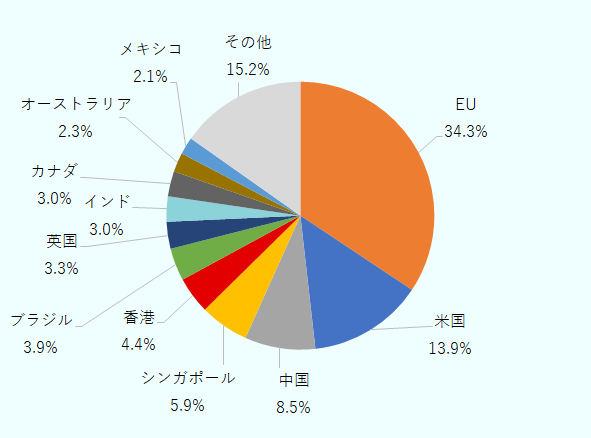
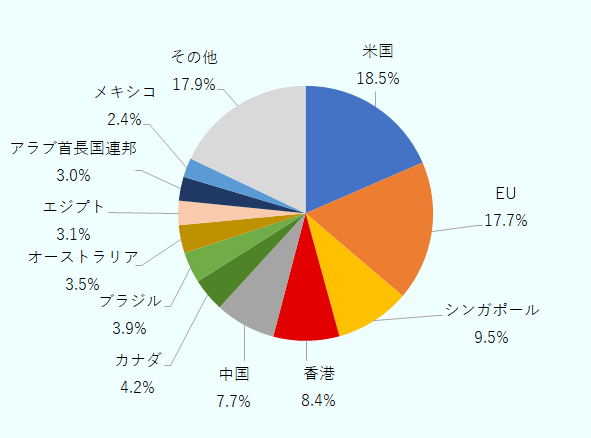
出所:UNCTAD「World Investment Report 2025」から作成
北米向けは、大型の企業買収案件もあり、2024年に22.6%増(米国で19.6%増、カナダで37.8%増)と堅調だった。米国ではクロスボーダーM&Aの買収額が倍増し、ハイテク産業やクリーンエネルギー分野への大規模投資が牽引した。他方で、欧州への投資は、2024年に前年から44%(導管国向けを除く)も減少した。ウクライナ情勢やエネルギー価格不安、金融市場の不安定化などが要因だ。EUは投資スクリーニング制度の対象拡大を進め、投資環境は一層複雑化している。
アジア太平洋地域では、米中対立を背景に「チャイナ・プラスワン」「イン・チャイナ・フォー・チャイナ」(注8)戦略が広がる中、アジア新興国やその他の有望市場に対する多国籍企業の進出競争が激化している。景気減速や米中対立の影響を受け、中国向け投資は前年比28.8%減と低調だが、ASEANへの投資は堅調で、2024年は前年比9.7%増、過去2番目に高い2,250億ドル規模に達した。中国企業自身もASEAN向け投資を増やしており、欧米と中国、現地企業の三極競争が激化している。
また、インドは近年、「メイク・イン・インディア」政策や生産連動型優遇策(PLI)の拡充により、製造業誘致を加速させている。PLI制度を背景に、電子機器などの分野で大型誘致が進展した。iPhoneの生産拠点移管はその象徴だ(2022年12月22日付地域・分析レポート参照)。戦略分野を中心とした投資規制緩和(2023年11月24日付調査レポート参照)や、2024~2025年度予算では海外企業向け法人税の引き下げ(注9)を打ち出し、国外企業にとって魅力的な投資先になることを目指している。その成果もあってか、2024年のインドは国別FDI流入額で第15位(2023年は第16位)となり、グリーンフィールド案件数も増加傾向になっている。
そのほか、新興国・地域では、中東・アフリカも存在感を高めている。中東は湾岸諸国を中心に経済多角化策が奏功し、2024年は前年比4.7%増となり、高水準の投資流入を維持している。アフリカでは75.1%増と大幅に増加し、同地域への対内直接投資流入額は過去最高を記録した。再生可能エネルギーや都市開発、インフラ整備を軸に、フロンティア市場として注目が高まっている。
このように、地政学リスクの高まりに加え、各国の積極的な誘致策も相まって、新興市場へのFDIは今後も拡大していくことが期待される。
2025年国際投資の展望:日本企業に求められる戦略的対応
2025年の世界の直接投資は、導管国・地域を除くと、2年連続で減少が見込まれる。UNCTADは2025年初頭には、同年の見通しについて緩やかな成長を予測していたが、同年6月にこの予測を下方修正した。足元では、追加関税の応酬に伴い、世界経済や資本市場や貿易の混乱、為替レートの乱高下、金融市場でのボラティリティーの上昇が投資マインドの回復を妨げている。また、地政学リスクや貿易摩擦も依然くすぶっており、UNCTADは「関税引き上げなどの影響で、2025年の国際投資の見通しは一段と不透明」と警鐘を鳴らしている。実際、2025年初頭時点の世界のクロスボーダーM&A(注10)は記録的な低水準に落ち込んでおり、企業は慎重姿勢を崩していない(図4参照)。地政学的対立と経済ブロック化の波を受けつつも、各国・企業が新たな成長分野への投資機会を模索する動きが今後のFDI動向を形作っていくと考えられる。
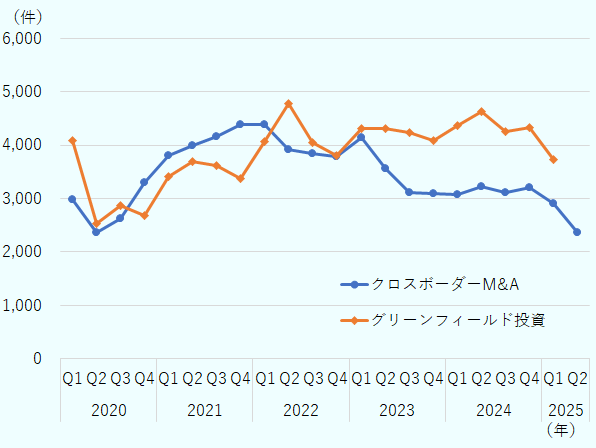
注1:クロスボーダーM&Aは実行ベース、グリーンフィールド投資は発表ベース。
注2:グリーンフィールド投資は2025年第1四半期(1~3月)まで。
出所:ワークスペース(LSEG、2025年7月2日時点)と fDi Markets(Financial Times)から作成
こうした中で、日本企業に求められるのは、投資先の再選別と供給網再編を同時に進める総合的な戦略だ。北米、インド、ASEANでは、戦略的分野の補助金連動型投資が拡大しており、日本企業は部品や素材、装置などの強みを生かし、とりわけ半導体や電気自動車(EV)、データセンターに関連する製品・サービス分野での存在感を高めることが急務だ。他方、中国市場は依然として高い魅力を有しているものの、投資環境には慎重な見極めが求められており、ASEANやインドを経由する供給網の再設計も視野に入れ、リスクを分散することが重要だ。また、投資を急速に呼び込む新興市場でも、中国やインドの資本との競争が激化しており、現地企業や第三国企業との合弁・共同投資を通じて競争力を確保する戦略が必要だろう。
総じて、日本企業はグローバル投資環境の再編を前提に、政策誘導型の成長市場を積極的に取り込みつつ、中国依存からの「デリスキング」を進め、新興市場での競争を勝ち抜くための協調的かつ戦略的な投資体制を構築することが求められるだろう。
- 注1:
- 米連邦議会が2021年度国防授権法に含まれたCHIPS法に対する予算措置を議論する中で、科学分野の研究開発向けの条項も盛り込まれた。そのため、CHIPSおよび科学法、またはCHIPSプラス法と呼ばれる。CHIPSはCreating Helpful Incentives to Produce Semiconductorsの略称。
- 注2:
- グリーン・ディール産業計画は、欧州委員会がEU域内への投資の呼び込みを目的に、2050年までの気候中立を目指す欧州グリーン・ディールの一環として、2023年2月に発表。米国IRAへの対抗策とされる。
- 注3:
- 「生産連動型奨励策(PLI)」は、インド政府が2020年度(2020年4月~2021年3月)に導入した国内製造業振興の目玉政策。対象の全14分野について、分野ごとの適格基準を満たせば、新規工場を設立した製造業企業に対し、売上高の増加額などに応じて、インセンティブ(補助金)を支給するスキーム。
- 注4:
- 多国籍企業が税負担の軽減などを目的に海外直接投資を行う場合に、優遇税制を有するルクセンブルクなどを介在するケースで、これらの国・地域は導管(conduit)国・地域と呼ばれる。2023年に起こったグループ再編や税務構造の最適化の反動で、2024年には一部再編スキームの終了や資金の後戻りが発生し、導管国への流入額が増加したとみられる。
- 注5:
- UNCTAD「World Investment Report2025」の投資形態分類、データに基づく。
- 注6:
- 国際プロジェクトファイナンスとは、資金調達方法にかかわらず、少なくとも1社の海外投資家が出資するプロジェクトを指す。グリーンフィールド投資(クロスボーダー)やクロスボーダーM&Aともそれぞれ重複する部分がある。実行済み案件ではなく、発表ベースの案件データを捕捉したもの。
- 注7:
- 本レポートでのグリーンフィールド投資の数字は、fDi Markets(「フィナンシャル・タイムズ」)に基づく。
- 注8:
- 「イン・チャイナ・フォー・チャイナ(In China, For China)」とは、主に外国企業が中国市場向けに製品やサービスを現地で開発・製造・販売する戦略を指すが、多国籍企業で中国拠点を中国市場向けに特化させ、それ以外のグローバル輸出拠点は中国以外に設けるという意味合いがある。
- 注9:
-
外国法人に対する法人税率については、ジェトロの制度情報(インドの税制:法人税
 )を参照。
)を参照。
- 注10:
- ワークスペース(LSEG)に基づく。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部国際経済課
馬場 安里紗(ばば ありさ) - 2016年、ジェトロ入構。ビジネス展開支援部ビジネス展開支援課/途上国ビジネス開発課、ビジネス展開・人材支援部新興国ビジネス開発課、海外調査部中東アフリカ課、ジェトロ・ラゴス事務所を経て、2024年10月から現職。






 閉じる
閉じる





