中国EV・車載電池企業のグローバル戦略中国電池企業の技術動向
2024年12月18日
中国自動車市場は2024年に入っても、新エネルギー自動車(NEV、注1)の快進撃が続いている。中国自動車工業協会(CAAM)の発表によると、2024年1~9月の国内自動車販売台数は前年同期比2.4%減の1,725万9,000台と減少しているものの、NEVの販売台数は35.6%増の739万2,000台と大きく増加した。NEVの自動車全体に占める割合は2024年1月の31.5%から9月には51.8%に上昇し、月を追うごとに高くなっている(図参照)。2024年1~9月のNEV販売台数の内訳をみると、バッテリー式電気自動車(BEV、498万8,000台)、プラグインハイブリッド車(PHEV、332万8,000台)の合計で全体(輸出の92万8,000台を含む832万台)の99.95%を占める。
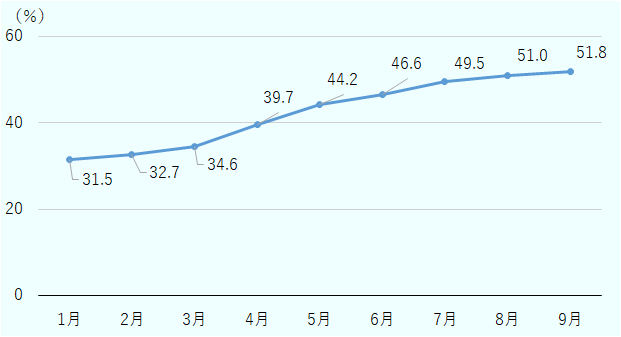
出所:中国自動車工業協会(CAAM)
国際エネルギー機関(IEA)が2024年4月に発表した「世界EV見通し2024![]() 」(注2)では、2030年までに中国で走る自動車の約3台に1台がEVに、米国とEUでは約5台に1台がEVになると予測している。EV市場が拡大する要因として、サプライチェーンへの大規模な投資や、政府による継続的な政策支援のほか、車体と車載電池の価格下落が挙げられる。IEAは同見通しの中で、2023年に中国市場で販売されたEVの約6割は内燃機関車(ICE)以下の価格と指摘。欧米でも今後数年間で、市場の競争や電池技術の向上により、EVの販売価格が下がっていくとの予測を示している。
」(注2)では、2030年までに中国で走る自動車の約3台に1台がEVに、米国とEUでは約5台に1台がEVになると予測している。EV市場が拡大する要因として、サプライチェーンへの大規模な投資や、政府による継続的な政策支援のほか、車体と車載電池の価格下落が挙げられる。IEAは同見通しの中で、2023年に中国市場で販売されたEVの約6割は内燃機関車(ICE)以下の価格と指摘。欧米でも今後数年間で、市場の競争や電池技術の向上により、EVの販売価格が下がっていくとの予測を示している。
LFP電池のシェアが7割強に
中国市場でのEV価格低下には、車両全体の価格をつり上げる最大の要因となっていた電池コストの削減に成功したことが大きく寄与している。現在主流の車載電池には、三元系電池とリン酸鉄(LFP)電池の2種類がある。LFP電池は三元系電池に比べて、エネルギー密度が低い。一方で、鉄とリン酸を主な材料としており、三元系電池のようにニッケル、マンガン、コバルトといった希少金属の使用が少ないことから、生産コストが安いのが特徴だ。
車載電池の業界団体、中国汽車動力電池産業創新聯盟(CABIA)の発表によると、2024年1~9月に中国市場の車載電池出荷量(搭載ベース)に占める三元系電池の割合は28.5%で、2020年同期の69.0%から大きく低下した。一方、LFP電池の割合は30.3%から71.4%に上昇した(表参照)。
| 年 |
出荷量 (全体) |
三元系電池 | LFP電池 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 出荷量 | シェア | 出荷量 | シェア | ||
| 2020年 | 34.2 | 23.6 | 69.0 | 10.4 | 30.3 |
| 2021年 | 92.0 | 47.1 | 51.2 | 44.8 | 48.7 |
| 2022年 | 193.7 | 77.2 | 39.8 | 116.3 | 60.1 |
| 2023年 | 255.7 | 81.6 | 31.9 | 173.8 | 68.0 |
| 2024年 | 346.6 | 98.9 | 28.5 | 247.5 | 71.4 |
出所:中国汽車動力電池産業創新聯盟(CABIA)
EV普及の初期段階では、航続距離を伸ばすことを優先課題として、エネルギー密度が高い三元系電池が多く採用されていたが、中国企業は技術革新を通じて、安価なLFP電池の性能を三元系電池並みに引き上げることに成功した。これにより、LFP電池の利用が一気に拡大した。
2024年1~9月のLFP電池のメーカー別出荷量ランキングを見ると、寧徳時代新能源科技(CATL)が全体の36.9%を占めて最も多く、続いて比亜迪(BYD、34.2%)、中創新航科技(6.3%)、国軒高科(5.0%)の順になっている。
中でも、BYDはLFP電池の性能向上に積極的に取り組む企業の代表例だ。同社は、EV向けの電池から車体まで自社で一貫して開発・生産している。同社が2020年3月に発表した独自開発のLFP電池「ブレードバッテリー」では、電池セルをモジュール化せずに、電池パックに直接接着・固定するため、限られたスペースに対してより多くのセルを搭載することができる。これにより、当時の同種類LFP電池に比べ、体積利用率(VCTP、電池バックの体積に対する電池セルの体積)を約50%高め、従来電池のエネルギー密度が低いという弱点を克服した。「ブレードバッテリー」を搭載した同社のEV車「漢(Han)」モデルでは、航続距離が605キロに延び、三元系電池とほぼ同じ水準に引き上げることに成功した。また、「ブレードバッテリー」は、モジュールとしての無駄を省いて、電池構造を簡素化したことで、電池の熱安定性が向上。熱安定の高さは、故障率の低減につながるとされる。
BYDはさらなる技術革新に向け、研究開発(R&D)に多額の投資を行っている。同社の2024年1~6月期のR&D費は前年同期比42.0%増の202億元(約4,242億円、1元=約21円)で、純利益を66億元上回った。この金額は中国の証券取引所のA株市場に上場する約5,300社の中で最高額を誇る。
また、安徽省合肥市に本拠を置く国軒高科は、材料の改良によりLFP電池の性能向上を図っている。同社は2023年5月、新型リン酸マンガン鉄リチウムイオン(LMFP)電池の「啓晨L600」を開発したと発表した。自社が開発したマンガンなどの材料と電解液を使用することで電力を高め、重量エネルギー密度を1キロ当たり190ワット時(Wh)に引き上げることに成功し、当時の三元系電池を上回った。航続距離も業界初の1,000キロを実現し、急速充電18分でフル充電が可能だという。
脱リチウムでナトリウムイオン電池が浮上
2021年半ばから2023年初めにかけては、中国市場などでのEV販売の急拡大に伴い、リチウムイオンバッテリー(LIB)の主要原材料のリチウムの供給が逼迫し、市場価格が高騰する中で、脱リチウムの開発が急速に進んだ。
注目される次世代電池の1つとして、ナトリウムイオン電池(NIB)が挙げられる。
NIBは、LIBに比べてエネルギー密度が低いが、海中などに豊富に存在するナトリウムを原材料とすることから、安定的な調達が可能で、製造コストも安いのが特徴だ。また、NIBの基本構造はLIBと似ており、従来の製造装置を流用できるなどの優位性もあるため、中国では早期の量産化に向けた動きが加速している。電池業界最大手のCATLは2021年7月、業界に先駆けて自動車向けNIBを開発したと明らかにした。電池セルの重量エネルギー密度は1キログラム当たり160Whで、通常の温度環境であれば15分で80%まで充電が可能だ。NIBは耐寒性に優れているため、氷点下20度の環境下でも90%以上の高い充放電効率(注3)も発揮できる。
同社は2024年10月24日に、PHEVとレンジエクステンダー式電気自動車(REV、注4)向け新型電池「驍遥超級増混電池」を公表した。同電池の搭載車両では、電動モーターだけで走行する(電動走行モード)距離で、世界で初めて400キロを突破したほか、4C(注5)急速充電も可能だ。同電池パックは、NIBとLIBのセルを一定の比率で統合した混合型電池のため、低温環境下の性能に優れたNIBの強みが発揮され、氷点下30度でも充電でき、氷点下40度でも放電が可能だ。既に理想汽車(Li Auto)や、長安汽車の傘下ブランドの「阿維塔(アバター)」「深藍」「啓源」、哪吒汽車(NETA)に納入しており、2025年までは吉利汽車、奇瑞汽車、広州汽車などの約30モデルにも搭載が予定されている。
全固体電池は小規模生産が開始
次世代電池として最も有望視されているのは、全固体電池だ。全固体電池は、電解液の代わりに、固体の電解質層を使う。低発火リスク、長寿命、高エネルギー密度などの特性を備え、航続距離の延長、安全性の向上が期待できる。また、可燃性の液体を使うLIBでは、発火リスクへの対応のために頑丈な金属の容器が必要となることから、重量が重くなる欠点があった。上述のとおり、低発火リスクを特徴の1つとする全固体電池では、そうした容器が不要となるため、軽量化できる。他方、実用化に向けては課題も指摘されている。固体電解質の価格が高く、使用量も多いことから、材料コストが高くなる。また、全固体電池は固体電解質の材料によって、硫化物系、酸化物系などに分かれるが、硫化物系の全固体電池では、固体電解質の製造に有毒な硫化水素ガスを使用し、製造した固体電解質も、硫化水素ガスの発生リスクを有することから、製造環境をコントロールするための設備コストがかかるとされる。
こうした中、北京経済技術開発区は2024年10月25日、開発区内の新興企業の北京純鋰新能源科技による全固体電池の生産ラインが本格的に稼働したと発表した。全固体電池の量産としては中国初となり、年間生産能力は200メガワット時(MWh)を計画している。電池のエネルギー密度などに関する性能指標は明らかにされていないが、高温性能に関しては、100度近い高温環境下でも正常に機能し、300度でも発火しないという。当面はエネルギー貯蔵、二輪車向けなどに供給する予定だ。
また、業界団体の中国電池協会は2024年10月26日、電池メーカーの上海屹鋰新能源科技が江西省於都県に建設した工場で、全固体電池の生産を始めたと発表した。年間生産能力は500MWhで、3C急速充電が可能な同電池は、主に中国の大手自動車メーカー、電池メーカーなどへの供給が予定される。同社は2021年に設立され、硫化物系全固体電池の開発・生産に取り組む新興企業だ。
全固体電池の実用化は現実味を帯びてきているが、上述の2社の生産規模はいずれも小さく、本格的な市場導入もこれからという段階だ。
BYD自動車工程研究院の院長で同社のチーフサイエンティストを務める廉玉波氏は2024年9月、海南省で開かれた「2024年世界新能源汽車大会」で講演し、BYDが全固体電池を幅広い領域で応用していくには今後3~5年を要するとの予測を明らかにした。廉氏は「全固体電池は生産コスト、材料調達などの制約があるため、LFP電池は今後15~20年にわたって淘汰(とうた)されることはない」とし、「全固体電池は主に高価格帯の車種での使用を想定しており、LFP電池とはそれぞれ異なる価格帯のモデルで使い分けていく」との見方を示した(「第一財経」2024年9月27日)。
裾野広がる応用領域
ここまでEVの競争力強化に向けた車載電池の技術動向について紹介してきたが、小型化が進み、エネルギー密度が向上した電池の応用先は、陸上の自動車にとどまらず、海上の船舶、空中の航空機にも広がっている。
電動垂直離着陸機(eVTOL)メーカーの上海峰飛航空科技は2024年8月、CATLから数億ドルの出資を受け入れるなどの提携契約に調印したと発表した。両社は今後、eVTOL向け航空機用電池の研究開発に共同で取り組んでいく。電池のエネルギー密度と性能の向上に力を入れ、eVTOLの飛行距離の延長と積載量の拡大を進めるとともに、安全性と安定性を強化する。CATLは資本参加を通じ、発展が期待される低空経済(注6)の成長を取り組む狙いだ。
上海峰飛航空科技は2024年4月、中国民用航空総局(CAAC)が同社の有人eVTOL「V2000EM(盛世竜)」の型式証明(TC、注7)の申請を受理したと発表した。盛世竜の最大離陸重量は2,200キロ、座席数は5座席の設計で、「空中タクシー」として利用する計画だ。ちなみに、同社が開発した貨物輸送向けeVTOL「V2000CG(凱瑞欧)は2024年3月、離陸重量1トン以上のeVTOLとして初めて中国民航空総局からTCを受領した。
安全性を疑問視する声も
中国電池業界は、巨額の投資を通じて原料調達から素材加工、部品生産、電池パックの組み立てまでのサプライチェーンを国内に集中させることで、車載電池の生産コストの低減だけでなく、技術開発の向上にもつなげてきた(2023年12月4日付地域・分析レポート参照)。中国企業はLFP電池市場で圧倒的なシェアを有し、電池価格の引き下げを通じて中国市場のみならず、世界市場でも価格競争力の高いEVを生み出している。
一方、中国メーカーの電池の安全性に関しては、疑問視する声も聞かれる。
CATLの曽毓群董事長は2024年9月1日、中国四川省宜賓市で開幕した「2024世界動力電池大会」で、中国で販売されているほとんどの電池は、発火や爆発のリスクを防ぐ安全性の確保が十分とは言えないと指摘した。同氏の発言によると、多くの電池の故障率は100万分の1だと主張されているものの、実際には1,000分の1程度だという。中国を走るEV約2,500万台に搭載されている電池セルは数十億個に達しており、その数字に故障率をかけると、潜んでいるリスクの高さは想像できると警鐘を鳴らした。
- 注1:
- NEVには、バッテリー式電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)のほか、燃料電池自動車(FCV)も含まれる。
- 注2:
- EVはBEVとPHEVの合計で、乗用車のみ。
- 注3:
- 充電電気量に対する放電容量の比率で、高いほど電池の性能が優れている。
- 注4:
- レンジエクステンダーとは、航続距離延長を目的に搭載される小型発電機からなるシステムを指す。レンジエクステンダーEVは、駆動用バッテリーの残量が低下すると、発電機として搭載しているエンジンが始動し、駆動用バッテリーに電気を補給する。
- 注5:
- Cレートは電池の充放電性能を指しており、1Cから始まり、数値が大きいほど性能が高い。
- 注6:
- 空飛ぶクルマやドローンなどの手段を用いて、低空飛行による乗客・貨物輸送を事業化し、社会変革をもたらす活動を指す。
- 注7:
- 航空機の開発時に必要な証明で、あらかじめ開発段階で設計や製造過程の検査を行っていくもの。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・上海事務所
劉 元森(りゅう げんしん) - 2003年、ジェトロ・上海事務所入所、現在に至る。




 閉じる
閉じる






