大阪・関西万博から世界へ、サステナビリティの社会実装「人権尊重」と「思いやり」は同じか
万博対話プログラムから見えた課題
2025年10月9日
「ビジネスと人権」分野における国際的な法規制の進展を受け、サプライチェーン全体での人権尊重の取り組み強化が求められている。日本では、大企業を中心に取り組みが進む一方、社会の「人権」に対する正しい理解が必ずしも十分でない点が指摘されている。本稿では、大阪・関西万博において「平和と人権」をテーマに実施されたプログラムを踏まえ、企業が「人権」を理解するために必要な視点を整理する。
大企業中心に人権尊重方針策定が進展、企業に求められる人権とは
日本では、経済産業省が、企業における人権尊重の取り組みを後押しするため、2022年に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」〔全文![]() (1.5MB)、ダイジェスト
(1.5MB)、ダイジェスト![]() (1.8MB)〕を策定した。翌年には、同ガイドラインの実務参照資料
(1.8MB)〕を策定した。翌年には、同ガイドラインの実務参照資料![]() も公表している。
も公表している。
これらのガイドラインや実務参照資料が明示する取り組みの1つが、国際的に認められた人権を尊重する旨のコミットメント(約束)を企業が示す、人権尊重方針の策定である。海外ビジネスに関心が高い日本企業に対してジェトロが実施した調査〔調査レポート「2024年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査(2025年3月)」〕によると、2024年度の調査時点で、人権尊重方針を策定し公開している企業は17.8%で、企業規模別にみると、大企業は59.4%、中小企業は10.7%と、取り組み状況に差がみられた(図参照)。しかし、中小企業において、今後方針を策定すると回答した割合は36.5%(注1)を占め、将来的な取り組みの進展が期待されている。
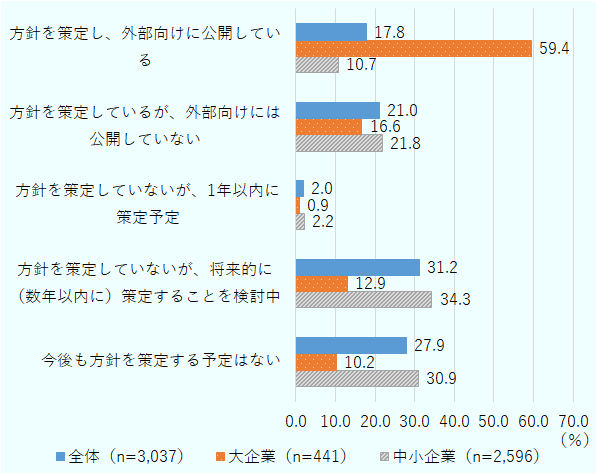
出所:ジェトロ「2024年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査(2025年3月)」
企業が方針の策定を含めた人権尊重に取り組む際に指針となるのは、2011年に、国連人権理事会において全会一致で支持された「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、指導原則)である。指導原則は3つの柱からなり、このうち第2の柱で、人権を尊重する企業の責任を定めている(注2)。この責任は、少なくとも「国際人権章典」および「労働における基本的な原則および権利に関する ILO の宣言」に表明されている国際的に承認された人権に適用される(注3)。これらの人権は、「ビジネスと人権」に関する取り組みが先行する大企業の人権尊重方針の多くで、尊重すべき人権として定義されている(表参照)。
| 企業名 | 制定日 | 方針の名称 | 尊重する人権の定義 |
|---|---|---|---|
| ファーストリテイリング | 2020年6月 | ファーストリテイリンググループ 人権方針 | 「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働の基本原則および権利に関する宣言」に記された人権を最低限のものとして理解。また「子供の権利とビジネス原則」「女性差別撤廃原則」の主旨に基づき、子供と女性の権利も尊重。 |
| キヤノン | 2021年10月 | キヤノングループ人権方針 | 「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」および「経済協力開発機構(OECD)責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」で表明されている国際的に認められた人権を尊重。 |
| 帝人フロンティア | 2021年12月 | 帝人フロンティアグループ人権方針 | 国連が規定した「国際人権章典」(「世界人権宣言」「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)および国際労働機関(ILO)が規定した「労働における基本的原則および権利に関するILO 宣言」に記されている原則を支持。 |
| 東芝 | 2022年3月 | 東芝グループ人権方針 | 「世界人権宣言」「OECD 多国籍企業行動指針」「労働における基本原則および権利に関する ILO 宣言」を支持。 |
| ワコール | 2022年4月 | ワコールグループ人権方針 | 国際的な原則・基準として、「ビジネスと人権に関する国連の指導原則」「OECD 多国籍企業行動ガイドライン」「国連グローバル・コンパクト 10 原則」「ILO 中核的労働基準」人権に関して最低限遵守されるべき原則・基準と理解し、支持。 |
| アシックス | 2022年6月 | アシックス人権方針 | 「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の中核的労働基準に表明されている人権を最低限のものとして理解し、これらの人権を尊重。 |
| ブラザー | 2023年1月 | ブラザーグループ 人権グローバルポリシー | 「国際人権章典」および「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」が定める人権を尊重。 |
| ミキハウスグループ | 2023年5月 | ミキハウスグループ人権方針 | 国際的に認められている「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」、「OECD 多国籍企業行動指針」などを尊重。 |
| パナソニック | 2023年8月 | パナソニックグループ人権・労働方針 | 「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」などに基づき国際的に認められた人権を支持。 |
注:ジェトロ、ILOの「責任ある企業行動と人権デューディリジェンス:日本企業のグッドプラクティス事例集(2024年)![]() (2.6MB)」の掲載企業のうち、人権尊重方針を公表している企業の事例を掲載。
(2.6MB)」の掲載企業のうち、人権尊重方針を公表している企業の事例を掲載。
出所:各社ウェブサイト
人権の尊重と「思いやり」の混同
こうした潮流の中、大阪・関西万博の「テーマウィーク」において、平和と人権をテーマに、多様な対話プログラムが実施された。本稿は、この一環として2025年8月9日に開催された「万博で考える平和と人権:平和はいかに実現し、人権はいかに保障できるのか?![]() 」というプログラムで紹介された「未来社会デザインに係る調査研究
」というプログラムで紹介された「未来社会デザインに係る調査研究![]() 」に触れたい。
」に触れたい。
同研究は、イベント主催者であるシェイプニューワールドイニシアティブと、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ、科学技術振興機構社会技術研究開発センターの共同プロジェクトである。8つのテーマ(注4)から未来社会のデザインを検討した報告書を公表しており、このうち、「平和と人権」をテーマとした報告書では、日本においては直接的暴力に関わる倫理観や社会制度の基礎は整っている一方、人権に対する意識が不十分と指摘した。例えば、日本は性的多様性に関する法整備の遅れがG7諸国と比較して顕著であるほか、多様性政策はグローバルサウスと比べても進んでいないことを挙げている。また、この共同プロジェクトでは、日本全国の1,200人を対象に、平和実現のために必要な価値観を自由記述形式で尋ねるアンケート調査も実施した。回答内容をもとに、傾向の分析を行ったところ、「人」「思いやり」「尊重」などが多く見られた一方、「人権」という単語はほとんど見られなかったという。
人権に対する認識の不足は、「未来社会デザインに係る調査研究」だけでなく、人権教育に関する研究でも指摘されている。例えば、宇都宮大学共同教育学部の黒川亨子准教授は、学校で行われる人権教育において、「思いやり」や「優しさ」が頻繁に取り上げられているが、思いやりは「自分が他者にどう接するか」という、主観的かつ人によって保障の程度が異なる、人権とは別の概念であると指摘している(注5)。広島修道大学人文学部の木村和美教授は、そもそも「権利」とは「道徳」や「倫理」と異なり、「実現を要求でき、その実現を果たす責任者が存在する」ものであるが、日本の人権教育では、権利そのものへの理解が欠けたまま、問題を私的な人間関係に矮小(わいしょう)化し、心の持ちようによる解決を委ねがちである点に懸念を示している(注6)。
人権は国際法によって定められた普遍的な権利であり、「人権の尊重」は主観に基づく「思いやり」とは本質的に異なる。各企業の人権尊重方針においても、人権の定義に共通点が見られ、人権は場所や立場を問わず尊重されるべきものであることが示されている。
企業は人権尊重をどのように捉え、進めるべきか
人権尊重への理解を深めるため、ジェトロは「万博で考える平和と人権:平和はいかに実現し、人権はいかに保障できるのか?」にて、登壇した4人の専門家にインタビューを行った。
まず、企業が「人権」を理解するために必要な視点を尋ねた。多様性などのテーマをフォローするコラムニストのサンドラ・ヘフェリン氏は、職場において従業員に対して妊娠・出産・育児休業を順番にとるよう強要することや、体質を考慮しない飲酒の強要など、いわゆるハラスメントとして認識されている事例は人権侵害に該当する、と指摘した。そのうえで、ヘフェリン氏は「企業は従業員の個人的なことに口出ししてはならない、と捉えるべき」と述べた。筑波大学人文社会系の秋山肇助教は、「自分はどう思うか?」という自身の感覚に落とし込んだ考え方は、人権尊重を考える入り口にはなりうるが、「自分と他者は違う」ことも認識する必要がある、と指摘した。筑波大学大学院国際公共政策学位プログラム博士後期課程在籍の上野流星氏は、企業において、経営層や現場などの立場によって理解の差異があることを認識することが重要、と指摘した。さらに、人権尊重はグローバルな概念でありつつも、そのままローカルに落とし込もうとしても、宗教や慣習などとの摩擦が生じ、通用しない場合があると述べた。清泉女子大学地球市民学部の佐々木萌専任講師は「企業における人権尊重は、労働者の現状を聞き取ることが第一であり、それが人権デューディリジェンス(注7)に必要なプロセスであると認識する必要がある」と指摘した。労働者の声を聞き取るにあたっては、一例としてEarthworm![]() のようにビジネス要素を考慮した活動を行うNGOに協力を依頼することも選択肢として考えられるという。
のようにビジネス要素を考慮した活動を行うNGOに協力を依頼することも選択肢として考えられるという。
また、すでに人権尊重に取り組む企業がある中、見落とされがちな視点を尋ねたところ、行き過ぎた配慮をしないことや、メンタルヘルスケアが挙げられた。行き過ぎた配慮について、上野氏やヘフェリン氏は、信仰や性的指向に基づいて、個人にラベルをつけ「この人は〇〇だからこのような配慮をされるべき」と決めつけることは、むしろ個人の意思が尊重されないと指摘した。行き過ぎた配慮はバイアスを助長する可能性があり、パターナリズム(強者が弱者に対し、相手の利益のためにという理由で、相手の意志にかかわらず干渉・介入すること)にもつながりかねないという。メンタルヘルスケアについて、佐々木専任講師は、全ての人がいきいきと働けるように、早期に相談できる環境づくりや、労働者のその時のニーズに合わせた労働環境の改善や医療機関との連携を含めた具体的なサポート体制が求められると指摘した。
本プログラムは、企業の人権尊重に関する取り組みを、社会的背景と結びつけて考える機会となった。「人権の尊重」と「思いやり」は異なる概念であり、企業が人権尊重方針を策定・実践するにあたっては、これらを混同せず、国際的な枠組みで定められている人権を理解する必要がある。そのうえで、さまざまな立場にあるライツホルダー(企業が尊重すべき権利を保持する主体)との対話を通じ、人権尊重方針の策定や、その実践をしていくことが求められる。
- 注1:
- 「方針を策定していないが、1年以内に策定予定」(2.2%)と「方針を策定していないが、将来的に(数年以内に)策定を検討中」(34.3%)の合計。
- 注2:
-
3つの柱は、(1)人権を保護する国家の義務、(2)人権を尊重する企業の責任、(3)救済へのアクセス。詳細は外務省「ビジネスと人権とは:ビジネスと人権に関する指導原則」
 (1.3MB)参照。
(1.3MB)参照。
- 注3:
-
外務省「国連の『ビジネスと人権に関する指導原則』に関するよくある質問―企業の尊重責任―
 (350KB)」。
(350KB)」。
- 注4:
- 8つのテーマは次の通り:未来への文化共創、未来のコミュニティとモビリティ、食と暮らしの未来、健康とウェルビーイング、学びと遊び、平和と人権、地球の未来と生物多様性、SDGs+Beyond いのち輝く未来社会。
- 注5:
-
黒川亨子、2022、「学校の常識」を法的観点から問い直す:人権教育を「砂上の楼閣」にしないために
 、立命館大学法学会、p.316–347
、立命館大学法学会、p.316–347
- 注6:
-
木村和美、2019、人権の視点から考える道徳科教科書:小学校第5学年、第6学年の「親切、思いやり」に着目して
 、広島修道大学ひろしま未来協創センター、p.215–229
、広島修道大学ひろしま未来協創センター、p.215–229
- 注7:
- 人権デューディリジェンスとは、次の(1)~(4)の一連の取り組みサイクルを回すこと。(1)事業活動による人権侵害リスクの特定・評価、(2)人権侵害リスクの防止・軽減、(3)人権尊重の取り組みの実効性の評価、(4)人権尊重の取り組みに関する説明、情報開示。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ企画部企画課
柏瀬 あすか(かしわせ あすか) - 2018年4月、ジェトロ入構。海外調査部国際経済課、市場開拓・展示事業部海外市場開拓課、海外調査部中国北アジア課、アジア経済研究所海外派遣員(台北市)を経て現職。






 閉じる
閉じる





