大阪・関西万博から世界へ、サステナビリティの社会実装地域コミュニティとの共創で実現するソーシャルインパクトの創出
難民経験者の社会起業家に学ぶESG経営
2025年8月29日
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)では、地球規模の課題解決について対話を行う「テーマウィーク![]() 」という取り組みを行っており、8月1~12日は「平和と人権
」という取り組みを行っており、8月1~12日は「平和と人権![]() 」がテーマに設定された。ジェトロでは、このテーマウィーク中に日本国際博覧会協会主催のプログラムに登壇した、ピース・バイ・チョコレートの創設者兼最高経営責任者(CEO)のタレク・ハドハド氏とラーンの創設者のパシュタナ・ドラニ氏に、取り組みや日本企業への期待について話を聞いた(取材日:2025年8月12日)。それぞれ、シリア難民、アフガニスタン難民としての経験を持つ。2人の社会起業家へのインタビューを通して、日本企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)経営を考える。
」がテーマに設定された。ジェトロでは、このテーマウィーク中に日本国際博覧会協会主催のプログラムに登壇した、ピース・バイ・チョコレートの創設者兼最高経営責任者(CEO)のタレク・ハドハド氏とラーンの創設者のパシュタナ・ドラニ氏に、取り組みや日本企業への期待について話を聞いた(取材日:2025年8月12日)。それぞれ、シリア難民、アフガニスタン難民としての経験を持つ。2人の社会起業家へのインタビューを通して、日本企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)経営を考える。
ハドハド氏の事例:難民受け入れが地域活性化の原動力に
ハドハド氏は2012年に、シリア内戦で難民となった。ハドハド氏の父はショコラティエで、シリアのダマスカスで製造したチョコレートを中東や欧州に販売していたが、シリア内戦で工場が爆撃されて全てを失った。レバノンでの3年間の避難生活を経て、2015年にカナダによる受け入れが決定。ハドハド氏の一家は、カナダのノバスコシア州アンティゴニッシュという小さな町で新たな生活を始めることになった。言語も文化も違う、未知の場所での再出発となったが、町の人々の協力で、チョコレートビジネスの再建に成功。平和を願って、会社をピース・バイ・チョコレート(Peace by Chocolate)![]() と名付けた。ハドハド氏は2020年に、カナダの市民権(国籍)を獲得。ピース・バイ・チョコレートは現在、アンティゴニッシュで3番目に多く従業員を擁する雇用主となっている。このサクセスストーリーは、同社名で本や映画にもなっており、大阪・関西万博でも映画が上映された。
と名付けた。ハドハド氏は2020年に、カナダの市民権(国籍)を獲得。ピース・バイ・チョコレートは現在、アンティゴニッシュで3番目に多く従業員を擁する雇用主となっている。このサクセスストーリーは、同社名で本や映画にもなっており、大阪・関西万博でも映画が上映された。
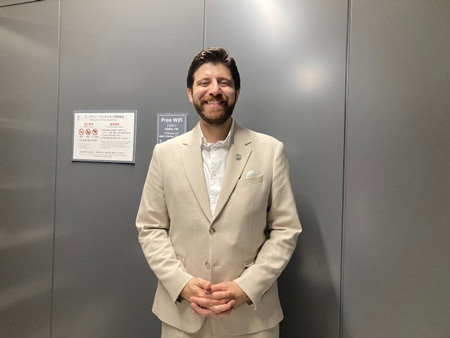
- 質問:
- 新たな場所でビジネスを成功させられた要因をどう考えるか。
- 答え:
- アンティゴニッシュという、カナダの中でも大都市から離れた、ハリファックスの近くの小さな町でビジネスを始めることは、当初、大きなチャレンジに思えた。しかし、今では、それが成功の大きな要因になったと感じる。新たな場所で人材を含むリソースを探し、戦略を練ることは容易ではなかったが、小さな町だからこそ、地域の人々の助けを得られた。また、小さな失敗を繰り返して、速いスピードでビジネスを成長させることができた。競争が激しい大都市ではこうはいかなかったと思う。
- 私たちは、アンティゴニッシュの人々の民間スポンサーシップでカナダに移住した(注1)ため、特に町の人々の協力を得やすかった。彼らはそれぞれ、医師、法律家、エンジニア、マーケターなどの経験をもつ優秀な人々であり、共にビジネスを成長させてくれた。起業には初期投資の資金も必要となるが、無利息でローンを提供してくれた。人々の協力でビジネスを急成長させることができたため、そのローンは3カ月で返済できた。彼らの協力は、学校での子供のケアや、空港への送迎など、生活の全てに及び、家族も含めて地域コミュニティの一部であると感じられた。政府のスポンサーシップでも支援は提供されるが、定められた職務内容の下に行われる。政府の枠組みよりも民間の枠組みの方が、地域コミュニティの自発的かつ包括的な難民の受け入れを促す上で効果的だと感じる。
- 移民の受け入れに積極的なカナダの制度と、持続的な発展のためにそれを生かす地域コミュニティの存在が、私たちの成功を可能にした。カナダでは、大都市に人口が集中しており、小都市はどのように人をつなぎとめ、持続的に発展するかが課題となっている。私たちはどんなに成長しても、地域コミュニティの声を聞き、地域経済に貢献する。ビジネスの成功で私たちの工場にツアーバスがくるようになり、近々、ミュージアムもオープンの予定だ。
- 質問:
- 日本企業へのメッセージは。
- 答え:
- 人工知能(AI)やSNS、コネクティビティの時代に、企業は常に社会から真価を問われている。企業経営において、利益追求にとどまらず、社会貢献に取り組むことは重要だ。日本企業の顧客第一の精神は、社会貢献の基礎になると思う。地域経済をリードする役割を果たし、人々のウェルビーイングに貢献する、利己的(Selfish)でなく、利他的(Selfless)な経営を目指すべきだ。
-
当社もサステナビリティ戦略を担当する、CSO(Chief Sustainability Officer)を置いて、社会貢献に取り組んでいる。私たちはピース・オン・アース・ソサイエティ
 というチャリティも立ち上げた。民間企業を含むさまざまなパートナーとともに、平和維持活動や難民支援、自然保護、先住民や若者の支援などに取り組んでいる。現在、日本でのチョコレートの販売開始に向けて準備中だ。日本でも、チョコレートを通じて平和の大切さを伝えたい。自社の取り組みに興味をもってもらえる日本企業があれば、コラボレーションしたい。
というチャリティも立ち上げた。民間企業を含むさまざまなパートナーとともに、平和維持活動や難民支援、自然保護、先住民や若者の支援などに取り組んでいる。現在、日本でのチョコレートの販売開始に向けて準備中だ。日本でも、チョコレートを通じて平和の大切さを伝えたい。自社の取り組みに興味をもってもらえる日本企業があれば、コラボレーションしたい。
ドラニ氏の事例:地域コミュニティとの対話が成功のカギ
ドラニ氏は、内戦でアフガニスタンを離れて難民となった両親の元に生まれ、パキスタンの難民キャンプで育った。パシュトゥーン人(注2)の部族のリーダーだった父親は、部族の繁栄を常に考え、教育熱心で、男女問わず教育機会を提供していた。ドラニ氏も、父親の教育を受け、また十分な教育を受けられない女性の実態を目の当たりにする中で、アフガニスタンでの女子教育の普及に身をささげることを決めた。2016年にはアフガニスタンに移り、子供と女性向けに教育の機会を提供するNGOであるラーン(LEARN)![]() を創立。2021年に女性の教育と就労に強く反対するタリバンがアフガニスタンに暫定政権を発足して以降は、米国に移住して活動を続けている。同年に、BBCの「影響力のある女性100人」に選ばれている。
を創立。2021年に女性の教育と就労に強く反対するタリバンがアフガニスタンに暫定政権を発足して以降は、米国に移住して活動を続けている。同年に、BBCの「影響力のある女性100人」に選ばれている。

- 質問:
- 現在の活動状況や課題は。
- 答え:
- アフガニスタンを拠点に活動することが困難なため、米国からプログラムをマネージする必要がある点がチャレンジだ。多くの面で、現地の関係者を信頼して任せる必要がある。現地への送金も困難だ。一方で、米国では私の活動を支持してくれる世界中の支援者とつながりやすい点が利点だ。米国には、支援者や多くの女性リーダーとつながりやすい環境がある。これまで、テック企業などの民間企業を含め、さまざまな支援者がインターネット環境やノートパソコン、資金などを提供してくれた。
- 質問:
- アフガニスタンでの活動で大切にしていることは。
- 答え:
- 地域コミュニティの信頼を得ることだ。教育の主体は地域コミュニティであり、私たちは彼らのリソースだ。プロジェクトを地域コミュニティに売り込むのではなく、彼らの意志で私たちを必要としてもらう。地域コミュニティとの対話を重視しており、彼らの課題が何か理解することから始める。私たちは女学校の運営も行っているが、その数は現在、アフガニスタンの14州に14校まで増えており、8月末には19校になる予定だ。アフガニスタンで女性教育に逆風が吹く中でこの成功を実現できたのは、地域コミュニティの実態を理解し、彼らとの協働を重視したからだ。
- 地域コミュニティの繁栄に貢献する女性の育成を考え、私たちはアフガニスタンで20のモバイルクリニックのプロジェクトも進めている。教育した女性が助産師となって、このプロジェクトをリードしている成功例がある。また現在、ヘルスケア領域のAIサービスの開発にも取り組んでいる。不安定な政情下におかれているアフガニスタンの女性に、AIを活用したメンタルケアサービスを提供すべくすすめている。
- 質問:
- 日本企業へのメッセージは。
- 答え:
- 持続可能な産業の発展と教育は表裏一体だ。教育とは学校を作ることではない。社会に貢献する人材を育てることだ。日本企業と私たちのようなNGOがコラボレーションすることによって、双方が持続可能な成長を実現できる。例えば、AI分野で日本企業がアフガニスタンの女性をトレーニングして雇用することで、アフガニスタンの女性はスキルを得られ、日本企業は彼女らの能力と新たな視点でビジネスを成長させることができる。AI分野に限らず、通信やコンテンツクリエーションなど、さまざまな分野でコラボレーションの可能性があるだろう。
万博で考えるビジネスにおける共創の大切さ
難民としての経験を経て、社会起業家として活躍する2人へのインタビューを通じて、地域コミュニティとの共創、というキーワードが浮かび上がってきた。ハドハド氏は、戦乱を逃れてたどり着いたカナダで、地域コミュニティと共同でビジネスを成功させている。ドラニ氏は、パキスタンの難民キャンプで育ちながら、母国のアフガニスタンのために、地域コミュニティと共同で女性教育に取り組み、その発展に貢献している。これらの事例は、社会に求められている価値を創出する上での、地域コミュニティとの共創の重要性を再認識させてくれる。
昨今、ESG経営に注目が集まり、ESGが形式的に企業統治に取り入れられることも多い。しかし、ビジネスの成功は、企業が社会での役割を果たすことで、おのずと実現されるという面もあろう。ESGを外部環境のトレンドとしてではなく、自社の理念に立ち返って社会と対話し、自社ならではの社会貢献の在り方を捉えなおすきっかけと位置付けることで、ビジネスの成長につながる、真のESG経営が実現できるのではないだろうか。
大阪・関西万博国連パビリオン陳列区域代表を務めるマーヘル・ナセル氏(国際連合事務次長補)もパレスチナ難民だ。同氏は、自国第一主義が台頭する昨今、国境をこえてあらゆる当事者が協力してグローバルな問題に対処する重要性を訴える。大阪・関西万博は、世界中のさまざまな人々の対話を通して、よりよい社会を実現するために、私たちができることを改めて考える場となっている。

- 注1:
-
カナダでは、政府による難民受け入れ制度に加えて、民間による難民受け入れ制度である「プライベート・スポンサーシップ」が発達している。カナダは1979年に、世界で初めて、ベトナム戦争で発生した多くの難民を受け入れるためにこの制度を作った。同制度では、衣食住に必要な経済的支援や、就業支援、学校や地域コミュニティへの参画のための支援を1年間提供するといった要件を満たせば、民間で難民を受け入れることが可能だ。この制度でこれまでに受け入れた難民の総数は39万人にのぼる。ハドハド氏は、「ブレンディッド・ビザ・オフィス・リファード・プログラム(BVOR)
 」という、政府と民間双方によるスポンサーシッププログラムでカナダへの移住が決まった。BVORでは、受け入れ先と難民のマッチメイキングは国連が、最初の半年間の経済的支援はカナダ政府が行うが、その他は民間のスポンサーが担う。ハドハド氏の民間スポンサーは、「シリア・アンティゴニッシュ・ファミリー・エンブレイス(SAFE)」と名付けられた、アンティゴニッシュの住人で構成されるグループだった。
」という、政府と民間双方によるスポンサーシッププログラムでカナダへの移住が決まった。BVORでは、受け入れ先と難民のマッチメイキングは国連が、最初の半年間の経済的支援はカナダ政府が行うが、その他は民間のスポンサーが担う。ハドハド氏の民間スポンサーは、「シリア・アンティゴニッシュ・ファミリー・エンブレイス(SAFE)」と名付けられた、アンティゴニッシュの住人で構成されるグループだった。
- 注2:
- アフガニスタンとパキスタンに居住するイラン系民族で、アフガニスタン国内で最大の人口を持つ民族。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部調査企画課 課長代理
新田 沙織(にった さおり) - 金融機関勤務を経て、2012年にジェトロ入構。デザイン産業課、スタートアップ支援課を経て2024年9月から現職。ケンブリッジ大学大学院修了(MBA)。




 閉じる
閉じる






