グローバルサウスでの競争激化、求められる日本企業のポジショニングとは中国製品の流入に揺れるタイ
現地日系企業は危機感
2025年3月24日
タイにおいて中国製品の流入が止まらない。関税措置を伴う米中対立や中国経済の低迷などを背景に、中国企業によるタイへの輸出が増加している。輸出製品は自動車や電気・電子、化学など幅広い分野に及ぶ。これら分野は、日系企業が得意としている分野とも重なる部分が多く、タイで操業する日系企業にとって中国製品との競争が激化している。最新の統計データや現地企業の声を拾うことで、タイにおける中国製品の存在感と日系企業への影響の実態に迫る(注1)。
自動車部品や電池、半導体デバイス、集積回路、PCBなどの中国からの流入が過去5年で顕著に
タイの中国からの輸入額を、10年前の2014年、トランプ政権1期目の2019年、2024年の3時点について、貿易統計データベースのグローバル・トレード・アトラスで見てみよう。全体として過去10年間、タイの対中輸入は増加傾向にあるが、2014年から2019年にかけての5年間と比べ、2019年から2024年にかけての後半の5年間における輸入の伸びが特に大きい(図1参照)。中国製品のタイ市場への流入が近年加速していることがみてとれる。
(金額、HSコード2桁ベース、2014年、2019年、2024年の3時点の比較)
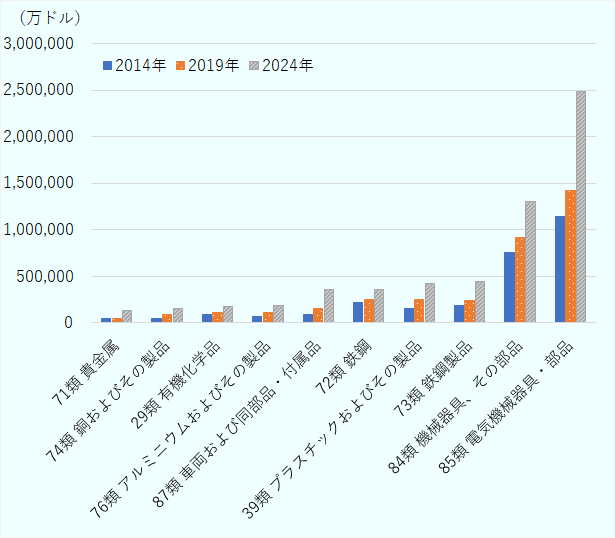
出所:グローバル・トレード・アトラスを基にジェトロ作成
直近5年間の輸入額の伸びが特に大きかったのは第87類(車両および同部品・付属品)であった。同類についてHSコード6桁ベースで見ると、「バッテリー式電気自動車(BEV、HS870380)」が直近5年で34倍となったのをはじめ、「自動車の部分品および付属品(車輪とその部分品・付属品、HS870870)」「自動車の部分品および付属品(車体のバンパー・シートベルトを除くその他の部分品および付属品、HS 870829)」「自動車の部分品および付属品〔駆動軸(差動装置を有するもの)および非駆動軸とこれらの部分品、HS870850〕」など、金額の大きな自動車部品関連品目でいずれも10年間で2倍以上の伸びとなっている(図2参照)。
(金額、HSコード6桁ベース、2014年、2019年、2024年の3時点の比較)
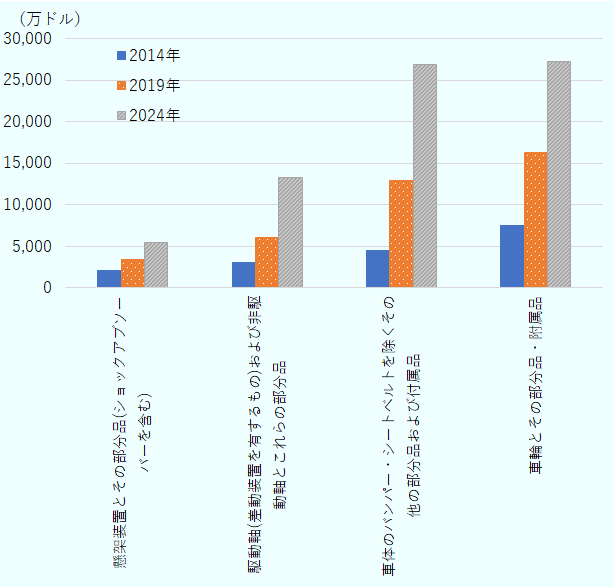
出所:グローバル・トレード・アトラスを基にジェトロ作成
また、タイの対中輸入において最大の品目(HSコード2桁ベース、2024年の対中輸入総額に占めるシェアは30.6%)である「電気機器およびその部分品」をHSコード4桁ベースで見ると、蓄電池(HS8507、うち9割近くをリチウムイオン蓄電池が占める)が直近5年で5倍近い伸びとなったのをはじめ、集積回路(HS8542)、印刷回路(HS8534、プリント基板:PCB)、半導体デバイス(HS8541)、コンデンサー(HS8532)などの品目が過去5年間で2倍以上の伸びとなっている(図3参照)。
前述の結果からは、米国がトランプ第1次政権期に打ち出し、バイデン政権においても維持された対中追加関税措置や新型コロナウイルスの感染拡大による国際的なサプライチェーンの混乱、中国国内市場の成長鈍化とそれを受けた競争激化(後述)などの変化を踏まえて、タイ市場に多くの中国製品・部品が流入していることがうかがえる。
(金額、HSコード4桁ベース、2014年、2019年、2024年の3時点の比較)

出所:グローバル・トレード・アトラスを基にジェトロ作成
中国過剰生産の「パワーゲーム」と対抗する日系企業
タイに流入する中国製品は、現地日系企業の製品とも競合しており、価格面だけではなく、品質面でも日本企業の優位性が失われつつある(2025年3月13日付地域・分析レポート参照)。プラスチック製品をタイで製造販売する日系化学メーカーA社は、中国企業の台頭について、「ここ数年で中国系企業の競合が30~40社増加した」と述べる。特定の製品領域では、中国における生産能力が世界需要の8割を占めるほどに拡大したという。中国にも駐在経験のあるC社担当者は、「(中国)国内で供給過剰のため東南アジアへの流入が起こっており、過当競争や市場価格の下落など、日韓欧米企業に甚大な影響が出ている」との見解を示す。
中国製品流入の影響は、他の業種にも広がっている。家電製品を製造販売するB社も、最大の競合相手は中国メーカーと指摘。「タイのみならずアジア全域で中国製品が台頭してきた」という。高付加価値な製品領域以外では差別化が難しく、圧倒的な生産規模で攻勢をかける中国企業による「パワーゲーム」になっていると懸念を示した。中国企業による大規模な生産に基づくコスト競争力、いわゆる規模の経済を問題視する声は他でも聞かれる。タイでエレクトロニクス関連製品を販売するC社は、中国からの製品流入によって、取扱製品について25%もの市場価格の下落を経験している。C社は、顧客とする自動車・家電分野の日系メーカーが中国の競合企業にシェアを侵食される中で、顧客市場の縮小と販売価格の低下という二重苦に直面していると語る。
中国企業によるシェア拡大については、自動車では中国メーカーがBEV(バッテリー式電気自動車)を筆頭に、タイの乗用車販売シェアを18.8%まで伸ばし、日本メーカーの同シェアは64.8%に低下している(2025年2月6日付ビジネス短信参照)。生産面でも、2024年にタイ工場を完工した比亜迪汽車(BYD)と広州汽車グループ傘下の広汽埃安新能源(AION)を含めて、主要メーカーがタイに進出している(2024年12月16日付地域・分析レポート参照)。家電では、2024年にハイアール(Haier)が東部チョンブリ県に約4億ドルを投じて、年間生産600万台規模のエアコン工場を設立することを発表した(注2)。美的集団(Midea Group)も年間60万台の空調設備を製造・(主に)輸出する工場を2025年第2四半期(4~6月)に稼働するほか、電子レンジや冷蔵・冷凍庫の生産拠点も別途建設する計画を有する(注3)。
こうした中国企業の攻勢にどう対応するべきか。各社に共通する認識は、生産規模や量産技術、コスト競争力では、中国競合に太刀打ちできないという点だ。そうした現状を踏まえ、中国メーカーには参入が難しい高付加価値な領域に注力するとの声が多い。B社は、中国競合にはない製品の多機能化に取り組むほか、最近では現地のタイ地場企業との協業を通じた新製品開発にも着手しているという。A社も、軽量・耐久性に優れた特殊製品を武器に、エンドユーザーの指定材となっている製品領域を維持・拡大する方針だ。ただし、A社は、優位な領域でも「一度参入されると、顧客(エンドユーザー)との製造技術の擦り合わせも進むため、中国企業が製造ノウハウを学び、そのまま市場を奪われるリスクもある」と警戒感を示している。
また、販売拡大に向けた輸出先として、米国への期待が大きい。産業機械部品を製造するD社など、タイで生産する製品の多くが米国向けという日系企業も複数みられる(D社、自動車部品メーカーE社)。トランプ新政権後も、公共事業を含めて米国の設備投資は足元で好調で、今後も受注が伸びるとの期待が高い。ジェトロの日本企業に対するアンケート調査(注4)でも、日本からの最重要輸出先として米国が首位に選ばれている。他方、E社は同政権による関税措置の税率次第で、タイからの輸出ではなく米国拠点での増産に切り替わる可能性があると述べる。D社も、為替の影響を受けて、タイ拠点ではなく日本本社から米国へ輸出する方が、コスト競争力が出てきていると指摘。C社は「全世界で地産地消のトレンドが浮上する中、タイの輸出競争力が低下している」との実感を示した。経済安全保障を動機とする国産優遇などの政策介入がグローバルに進む中、輸出拠点としてのタイの真価が問われる。
- 注1:
- ジェトロは2025年2月24日から26日にかけて、タイで事業活動する日系企業7社に対し、本調査にかかるヒアリングを行った。
- 注2:
- タイ投資委員会(BOI)プレスリリース(2024年9月19日)。
- 注3:
- バンコクポスト紙(2025年1月20日付)。
- 注4:
-
ジェトロ「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査(2024年度)
 (2.1MB)」。
(2.1MB)」。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・バンコク事務所 広域調査員
藪 恭兵(やぶ きょうへい) - 2013年、ジェトロ入構。経済産業省通商政策局経済連携課(日本のEPA/FTA交渉に従事)、戦略国際問題研究所(CSIS)日本部客員研究員、調査部国際経済課(経済安全保障)などを経て、2024年10月から現職。主な著書:『グローバルサプライチェーン再考:経済安保、ビジネスと人権、脱炭素が迫る変革』(編著、文眞堂)、『FTAの基礎と実践:賢く活用するための手引き』(共著、白水社)、『NAFTAからUSMCAへ-USMCAガイドブック』(共著、ジェトロ)。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部中国北アジア課 リサーチ・マネージャー
小宮 昇平(こみや しょうへい) - 2013年、ジェトロ入構。海外調査部中国北アジア課に配属。2016年3月より1年間の海外実務研修(中国・成都事務所)を経て、2017年3月から2018年8月まで中国北アジア課に所属。2018年8月から2023年7月まで中国・北京事務所にて調査業務等に従事。2023年7月から現職。






 閉じる
閉じる





