グローバルサウスでの競争激化、求められる日本企業のポジショニングとは化学企業、多角化と顧客関係強化を図る
インドでの競争環境(2)
2025年3月21日
インドでの競争環境の実態に迫る連載。第2回では、インドに進出する化学関係の日系企業に焦点を当ててリポートする。在インドの化学関連企業は、自動車向けの需要拡大により業況感は良好だ。他方、輸入品を中心に競合製品も徐々に増大しており、危機感を持つ企業も少なくない。日系企業のサプライチェーン以外での販路開拓や、新規事業領域の開発といった多角化戦略のほか、技術サービス拠点を設けてカスタマーリレーションシップを強固にする取り組みなどが進んでいる。
日系企業、インドでの市場シェア、競合とも増大
ジェトロが実施した「2024年度海外進出日系企業実態調査」では、各国に進出している日系企業に対し、競争環境の変化についてアンケートを行っている。図1は、主要製品・サービスの「現地市場シェア」が新型コロナ感染拡大前の2019年と比較して、どのように変化したかを示したものである。インド進出日系企業のうち、新型コロナ前と比較して市場シェアが「増加」した企業は6割を超える。ASEAN(38.5%)や中国(29.2%)と比較して大幅に高い(2025年3月13日付地域・分析レポート参照)。
業種別
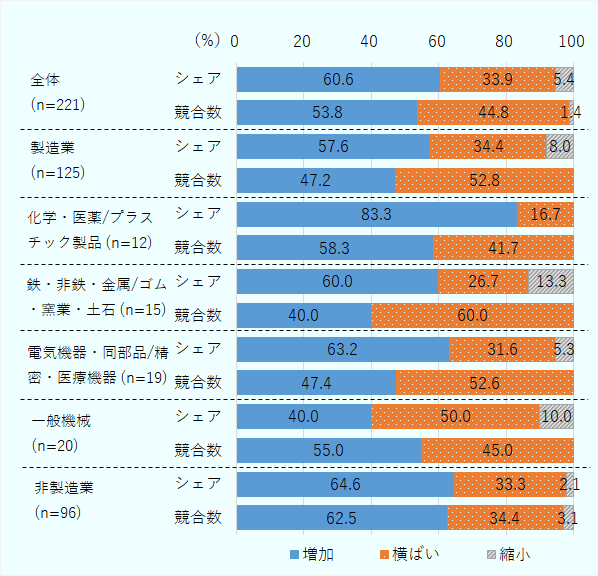
注:カッコ内は、有効回答数。「進出先市場における競合はない」と回答した企業を除いている。
出所:ジェトロ「2024年度海外進出日系企業実態調査」
他方、53.8%のインド進出企業が「競争相手数が増加」したと回答しており、大半の企業は競合の増加を感じている。この割合はASEAN平均(46.5%)より高いが、中国(60.4%)、ベトナム(57.4%)よりは低い。ただし、図1にもみられるように、業界により状況は様々である。そこで、今般の現地での日系企業へのヒアリング(注)を通じて得た情報を交え、産業ごとにインドにおける競争環境をリポートする。本稿では、化学関連企業に焦点を当てる。
化学・医薬/プラスチック製品の日系企業では、市場シェアが増加している企業が83.3%に上るが、他方で競合が増加していると回答した企業も58.3%と全体平均よりも高い状況だ。同業種に、競争相手(1~3番目に競争力があると考える企業)についてアンケートしたところ、「地場企業」を挙げる企業が92.3%と最も多かった。続いて、欧州企業が69.2%と続く。
化学・医薬およびプラスチック製品

出所:ジェトロ「2024年度海外進出日系企業実態調査」
日系化学A社:技術営業で一段階上のカスタマーリレーションシップを構築
日系化学メーカーA社は、ベーシックな化学品のほか、自動車産業、情報通信産業、ヘルスケア、農業など幅広い用途の商品を扱っている。委託生産品や輸入品を販売しており、2021年ごろからインドでの売り上げが伸びてきている。特に包装資材用の化学材料に、インド顧客からの引き合いが多い。インドではプラスチック廃棄物の規制が導入・強化され、プラスチック製品から紙製品への切り替えが進んでいる(2023年1月13日付地域・分析レポート参照)。ただ、インドでは一般的に、紙の包装資材にポリエチレンフィルム等がラミネーションされている(貼り付けられている)ため、当該資材の再生利用や再資源化は難しい。他方、同社製品はコーティングが薄く、再生利用が容易であるため、資材のリサイクルにも関心のある企業から購入が進んでいる。
同社のインドにおける競合相手は欧米系メーカーが中心である。こうした競合メーカーの多くはシンガポールやタイから競合製品を輸入している。競合製品には輸入関税が賦課される一方、A社では、同等の化学品をインド地場企業に委託生産することで関税を回避し、コスト面で現地生産の強みを得ている。また、現在のところ中国企業の製品は脅威となっていないものの、中国本土からの輸入品が徐々に流入しており、警戒感を強めている。「中国本土では、中国資本の競合メーカーが(自社の得意とするセグメントである)技術水準の高度な製品の生産能力を増強している。もし中国から、汎用品に加えて高付加価値品がインドに流入してきた場合、価格で競争していくのは難しい」とA社担当者はいう。
A社は競合との差別化に向けて、技術サービス拠点を設置した。同社は地場企業からの受注が圧倒的に多い。直接的な顧客のみならず、エンドユーザー(顧客がA社材料を使って製造した製品を利用)にも、センターに来訪してもらう。そこで、エンドユーザーのニーズをくみ取り、彼らが実現したいような材料の使い方や機能を提案する。「エンドユーザーと一緒に作り上げることで、従来よりも1~2段階上の商品開発・提案ができる。コストダウンも可能」とA社担当者はいう。研究開発拠点は日本にあるため、顧客との距離が遠かったが、技術サービス拠点を持つことで、インドでの技術営業がしやすくなった。結果的に、エンドユーザーからの指定買いにつながる。
日系化学B社:「宝の山」の市場で、投入する技術スペックとタイミング見極めがカギに
日系化学メーカーB社は、インド南部に工場を有し、自動車・オートバイや日用品・消費財(FMCG)業界向けの素材を生産・販売している。B社の担当者はインド市場について、「宝の山」だと感じている。競合メーカーなどが未着手で、製品自体が持ち込まれていなかったり、輸入品で対応していたり、開拓余地のある事業領域がまだたくさん残っているからだ。同担当者は、自社の持つ様々な素材技術を、どの分野で、どういった時間軸でインドに持ち込むか、日頃から戦略を考えている。高機能素材は、市場の成熟度と合致しなければ売れない。特に地場企業向けでは価格が合わないからだ。例えば、FMCGについては、インドの世帯年収の伸び率が想定よりも緩やかであるため、より付加価値の高い高機能素材を投入するにあたっては、そのタイミングも重要となる。
現在、B社では、自動車・オートバイのサプライヤー向けの製品を生産している。最終的には、主に日系自動車メーカーに使われる素材だ。競合製品としては、日系企業が日本、ASEAN等から輸入する製品や、欧州メーカーの現地生産品があり、コスト競争が厳しい面もある。輸入品に対しては、基本関税(7~8%)に加えて、社会福祉課徴金として基本関税の10%が課税されるため、現地生産しているメリットを最大限に生かす。
B社の取り組みの1つに、販売先の多角化が挙げられる。日系自動車メーカーが上り調子となっているが、同社では、日系自動車メーカーに加えて、韓国系メーカーへの売り込みを強化するため、韓国人の営業担当者を現地採用した。インドの乗用車市場では、現代自動車と起亜が約20%のシェアを有しており、非日系への販売にも取り組む余地は大きい。別途ヒアリングした日系金融機関の自動車業界担当者も、「日系企業同士のサプライチェーンでは、仕事が安定して得られる一方、利幅は薄くなりがち。他国市場に比べて製品単価の低いインドでは量を売ることが重要。さもなければ赤字経営となり、インドから退場を迫られる」と指摘する。
B社は、事業領域の多角化にも取り組む。インドでの市場は育っていないが、新たな事業のシード段階として、インドの大学と産学連携のプロジェクトを進めている。加えて、現地のパートナー企業との合弁事業の検討も進めている。「中国市場に比べて、インド市場の売り上げや利益の規模は現状では小さいが、今後30年~40年と安定して経営できるように事業を育てていきたい」と同社の担当者は考えている。
日系化学C社:自動車向け材料は好調も、安定的な事業継続のため市場多角化を目指す
日系化学C社も、事業領域を広げようと取り組んでいる。同社は、グローバルでは電気・電子機器や液晶、環境など、多様な事業領域があり、様々な業界に化学素材を供給する大手企業だが、インドに関しては自動車産業向けの売り上げが全体の8割以上を占めている。インドの自動車市場の発展に伴って、同社の売り上げも増大している。インドに進出した2000年代から年数を経ており、現地で採用・育成されたインド人営業マネージャーが活躍している。日系に加えて、地場大手自動車メーカーからの受注も獲得できている。ローカル企業の成長を取り込むことには成功したが、特定産業に偏りがあることには一定のリスクも伴う。同社の社長は「現在の事業領域における既存製品のみでは、市場競争の観点からは経営は厳しくなっていくだろう。新たな製品分野にも取り組んでいきたい」と危機感を持つ。
自動車産業以外に目を向けると、インドでは電気・電子機器産業、一例としてスマートフォン向けの化学材料に需要が高まっている。米中対立の潮流から、電子機器製造受託(EMS)メーカーは、生産地を中国からインドやベトナムにシフトさせる流れがある。これまでインドで行われるのは部品の組み立て工程のみであったが、スマートフォン用の部品もインドで現地生産される潮流があり、当該部品のサプライヤーから化学材料の現地調達ニーズが生まれている。現在、インド政府が誘致・育成しようとしている半導体産業(2024年12月3日付地域・分析レポート参照)についても、「半導体製造工程の一部で使われる化学材料を有しているため、インドでも新たな納入機会が生じる可能性がある」(C社社長)という
現在のモディ政権が推進するインフラ開発の恩恵もあり、鉄道向けも期待できる分野だ。インドでは、鉄道車両の生産が増大している。鉄道車両向けの材料は、自動車向けの材料から応用が利くため、ゼロから開発しなくてよいのがメリットだ。ただし、インドの鉄道車両は、欧州の技術が規格・標準となっていることも多く、欧州メーカーが手ごわいライバルとして存在する。
ほかにも、バイオ燃料などのエネルギーや医療・医薬品といった新たな領域もあり、C社は調査を始めているところだ。C社の社長は「今後5~10年で新たな事業領域が育てば、安定的な収益につながる」と期待する。競合メーカーは基本的に輸入で対応している中で、新たな製品群での現地生産を開始すれば競争力も出てくる。しかし、「やみくもに現地化しても、必ずしもコストが安くなるわけではない」と同社社長はいう。「一度、生産を開始してしまうと、小規模であっても撤退に時間と労力が伴う。慎重に育つ領域を見極める」と語る。
本稿では、化学メーカー3社の事例を紹介した。市場シェアの拡大がみられる業界だけに、各社とも現状の業況感は良好である。他方、特定産業への依存度の高さや、競合製品の増大により、危機感を有する企業は少なくない。各社では、販売先や事業領域の多角化、顧客関係の強化といった取り組みを進めている。
- 注:
- ジェトロは2025年2月10日から14日にかけて、インドで事業活動する日系企業13社に対し、本調査にかかるヒアリングを行った。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部国際経済課 課長代理
北見 創(きたみ そう) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部アジア大洋州課、大阪本部、カラチ事務所、アジア大洋州課リサーチ・マネージャーを経て、2020年11月からジェトロ・バンコク事務所で広域調査員(アジア)として勤務。2024年10月から現職。






 閉じる
閉じる





