高度外国人材と創出する日本企業のイノベーティブな未来現場の課題を題材に、独自の研修で人材育成(愛知・高砂電気工業)
2025年4月15日
精密部品の設計・製造を行う高砂電気工業(本社:名古屋市緑区)では、2021年ごろから高度外国人材の採用を本格化し、現在は12人の高度外国人材が在籍する(2025年1月31日時点)。出身地はインド、中国、台湾、インドネシア、アフガニスタンなどアジア地域を中心に多岐にわたる。2022年度にジェトロの「高度外国人材活躍推進コーディネーターによる伴走型支援」に採択され、ジョブフェアへの参加や育成定着に関する取り組みを進めている(2024年3月19日付地域・分析レポート参照)。今回は、同社で実施した「暗黙知」(注1)に関する外国籍社員向けの社内研修を取材した(取材日:2025年1月31日)。
育成~定着フェーズ、現場の課題解決につながる研修企画
同社では、外国籍社員を本格的に増やし始めた2023年1月から、社内研修やイベントを開始し、職場の実際の課題解決を目的に、毎年度テーマを決めて社内研修の企画をしている。2024年10月から開始した研修テーマの1つが「暗黙知」だ。このほかにも、社員がそれぞれの母国を紹介して社内の多様性を理解する企画や、外国籍社員が自身のキャリアに対する考えを共有する企画の実施を予定している。
採用や研修などの人事関連業務を担当する中野咲樹チーフは「社内研修のテーマには、現場でのリアルな課題を取り上げることを重視している」と強調する。特に外国籍社員が多く在籍する未来創造カンパニー設計技術課の浅井公規課長と定期的に情報交換し、現場の課題を把握している。
今回の「暗黙知レクリエーション」は、日本語特有の曖昧な表現から生じる、日本人社員と外国籍社員の間の認識のギャップを埋めるために企画された。外国籍社員に、意図が不明瞭な点は質問をすることが大切ということを理解してもらうことを目標としている。また、日本人社員にも今回の研修の様子を共有し、明確な表現を心がけてもらうことが狙いだ。一方通行ではなく、「外国籍社員、日本人社員の双方の目線を合わせることが大切だ」と中野氏は強調する。
実際の現場でのコミュニケーション題材にクイズ形式で考える
研修内容は、ウォーミングアップとして「オノマトペ(擬音語・擬態語)クイズ」「Kokiさんの日本語を当てろ!」「こんなときどうする」という3つのパートに分けて、2時間にわたって行われた。どのテーマも実際に現場でよくあるコミュニケーションの課題を題材にしたものだ。研修には12人の外国籍社員全員が参加した。各テーマともディスカッションの時間を設け、できるだけ日本語で話すことを意識して進められた。
「オノマトペクイズ」は、日本人が普段から多用するオノマトペの意味を当てるクイズだ。表示される画像の様子に適したオノマトペを3つの選択肢の中から選ぶクイズを5問出題し、チーズが溶けて「とろとろ」している様子や、たくさんの荷物が積み上がって「ぐらぐら」している様子などの問題が出された。中野チーフは、「オノマトペを使った表現は外国人にとって難しい」という。外国籍社員の平均的な正解数は2~3問で、全問正解できたのはわずか1人だった。
「Kokiさんの日本語を当てろ!」では、「Kokiさん」こと浅井課長の指示や発言を題材にして作成した問題だ。例えば、Kokiさんから月曜日の朝に「急いでいません。時間がある時に書類を提出してください」という指示を受けたことを想定し、いつまでに提出するかを問う問題などが出された。「時間がある時に」といった曖昧な表現について、Kokiさんがどのぐらいの期限を想定して指示をしているのかを考える。この例では、「当日の昼」や「2日後の水曜日中」など、外国籍社員の答えは分かれた。このほかにも、「すぐに修正して」といった問題も出された。指示された人によって捉え方が変わってくる表現について、どのような表現ならば双方の認識のずれが発生しないかをグループで議論した。外国籍社員は「具体的な日時の指示が必要」などの意見を交わした。
最後は、「こんなときどうする」。実際に業務中によくあるやり取りを想定し、どのように行動すればよいかを考えるという内容だ。例えば、自分が上司に対して「この資料は明日までに提出する必要がありますか」と質問し、「大丈夫です」と返された場合、どのように行動するのがベストかを考える。外国籍社員からは、「コンビニなどで『袋、要りますか』に対して『大丈夫』と言うケースなど、『大丈夫』という言葉は意味がたくさんあって難しい」との声も上がった。また、この問題に対する行動については、「いつまでに提出するか聞き返す」とか、「明日出しますと伝える」など、さまざまな意見が出された。浅井課長は「曖昧な指示を受けた時は、自分が理解した内容を相手に伝えることが大切」とアドバイスした。
全体を通じ、それぞれの外国籍社員は自分の実際の経験と照らし合わせながら、積極的に議論を展開し、講師の浅井課長や中野チーフとも活発なやり取りを行った。

研修後、同社で2人目の高度外国人材として入社した外国籍社員、未来創造カンパニー第二海外戦略室長のアディ氏(インド出身、2021年入社)、2024年10月入社の未来創造カンパニー設計技術課のアリ氏(アフガニスタン出身)に研修の感想や今後の目標などについて聞いた。
新人のアリ氏は今回の研修で、「円滑に業務を進めるためにも、言葉の意味を確認することや、密なコミュニケーションが大切ということを学んだ」と話す。2年前に来日し、日本語でのコミュニケーションはまだ難しいというアリ氏は「日本語の講義を受講して勉強に取り組んでいる」と言い、日本語能力の向上を直近の目標に挙げた。
管理職として同社の海外戦略立案にも携わるアディ室長は研修中、率先してチームの後輩に意見を促す様子が見られた。研修参加の目的について「これまでの自分の経験から得た感覚を基に、新人の外国籍社員たちに日本人の考え方のポイントを伝えること」といい、先輩社員として後輩の育成に尽力していることがうかがえた。また、「後輩のロールモデルとなることが目標だ。後輩の外国籍社員の全員が自分と同じキャリアをたどるとは限らないが、1つのお手本として自分の道を作りたい」と今後の目標を語った。
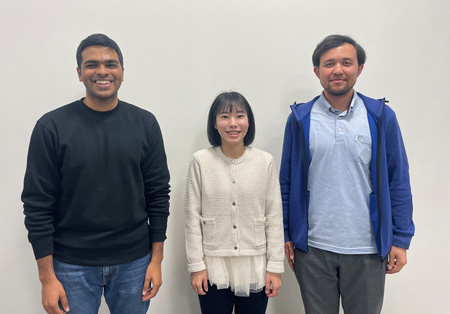
「日本語を諦めない」が外国人材の成長に不可欠
講師を務めた浅井課長は、今回のレクリエーションを通して「日本人はさまざまな擬音語、擬態語、副詞などを無意識に使っている。それが誤解を生むケースもあるということを外国籍社員に知ってもらえたことが最大の成果だ」と話す。日本語では子供に対して擬音語や副詞を多用することが多い。そのため、日本語が不得手な外国人に対しても、「『やさしい日本語』を子供に話すように伝えればよいと無意識に考え、擬音語や擬態語を多用する傾向がある」と指摘する。
研修の中で浅井課長が特に驚いたのは、「そっと」(静かに、音を立てないように物事を行うさま)という副詞を理解している外国籍社員が少なかったことだという。N1(注2)取得者で流ちょうに日本語を話す社員を含め、「適当に」という意味だと認識している社員が多かったのだ。現場でも製品の取り扱い時に「そっと扱ってください」などと多用する言葉でもあり、「研修で取り上げたほかの単語はともかく、『そっと』は当然理解できていると思い込んでいた」という。今回の外国籍社員の反応で、浅井課長自身も気づきがあったといい、「認識のギャップを双方の視点で考えるきっかけになった。ディスカッションの様子からそれぞれの社員の日本語能力もあらためて把握できた」と話す。「日本語がウイークポイントになっている社員には、より頻繁にコミュニケーションをし、ケアしていきたい」という。
浅井課長は外国籍社員に対して強く思っていることとして、「日本語を諦めてほしくない」という思いを挙げる。「日常会話で不自由しないレベルで満足してしまうと、技術面でのノウハウや知識を新たに得る機会を失ってしまう」と考えるためだ。技術やノウハウを学べる相手は、上司や同僚、顧客などが挙げられるが、日本で働く以上、その相手はほぼ日本人で、英語で伝えられる人たちばかりではないのが実態だ。浅井課長は「例えば、ある程度日本で働いて、技術力を身に着けて母国に帰ろうとしている外国人の場合、日本語能力を諦めずに、いかに向上できたかによって、帰国時までに得られる技術力や知識には大きな差が出ると思う」と指摘する。同社で働く外国籍社員の技術力や知識向上のためにも、日本語能力向上の手助けを積極的にしていきたいという。
今回の研修を録画し、日本人社員にも共有する。日本人社員にも外国籍社員との業務上のコミュニケーションでどんな点に気を付けるべきかを考えてもらうことで、社内全体の日本語コミュニケーションの底上げを図る。
現場と二人三脚、できることから始めてみる
同社の社内研修は全て中野氏が企画・運営している。「研修が目的ではなく、現場が困っていることを、研修を通して解決するのが目的」といい、「自社の課題と目指すべきゴールがイメージできているので、社内のリソースで進めていくのが近道だ」と話す。
社内研修以外にも、日本での生活のためのガイドブック作成やサポート体制構築をはじめ、外国籍社員も働きやすい職場整備も進めている。最近では、イスラム教徒の社員の入社をきっかけに、礼拝用の手洗い場やスペースを確保した。礼拝用スペースは、礼拝時に職場の一角をパーティションで区切るというスタイルだが、各自の慣習を尊重することで社内の理解も深まる。また、中野氏は外国人労働者雇用労務責任者講習を受講し、同社持ち株会社の高砂ホールディングスの田中雄一朗代表取締役社長と2人態勢で外国人労働者雇用労務責任者に就き、いつでも相談できる態勢があることをポスター掲示で広く周知し始めた。中野氏は自身について「お節介、オープンな姿勢を心がけ、誠意をもって対応している」と話す。外国籍社員の生活サポート、日本人社員とのコミュニケーション促進の橋渡しなど、業務に関連することだけでなく、日本食をふるまったり、子供たちにクリケットを教えてもらったり、業務外でも関わりを増やすことで、外国籍社員との信頼関係を構築し、職場や社会に早く溶け込めるように努めているという。
ビジョンを明確に、全社的に取り組む姿勢が重要
外国籍社員の活躍に向けて大切なこととして、中野氏は「まずは社長が決断すること。外国籍社員の活躍を含めた自社の将来ビジョンを明確化し、社内に発信、浸透させることが大前提」と話す。その上で、中野氏自身のように「お節介を焼きつつ、手厚くサポートできる態勢が必須」だという。アディ室長も「社長が方針を決め、中野チーフが制度を作り、自分が実行部隊として後輩に行動で示す。(同社の人材育成にとって)この三つどもえが重要」と話す。また、同社未来創造カンパニーの平谷治之代表取締役社長は同社の強みとして、社長自身も過去に外国で「外国人」として働く経験をしていることを挙げる。「アウェーで働くことの不安や辛さを実体験しているので、安心感を与えられている。また、そうした経験をした上で今、社長になっているということは、外国籍社員にとってのロールモデルにもなり得る」と話し、外国籍社員の立場を理解できる存在がいることの重要性を強調した。
同社の外国籍社員は着実に成長している。インド向けビジネスでは、社長の出張にアディ室長を筆頭に、インド出身の社員がそろって同行し、現地での移動や顧客との商談を補佐する。現地企業との契約などに関連したタフな交渉の現場にも同席し、将来の幹部候補として対外交渉も実地で学ぶ。社長が描くインドビジネス拡大戦略の実行部隊として、外国籍社員たちが活躍する。また、2023年10月に入社したシャラス氏は、入社当時は全く日本語が話せなかったが、1年半もかからずに先日、N3に合格した。「インド工科大学を卒業しており、もともと優秀なことに加えて、努力家、かつ負けず嫌いでもあり、同じインド出身のアディ室長を見て『負けじ』と頑張っている」と平谷社長は評する。人材育成への取り組みに加え、外国籍社員同士の切磋琢磨(せっさたくま)も、同社のビジネスを支える重要な要素となっている。

- 注1:
- 主観的で言語化することができない知識。または、社員や技術者が暗黙のうちに有する長年の経験や勘に基づく知識。同社の研修では、日本人社員が感覚的に使っている副詞や擬音語を使ったコミュニケーションを主眼としている。
- 注2:
- 日本語能力試験で最も上のレベル。同試験では、N5(基本的な日本語をある程度理解することができる)から、N1(幅広い場面で使われる日本語を理解すること)までの5段階で日本語能力を測定している。
- 変更履歴
- 文章中に誤りがありましたので、次のように訂正いたしました。(2025年4月24日)
- 第3段落
-
(誤)未来想像カンパニー
(正)未来創造カンパニー

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部国際経済課 課長代理
田中 麻理(たなか まり) - 2010年、ジェトロ入構。海外市場開拓部海外市場開拓課/生活文化産業部生活文化産業企画課/生活文化・サービス産業部生活文化産業企画課(当時)、ジェトロ・ダッカ事務所(実務研修生)、海外調査部アジア大洋州課、ジェトロ・クアラルンプール事務所を経て、2021年10月から現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ知的資産部高度外国人材課
吉武 果実(よしたけ かじつ) - 2024年、ジェトロ入構。高度外国人材課で主に海外プロモーション事業を担当。




 閉じる
閉じる






