中国事業が「好調」な日系企業の要因分析
コラボやSNSの活用でブランドの浸透図る
2025年9月16日
中国では、景気の減速や競争激化が指摘されており、日系企業の経営を取り巻く環境も厳しさを増しているが、その中でも業績が好調で事業拡大意欲が旺盛な企業は依然として存在する。本稿では、ジェトロの実施したアンケートのデータや現地でのヒアリングなどを踏まえて、中国事業が好調な在中国日系企業の強みや取り組みについて紹介する。
中国事業が好調な日系企業は品質、ブランド、人材に強み
ジェトロが日本企業の海外現地法人に対して毎年実施している「海外進出日系企業実態調査」の2024年度版(2024年8~9月実施)では、同年の営業利益見込みを「黒字」と回答した在中国日系企業が58.4%となり、反日デモ直後の2012年度調査(57.2%)以来の低水準になった(注1)。また、今後1~2年の事業展開の方向性について、「拡大」と回答した企業が21.7%で、比較可能な2007年以降で最低となった(図1参照、注2)。
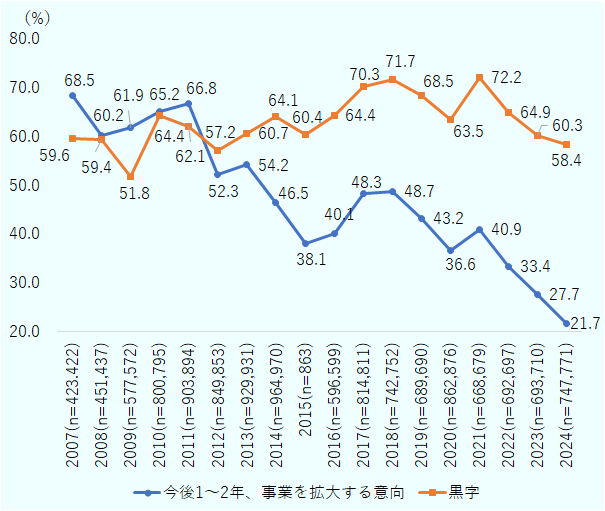
注:nは有効回答数。数値が2つある場合、前者が当該年の営業利益見込みに関する設問の有効回答数、後者が今後1~2年の事業展開に関する設問の有効回答数。
出所:ジェトロ 海外進出日系企業実態調査各年版
他方で、2024年の営業利益見通しが「黒字」かつ今後の事業展開について「拡大」と回答した在中国日系企業が118社あった(以下、「黒字」「拡大」企業)。こうした「黒字」「拡大」企業が他社と比べて強みとしている点を聞いたところ、「性能・品質の高さ」「ブランドの浸透度」「人材」の3つの項目が全体平均を10ポイント以上も上回ったほか、「知的財産」「ビジネスモデル」の項目も全体平均より約5ポイント高くなった(図2参照、注3)。この結果から「黒字」「拡大」企業は他の在中国日系企業と比べて価格面での競争よりも、ブランドや製品・サービスの品質の高さによって差別化を図れているケースが多いとみられる。
(「黒字」「拡大」企業と全体平均の比較、複数回答、DI値)
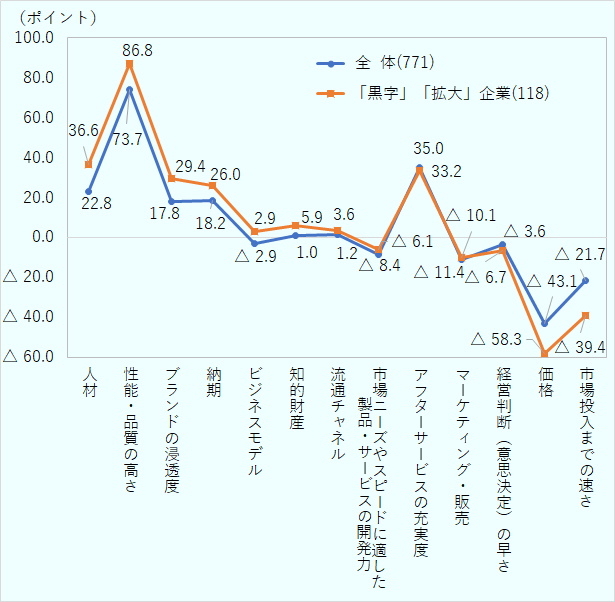
注1:DI値はDiffusion Indexの略称。本図では販売マーケットにおいて、当該項目について自社に強みがあると回答した企業の割合から弱みがあると回答した企業の割合を差し引いた数値を指す。
注2:横軸の項目の並びは「黒字」「拡大」企業と全体平均の回答の差分が大きい順。
出所:ジェトロ 2024年度海外進出日系企業実態調査中国編
黒字実現の一因に自社ブランドの浸透あり
そこで、「黒字」「拡大」企業の具体的取り組みや戦略などに関して深堀りをすべく、フォローアップヒアリングを行った〔前述118社のうち23社に対して、ジェトロ中国7事務所(北京、大連、青島、上海、武漢、成都、広州)が2025年6~8月に実施〕。以下ではその概要について紹介する。
まず、「黒字」「拡大」企業が営業利益「黒字」を実現できている要因として、食生活の西洋化や日系コンテンツに親しみのある30代以下の若年層の消費者としての台頭、中東情勢の緊張による海上輸送の長期化など地政学的な影響を受けた物流変化による関連市場の拡大(注4)など、外部的な要因もある。他方で、企業自身の取り組みとしては、業界内での自社ブランドの浸透、コスト削減、販売先の新規開拓、新製品の発売などが要因として挙げられている。
今後の事業展開「拡大」を実現できている要因としては、中国国内市場の拡大〔例:電子化に伴うデバイス需要増、家電買い替え需要増(注5)〕、造船業など顧客企業の投資・生産拡大、日本食品の浸透やパンブームに伴う関連製品需要の拡大、高齢化による診断・検査需要の拡大、中国国内の大都市周辺に位置する都市や中・西部地域の需要獲得を目的とする生産や出店の拡大、中国政府の国産品優遇政策(注6)への対応や競争力強化のための中国現地での設計・生産の拡大、従来輸出主体だった企業が中国国内への販路拡大を図る中での現地生産拡大、などを挙げる回答があった。
ブランド浸透には他社・異分野とのコラボ、SNS活用が有効
続いて、図2で「黒字」「拡大」企業が他社と比べて強みと回答している比率が高かった5項目(「ブランド」「性能・品質の高さ」「人材」「知的財産」「ビジネスモデル」)についてその具体的な取り組みを聞いた。
製品・サービスのブランドを高めるため、あるいは現地市場で浸透させるために展開している取り組みとして、中国で自社ブランドを確立したメーカーは自社独自のイベントを長期間継続することを、日本のIP(知的財産)を保有するエンタメ関連企業は事業の多角化や多分野とのコラボの重要性を、素材メーカーは大学や研究・医療機関との連携による自社製品の信頼性向上を挙げた。医療機器分野では、自社の製品を中国の国家標準に採用させることで中国でブランドを構築できたとの声があった。食品関連の材料メーカーは、顧客の中国企業を日本に案内し日本で流行している製品を中国に導入してもらうことで、自社の材料が生きるハイエンド市場を中国でも創出しようとしている。中国企業に機械を納品するサプライヤーは、丁寧なアフターケアや顧客とのコミュニケーションなどの「日本的サービス」で勝負している。
また、自社ブランド浸透のため、展示会への出展に加えて、TikTokでのライブ販売や、WeChatなどのSNSを活用した製品情報などの発信を通じて認知度向上を図っている企業もある。一方、コアな消費者との接点として実店舗やリアルイベントの活用も必要であり、リアルとオンラインの組み合わせが重要だと指摘する声もある(注7)。
コストやスピードの面でも競争力を持つべきとの声も
製品・サービスの性能・品質を高く維持するための取り組みとしては、SNSやEC(電子商取引)プラットフォームを活用した販促や、現地企業との連携による商品力強化が挙がった。例えば食品関連の材料メーカーは、現地の味や食感に合わせた商品開発を行っており、日系企業に部品を販売する企業は、顧客の工場を訪問してDX(デジタルトランスフォーメーション)化に伴うニーズを聴取し、ニーズに合わせた改善提案を行っている。このほか、あるメーカーは、日本で行っているサプライヤーの生産性向上活動を中国でも展開している。代理店のアフターサービスのパフォーマンスを顧客へのアンケートを通じて把握するなど、アフターサービスの質の向上に取り組む企業もあった。
他方、品質と信用の面での中国企業に対する優位性には自信を持ちながらも、中国企業との競合においては、スピードや価格の面でも競争力を持つ必要性があるとの認識を持つ企業もある。同企業は、スピード・価格面での競争力向上のために、開発から生産・販売までを中国内で完結させる一貫体制の構築のため、中国での開発機能を強化しているほか、投資に対する決裁権限の一部を中国現地法人へ委譲している。
人材に関連する取り組みとしては、多くの企業で、経営理念の浸透や実績に基づく評価・報酬体系の整備などを実施している。日本本社などと協力した研修プログラムの提供や、特許、業界資格(技能士など)の取得をKPI(重要業績評価指標)として設定する取り組みもみられる。
知的財産に関しては、中国でのブランドの商標登録、設計図面の管理など、各社の取り扱う商材やビジネスモデルに則した知財保護に取り組む企業が多い(2024年11月27日付地域・分析レポート参照)。コアな営業秘密については、ブラックボックス化を行う企業もある。日本のIPを活用した中国でのビジネス展開を検討・実施するとの声もあった。
中国でのビジネスモデルに関しては、日本の技術を中国に持ち込んで顧客に合わせてカスタマイズする、製品の保証期限終了後も部品を交換するなど丁寧なアフターサービスを行う、日本製部品を用いて中国でも日本と同じ工程や品質で組み立てることでコストを抑えつつ「メード・イン・ジャパン」の価値を提供する事例などがある。また、従来、富裕層向けに高価格帯の製品を提供していた企業が、市場の拡大に合わせて価格を下げた商品を業務用に展開し、中間層マーケットの獲得を図る動きもみられる。
競合との差別化でもブランド力の維持・向上がカギに
このほか、自社の競合他社としては、コスト競争力に強みを持つ中国地場企業を挙げる声が多数あった(注8)。競合企業については、開発力や生産力が向上していること、新規取り組みなどが自社よりも優れている点を評価する声が多い。競合企業への対抗策としては、製品・サービスの品質や自社のブランド力・信用力の維持・向上のほか、世界各国に販売・調達先を有するネットワークを活用したサプライチェーンの機動的な調整、中国企業とのパートナーシップも活用した新規のビジネススキーム・商流の提案力などのほか、貿易保険による損害カバー、支払いの一部肩代わりによる与信付与など金融サービスの提供が挙げられた。
なお、米国と中国の間で行われている追加関税賦課や対抗措置などの影響や対応についても聞いたところ、米国との間で直接輸出入を行っている企業は限定的で、直接的・間接的な影響はないとの声が多数だった(注9)。米国製品の中国への輸入で仮に影響が出る場合も、商流の切り替えで対応可能(例:穀物の調達先を米国からブラジルへ切り替えるなど)との指摘があった。ただし、化学品や衛生材料で顧客企業が中国から米国へ輸出しており若干の影響があるケースや、中国から米国向けの食品輸出を止めている企業などもあった。また、中国で建造された船舶の米国港湾への入港について、2025年10月から米国が追加料金を課すと発表していることの今後の影響を懸念する声もあった(2025年4月22日付ビジネス短信参照)。
さらに、日本本社経由で小麦粉を米国から中国へ輸入しており、現在は在庫で対応しているが、在庫が切れた場合には価格転嫁交渉が必要になるとする企業があったほか、モーターにレアアース磁石が使われており、中国から第三国・地域向けの輸出手続きが長期化するというかたちで影響を受けた企業もある(注10)。
今回のヒアリング結果からは、景気減速や競争激化の中でも異分野・異業種とのコラボレーションやSNSなどデジタルツールの活用といった取り組みによってブランド力を維持・向上させつつ、人材育成などにも取り組み、好業績や事業拡大を実現している在中国日系企業の姿が浮き彫りとなった。現下の厳しい状況であっても、こうした様々なアプローチで中国市場に挑む事例を収集・把握し、参照することは重要であり、また、こうした情報は日系企業が今後の中国ビジネスを検討・判断する上でのヒントの1つになりうる。
- 注1:
- 調査実施年の営業利益見込みについて、「黒字」「均衡」「赤字」のいずれかを選択する設問。2012年度調査は2012年10月~11月実施。
- 注2:
- 今後1~2年の事業展開の方向性について、「拡大」「現状維持」「縮小」「第三国・地域への移転・撤退」のいずれかを選択する設問。
- 注3:
- 販売先市場において、自社の強み、弱みがあると思うものを選択する設問、複数回答。本設問の選択肢は図2のグラフ横軸に記載されている13項目。
- 注4:
- 中東情勢の悪化により、コンテナ船がスエズ運河を通れなくなり、航路が長距離化したことにより、大規模なコンテナ船への需要が増加した。また、運賃が上昇したことによって、船主が船舶に対して投資しやすくなったことも理由となり、中国国内での船舶需要が急拡大している(2025年7月、ジェトロによるヒアリングによる)。
- 注5:
- 中国は家電製品など消費財の買い替えについて補助金を支給する政策を実施している(詳細はビジネス短信特集「中国の設備更新と消費財買い替え推進政策の最新動向」参照)。
- 注6:
-
中国の財政部と工業情報化部は2021年5月、内部通知として示した「政府調達輸入製品審査指導標準(2021版)」において、医療機器など各種製品について国産品などの推奨調達割合(100%、75%、50%、25%の 4 段階の基準)を定めたとされている。同標準に記載された全315品目のうち、調達の100%を国産品などとするよう要求された品目は約70%に達しており、例えば、医療機器は178 品目が掲載され、そのうち137 品目について100%を国産品などで調達するよう要求しているとされる(ジェトロ調査レポート「政府調達関連法令・運用の最新動向
 (765KB)」参照)。
(765KB)」参照)。
- 注7:
- 中国消費市場開拓におけるリアルな顧客接点の重要性については、2025年2月25日付地域・分析レポートでも紹介している。
- 注8:
-
2024年度海外進出日系企業実態調査(アジアオセアニア編)
 (2.4MB)でも、在中国日系企業(回答企業数512社)の96.7%が地場企業(中国企業)と競合していると回答している(同調査P25、競争力が高い順に競合先として上位3カ国・地域の企業を回答する形式)。
(2.4MB)でも、在中国日系企業(回答企業数512社)の96.7%が地場企業(中国企業)と競合していると回答している(同調査P25、競争力が高い順に競合先として上位3カ国・地域の企業を回答する形式)。
- 注9:
-
2024年度海外進出日系企業実態調査(中国編)
 (1.62MB)によると、在中国日系企業において米国向け輸出を行っている企業は回答企業全体の5.4%にとどまっている(同調査P36)。
(1.62MB)によると、在中国日系企業において米国向け輸出を行っている企業は回答企業全体の5.4%にとどまっている(同調査P36)。
- 注10:
-
中国は2025年4月4日、一部の中・重希土類関連品目(サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムの金属、合金、関連製品、酸化物とその混合物、化合物とその混合物)に対する輸出管理の実施を公告し、即日実施した(中国商務部ウェブサイト参照
 )(2025年4月7日付ビジネス短信参照)。同措置の関連動向およびその影響については、2025年4月28日付、5月12日付、6月5日付、6月9日付、6月18日付ビジネス短信参照。
)(2025年4月7日付ビジネス短信参照)。同措置の関連動向およびその影響については、2025年4月28日付、5月12日付、6月5日付、6月9日付、6月18日付ビジネス短信参照。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部中国北アジア課 リサーチ・マネージャー
小宮 昇平(こみや しょうへい) - 2013年、ジェトロ入構。海外調査部中国北アジア課に配属。2016年3月より1年間の海外実務研修(中国・成都事務所)を経て、2017年3月から2018年8月まで中国北アジア課に所属。2018年8月から2023年7月まで中国・北京事務所にて調査業務等に従事。2023年7月から現職。




 閉じる
閉じる






