活用事例から見るEPA活用のメリットとコツ総論:日本企業の輸出におけるEPA/FTA活用の現在地
2025年7月30日
経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA、注1)は、関税撤廃・削減を中心に、特定の国・地域間での貿易投資促進に向けた合意を定めた条約だ。企業はFTAを活用することで、通常よりも低い関税率で取引を行うことができる。輸出を行う日本企業にとっても、海外市場での競争力を強化する有効な手段の1つだ。
ただ、FTAによる関税減免を受けるには、原産地証明書の作成など、所定の手続きを行う必要がある。この手続きについて、複雑な制度の理解や実務を担う社内体制の構築に課題を抱える企業も多い。本稿では、ジェトロが2025年1月に行った「2024年度輸出に関するFTAアンケート調査」(以下、FTAアンケート)の結果と、2025年1~6月に行った各社へのヒアリングを基に、日本企業のFTA利用の現状と課題を概観する。
輸出企業の約6割がFTA利用、前回調査から横ばい
FTAアンケートの結果によると、日本のFTA締約国へ輸出を行う企業のうち、1カ国・地域以上への輸出でFTAを利用している企業(以下、FTA利用企業)の比率(以下、FTA利用率)は61.3%だった。企業規模別で見ると、大企業(同71.3%)が中小企業(57.5%)に比べてFTA利用率が高い結果となった(図1参照)。FTAを利用していないが、関心があると回答した企業は13.4%だった。日本関税協会が2023年末から2024年初にかけて行った「経済連携協定(EPA)利用に係るアンケート![]() 」でも、FTA締約国への輸出経験がある企業のうち、63.4%がFTAを現在利用していると回答している。
」でも、FTA締約国への輸出経験がある企業のうち、63.4%がFTAを現在利用していると回答している。
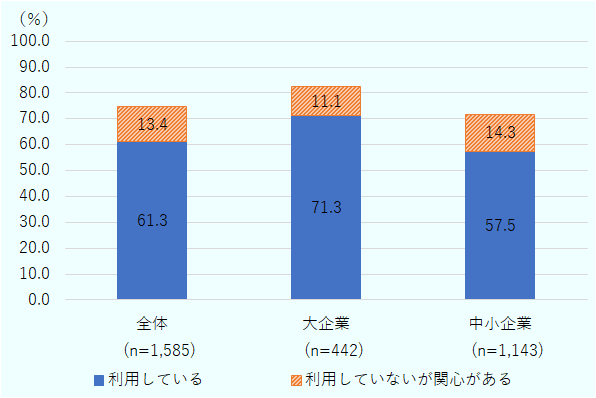
注1:nは、FTAなどの貿易協定の相手国・地域(調査時点で日本と協定が発効済みのタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ブルネイ、シンガポール、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インド、モンゴル、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、EU、英国、メキシコ、チリ、ペルー、カナダ、米国)のいずれか1カ国・地域以上に輸出を行っている社数。
注2:利用率を計算する際の母数には、一般関税が無税、またはFTA以外の関税減免措置を利用している企業も含まれる。
出所:2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
過去のジェトロ調査から、FTA利用率全体の推移を見ると、2020年度調査は48.6%、2022年度は62.4%(注2)と増加していたが、2024年度は61.3%と横ばいだった。2020年度から2022年度にかけての利用率増加は、日本との貿易額が大きい中国と韓国との間で初めてのFTAとなる地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が2022年に発効したことが要因の1つと考えられる(注3)。RCEP以降、日本は新たな国とFTAを締結していない。過去調査の連続回答企業に絞ると、一定の利用率増加が見られるものの、ここ数年のFTA利用は大幅な拡大を見せているとは言えないのが現状だ。
積極的なFTA利用がメリットにつながる
FTA利用が拡大しない1つの原因として、輸出者がメリットを感じにくいという課題がある。契約内容によっても異なるが、多くの場合、関税を支払うのは輸入者だ。そのため、FTAによる関税削減効果の直接的なメリットを享受するのは輸入者になる。輸出者にとっても、削減した関税額の分だけ販売価格が下がれば、自社製品のコスト競争力が高まり、取引が拡大するというメリットはある。ただ、関税削減効果は間接的なため、メリットを実感していない企業も多い。FTAアンケートで、FTA利用によって取引に変化(輸出量・取引量の増加など)が起こったか聞いたところ、57.5%が「変化なし」と回答した。
こうした背景もあり、FTA利用は輸入者が主導し、輸出者は単に手続きを行う「受動的」な利用にとどまってしまうことが多い。アンケートでも、67.9%の企業がFTA利用のきっかけは「輸出先国の取引事業者からの要請」と回答している。どの協定を利用するかについても、「取引先からの指示または要請」(63.6%)が最も高く、「特恵関税率の低さ」(55.9%)を上回った(図2参照)。
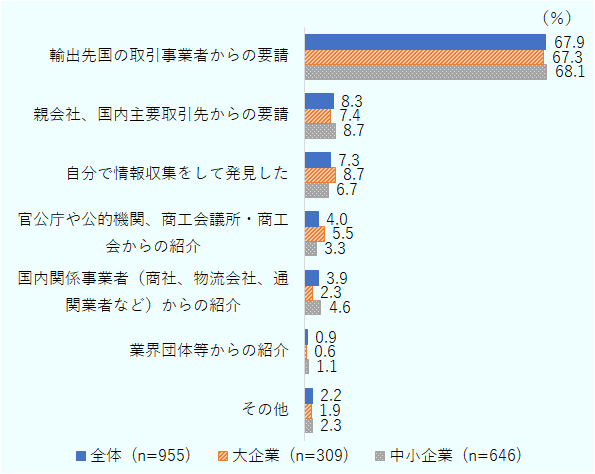
注:nは、「FTAを利用している」と回答した企業。
出所:2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
一方で、輸出者が積極的にFTAを利用することで、メリットをより享受することにつながる可能性がある。ジェトロがインタビューを行った企業では、「FTA利用の費用対効果を営業サイドで商社と詰めた上で、競争力強化や、顧客との取引量アップの交渉につなげている」「営業担当者は、FTAが利用できることを前提に、顧客に営業活動をしている」など、FTA利用を顧客との交渉や新規取引獲得の材料としていた。
また、一部では、FTA利用がアドバンテージではなく、市場参入への条件になっているケースもある。インドに工具を輸出する企業は「現在ではFTA活用が当たり前になってきてしまっている」と語る。ほかにも、「高価格帯の製品を、東南アジアなど価格を低く設定しなければいけないような市場に輸出する際、FTAによる関税削減が取引成立に寄与している」など、特に価格競争が激しい地域や製品分野でFTAが利用できることが重要になっているようだ。
複雑な制度がハードル、社内外の体制整備がカギ
FTA利用のもう1つの大きなハードルとしては、HSコードや原産地規則などのルールの理解や、原産性裏付け書類の作成など、利用に係る手続きコストが挙げられる。特に課題となるのが、制度が自社製品にどう適用されるかがわかりにくい点だ。同じ製品でも、輸出先や協定によって特恵関税率や品目別原産地規則などが異なり、全体像を理解していないと混乱しやすい。FTAアンケートの結果を見ても、FTA利用に当たって手に入りにくかった情報として、「自社製品が各FTAで原産地規則を満たしているか否か」(24.7%)と、「自社製品が各FTAの対象か否か」(23.4%)がそれぞれ2、3番目に多かった(図3参照)。「自社製品が各FTAで原産地規則を満たしているか否か」については、3割以上の企業が「手に入ったがわかりにくかった情報」にも挙げた(図4参照)。インタビューでも、「基本的な原則は理解できても、それが自社にどう当てはまるのかがわかりにくい」と複数企業の担当者から言及があった。
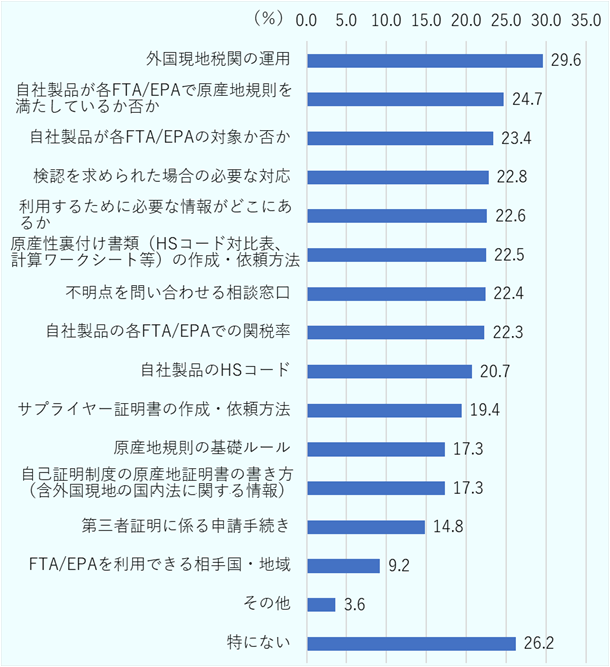
注:n=813、「FTAの利用方法を調べたことがある」と回答した企業(無回答を除く)。
出所:2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
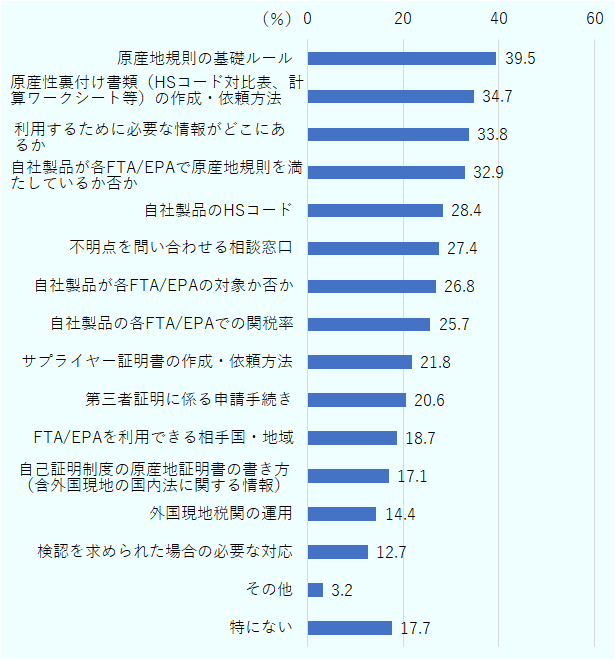
注:n=977、「FTAの利用方法を調べたことがある」と回答した企業(無回答を除く)。
出所:2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
加えて、事務手続き自体の負担に苦労する企業も多い。FTAアンケートでFTA利用のコストが大きい項目として最も多かった回答は「人件費が掛かる」(63.2%)で、「原産地証明書の作成に必要な取引情報の確認」(46.2%)、「FTAを利用する手続きに必要な情報(関税率、原産地規則など)の収集」(43.3%)と続いた(図5参照)。制度を理解していたとしても、原材料の価格や正確なHSコードの確認、計算ワークシートやHSコード対比表の作成に多くの手間と時間がかかっている現状が明らかになった。自社内の手続きだけではなく、アンケートやインタビューの中では、調達先からサプライヤー証明書をもらうハードルの高さを指摘する声も一定数あった。
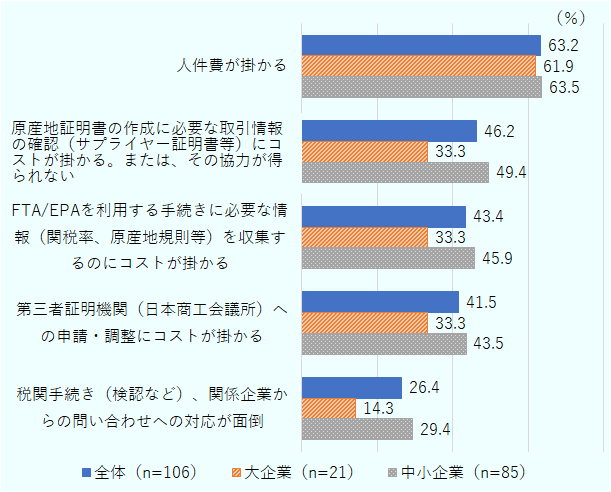
注1:nは、FTAを利用する場合のメリットとコストの検討の結果、「コストの方が大きかった/メリットが少なかった」と回答した企業。
注2:グラフには上記5項目のみ表示。
出所:2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
こうしたハードルを乗り越えるには、社内外の体制整備が肝要だ。FTAについて理解している人材の育成に加え、メーカーであれば、原産性判定の根拠資料を提供する製造部門の協力も必要になる。体制を整備できている企業は少なく、FTAアンケートでは、社内体制面での取り組みについて「特に行っていない」と答えた企業が76.8%に上った。一人がFTA関連業務を長年担当しているため、利用件数が増えると対応できないなどといった課題を抱える企業も少なくない。体制整備の取り組みとして最も行われていたのは、社内人材育成(19.7%)だった。「まず取締役会でFTA利用のメリットを説明してから、体制整備につなげた」という企業もあり、経営層がFTA利用に積極的なことも重要な要素と考えられる。また、原材料の国内調達先に対してサプライヤー証明書を要求する際に、調達先企業が全く海外ビジネスの経験がない場合も多い。インタビュー先の中には、関税やHSコードの仕組みから丁寧に説明し、書類作成の支援まですることで協力を取り付けている企業もあった。
社内体制の充実と合わせて、通関業者や物流会社などの取引先、ジェトロや東京共同会計事務所に設置している公的な相談窓口(注4)といった、外部リソースの活用も有効だ。財務省と日本通関業連合会が主導して、通関士を対象に「EPA関税認定アドバイザー(仮称)」の養成講座を実施し、企業への支援を強化する取り組みも始まっている。
FTAを輸出拡大の推進力に
FTAアンケートでFTA利用のコストとメリットのどちらが大きいか聞いた設問では、「コストの方が大きかった/メリットが少なかった」と答えた企業は24.4%なのに対し、「メリットの方が大きかった/コストが小さかった」と答えた企業は58.8%と大きく上回った。母数はコストとメリットの比較を行った企業に限定されるものの、利用のメリットを実感している企業が一定数存在するのは事実だ。
米国のトランプ政権による追加関税の拡大が進む中で、日本企業には米国以外の市場拡大を狙う動きも見られている(注5)。日本のFTA網は、東南アジアやインド、欧州など、市場として一定規模がある地域もカバーしている。そのため、新規販路開拓でも、FTAによる関税コストの削減は顧客へのアピールポイントとなり、競争力向上につながる。FTAが利用できることはますます重要性を増していると言えるだろう。
- 注1:
- 本稿では、物品貿易以外の幅広い対象分野をカバーするEPAも含め、貿易の自由化を目的とした通商協定をFTAと呼ぶ。
- 注2:
- 2024年度調査報告書では、定義変更のため2022年度のFTA利用率を62.6%としているが、本稿では、報告書発表時点の数値を用いることとする。
- 注3:
- FTAアンケートは隔年で実施しており、2020年度調査は2020年10月、2022年度調査は2023年2月に実施した。日本でRCEP協定が発効したのは2022年1月。
- 注4:
-
ジェトロが設置しているEPA相談窓口、東京共同会計事務所が設置しているEPA相談デスク
 では、EPA/FTAの利用に関する個別の問い合わせを受け付けている。
では、EPA/FTAの利用に関する個別の問い合わせを受け付けている。
- 注5:
- ジェトロが4月に行った「米国トランプ政権の追加関税に関するクイック・アンケート調査(1.06MB)」で、追加関税措置への対応策として25.3%が「米国以外の国・地域への販路拡大」を選択した。
- 変更履歴
- 図3を差し替えました(2025年9月25日)。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部米州課中南米班
加藤 遥平(かとう ようへい) - 2023年、ジェトロ入構。調査部調査企画課を経て、2025年4月から現職。






 閉じる
閉じる





