活用事例から見るEPA活用のメリットとコツスリーボンド、EPA活用でさらなる飛躍を(東京都)
FTAチームの活躍
2025年5月8日
株式会社スリーボンド(本社:東京都八王子市)は、工業用接着剤・シール剤のメーカーで、自動車や電子機器、建築分野など幅広い市場に製品を提供している。グループ全体で約3,000人が在籍し、アジア・米州・欧州など海外にも拠点を展開。同社の欧州事業ならびに日EU、日英の経済連携協定(EPA)の利用状況について、同社サプライチェーンマネージメント本部 購買・物流企画部 貿易企画課FTAチームに聞いた(取材日:2025年2月7日)。

世界6極体制、4つの市場で製品を展開
スリーボンドは1955年創業で、「貴重なエネルギーの漏れを未然に防ぎたい」という創業からの思いを大切にしている。自動車のエンジンオイル漏れを防ぐ液状ガスケットと呼ばれるシール剤を開発・製造したことからスタートした。現在では、シール剤、接着剤などを商材とし、(1)輸送市場(自動車などの輸送機器全般)、(2)電気・電子市場(スマートフォンなどの内部)、(3)工材公共市場(医療、インフラなど)、(4)オートアフターマーケット(自動車のメンテナンス、内装、外装、保守・点検など)の4市場のビジネスを展開している(図参照)。

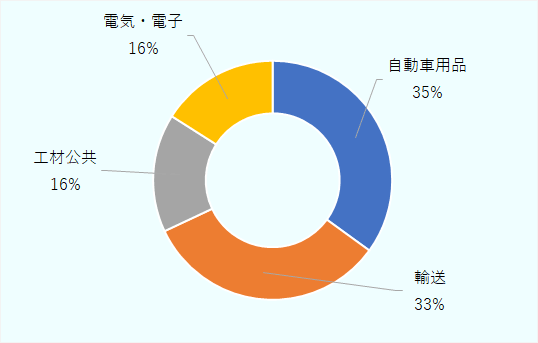
出所:スリーボンド提供のデータを基にジェトロ作成
スリーボンドは現在、23カ国153拠点に開発、生産、販売、物流拠点を有する、グローバルな体制を構築している。日本圏を筆頭に、北中米圏・南米圏・欧州圏・アジア圏・中華圏の6極体制を展開。総売上高における海外の比率は約50%と高い。
欧州においては、フランスに欧州統括会社としてスリーボンドヨーロッパを置き、英国とトルコに支店を持つ。また、ドイツとハンガリーには現地法人があり、欧州圏の生産はハンガリーで行っている。ハンガリー工場で生産していない製品については、日本生産品を欧州の各販売拠点に輸出しており、その際にEPAを活用している。
2022年、貿易企画課内にFTAチームを設置
2016年以降、すでに日本とインド・ベトナムとのEPAを活用していたスリーボンドは、2021年から日英EPAの利用も開始した。欧州市場では、日本からの輸送距離が長く輸送コストも高いため、CIF価格(運賃・保険料込み価格)ベースで申請する特恵関税のメリットは大きいと判断。同社の欧州向け主要化学製品については、日EUおよび日英EPAの適用により、一般関税率が減免されている。
このころには、「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」活用についても議論があったため、これまで属人的に行っていたEPA/FTA(自由貿易協定)関連業務を社内で横断的に総括するチームの必要性があると判断し、約1年の準備期間を経て、2022年に同社サプライチェーンマネージメント本部購買・物流企画部 貿易企画課内にタスクチームとして「FTAチーム」が設置された。
チーム活動として、各海外拠点に対してFTA/EPAの説明を行っており、HSコードについての基礎知識や、事前教示制度、CTC(関税番号変更基準)(注1)で対応していること、EPA/FTAを活用した場合のメリットやリスクなどについても伝えている。
申請においては、輸入国側が商品ごとにHSコード(国際的な関税分類)の事前教示を受けることを原則としている。事前教示を受けたHSコードに対して、原産地基準を満たす根拠資料の準備・最終承認をFTAチームが行うほか、必要に応じて他部門と連携し、社内横断的にEPA/FTAの活用を推進している。
また、多くの場合、原産地証明には商工会議所などが発行する「第三者証明」が用いられる。しかし、日EUおよび日英EPAでは、当該産品が協定上の原産品であることを示す方法として「自己申告制度」が採用されている。この制度では、最終的な判断を輸出者であるスリーボンドが担う必要があり、他国向けの輸出に比べて責任が重い。そのため同社では、FTAチームを中心に、サプライヤーや生産委託先との情報共有やサポート、ガバナンスの徹底を図っている。
輸出におけるEPA/FTA活用の課題
FTAチームのこれまでの経験から、EPA/FTA活用の課題として次の3点が挙げられる。
- 原料構成や調達先などの5M(注2)変更時の原産性維持・確認
- サプライヤー(原料調達先)や生産委託会社に対する、EPA/FTAについての継続的な知識の共有、サポート
- サプライヤー(原料調達先)、生産委託会社の原産地根拠資料や申請書類の準備
これらの課題を解決すべく、同社の物流戦略の中で、EPA/FTA活用と物流のオペレーション改革の融合を検討している。現在スリーボンドでは、日本から海外に輸出する場合にEPA/FTAを活用しているが、将来的には、海外拠点間や、海外原材料(商社経由を含む)の輸入品においてもEPA/FTAを活用するなど、今後も制度利用拡大の可能性がある、とチームリーダーは語った。
最後に、EPA/FTAの制度利用の拡大においては、EPA/FTAに関して気軽に相談できる外部の窓口の必要性にも触れた。こうした外部窓口があれば、スリーボンドだけでなく、サプライヤーや生産委託会社の各社においてもEPA/FTA関連業務について理解を深めることに役立つのではないか、とFTAチームリーダーは述べた。
- 注1:
- 品目別原産地規則の証明方法の1つ。最終産品と産品を生産するために使用した非原産「材料・部品」との間でHSコードが変更されている場合(変更されるような生産・加工が行われた場合)に、当該産品を原産品であると認める基準。
- 注2:
- 製造業における生産の5要素〔(1)Man(人)、(2)Machine(機械)、(3)Material(材料)、(4)Method(方法)、(5)Measurement(計測)〕を用いたフレームワーク。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部欧州課
近藤 慶太郎(こんどう けいたろう) - 2024年、ジェトロ入構。同年4月から現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部欧州課
岩田 薫(いわた かおる) - 2020年5月から調査部欧州課勤務。




 閉じる
閉じる






