活用事例から見るEPA活用のメリットとコツRCEPやCPTPPなど使い分け(東京都)
物流企業に聞くEPA利用状況と課題
2025年4月24日
2000年代以降、日本と諸外国との間で、2国間や多国間の経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)網が拡大し、企業によるEPA/FTA活用も進んできた。国内外の物流や日本の輸入通関を手掛けるインターナショナル・エクスプレス(本社:東京都港区)は、世界各国からの輸入貨物のFTA実務を担う。同社の本田和久執行役員兼東京支店現業部長、東京支店営業第一部営業課の藤井智也課長代理、国際業務室 甲斐陽一郎氏に、国や品目、協定ごとの利用傾向や、実務上の課題、物流トレンドについてインタビューした。(インタビュー日:2025年2月12日)
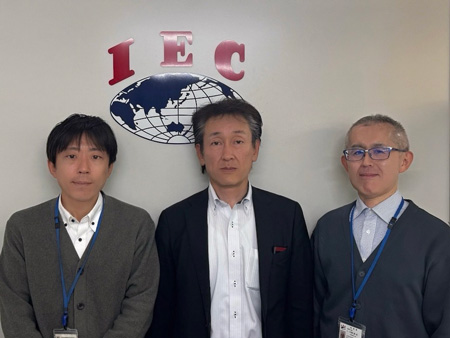
- 質問:
- 会社の概要は。
- 答え:
- 当社は国際物流会社として、貨物の輸送や、日本での輸出入通関手続きを担っている。当初は報道機材の航空輸送に特化した通関業者として創業した。急ぎの貨物輸送を強みとしていたため、航空貨物に注力してきたが、現在は海上貨物にも対応し、生鮮食品から衣類などのドライ貨物まで、さまざまな品目を取扱う。
- FTAの利活用は、荷主が決めるものだが、輸入通関手続きを行う当社から、状況に応じて提案するケースもある。
CPTPPやRCEPで実務面はさらに使いやすく
- 質問:
- EPA/FTAの利用はどの時期から進んだと感じるか。
- 答え:
- 日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定が先行5カ国との間で発効した2008年のころと認識している。当初は原産地規則が複雑だと感じていた。中でも第三国の材料(非原産材料)が使用される製品は、原産性を判定するための基準が品目や協定ごとに細かく規定されており、利用前の調査に手間がかかるため、利用のハードルが高かった。例えば、繊維製品は、AJCEPをはじめとした多くの協定で、関税番号変更基準(CTCルール)の確認に加え、製造工程のうち2つの工程を締約国で行うこと(2工程ルール)が要件とされていた(注)。地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の発効により条件が緩和され、利用しやすくなったと感じる。RCEPでは、CTCルールのみとなり、加工要件は生地から衣類への加工のみで原産性が認められる(1工程ルール)ようになった。
- 質問:
- EPAの利用に向けて、どのように取り組んだか。
- 答え:
- 社内でノウハウを蓄積しながら取り組んだ。日本の経済産業省や税関の解説資料を基に、本田部長が自ら資料を作成し、社内の関係部署に共有するなどしていた。また、実務面では、社内の通関部門が税関と相談しながら進めた。
- 質問:
- 日本での輸入時にどの協定が利用されているか。
- 答え:
- 中国からの輸入が多いため、中国との唯一のFTAであるRCEPの利用が多い傾向がある。その他の国・地域からの輸入では、ベトナムの場合はAJCEP、欧州では日EUEPAや日英EPA、オーストラリアでは日豪EPAなど、相手国との2国間協定を利用することが多い。
- 地域ごとに見れば、このような傾向だが、加えて、品目や輸入相手国に応じて、関税率がより低い協定や、原産品の証明がより容易な協定を利用するよう意識している。関税率の観点では、例えば、ベトナムから繊維製品を輸入する場合、RCEPでは関税が撤廃されていないが、AJCEPでは関税が撤廃済みのため、AJCEPの利用が多い。また、原産品の証明の観点では、ベトナムから一次産品を輸入する場合、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)をよく利用する。原産品の証明方式として、多くの2国間・多国間協定では、第三者証明制度が適用されている一方、CPTPPでは、自己申告制度が利用できる点が便利だ。なお、RCEPにも自己申告制度はあるが、輸出者または生産者による自己申告制度は2025年3月時点で、締約国がオーストラリア、ニュージーランド、韓国の3カ国のみで、ベトナムとは締約していない。
RCEPを使った中国からの輸入は実務面で課題あり
- 質問:
- EPAの利用に当たって課題はあるか。
- 答え:
- 中国からの輸入に当たってRCEP協定を利用する場合、実務面での課題が2つある。
- 1つ目は、航空貨物ならではの課題で、原産地証明書の発給が貨物の到着に間に合わず、通関手続きで待ち時間が生じるケースだ。船便なら輸送に1週間~10日かかるため、このような問題は起きないが、航空便は5~6時間で到着するため、現地発給機関の発給待ちとなるケースがある。当社としては、荷主(輸入者)を通じて現地の送り主に対して、早く提出するよう求めるしかない。
- 2つ目に、中国で原産地証明書の発給申請を代理人が行う場合、日本での輸入通関時に追加書類を求められ、この書類の手配に時間を要して、納期が遅れるケースがある。ルール上、代理人が原産地証明書の発給を申請することは可能だが、この場合、インボイスと原産地証明書で輸出者が異なるため、日本の輸入通関では、輸出者と代理人の関係性を示す証明書(契約書など)が求められる。この書類が整っていないために納期が遅れるケースが散見される。
日本から米国向け航空貨物は運賃が高い状態続く
- 質問:
- 近年、貴社の取扱い品目や物流トレンドの変化はあるか。
- 答え:
- 当社の取り扱い品目について、大きな変化はない。他方、物流トレンドに関しては、幾つか変化がある。まず近年のトレンドとして、東南アジアから日本を経由して、米国向けに輸送される航空貨物が増えている。また、中国系ECサイトが台頭する中、これらEC貨物の一部が日本を経由して米国に輸出されており、一時は日本発米国向けの航空貨物のスペースが逼迫した時期もあった。スペースの逼迫は改善しているが、日本発米国向け航空貨物は、運賃が高い状態が続いている。 海上輸送では、新型コロナウイルス禍以降、香港と中国の往来が難しくなったことで、香港を中継しない貿易が増えつつある。特に深センや広州など華南地域で、日本に直送される貨物が増えている。
- 注:
- AJCEPでは、2工程のうち1工程が締約国以外のASEAN加盟国で行われることを許容している。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 リサーチ・マネージャー
山口 あづ希(やまぐち あづき) - 2015年、ジェトロ入構。農林水産・食品部農林水産・食品課(2015~2018年)、ジェトロ・ビエンチャン事務所(2018~2019年)を経て現職




 閉じる
閉じる






