世界のクリーン水素プロジェクトの現状と課題水素需要の側面から中南米のポテンシャルを探る
2025年4月23日
豊富な再生可能エネルギーおよび化石燃料を有する中南米では、生産過程で排出する炭素量を最小限に抑えた水素、いわゆる低排出水素を比較的安価に生産することができるため、水素生産プロジェクトの構想が相次いでいる。世界エネルギー機関(IEA)によれば、2024年11月13日時点で、構想段階も含め154の水素製造プロジェクトが中南米・カリブ地域において報告されている。中でも、中南米地域では、豊富な再生可能エネルギーを用いて低炭素水素を生産し、欧州などの消費地に輸出することが念頭に置かれているプロジェクトが多い。また、域内における水素需要については、中南米地域の主要産業といえる農業、石油精製、製鉄などの分野で水素活用のポテンシャルを秘めている。本稿では、IEAの報告書「Global Hydrogen Review(GHR)2024![]() 」を基に、水素の需要面に焦点を当てて中南米のポテンシャルを紹介する。
」を基に、水素の需要面に焦点を当てて中南米のポテンシャルを紹介する。
中南米・カリブ地域における水素需要の現状
IEAは2024年10月2日、世界の水素動向を分析する年次報告書「Global Hydrogen Review(GHR)2024![]() 」を発表した。本報告書は全10章で構成されており、その中の1つに「Latin America in focus(注目の中南米)」と題した中南米地域に着目した章立てがある。2021年の年次掲載の開始以降初めて、地域に特化した章が立てられた。
」を発表した。本報告書は全10章で構成されており、その中の1つに「Latin America in focus(注目の中南米)」と題した中南米地域に着目した章立てがある。2021年の年次掲載の開始以降初めて、地域に特化した章が立てられた。
同報告書によると、2023年の中南米・カリブ地域における水素需要は、世界需要の約4%を占める400万トンを記録した。同地域内では、トリニダード・トバコ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアの順で水素需要が多い。産業分野別の需要を見ると、トリニダード・トバコを中心に輸出用のアンモニアやメタノールを大量に生成するために水素が利用されており、域内の総需要の61%を占めている(図1参照)。石油精製は32%を占めているが、過去10年間の石油精製量の減少とともに、同分野での水素需要も減少している。
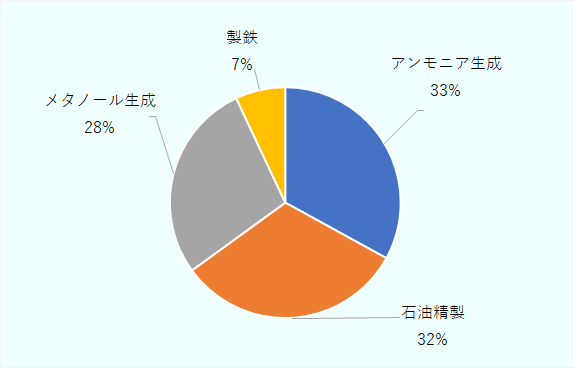
出所:国際エネルギー機関(IEA)「Global Hydrogen Review 2024」
中南米で生産されている水素の90%以上は、天然ガスの水蒸気改質法(注1)によって生産されている。この製造プロセスにおいて年間3,000万トン相当の二酸化炭素(CO2)が排出されており、いわゆるグレー水素(注2)の生産が主となっている。各国が国内消費する天然ガスのうち、水素生産に用いられる割合は、トリニダード・トバゴ(生産量全体の40%以上)を除けば、中南米地域では3~14%程度となっている。なお、各国が輸入している天然ガスを分母として見た場合、水素生産に用いられる割合は多くの国で更に高くなり、例えばブラジルでは22%に達する。IEAは、中南米地域の特徴として、天然ガスの輸入国が多い一方、再生可能エネルギーが豊富なため、水素製造において輸入した天然ガスを利用する場合よりも、再生可能エネルギーを利用する場合の方が製造コストは安価になる場合がある、と指摘している。
肥料の原料となるアンモニア生成における水素需要
中南米・カリブ地域内における水素需要の約3分の1はアンモニアの生成に占められている(図1参照)。またIEAによれば、トリニダード・トバゴを除く中南米・カリブ地域は、アンモニア需要のうち44%を輸入に頼っている現状がある。では、中南米・カリブ域内でアンモニアは何に使われているのか。
IEAが2021年10月に発表した「Ammonia Technology Roadmap![]() (7.4MB)」によれば、世界で生産されるアンモニアの約7割が肥料に利用されており、その他はプラスチック、爆薬、合成繊維などの産業用途だ。食糧輸出国が多い中南米・カリブ地域においても、アンモニアの利用用途の7割が窒素肥料に利用されている。
(7.4MB)」によれば、世界で生産されるアンモニアの約7割が肥料に利用されており、その他はプラスチック、爆薬、合成繊維などの産業用途だ。食糧輸出国が多い中南米・カリブ地域においても、アンモニアの利用用途の7割が窒素肥料に利用されている。
IEAによれば、中南米・カリブ地域における窒素肥料需要は2021年で1,600万トンのアンモニア相当となっており、そのうち域内生産で賄われたのはわずか20%だった。特に、中南米・カリブ地域において窒素肥料の需要が旺盛な国は、農業大国のブラジルで域内需要の55%を占めている。ブラジルの貿易統計において窒素肥料(HSコード3102)の輸入額は約45億6,100万ドルとなっている。2010年以降の推移を見ると、2020年までは20億~30億ドルの間を推移していたが、2021年以降は2022年を除き40億ドル超で推移している(図2参照)。一方で、輸入量は右肩上がりに伸び続けており、2024年は、統計が残る1997年以降で過去最高の約164億キログラムを記録し、実質的な需要は年々拡大していることが分かる(図2参照)。
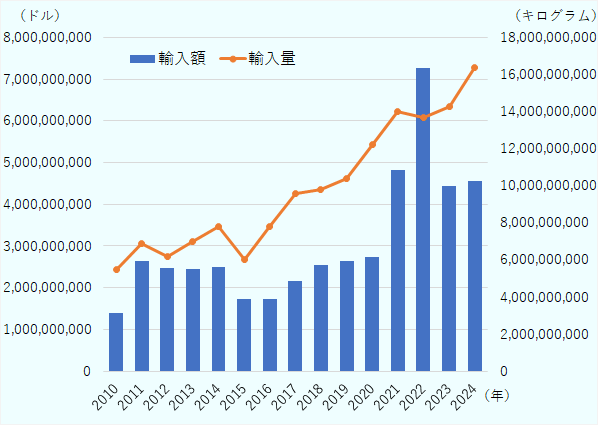
注:HSコード3102でデータを抽出。輸入額はCIF価格。
出所:ComexStatからジェトロ作成
窒素肥料の輸入相手国を見ると、1位は中国、2位はロシアとなっており、この2カ国を合わせると窒素肥料輸入額全体の約42%を占めている(図3参照)。サンパウロ大学応用経済研究所(CEPEA-USP)によれば、ブラジルはアグリビジネスがGDPの約22%を占めている農業大国だ。その生命線となる肥料を、調達リスクのある国からの輸入に頼っている現状は好ましくないだろう。
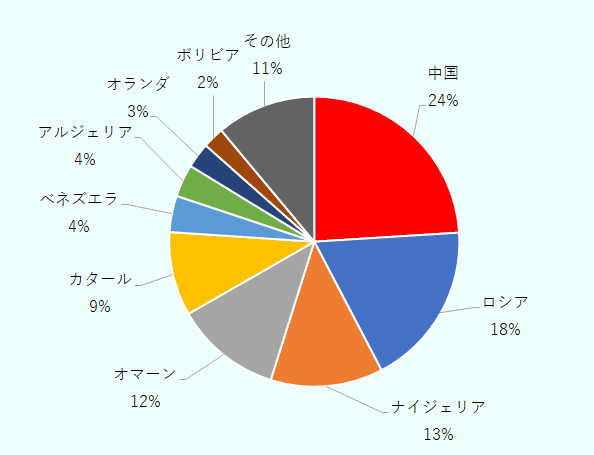
注:HSコード3102でデータを抽出。
出所:ブラジル開発商工サービス省「Comex Stat」からジェトロ作成
この調達リスクを抑えるために、ブラジルでは窒素肥料を含む肥料の国内生産を政府が支援する動きがある。ブラジル政府は、肥料の輸入を減らし、国産化を促進する目的で、2022年3月に「国家肥料計画2022-2050」を策定する政令10,991号を施行した。同計画内では、2050年までに280万トンの窒素を国内生産する目標が掲げられている。同計画の行動目標には、窒素の国内生産に向けた「国家水素戦略」と肥料チェーンの統合や、水素をベースにした窒素プラントの建設など、水素の活用を促す目標が複数見られる(参考参照)。
参考:「国家肥料計画」の目標(抜粋)
- 1.
- 2025年までに年間160万トン、 2030年に190万トン、2040年には230万トン、2050年には280万トンの窒素を生産。
- 16.
- 窒素肥料の製造拡大に向け、2030年までに少なくとも100億ドルの民間資金を誘致し、2050年まで10年ごとに同額を誘致する。
- 27.
- 2050年までに、グリーンまたはブルー・アンモニアに基づく窒素製造装置を少なくとも3基設置するための投資を誘致する。
- 29.
- 2022年から、ブラジルの国家天然ガス政策、国家水素政策と肥料チェーンの統合を積極的に推進する。
- 31.
- 南米における肥料原料の供給を拡大し、ブラジルの需要を2030年に少なくとも5%、2040年に10%、2050年に15%満たす。
- 55.
- グリーン/ブルー水素をベースとした窒素プラントを、10年ごとに少なくとも1カ所、できれば民間および/またはPPIの資源で導入するための技術開発を奨励する。
- 56.
- 2040年までに少なくとも窒素年産100万トンの生産能力を持つ、グリーン水素チェーンに接続された、尿素に代わるブラジルの基礎肥料(硝酸塩、硫酸塩)の生産を多様化するための技術革新を奨励し、資金を提供する。
出所:ブラジル農業畜産省ウェブサイト「Objetivos Estratégicos, Metas e Ações do Plano Nacional de Fertilizantes 2050」から抜粋
水素を活用したアンモニア製造の動きは、ブラジル国内で出てきている。水素・アンモニア製造を手掛ける英国ヤムナ(Yamna)とリオデジャネイロ州の港湾兼工業団地のポルト・ド・アス(Porto do açu、注3)は2025年1月7日、同港内にある低炭素水素ハブ内にグリーンアンモニア製造プラントの建設用地を確保することで合意したと発表した。ヤムナによれば、最終投資決定は2027年で、2030年からの生産開始が見込まれる。年間100万トンのグリーンアンモニア生産キャパシティを誇り、農業肥料に加え、化学製品や医薬品の製造に使用されることが想定されている。
またブラジルでは、民間企業だけでなく、農業セクターに強みを持つ州政府が動いている例もある。ブラジル南部リオ・グランデ・ド・スル州政府は2024年9月に、ビーグリーン・バイオエネルジア・イ・フェルチリザンチス・スステンターベイス(Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis)と覚書(MOU)を締結した。グリーン水素と持続可能な肥料の生産プラント3基の建設に向けた戦略的パートナーとなったことを発表した。総投資額は約1億5,000万レアル(39億円、1レアル=約26円)が見込まれている。年間8,000トンのアンモニア生産が可能となり、2027年までに操業を開始する予定だ。リオ・グランデ・ド・スル州は国内有数のコメの生産地で、ブラジル地理統計院(IBGE)のデータから試算すると、ブラジルにおけるコメ生産の約67%を占める。その他にも小麦や大豆、トウモロコシなども多く生産しており、農業が州の経済を支える産業の1つだ。同州政府は、今回のプロジェクトにより肥料の自給を達成すれば、農業資材の輸入が削減されると期待を寄せる。
ブラジルの肥料依存度の高さに注目している日本企業もいる。低温・低圧でアンモニアを合成し、分散型のアンモニア装置を展開する東京工業大学(現:東京科学大学)発のベンチャー企業「つばめBHB」だ。同社のプロジェクトは、経済産業省の「(令和5年度)質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性 調査事業」に採択されている。分散型グリーンアンモニアをベースとした小型低炭素窒素肥料製造プラントの南米展開を視野に、ブラジルにおいてモデルプラント設置に向けた実施可能性調査を行う。同社はプレスリリースで、同国が肥料の輸入依存率の高さから、国家肥料計画に基づいて官民が一体となって国内自給に向けた姿勢を見せている点に言及している。
石油精製におけるグリーン水素導入のカギを握る国営石油会社
中南米における水素需要の32%を占めている石油精製においても、今後、グリーン水素の利用が進む可能性がある。IEAによれば、中南米における2022年の製油所における水素需要は約100万トンで、国別ではブラジル(30万トン)、メキシコ(20万トン)、コロンビア(14万トン)、アルゼンチン(11万トン)と続く。石油精製プロセスにおいては、通常、石油の水素化処理などで大量の水素を利用するため、製油所内に大規模な水素製造プラントがあることが多く、グリーン水素導入への障壁は比較的低い。
既に製油所内でグリーン水素を生産し、石油精製に利用しているプロジェクトもある。例えば、コロンビアの石油公社エコペトロールが所有する同国北部のカルタヘナ製油所では、2022年3月から太陽光エネルギーを利用して工業用水からグリーン水素を生産するパイロットプロジェクトを実施している。2024年12月には、同製油所に5メガワット(MW)規模の電解槽を新設し、年間最大800トンのグリーン水素を生産するプラントの新設計画が発表された。プラントの稼働は2026年上半期とされており、年間で最大7,700トンの二酸化炭素(CO2)排出量削減(自動車1,650台の年間排出量に相当)が期待されている。生産されたグリーン水素は主に製油所内で水素化処理に利用される。
チリでは、2024年4月にチリ石油公社(ENAP)がマガジャネス州プンタアレナス市内カボ・ネグロにある同社の複合工業団地内にグリーン水素の生産プラントを建設すると発表している。同社が筆頭株主を務める風力発電所の電力を利用する水素生産プラントが建設され、製油所などでの利用が想定されている。生産開始は2025年を見込んでいる。 ブラジルでは、2025年1月に国営石油会社のペトロブラスが、サンパウロ州を低排出水素ハブの開発地に選定した。現地報道によれば、同社はサンパウロ州に所有する4つの製油所における消費に加えて、脱炭素化の難しい化学部門やセメント部門の潜在的な需要に注目しているとされている。
このように、各国の国営石油会社が製油所へのグリーン水素導入のカギを握る、とIEAは指摘する。コロンビアのエコペトロールは、2050年までにスコープ1、2、3のCO2排出量を50%削減する目標を掲げており、2040年までの水素プロジェクトへの総投資額を25億ドルと見込んでいる(表1参照)。ブラジルでは、国営石油会社ペトロブラスが2050年までにゼロエミッションを達成することを目標とし、2025年から2029年にかけて、水素に5億ドルの投資を見込んでいる。メキシコの石油公社ペメックス(PEMEX)は2024年3月に「持続可能計画」を発表した。2030年~2035年にかけて、米国から北東部ヌエボレオン州へグリーン水素を輸入して製油所での利用を開始、2035年からは電力庁(CFE)と連携して水素を国内生産する計画を打ち出している。
| 企業名 | 国 | 各社の脱炭素目標と水素利用 |
|---|---|---|
| エコペトロール | コロンビア |
|
| ペトロブラス | ブラジル |
|
| ペメックス | メキシコ |
|
| YPF | アルゼンチン |
|
出所:各社プレスリリース、現地報道など
鉱業部門における脱炭素化、火薬と重機に注目
豊富な鉱物資源を抱える中南米では、鉱業部門は重要な産業である。IEAによれば、中南米のGDPの約5%を鉱業部門が占めており、特に銅の世界最大の生産国であるチリやペルーでは鉱業部門がGDPの12%以上に達する。一方で鉱業は、採掘や加工のプロセスで温室効果ガス(GHG)を排出するため、鉱業部門の企業は排出の抑制に取り組む必要がある。
例えばチリでは、同国の鉱業評議会(Consejo Minero)に加盟する鉱業部門の大企業が温室効果ガス削減目標を設定している(表2参照)。
| 企業名 | 削減目標 |
|---|---|
| アングロ・アメリカン |
|
| アントファガスタ・ミネラルズ |
|
| BHP |
|
| テック |
|
| KGHM |
|
| コジャワシ |
|
| カセロネス |
|
| グレンコア |
|
| リオ・ティント |
|
| コデルコ |
|
注:2025年1月30日時点。
出所:チリ鉱業評議会(Consejo Minero)から抜粋
IEAによれば、今後、鉱業、特に銅への投資が拡大すれば、直接的な電動化が困難な火薬や重機・トラックの脱炭素化に水素が貢献する可能性がある、と指摘している。銅は、自動車の電動化、AI(人工知能)データセンターの増加、送電線の増加などの影響で今後需要の増加が見込まれている。銅需要の増加に伴い、銅の採掘で利用される爆薬の1つである「硝酸アンモニウム燃料油(ANFO)」の需要の増加も見込まれている。ANFOは硝酸アンモニウムと軽油などの燃料油を水中で反応させて生成する。比較的安価で容易に手に入ることから、一般的な工業用の爆薬として広く利用されている。IEAによれば、2023年の中南米地域における火薬消費量は約150万トンで、一部の専門家は今後の10年間で年平均5~8%のペースで同地域の火薬消費量が増加すると予測している。銅産業で使用される火薬のほとんどが硝酸アンモニウム由来のものだ。
この硝酸アンモニウム製造プロセスの脱炭素化を進めているのが、硝酸アンモニウムを製造するチリのエナエックス(Enaex)だ。同社は、2018年からチリ北部アントファガスタ州のトコピージャで、同地域に豊富な太陽光エネルギー由来のグリーン水素を利用したグリーンアンモニアの製造を目指す実証事業「HyEx」を実施している。エナエックスによれば、同社が原材料として輸入しているアンモニアは、硝酸アンモニウム生産プロセスにおける炭素排出量の90%を占めているという。このアンモニアをチリ国内で、太陽光エネルギーを利用して製造することで炭素排出量を削減する狙いがある。HyExプロジェクトは、2つのフェーズに分かれており、第1フェーズでは、2025年までにアンモニアを年間1万8,000トン生産し、メジジョネス港にある同社の工場で利用する。第2フェーズでは、2030年までにアンモニアの生産量を年間70万トンまで拡大し、同社工場での使用の他、輸出も視野に入れている。このようにして生産された、硝酸アンモニウム由来の火薬は鉱山会社のスコープ3(注4)における排出量削減に役立つ上、原料となるアンモニアの輸入を削減することができる。なお同プロジェクトでは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から「2022年度下期エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業(実証前調査)」の採択を受けた三井物産と東洋エンジニアリングが共同で、グリーンアンモニア製造プラントの建設に向けた実証事業を実施する。
また銅産業においては、トラック、ブルドーザー、掘削機などのディーゼルエンジンで駆動する重機から排出されるGHGの削減も課題だ。中南米で事業を展開する鉱山会社の多くが所属している国際金属・鉱業評議会(ICMM)は、2050年までにスコープ1、2におけるGHG排出のネットゼロを目標に掲げている。ディーゼルの代わりに電気や代替燃料で駆動する輸送手段や、GHGを排出しない露天掘り掘削機の導入を目指す「ICSVイニシアチブ」を発表している。
このように銅産業で利用される重機の脱炭素化が目指されている中、水素の利用を検討する企業も出てきている。2023年12月、コマツはゼネラルモーターズ(GM)と、コマツの超大型ダンプトラック向けの水素燃料電池パワーモジュールを共同開発する契約を締結したと発表した。コマツのプレスリリースによれば、ディーゼル駆動の機械の電動化に向け水素燃料電池を採用する利点について、軽量で充填(じゅうてん)時間が短い点、積載量を下げず、多量のエネルギーを効率的に搭載できる点、車両台数の規模に合わせ水素充填インフラを効果的に準備できる点を挙げている。
自動車業界で進むグリーンスチールの利用
IEAによれば、中南米地域は世界の鉄鉱石埋蔵量の約5分の1を占めている。2023年には世界の鉄鉱石貿易のうち金額ベースで約20%を中南米地域が占めており、そのうち90%をブラジルが占めている。世界鉄鋼協会(World Steel Association)の「World Steel in Figures 2024」によれば、2023年の粗鋼生産の国別ランキングではブラジルが9位(3,180万トン)、メキシコが15位(1,620万トン)となっている。中南米地域の中でも、特にブラジルにとって製鉄業は重要な産業だ。現在、鉄鉱石から鉄を取り出す方法として、コークス(炭素)を用いて鉄鉱石を還元する高炉法や、天然ガスを使用して鉄鉱石を還元する直接還元法が用いられるが、いずれも還元の過程でCO2を排出する点が課題となっている。IEAによると、製鉄は中南米地域におけるエネルギー関連の温室効果ガス排出量の約4%を占めており、年間6,500万トン以上のCO2が排出されている。そこで、製鉄プロセスに係る温室効果ガス排出を抑えるために注目されているのが、鉄鉱石の還元に水素を用いる方法だ。この方法であれば、酸素を除去する還元の過程でCO2を排出せず、水素と酸素が結びついた水が発生するので、CO2の排出を限りなく抑えることが可能だ。このようにCO2などの排出を削減して作られた鉄鋼材は「グリーンスチール」などと呼ばれ、IEAは今後、このようなグリーンスチールの需要が特定のセクターで高まると指摘している。
例えば自動車業界では、ここ数年でグリーンスチール調達に向けた各社の動きが活発になっている(表3参照)。国際自動車工業連合会(OICA)が発表している2023年の国別の自動車生産台数で、メキシコは世界第7位(400万2,047台)、ブラジルは9位(232万4,838台)となっている。ブラジル鉄鋼協会(Instituto Aço Brasil)によれば、鉄鋼製品の最終消費者の23.5%が自動車関連だ。メキシコやブラジルにおける自動車生産においてグリーンスチールの活用が始まれば、グリーンスチール製造に必要な水素の需要が拡大する可能性があるだろう。
| 自動車メーカー | 概要 |
|---|---|
| ゼネラルモーターズ(GM) |
|
| BMW |
|
| ボルボ |
|
| メルセデス・ベンツ |
|
| フォルクスワーゲン |
|
| フォード |
|
| トヨタ |
|
| 日産 |
|
出所:各社プレスリリース
ブラジルでは既に、グリーンスチール生産に向けた動きも出ている。ブラジルの資源大手ヴァーレは2023年9月、グリーンスチールを生産するスウェーデンのスタートアップ企業のステグラ(旧:H2グリーンスチール)と、ブラジルと北米における工業団地の開発を共同研究する契約を締結した。ステグラは、ブラジルや北米の工業団地で、ヴァーレが生産する鉄鉱石ブリケットと再生可能エネルギー由来の電力で生成したグリーン水素を利用した低炭素鋼の生産を目指す。ステグラは、表3の通り、既に欧州の主要な自動車メーカーにグリーンスチール供給の契約を取り付けている新興企業だ。同社がブラジルにおいてグリーンスチールを生産することになれば、中南米域内での水素需要の拡大に寄与するだろう。
- 注1:
- 天然ガスなどの炭化水素を高温の水蒸気と触媒反応させ、水素と炭酸ガスを製造する方法。
- 注2:
- 水素精製時に発生する二酸化炭素(CO2)を回収しない方法で作られる化石燃料由来の水素。約65%が天然ガス由来、20%が石炭由来、残り15%程度が石油精製プロセスなどでの副産物として得られる水素。
- 注3:
- 米国に拠点を置く投資会社EIG Global EnergyPartnersと投資ファンドMubadalaが管理するPrumo(出資率98%)と、ベルギーのAntwerpen(アントワープ)港(同2%)による合弁会社である。ブラジルの石油輸出の40%がPorto do Açuを経由している。
- 注4:
- スコープ1は、事業者自らによるGHGの直接排出、スコープ2は他社から供給された自社が用いる電気、熱・蒸気を生産する過程における間接排出、スコープ3はスコープ1、2以外の間接排出(事業活動に関連する他社の排出)。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ企画部企画課海外地域戦略班(中南米担当)
小西 健友(こにし けんゆう) - 2022年、ジェトロ入構。調査部米州課中南米班でメキシコや、ブラジルを中心とするメルコスールの政治・経済の調査を担当。2024年9月から現職。




 閉じる
閉じる






