世界のクリーン水素プロジェクトの現状と課題アルミ水素で北陸に自立型水素社会の実現を目指す(日本)
世界のクリーン水素プロジェクトの現状と課題
2025年8月22日
クリーン水素(低炭素水素)としては、再生可能エネルギーを利用した水の電気分解によるグリーン水素、化石燃料から水素を製造する際に発生する二酸化炭素(CO2)を回収するブルー水素が有名だが、水溶液にアルミニウムを浸して水素を取り出す方法もある。アルミ廃棄物からアルミを回収し、アルミから効率的に水素を取り出す技術を開発したアルハイテック社(富山県高岡市)は、廃棄物とエネルギーの地産地消を目指し、自立分散型水素社会を北陸に実現することを目指す。
廃棄されるアルミの再利用に着目
アルミニウムは製造・運搬・廃棄のそれぞれでCO2を排出する。通常のアルミリサイクルではアルミドロスという不純物が多いものが2~3割発生し、現状では焼却している。アルミ業界ではリサイクルの取り組みが進んでおり、再生インゴットなどに戻すことも多いが、リサイクルしたものをそのまま使うことは難しく、純度の高い新しいアルミと混ぜる必要がある。
アルハイテックの水素製造装置の原料となるアルミとしては、アルミ缶や包装材、紙パックなどの家庭ごみ、製造端材や切粉などの工場廃棄物がある。アルハイテックは、回収が難しいアルミ付き紙容器から紙を分離するパルパー型分離機を開発し、紙容器をパルプとアルミ付きプラスチックに分離することを可能にした。回収した紙パルプは、トイレットペーパーなどにリサイクルできる。その後、アルミ付きプラスチックを同社が開発した乾留式アルミ回収装置に入れ、アルミに付着したプラスチックを熱によって分解除去し、可燃性ガスを生成して燃焼させて熱エネルギーとして利用する。これで、プラスチックが除去された純度の高いアルミを取り出すことが可能。


これらの装置で回収されたアルミや空き缶、アルミホイル、端材などを原料とし、水素製造装置で水素を製造する。アルミは以下の化学式のように、水と反応して水素を発生させるが、通常の状態では表面に酸化アルミニウム膜が形成されているため、水と直接反応せず、水素を発生しない。そこで、水酸化ナトリウム水溶液などのアルカリ性溶液を用いて酸化膜を破壊することで水との反応を促す。アルハイテックは、水酸化ナトリウムをベースとした特殊な水溶液を開発し、効率的な水素生産を可能にした。アルミを水溶液に浸すだけで水素が発生するため、電力や熱などのエネルギーは不要。反応プロセスでもCO2は排出しない。1キログラム(kg)のアルミを投入すると0.11kgの水素が発生する。これは、最新型の燃料電池で2キロワット時(kWh)の発電を可能にし(注1)、水素燃料電池自動車(FCV)が20キロメートル(km)走行できる量となる(同社試算)。
- 2Al+6H2O→2Al(OH)3+3H2
- Al:アルミニウム
- H2O:水
- H2:水素
- Al(OH)3:水酸化アルミニウム
同社は、顧客の需要に応じたオンデマンドの定置型水素製造装置に加え、装置を移動可能にした「エ小僧」という可搬型水素製造装置も開発。エ小僧は、電源がない所でも利用可能、常温・常圧で安全に運搬することができる。反応液(水溶液)は毒物対象外で、高圧ガス製造保安責任者も不要。使用済みの反応液は、不純物を取り除くことで約100回再利用が可能。アルミの自動投入機能など、利便性を向上させた「エ小僧SMART」も開発中だ。装置内で水素の貯蔵はできないため、地産地消型の利用、例えば燃料電池を介した電力による通信や情報提供など、比較的小規模な利用が想定される。


副産物収入で導入コストを削減
アルミ水素の製造プロセスにおいては、副産物として水酸化アルミニウムが発生する。水酸化アルミニウムは、工業原料として利用できるため、売却して収入を得ることにより、水素製造コストを相殺して下げることが可能になる。アルミ1kgを反応させると水素が0.11kg、水酸化アルミは2.9kg発生する。単価は品質や用途によって異なるが、1kg当たり100円以上で売れる。
水酸化アルミニウムは、質が悪いものは凝集剤(注2)、質が高ければ医療品として利用可能。水素製造装置の副産物として出る水酸化アルミニウムでも、壁紙や車のシートに使われる難燃剤の原料として利用可能であることは実証済みだ。アルハイテック社によると、最近は人工大理石の原料として使えないかどうか、引き合いがあったようだ(表参照)。現在、水酸化アルミニウムの需要が高まっている。要因としては、米国のアルミ製造大手アルコアがオーストラリア西部のアルミナ精錬所を閉鎖したことなどによる供給不足が考えられる。また、環境に優しい方法で生産された水酸化アルミニウムを購入したいと考える顧客もいるようだ。
| 用途 | 製品 |
|---|---|
| 凝集剤原料 |
|
| 土壌硬化剤原料 | アルミン酸ソーダ |
| 難燃剤原料 |
|
| 顔料原料 | 各種顔料 |
| 人工大理石原料 | 各種人工大理石 |
| 医薬品原料 | 各種医薬品(経口剤) |
出所:アルハイテック社提供資料から作成
アルミは一般的にボーキサイトから製造するが、精練のために大量の電力を要し、コストもかかる上、製造過程で大量のCO2を排出する。また、中間製品の水酸化アルミニウムやアルミナを製造する過程で副産物として発生する、ボーキサイト残渣(ざんさ、赤泥)が環境汚染につながるという課題もある。水素の製造過程で生産された副産物の水酸化アルミニウムをリサイクルして、図のようにアルミニウムの製造工程に再投入できれば、CO2の排出削減や発生する赤泥の減少を通じた環境汚染の軽減などの効果が得られる可能性もある。
図:アルミニウムの製造工程と回収した水酸化アルミニウムの再投入
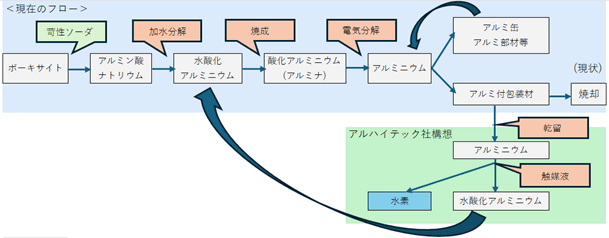
出所:アルハイテック社提供資料から作成
アルミを水素輸送のためのキャリアに
他の水素製造方法と比較した場合のアルミ水素のもう1つのメリットとして、運搬と貯蔵が容易なアルミを、水素のキャリア(運搬手段)として利用できるという点だ。水素のエネルギー密度は、重量当たりでは33.3kWh/kgと高いが、体積当たりでは天然ガスの約3分の1、ガソリンと比較すると約2,900分の1の熱量しかない。そのため、水素を効率的に輸送・貯蔵するためには、高圧化や液化などの工夫が必要だ。輸送・貯蔵に際し、特別な設備やインフラが必要となり、そのためのコストが高い(注3)。アルミ水素の場合、回収したアルミスクラップを運搬・貯蔵し、必要な時に必要な量だけ水素を製造すればよいため、運搬・貯蔵のための費用が低く抑えられる。
逆に、アルミ水素のデメリットは、原料となるアルミを投入し続けないと水素の連続的な生産ができないことだ。したがって、系統電力向けの大規模発電用途などには向かない。例えば、山梨県富士吉田市でHydrogen Technology社が2022年4月から実証運転をしている水素エンジン発電機(出力320kW)を動かすために必要な水素量は、1時間当たり270ノルマルリューベ(Nm3)だが、アルハイテック社の試算によると、アルミ水素でこの水素を製造する場合、1時間当たり約270kgのアルミニウムの投入が必要になる。アルミ水素の用途として適しているのは、工場などにおける熱源の代替(水素バーナー・ボイラー)や燃料電池などを利用したバックアップ電源、製造工程の一部をクリーン電力に代替する用途などだという。
アルハイテック社は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成を活用した実証事業として、2023年5月に北陸ミサワホーム株式会社(金沢市)が運営するレジャースポットのモン・ラック・タカオカにおいて、アルミを原料として製造した水素で湯を沸かす「温泉パッケージ」を完成させた。アルハイテック社によると、同温泉が1日に利用するお湯を温めるための水素は、1時間当たり8kgのアルミを水素製造装置で8時間反応させれば製造できる。温浴施設のボイラーの燃料は主に化石燃料由来の燃料を使っており、CO2を排出しない水素の利点を訴えて、全国の旅館やスーパー銭湯などに導入を働きかけている。同社によると、温泉パッケージ1システム当たりの年間CO2削減量は、738トンCO2に及ぶ。
地産地消の地域プロジェクトで商業化を目指す
富山県は、水力発電による安定した電力供給を背景に、アルミ産業が成熟した。現在は、アルミの精練は行われていないものの、加工業は残っており、アルミ加工工場から廃棄されるアルミの量が一定規模存在する。特に細かいアルミ(機械加工工程などで発生する切粉など)は再利用するのが難しく、水と反応してしまうと危険物にもなりやすいので、廃棄されることが多い。そのため、水素製造への利用に適している。技術的に回収が困難なために、今までは捨てられていたアルミ付き紙容器などから回収されるアルミも同様である。
アルミは世界中で利用されており、燃費効率や電動車の航続距離の観点から軽量化が求められる自動車産業などでは、今まで以上に利用が増加することが見込まれる。アルミの再利用やそこからクリーンエネルギーを生み出すアルハイテック社の技術に対する需要は、世界的にも存在すると考えられるが、同社としては、まずは北陸を中心に地産地消の商業化プロジェクトを増やしていき、確固たる技術を確立した上で国際展開に臨む方針だ。前述した中小規模の商業施設や工場における熱源代替に加え、アルミの切粉などが大量に発生する自動車部品の製造工場などにおいても、工場内で発生する廃アルミを原料に、一部の製造工程の熱源や電源を水素由来のものに転換していく需要が見込めると考えている。
将来的なビジョンとしては、輸送が比較的容易なアルミを、エネルギーキャリアとして国際的に循環利用する構想を掲げている。アルミ水素の副産物であり、アルミ製造の原料工程の中間生成物でもある水酸化アルミニウムの一部を、アルミ精錬が盛んな海外の国へ輸出してアルミに戻し、再度日本に輸入し、そこからアルミ水素を得てエネルギー利用をするというものである。同構想が国際的なアルミ、水素および水酸化アルミのサプライチェーンの脱炭素化にもつながることを視野に入れたものだ。

- 注1:
- 水素のエネルギー密度である1kg当たり33.33kWhから計算。
- 注2:
- 液体中の微細な固体粒子やコロイド上の物質を集めて大きな塊にし、沈降や分離を促進させるための薬品。水の濁りなどを除去する目的で用いられる。
- 注3:
- 最も効率的な輸送形態である液化水素の場合、マイナス253℃まで冷却する必要があり、液化天然ガスのマイナス162℃よりもさらに低温が求められる。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部米州課主幹(中南米)
中畑 貴雄(なかはた たかお) - 1998年、ジェトロ入構。貿易開発部、海外調査部中南米課、ジェトロ・メキシコ事務所、海外調査部米州課を経て、2018年3月からジェトロ・メキシコ事務所次長、2021年3月からジェトロ・メキシコ事務所長、2024年5月から調査部主任調査研究員、2025年4月から現職。単著『メキシコ経済の基礎知識』、共著『グローバルサプライチェーン再考: 経済安保、ビジネスと人権、脱炭素が迫る変革』、『NAFTAからUSMCAへ-USMCAガイドブック』など。






 閉じる
閉じる





