Alterno-砂電池を開発・展開
ベトナムスタートアップに聞く(2)
2024年1月18日
ベトナムを含めた東南アジア地域は、日系企業の「生産拠点」としての魅力に加えて、多くの人口と購買力の向上を背景にした「消費市場」としての魅力がある。近年は、さらに「イノベーション創出拠点」としての魅力も注目されている。中でもベトナムは、(1)1億人に増加した人口を背景とした消費市場拡大への期待、(2)依然として金融、交通・物流、医療などを中心とした多くの社会課題が山積していること、(3)高いインターネット利用率やデジタルネイティブな若年層人口が豊富であることを背景としたリープフロッグ現象(注1)の出現、などの観点から、インドネシアなどとともに「コンシューマードリブン(Consumer-driven)イノベーション」の地として分類される(注2)。
本シリーズでは、さまざまな社会課題の解決に取り組むベトナムのスタートアップ創業者などへのインタビューを通じ、同国のスタートアップ・エコシステム、デジタルトランスフォーメーション(DX)、グリーントランスフォーメーション(GX)の最新動向や日本企業との協業に向けたヒントを探る。
第2回は、砂の蓄熱力を利用して熱エネルギーを貯蔵、分配する「サンドバッテリー(砂電池)」を提供する「アルテルノ(Alterno)」を取り上げる。ベトナム政府が2050年までに温室効果ガス(GHG)の排出量実質ゼロ(カーボンニュートラル)を目標としている中(2021年11月9日付ビジネス短信参照)、ベトナム国内でも温室効果ガス削減に向けたソリューションを生み出すさまざまなスタートアップも生まれている。ホーチミン市に拠点を置くアルテルノは、砂電池をはじめとする独自設計の設備を顧客に導入してもらうことで、中長期的な温室効果ガスや燃料コストの削減を目指している。2023年2月の創業後、国内外のコンテストで数多く入賞するほか、シンガポールのベンチャーキャピタル(VC)からの資金調達を実現している。起業の経緯から今後の展望まで、同社の共同設立者である最高経営責任者(CEO)のグエン・テー・ルアン氏と最高顧客責任者(CCO)のハイ・ホー氏に聞いた(インタビュー日:2023年8月2日、9月19日)。

ハイ・ホーCCO。奥のオレンジ色の装置が蓄電装置(砂電池)、その右にある銀色の装置が乾燥装置
(アルテルノ提供)
- 質問:
- 提供している製品は。
- 答え:
- 当社の製品は、(1)システム全体のコントロール装置(コントロールボックス)、(2)蓄熱装置(砂電池)、(3)乾燥装置の3つのコンポーネントで構成されている。
- (1)のコントロールボックスは、送電網からの電力(グリッド電力)や、ソーラーパネルなどからの電力を砂電池で熱に変換して蓄えられるようにコントロールするほか、砂電池や乾燥装置の温度や湿度などを管理する。IoT(モノのインターネット)の進展により、データはクラウド管理されており、コントロールボックスは遠隔操作が可能だ。(2)の砂電池は、コントロールボックス経由で供給される電気を熱に変換し、貯蔵する装置。熱エネルギーにいったん変換すれば、600度で30日間の貯蔵が可能だ。(3)の乾燥装置は、農産物の乾燥や、工業プラント、商業ビル向けの乾燥システムなどに用いられる。砂電池を使用することで、石炭・石油などの化石燃料や木を燃やすことによる乾燥手法よりも安価で、二酸化炭素(CO2)の排出が少ないことが特徴だ(図参照)。現在は環境配慮への意識が高いオーガニックの青果物農家や茶農園、コーヒー農園などへの導入が決まっている。
-
図:エネルギー源別の農産物乾燥コスト比較 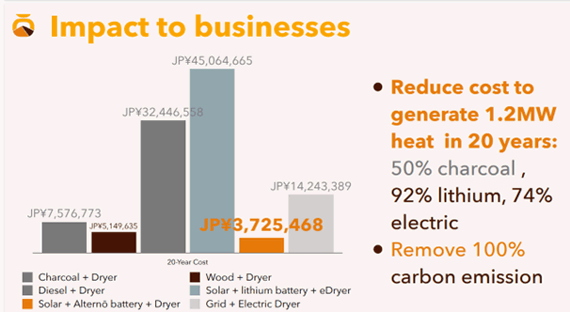
出所:同社ピッチ資料
- 質問:
- 設立のきっかけは。
- 答え:
-
コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査
 によると、世界のエネルギー消費量のうち、産業や建物向けの冷暖房が占める割合は52%に上る。これらを砂電池システムに置き換えると、年間5,400億ドルものコストを節約できると試算している。二酸化炭素の排出を抑えることから環境に優しく、大きなビジネスチャンスであると感じた。創業時のボードメンバー(役員)でベトナム各地を訪れ、砂電池の応用可能性を調査した結果、特に茶葉、コメ、コーヒー豆などといった農作物の乾燥工場において、幅広い用途で活用可能であると判断した。
によると、世界のエネルギー消費量のうち、産業や建物向けの冷暖房が占める割合は52%に上る。これらを砂電池システムに置き換えると、年間5,400億ドルものコストを節約できると試算している。二酸化炭素の排出を抑えることから環境に優しく、大きなビジネスチャンスであると感じた。創業時のボードメンバー(役員)でベトナム各地を訪れ、砂電池の応用可能性を調査した結果、特に茶葉、コメ、コーヒー豆などといった農作物の乾燥工場において、幅広い用途で活用可能であると判断した。
- 質問:
- 今後の事業計画は。
- 答え:
- 2023年に、新たな事業や産業の創造や成長支援を行うドリームインキュベータ(東京都千代田区)と国際協力機構(JICA)が実施する実証プログラムに採択されたこともあり、当面はプロダクトマーケットフィット(PMF、注3)の検証活動に取り組んでいく。特許については、ベトナム国内で出願中だが、今後は米国での特許取得も目指している。加えて、顧客の拡大と、製品の改良やシステムの性能向上を図っていく。資金調達に関しては、2023年にシードラウンド(注4)を終えたので、2024年第2四半期(4~6月)までにシリーズAの調達を実施する予定だ。
- 質問:
- 日本企業などに対して期待することは。
- 答え:
- 日本企業などに対しては、(1)当社の顧客にファイナンスサービスを提供可能な金融機関の紹介、(2)日本市場で当社製品を製造・展開するためのパートナーの模索、 (3)太陽光による蓄電・蓄熱効率の向上、他の再生可能エネルギーから熱を回収する方法の研究協力が可能な大学との連携、(4)資金調達での協力、を期待したい(注5)。
- 注1:
- 新興国で新しい技術やサービスなどが、先進国が歩んできた過程を飛び越えて急速に広まること。
- 注2:
- ジェトロ調査レポート「東南アジアにおけるイノベーション創造活動に関する調査」(2022年8月)を参照。
- 注3:
- プロダクトマーケットフィット(PMF)とは、顧客の課題を満足させる製品を提供し、それが適切な市場に受け入れられている状態〔出所:東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC)ウェブサイト〕。
- 注4:
- シードラウンドとは、スタートアップが創業する段階での最初の資金調達のラウンドを指し、その次の調達ラウンドを、シリーズA、シリーズBと呼ぶ。
- 注5:
- 本スタートアップへの取り次ぎを希望する場合は、ジェトロ・ホーチミン事務所(VHO@jetro.go.jp)まで連絡を。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ホーチミン事務所 事業統括ディレクター
三木 貴博(みき たかひろ) - 2014年、ジェトロ入構。海外見本市課、ものづくり産業課、ジェトロ岐阜を経て海外調査部アジア大洋州課にてベトナムをはじめとしたASEANの調査業務に従事。2022年7月から現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ホーチミン事務所
ファン・ウィン - 2023年から、ジェトロ・ホーチミン事務所勤務。日本とASEANなどの企業によるデジタル技術を活用した連携を推進する「J-Bridge」事業を担当。






 閉じる
閉じる





