昆虫食解禁へ、環境負荷の少ない新たな代替タンパク源に注目
食料自給率引き上げへ、都市国家シンガポールの試み(1)
2023年3月3日
シンガポールでは、2023年中にも人向けの食用や、動物飼料としての昆虫の輸入や販売が解禁となる見通しだ。また、同年中には細胞培養肉の商業生産が始まる。同国では、新たな代替タンパク源としての細胞培養肉や植物代替肉、昆虫食などへの投資のほか、都会型農業事業者の新規参入が活発化している。食料自給率向上に向けたシンガポールの取り組みを3回に分けて報告する。
日系昆虫スタートアップも拠点設立
シンガポール食品庁(SFA)は2022年12月4日、食用としての昆虫や、動物飼料としての昆虫の輸入、販売を認める制度案について、食品や畜産飼料関係者からの意見公募を締め切った。同国ではこれまで、食用としての昆虫の輸入と販売は認められていない。動物飼料用の昆虫については、一部条件付きで認めている(注1)。しかし、2023年中にも、人や動物を対象とした昆虫食が解禁となる見通しだ。
SFAの意見公募によると、販売や輸入が認められるのは、これまでに食品としての実績がある昆虫だ。具体的には、(1)バッタやコオロギなどの直翅類(ちょくしるい)、(2)甲虫類などの鞘翅目(しょうしもく)、(3)ハチミツガやカイコなどの鱗翅目(りんしもく)、(4)コガネムシ類、(5)ミツバチに代表される膜翅目(まくしもく)の5種類の昆虫だ(注2)。
食用としての制度の導入を前に、シンガポールでは食用や動物飼料などを目的とした昆虫の育成に取り組むスタートアップが増えつつある。シンガポール企業庁(EnterpriseSG)によると、2016年には1社だったスタートアップは、2022年末時点で15社へ増えた。シンガポールを拠点とする昆虫系スタートアップへの投資額は2019年から2022年9月までの3年弱で合計4,000万米ドルに上っている。
さらに、2022年には機能性タンパク源としてカイコの研究に取り組むMorus(モールス、本社:東京都)がシンガポールに法人を設立するなど、日系の昆虫スタートアップの進出もあった。食用としての昆虫が2023年中にも解禁となれば、海外からの昆虫系スタートアップの進出が増えていくと期待されている。
環境に優しい代替タンパク質としての昆虫食に注目
食料の約9割を輸入に依存するシンガポールは2019年3月、栄養ベースでの食料自給率を2030年までに30%へ引き上げる目標「30×30」を発表した(2020年9月17日付地域・分析レポート参照)。この目標を達成する上で、昆虫食は新たなタンパク源の1つとして期待されている。
また、昆虫の優位点は、生産するに当たって農地や水、労働投入量が他の食品原料と比べると少なく、環境への影響が小さいことにある(図参照)。例えば、コオロギの生産に必要な農地はタンパク質1グラム当たり牛肉の約14分の1、水の量も牛肉の約56分の1ですむ。飼育に必要な作業量も、鶏や牛に比べると圧倒的に少なく、コストも抑えられるメリットがある。
図:主要食品およびコオロギの生産に必要な農地、水量、労働投入量の違い
(単位:平方メートル)
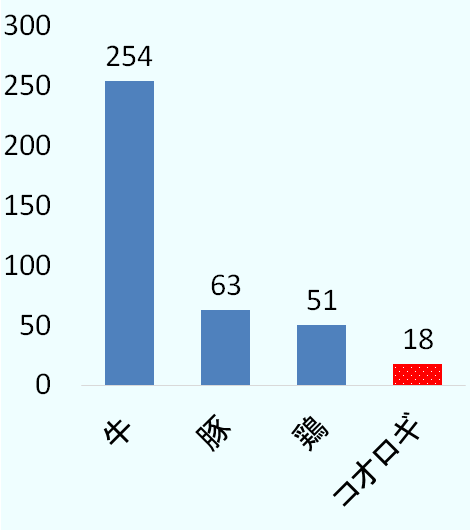
(単位:リットル)
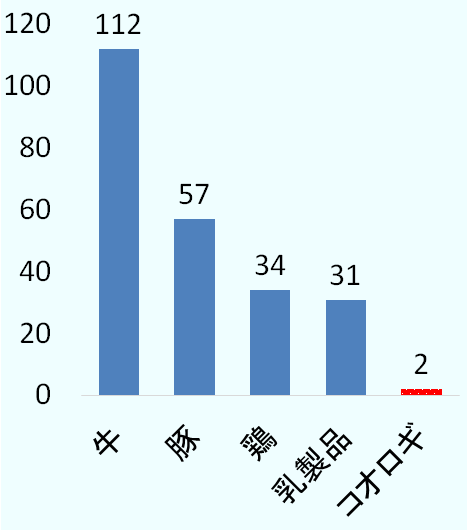
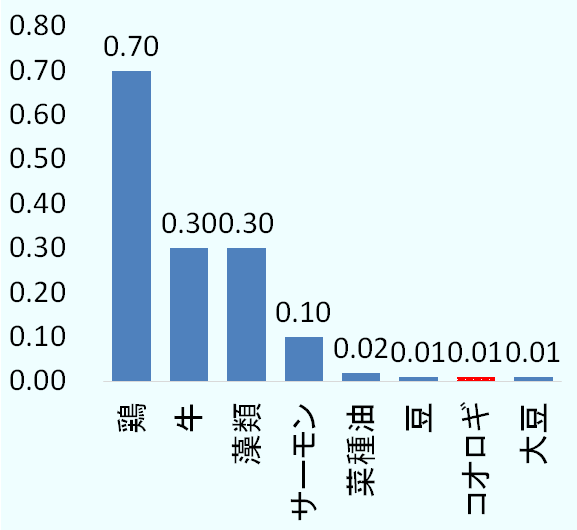
注:農地については2018年、水量、労働投入量については2016年時点の数値。
出所:Statista
ただ、シンガポールに本社を置く昆虫系スタートアップの多くは、国内に昆虫を飼育する農園を置いていない。同国では農地のリースが難しく、労働力が確保しにくい上、人件費も高い。このため、昆虫の餌となるパーム油の搾りかすなど食品廃棄物の入手が容易で、土地も労働力も安価な国外に農園を置くことが多い。例えば、シンガポールで最も早くから昆虫食の開発に取り組むプロテンガ(2016年創業)は、2018年から隣国マレーシア南部ジョホール州でアメリカミズアブ(black soldier fly)の飼育農場を運営している(2022年7月20日付ビジネス短信参照)。
バイオ原料としての昆虫に期待
一方、需要面をみると、シンガポールで昆虫食が一般に普及するまでには、時間がかかりそうだ。昆虫はもともと、日本や中国、タイなどアジアの国々で食べられてきた歴史があるが、シンガポールでは昆虫食の習慣がほとんどない。プロテンガも、アメリカミズアブの幼虫を原料とする犬や猫などのペットフードを中心に開発する。その理由について、レオ・ウェイン創業者兼CEO(最高経営責任者)は2022年7月4日、ジェトロのインタビューで、「人向けの昆虫食は(一般化するまでに)まだハードルが高い」ことを挙げた。同CEOは「世界の肉の20%がペットフード向けに使用されており、食料安全保障の観点からも、肉以外の代替食が必要」との考えを示した。
シンガポールを拠点とする昆虫系スタートアップ15社(2022年末時点、表参照)のうち、人の食用として昆虫食に取り組むのは3社にとどまる。プロテンガのように、昆虫由来の動物飼料やペットフードの開発に取り組むスタートアップが8社と最も多い。
| 分類 | 企業名 | 創立年 | 製品・ソリューション |
|---|---|---|---|
| 昆虫由来の飼料・肥料 |
ブルー・アクア・フード・テック (Blue Aqua Food Tech、注) |
2021 | 養殖エビ・魚用飼料 |
|
エント・インダストリーズ (Ento Industries) |
2020 | アメリカミズアブ由来の動物飼料、肥料 | |
|
フィードワークズ (FeedWerkz) |
2020 | 動物飼料、肥料 | |
|
インセアクト (Inseact) |
2019 | アメリカミズアブ由来の養殖用飼料、肥料 | |
|
インセクト・フィード・テクノロジーズ (Insect Feed Technologies) |
2020 | アメリカミズアブ由来のペットフード、肥料 | |
|
ニュートリション・テクノロジーズ (Nutrition Technologies) |
2017 | アメリカミズアブ由来のペットフード、肥料 | |
|
プロテンガ (Protenga) |
2016 | アメリカミズアブ由来のペットフード、肥料 | |
|
ワームズ (Werms) |
2020 | コオロギ、ミールワーム由来の観賞魚、鳥等のペットフード | |
| 昆虫由来の化粧・製薬・バイオメディカル |
バイトベック・バイオテクノロジー (Biteback Biotechnology) |
2016 | 昆虫由来のパーム油に代わる代替油 |
|
インセクタ (Insectta) |
2018 | アメリカミズアブ由来のキトサン、メラニン | |
|
イエロー・バイオテック (Yellow Biotech) |
2022 | 動物飼料などの栄養添加剤 | |
| 昆虫食(人用) |
アジア・インセクト・ファーム・ソリューション (Asia Insect Farm Solutions) |
2017 | コオロギ由来の代替タンパク質パウダー |
|
アルティマイト・ニュートリション (Altimate Nutrition) |
2020 | コオロギ由来のプロテイン・バー(栄養補助食品) | |
|
フューチャー・プロテイン・ソリューションズ (Future Protein Solutions) |
2019 | コオロギ由来の人向け、および動物向けパウダー | |
| 昆虫農園システム |
エントモ・ベンチャー (Entomo Venture) |
2018 | 昆虫農園のデジタル管理システム |
出所:シンガポール企業庁(EnterpriseSG)、各社ホームページ
このほか、アメリカミズアブを原料に、化粧品や医薬品用のバイオ材料を開発するスタートアップもある。シンガポールのスタートアップのインセクタ(2018年創業)のチュア・カイニン最高マーケティング責任者は2022年7月25日、ジェトロのインタビューで「昆虫系代替タンパク質に取り組むスタートアップはかなり飽和状態とみて、(昆虫由来の)バイオ材料に特化している」と述べた。同社はアメリカミズアブからキトサンやメラニンの抽出に取り組む。キトサンは化粧品や薬、サプリメントとしての使用が期待できるほか、メラニンは医薬品の材料として使えるだけでなく、人の体内に埋め込み可能な有機半導体の材料にもなるという。食用としての代替タンパク質だけでなく、環境に優しい動物用飼料、医薬や化粧品のバイオ材料へと、その用途拡大に向けた開発が進んでいる。
- 注1:
- シンガポールの飼料法(Feeding Stuffs Act)では、動物飼料(ペットフードは含まず)に昆虫を含むことを認めている。しかし、その原料となる昆虫を飼育する際に、餌として植物由来の廃棄物を使用するなど、条件を限定している。
- 注2:
-
食用として認める予定の具体的な昆虫の種類については、SFAの発表資料(182KB)
 を参照。
を参照。
食料自給率引き上げへ、都市国家シンガポールの試み

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・シンガポール事務所 調査担当
本田 智津絵(ほんだ ちづえ) - 総合流通グループ、通信社を経て、2007年にジェトロ・シンガポール事務所入構。共同著書に『マレーシア語辞典』(2007年)、『シンガポールを知るための65章』(2013年)、『シンガポール謎解き散歩』(2014年)がある。




 閉じる
閉じる






