細胞培養肉や植物代替肉、新たなタンパク源開発が加速
食料自給率引き上げへ、都市国家シンガポールの試み(2)
2023年3月3日
シンガポールでは近年、植物代替肉や細胞培養肉などフードテック関連のスタートアップが急速に集積している。その背景には政府が積極的に代替肉産業を支えるエコシステムを整備しているほか、人々の環境や健康に対する意識の高まりもある。食料自給率向上に向けた政府の取り組みの現状を伝える特集の2回目。
高まる健康や環境への意識、代替肉に注目
シンガポールでは近年、植物由来肉や細胞培養肉など代替肉を提供する飲食店が増えている。都心部の高級食材店フーバーズ・ブッチャリーで2023年1月から、米国のイート・ジャストが開発した鶏の細胞培養肉の販売が限定的に始まった。2022年1月には中華街の一角に、豆などの植物由来の代替肉を販売するアジア初の植物由来の専門肉店「ラブ・ハンドル」が開店した。また、大手バーガーチェーンのマクドナルド、バーガーキングやケンタッキーも2021年以降にそれぞれ植物代替肉を使ったバーガーの提供を始めた。このほか、主要なスーパーマーケットでも、植物代替肉の缶詰や冷凍食品の取り扱いが増えている。

こうした代替肉の普及を後押ししているのが、人々の健康や環境意識の高まりだ。英国の調査会社ユーガブ(YouGov)が2020年2月に発表した調査によると、シンガポール国民に占めるベジタリアンやビーガンの割合は7%、肉を食べないが魚介類を食べるペスカタリアンが3%にとどまる。ただし、野菜中心で肉を時々食べるフレクスタリアンは39%と、肉を食べると答えた人(42%)とほぼ同じ比率だ。肉を食べると答えた人や時々食べるフレクスタリアンが、ベジタリアンやビーガンの食事を検討する理由として、上位3位が「健康への懸念」を挙げ、第4位に「環境のため」と答えている(複数回答、図参照)。
ベジタリアン、またはビーガンの食事を検討する理由(単位:%、複数回答)
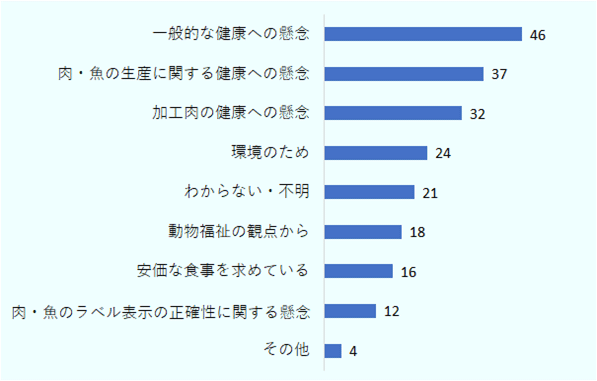
出所:ユーガブ(YouGov)2020年2月発表
代替タンパク質企業、30社以上が集積
こうした代替タンパク食品を開発するフードテック分野のスタートアップも近年、シンガポールに集積しつつある。米アグリフードテック専門のベンチャーキャピタル(VC)のアグファンダー(Agfunder)によると、シンガポールには2022年11月時点で、30社以上の代替タンパク質を開発する企業が拠点を置く。同国の代替タンパク質を中心とするフードテック関連のスタートアップが2022年上半期に調達した資金総額は、1億110万米ドルとアジア太平洋地域で最も多かった。
シンガポールに代替タンパク質食品を開発するスタートアップが集まる背景には、政府の積極的な後押しがある(2022年2月18日付地域・分析レポート参照)。シンガポール食品庁(SFA)は食料自給率を2030年までに30%へ(栄養ベース)引き上げる目標を設定。昆虫食と同様、植物代替肉、細胞培養肉なども新たな代替タンパク源と位置付けている。
さらに、グレース・フー環境持続相は2022年10月26日、フィンランドのソーラー・フーズ(Solar Foods)が開発した微生物タンパク質「ソレイン(Solein)」の販売を承認した。ソレインは、微生物に二酸化炭素、水素、酵素と少量の栄養素を与えて生成した粉末状の代替タンパク源のこと。代替乳製品や代替肉、スナックやパスタ、飲料やパンなどに利用ができると期待されている。ソレインの販売を許可したのは、世界でもシンガポールが初めてだ。ソーラー・フーズは2024年にフィンランドでソレインの商業生産を開始する予定だ。
内外のスタートアップ、細胞培養肉の商業生産開始へ
SFAは細胞培養肉について、2019年11月に新規食品(ノベルフード)の販売、製造に関する規制の枠組みを世界に先駆けて導入している。こうした規制環境の整備を受けて、内外の細胞培養のスタートアップが同国での商業生産の準備を進めている。米国のスタートアップ、イート・ジャスト(Eat Just)が培養肉の増産に向けて建設中の製造施設兼研究・開発(R&D)施設は2023年中にも完成する予定だ。同工場には、培養肉業界では最大容量の6,000リットルのバイオリアクターが設置される。また、魚の培養肉を開発する中国のアバント・ミーツもシンガポールでのR&D兼パイロット製造施設を2023年に稼働開始する見通しだ。さらに、地場のスタートアップでも、甲殻類の培養肉を開発するシオック・ミーツ(Shiok Meats)が2023年、魚の培養肉の開発に取り組むウマミ・ミーツが2024年以降に、それぞれ商業生産の開始を目指している(注)。
細胞培養肉の本格普及、コストや規制の整備など課題も
ただ、本格的な商業生産に当たっては、さまざまな課題がある。予定されている商業生産の規模は依然として小さく、そのため製品販売価格も高額となる。この解決手段として、細胞培養肉に植物代替肉を混ぜたハイブリッド製品を開発すれば、コストを削減できる可能性がある。牛や豚などの細胞培養肉を開発するオランダのミータブル(Meatable)は2022年11月16日、冒頭のラブ・ハンドルと共同で、ハイブリッド肉開発を専門とするイノベーションセンターの設置を発表した。ミータブルはラブ・ハンドルとの提携を通じて、ハイブリッド肉で製造したミートボールやパテ、豚バラ肉の代替肉などを2024年までにシンガポールのレストラン、翌2025年にはスーパーマーケットへの出荷を目指す計画だ。
さらに、市場拡大の課題もある。シンガポールに地域統括本部を置く非営利団体グッド・フード・インステチュート(GFI)のミルテ・ゴスカー・アジア太平洋地域代表は2022年10月28日、ジェトロの取材に対し、「シンガポールの限られた市場での事業拡大は難しい。このため、他の国々でも細胞培養肉(の販売)承認が必要になる」と指摘した。その上で、同代表は現段階で「シンガポールはこれまで蓄積した成功事例を国連食糧農業機関(FAO)などに共有することに非常に前向きで、(市場拡大のためには)シンガポールが重要な役割を果たすのは確実だ」との見方を示した。
エジプトで2022年11月に開催された国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)の期間中、フー環境持続相が主催した夕食会で、イート・ジャストの培養鶏肉が出席者に提供された。イート・ジャストのジョシュ・テトリック共同創業者兼CEO(最高経営責任者)は同月7日の報道発表で、「シンガポールは森を伐採、または動物の生態系を破壊せずに生産した肉を認めた最初の国だ。他の国も追随することも望む」と期待を示した。
- 注:
- シンガポールに集積する細胞培養肉など代替タンパク質関連のスタートアップや企業の動向については、ジェトロの「世界は今―JETRO Global Eye」を参照。
食料自給率引き上げへ、都市国家シンガポールの試み

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・シンガポール事務所 調査担当
本田 智津絵(ほんだ ちづえ) - 総合流通グループ、通信社を経て、2007年にジェトロ・シンガポール事務所入構。共同著書に『マレーシア語辞典』(2007年)、『シンガポールを知るための65章』(2013年)、『シンガポール謎解き散歩』(2014年)がある。






 閉じる
閉じる





