【コラム】ロックダウンでベトナムのサプライチェーンが脱中国依存の試金石に
新型コロナ禍の現状を駐在員視点で読み解く(4)
2021年11月10日
ベトナムには、サプライチェーン強靭(きょうじん)化の拠点として期待が高い。一方で、新型コロナウイルス対策として導入された厳しい操業規制や移動制限により、工場での生産が停止・縮小。日本への部品供給などに支障が生じた。今後、ベトナムでの生産比率を見直すか否かが検討材料になっていくかもしれない。その際は、品目ごとに、中国をはじめ他国からの輸入割合などをきめ細かく検討することも重要だ。
ウィズコロナ(新常態)への転換で企業生産活動が順次再開
ホーチミン市では2021年9月30日午後6時から、外出制限などの厳しい社会隔離措置が緩和された(2021年10月4日付ビジネス短信参照)。これまでは、新規感染者が0人になってから緩和されてきた。しかし、9月30日の新規感染者の増加は4,372人。ゼロコロナからウィズコロナ(新常態)へと政策が抜本的に転換されたことになる。並行して、企業による生産活動の再開は順次進展した(2021年10月19日付ビジネス短信参照)。たとえば、ホーチミン市輸出加工区・工業団地管理委員会(HEPZA)によると、活動しているのは全工場の92%以上に上る(「Diễn đàn Doanh nghiệp」紙 10月23日)。
それ以前は、新型コロナ対策として、厳しい操業規制や移動制限などが導入されていた。それにより、多くの企業が活動停止・縮小を余儀なくされた。影響は製造業だけでなく、小売り、飲食、サービスなど広範に及ぶ。製造業では、3オンサイト(工場での宿泊・飲食・生産)などの対策を取らない限り、操業自体が望めなかった。ホーチミン日本商工会議所(JCCH)によると、そうして操業を維持できた企業でも、稼働率が通常時の10%~50%に低下した。ホーチミン市では、鉱工業生産指数が8月に前年同月比49.2%減と、大きく落ち込んだ。
その結果、ベトナムの第3四半期(7~9月)の実質GDPの成長率は前年同期比でマイナス6.2%。2000年に統計総局が四半期ごとのGDP公表を始めて以来、最大の減少率となった(2021年10月5日付ビジネス短信参照)。
ベトナムの日本向け輸出額が2割減
このような状況は、当然、貿易にも影響する。2021年7月から9月にかけて、ベトナムの日本向け輸出額は23%減少。日本からの輸入額も9%減少した。
ベトナムから日本向けの主要輸出について、品目別に確認してみる。金額ベースで2021年7月から9月にかけての増減を見ると、履物は58%減、水産物は39%減、電話機・同部品は32%減、輸送機器・同部品は29%減。幅広い品目で大きく減少したことが分かる(表1参照)。
| 品目 | 7月 | 8月 | 9月 | 7月から9月の増減 |
|---|---|---|---|---|
| 縫製品 | 267 | 239 | 204 | △24% |
| 機械設備・同部品 | 204 | 193 | 183 | △10% |
| 輸送機器・同部品 | 204 | 175 | 144 | △29% |
| 木材・木製品 | 129 | 96 | 103 | △20% |
| コンピュータ電子製品・同部品 | 75 | 75 | 80 | 7% |
| 水産物 | 122 | 78 | 75 | △39% |
| 電話機・同部品 | 105 | 70 | 71 | △32% |
| プラスチック製品 | 59 | 57 | 53 | △10% |
| 鉄鋼製品 | 46 | 43 | 39 | △15% |
| 履物 | 60 | 29 | 25 | △58% |
| 合計(その他含む) | 1,753 | 1,481 | 1,349 | △23% |
注:輸出額は通関ベース。
出所:ベトナム税関総局の資料を基にジェトロ作成
同様に輸入についても、鉄スクラップ(53%減)、自動車部品(45%減)をはじめ、多くの品目で減少した(表2参照)。
| 品目 | 7月 | 8月 | 9月 | 7月から9月の増減 |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータ電子製品・同部品 | 511 | 518 | 593 | 16% |
| 機械設備・部品 | 369 | 358 | 332 | △10% |
| 鉄鋼 | 144 | 169 | 136 | △6% |
| プラスチック製品 | 68 | 75 | 62 | △9% |
| 化学製品 | 58 | 49 | 47 | △19% |
| 鉄スクラップ | 98 | 51 | 46 | △53% |
| 織布・生地 | 57 | 42 | 46 | △19% |
| プラスチック原料 | 44 | 51 | 40 | △10% |
| 鉄鋼製品 | 47 | 42 | 38 | △18% |
| 自動車部品 | 61 | 40 | 34 | △45% |
| 合計(その他含む) | 1,924 | 1,805 | 1,755 | △9% |
注:輸入額は通関ベース。
出所:ベトナム税関総局の資料を基にジェトロ作成
躍進を遂げたベトナムの対日往復貿易額、日本経済にも影響
このような対日貿易の低迷は、日本の経済活動にも影響を与えていく。この点、貿易統計から検証してみる。
日本の往復貿易額(輸出額+輸入額)を国・地域別に見ると、ベトナムは1990年には50位(図1参照)。これに対し、ASEAN原加盟5カ国(タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン)は、7位(インドネシア)から23位(フィリピン)と先行していた。2010年代に入っても、両国の差は大きかった。日本との貿易額(2010年)は、タイが6位、ベトナムが21位。2011年10月に発生したタイの洪水被害では、日本企業の部品供給が寸断。日本のメディアで大きな話題になった。
しかし、2020年にはかなり様子が違う。日本の往復貿易額全体の中でベトナムは3.1%(7位)。タイを除いて、ASEAN原加盟国全てを上回っているのだ。タイ(3.9%、5位)と比肩するほど、日本経済との相互依存関係が深まった、とも言える(図1参照)。
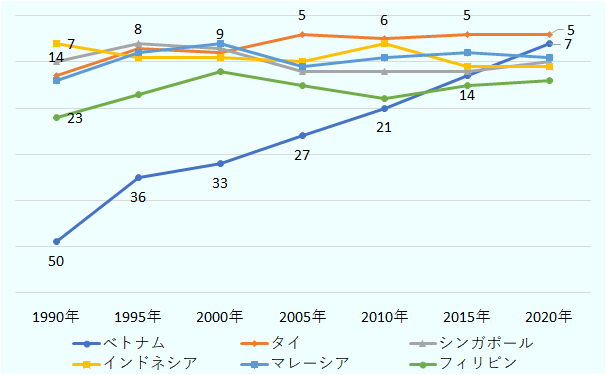
出所:日本の財務省貿易統計を基にジェトロ作成
ベトナムでの供給中断に、国外への生産移管で対応する例も
日本政府は2020年、サプライチェーン多元化を⽬的とした補助金(海外サプライチェーン多元化等支援事業)を導入した。サプライチェーンの分断リスクを低減し、持続可能で責任ある供給体制を確立するのが、その狙いだ。
この補助金は、とくにASEANなどの地域を念頭において設計された。とくにベトナムの存在感が目立つ。これまで4回の公募で採択された92件(設備導入補助71件、実証事業等21件)のうち、ベトナム関連は38件(設備導入補助32件、実証事業等6件)と最多だ。
このように、ベトナムは生産拠点として高い評価を受けていた。しかし、2021年はデルタ型変異株の感染拡大防止のため、厳しい規制が導入された。ベトナムを起点とするサプライチェーンが分断されるという事態が発生したことになる。当地での生産停止・縮小の影響を受け、調達をベトナム以外に求める動きも出てきている。たとえば、在ベトナム米国商工会議所(AmCham Vietnam)が会員企業(240社)を対象に8月23~25日に実施したアンケート回答によると、2割の企業がベトナム国外に何らかの生産移管を既に実施済みだ。
ベトナムへの依存度が高い品目で、日本での輸入に占めるベトナムの割合が急減
日本の財務省貿易統計によると、2020年にベトナムから日本に輸入されたのは、2,658品目(HSコード9桁ベース)。その中で、同年に輸入額が大きかった上位10品目は表3のとおりだ。
2021年8月(1カ月)には、その輸入額全体に占めるベトナムの割合が、10品目のうち7品目について前年同月比で低下。2020年(通年)での割合と比較しても6品目で低下している(表3参照)。ベトナムにおけるロックダウンの影響を1つの要因としてベトナムからの輸入額が減ったこと、ベトナム以外からの輸入の割合が増えたことがうかがえる。
| 順位 | 品目名 |
ベトナムからの 輸入実績 (2020年1~12月) |
ベトナムからの 輸入割合 (2020年8月) |
ベトナムからの 輸入割合 (2021年8月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入額 | 輸入割合 | ||||
| 1 | 自動車用ワイヤーハーネス | 1,887 | 39% | 39% | 31% |
| 2 | 携帯電話 | 1,347 | 8% | 9% | 15% |
| 3 | 木材チップ | 558 | 35% | 42% | 44% |
| 4 | 基地局 | 436 | 47% | 64% | 55% |
| 5 | 冷凍シュリンプ | 342 | 24% | 23% | 21% |
| 6 | 旅行用バッグ | 335 | 14% | 13% | 9% |
| 7 | スポーツ用の履物 | 316 | 47% | 46% | 26% |
| 8 | 木製家具 | 271 | 24% | 25% | 20% |
| 9 | プラスチック製の包装用袋 | 260 | 22% | 21% | 22% |
| 10 | 男性用のズボン | 256 | 32% | 33% | 24% |
注:HSコード9桁ベース。
出所:日本の財務省貿易統計を基にジェトロ作成
ベトナムから日本への輸入額(2020年)を品目別に見た場合、最も輸入額が大きい品目は、自動車用のワイヤーハーネス(8544.30-01)だ。この生産は労働集約的と言われる。ロックダウンにより、ベトナムで生産が停止・縮小した結果、日本の一部工場では、自動車の生産工程全体が休止に追い込まれた。
当該製品の日本への輸入(金額ベース)は、中国が2000年にフィリピンを超えて最大に。2010年には構成比が41%に達していた。しかしその後は、ベトナムが伸びる。中国を上回って最大となったのは2015年のことだ。その後も伸び続け、2020年には39%に達した(図2参照)。しかし、2021年は、ベトナムでの工場の生産停止・縮小の影響を受けて、ベトナムからの輸入(月次)が40%(7月:201億円)から31%(8月:122億円)に減少。代えて、中国からの輸入が12%(59億円)から17%(65億円)に増えた。
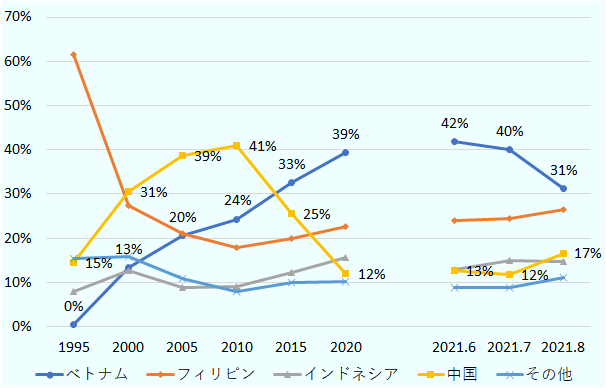
出所:日本の財務省貿易統計を基にジェトロ作成
スポーツ用の履物の場合、2005年には中国からが日本への輸入全体の7割を超えていた。当該品目についてもその後、ベトナムからの割合が増え、2020年には約5割に達した(図3参照)。しかし、今回のロックダウンによる生産停止・縮小に伴い、ベトナムからの輸入割合がこの品目でも大きく低下した。7月に52%だったのが、8月には26%に半減したのだ。反対に、中国とインドネシアからの割合がそれぞれ33%に跳ね上がった。
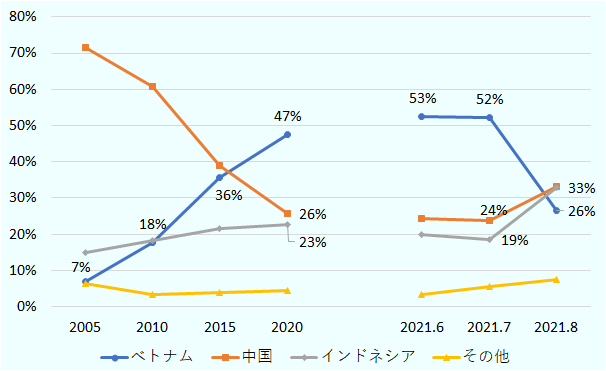
出所:日本の財務省貿易統計を基にジェトロ作成
冷凍シュリンプについても、当年8月の落ち込みが顕著だ。そのベトナムの割合は、2021年7月から8月に27%から21%に減少。代えて、インドからの割合が22%から35%に増加した(図4参照)。
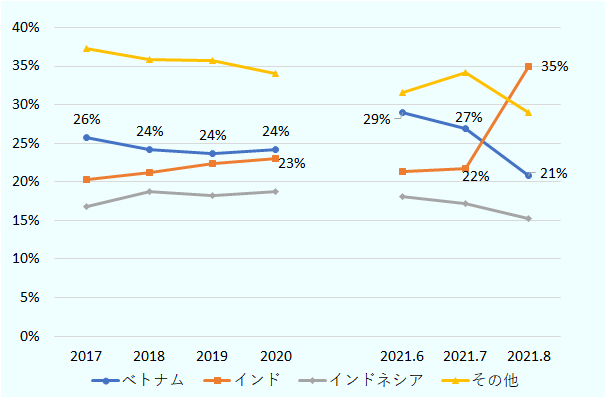
出所:日本の財務省貿易統計を基にジェトロ作成
日本のメディアでは、ベトナムのロックダウンによる影響が報じられた例があった。そこでとくに取り上げられたのが、この3品目(自動車用ワイヤーハーネス、スポーツ用履物、冷凍シュリンプ)だった。いずれも2021年7月までは高い水準にあったものが、8月に落ち込んだことが分かる。日本とベトナムとの貿易関係は、日本の経済活動に影響を与えるほど深くなったといえるのだ。
ベトナムでの生産見直しに際しては、中国からの輸入割合にも要留意
ベトナムは、日本企業から高い評価を受けてきた。それは、ジェトロの「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」(2020年度)![]() (1.93MB)でも、「海外で事業拡大を図る国・地域」で2位だったことにも表れている。
(1.93MB)でも、「海外で事業拡大を図る国・地域」で2位だったことにも表れている。
しかし、物資の調達を特定の国に大きく依存することは、予期せぬ危機に際して供給途絶を生じさせるリスクがある。ベトナムについても決して例外扱いはできないことが明らかになった。今後、日本企業がベトナムを見る視線が厳しくなる可能性は否めない。「ベトナムで生産活動が停止するリスクが顕在化したのだから、ベトナムでの生産比率を見直す」という声も出てくるだろう。
もっとも、「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」ことにならないか、気になるところだ。この点、中国をはじめ他国からの輸入割合など品目ごとに、きめ細かく検討し、生産拠点が分散化されていくことが望ましいだろう。ベトナムから日本への輸入額が多い10品目(表3)に限っても、2品目は中国からの輸入割合がすでに50%を超えているのだ(図5参照)。
(2020年)
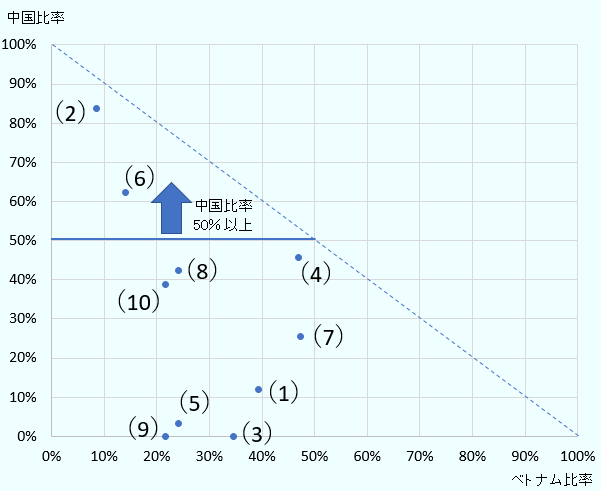
(1)自動車用ワイヤーハーネス (2)携帯電話 (3)木材チップ (4)基地局
(5)冷凍シュリンプ (6)旅行用バッグ (7)スポーツ用の履物
(8)木製家具 (9)プラスチック製の包装用袋 (10)男性用のズボン
注:(1)~(10)は表3のベトナムからの輸入額が大きい上位10品目。
出所:日本の財務省貿易統計を基にジェトロ作成
主要100品目のうち41品目で、中国からの輸入割合が過半
2020年にベトナムから日本に輸入された品目は、HSコード(9桁)で2,657品目あった。ベトナムからの輸入額の大きい上位100品目のうち、41品目は中国からの輸入割合が50%を超える(図6参照)。まずは、この図の中でどこに位置するかを確認する必要がある。図の中で3つの隅(右下、左上、左下)にある品目を確認してみる。例えば、右下隅(ベトナムの比率が最も高い)は「トラックスーツ、スキースーツ、水着等(絹製)」(HSコード6211.49-210)だ。左上隅(中国の比率が最も高い)が「ビデオゲーム用のコンソールまたは機器」(HSコード9504.50-000)。左下(ベトナムと中国いずれの比率も0%に近い、注)が「原油」(HSコード2709.00-900)になる。こうしてみると、品目ごとにそれぞれ対応すべきことがおのずと異なってくることが想起できるだろう
なお、生産拠点の分散化を進めるに当たり、ベトナムの場合、地方省ごとに規制やその運用が異なることがプラスに働くこともある。実際、進出企業の中には、ベトナム国内で、複数の地方省・市に工場があったため生産を継続できた企業もあった。このように、留意すべきなのは、国別の拠点配置だけではない。
中国と比較(2020年)
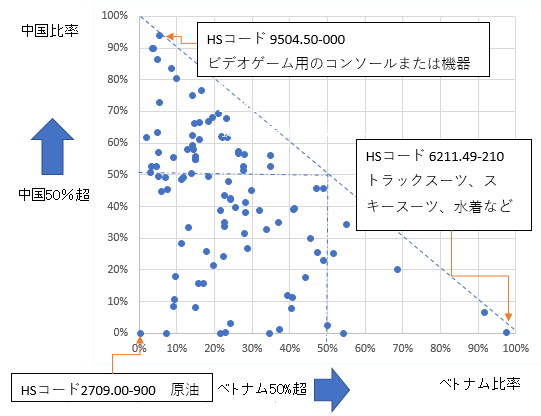
注:ベトナムから日本へ輸入される主要100品目について、横軸にベトナム比率、縦軸に中国からの輸入比率をプロット。ベトナム比率が50%超の品目が7品目に対し、中国比率が50%超の品目は41品目。
出所:日本の財務省貿易統計を基にジェトロ作成
ベトナム政府は企業との対話を重視
多くの日本企業にとって、ベトナムに進出を開始したのは1990年代半ば以降のことだ。他のASEAN諸国と比べて浅い。そのせいか、日本から当事務所にご相談を頂く際には、ベトナムは中国と同じ社会主義の国という印象をお持ちの方が多いようだ。さらに、「政府の規制、ましてベトナム国民の生命・身体を守るための感染対策を企業が批判することは許されない」という理解が一般的と感じられる。
しかし実際には、ウィズコロナへの政策転換に当たって、産業界の声が大きな役割を果たしてきた。ファン・ミン・チン首相やファン・バイ・マイ人民委員長(ホーチミン市の行政トップ)は、積極的に外国企業との意見交換の機会を設けている。こうした場で、企業は率直な意見を述べていた。また、感染対策と経済回復に関する政策立案に関してはパブリックコメントによる意見募集も行われる。こうした機会にも、日本企業は商工会議所などを通じ意見を表明してきた。

(記事中の日系企業提供)

(記事中の日系企業提供)
JCCHは7月20日、当該経営者による緊急講演を開催。JCCH会員企業からは、「サプライチェーンを守るための懸命な努力に感銘を受けた」「監査の状況、内容などが大変参考になった」との声があった。
たしかに工場での宿泊は、家庭に幼い子供を抱える労働者などには過大な負担だ。そのため、実施したくてもできない企業が多々あった。しかし、講演で、実際に取り組んだ経験を踏まえ、「工場宿泊は、地方出身の労働者やベトナム戦争直後の貧困を体験した年配の労働者には、日本人が想像するのに比べて抵抗感が少ない。ぜひ実施すべき」という話が印象的であった。あわせて、JCCHには相互扶助の意識が高い特徴があることも、指摘しておきたい。先の緊急講演会のように、現場の状況を踏まえ、タイムリーに意見交換の機会などが設けられている。
新型コロナ禍前まで、ベトナムには進出ブームが続いてきた。それが、ロックダウンの長期化により踊り場に差し掛かっている。しかし、スイスの大手食品・飲料メーカーのネスレのように、ベトナム南部(ドンナイ省)で新規の投資計画を発表した外資企業もある(ベトナム政府ウェブニュース10月4日)。今後、日本企業の動きが注目される。
- 注:
- サウジアラビアやアラブ首長国連邦の比率が高い。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ホーチミン事務所 所長
比良井 慎司(ひらい しんじ) - 1996年、経済産業省入省、ジェトロ・シンガポール事務所勤務(2006~2009年)、在トルコ日本大使館勤務(2011~2015年)、経済産業省資金協力課長(2015~2017年)。2019年より現職。専門はアジアを中心とした国際開発。






 閉じる
閉じる





