高度外国人材を輩出する大学、その最前線に迫る総論:高度外国人材採用に向け、海外大学と英語トラックに注目
2025年10月16日
近年の日本の新卒採用市場は売り手優位が続いており、日本企業は人材獲得に苦慮している。特に理系人材の不足は深刻化している。この状況を受け、外国人材に目を向ける企業が増加している。中でも、高度外国人材の雇用は、単なる人手不足への対応にとどまらず、「海外展開への貢献」や「企業の多様性促進」といった付加価値ももたらす。
他方、外国人材の採用には課題も多い。これまで国内留学生を中心に採用活動を行う日本企業が多かったが、留学生の約7割が人文科学や社会科学分野の専攻で、理系人材の確保には限界がある。今後は、海外大学からの直接採用や、国内大学の英語トラック(注1)で学んでいる留学生の採用が、優秀な専門人材確保の有力な選択肢となると見込まれる。
高度外国人材の積極採用に取り組む日本企業
ジェトロが実施した「2024年度日本企業の海外展開に関するアンケート調査」(注2)では、外国人材を雇用する日本企業は49.7%に達する。そのうち在留資格別では、高度外国人材に該当する在留資格の1つである「技術・人文知識・国際業務」の割合が54.0%と最も高かった。高度外国人材を雇用している企業は「海外展開への貢献」や「多文化共生の推進」など、多面的な効果を実感している。実際に日本企業で活躍する高度外国人材の事例は、ジェトロ地域・分析レポート「高度外国人材と創出する日本企業のイノベーティブな未来」を参照いただきたい。
また、同調査では、今後2~3年の外国人材の雇用方針として、約3割の企業が「今後増やす、新たに雇用する」と回答した。中でも、高度外国人材の雇用拡大を見込む企業の割合が、その他の在留資格(技能実習や特定技能)と比べて最も高かった。実際にジェトロには、「理系人材の確保が難しく、外国人材も採用対象としたい」「施工管理者として活躍できる外国人エンジニアを求めている」「海外展開に向けて現地の言語や文化慣習が分かる外国人材を採用したい」といった、高度外国人材の採用を検討する企業からの声が寄せられている。こうした企業ニーズに応えるため、ジェトロでは2019年度から日本企業向けの支援事業を実施しており、これまでに延べ1,500社以上の日本企業を支援。2025年度は支援社数を前年度の305社から360社程度に増やして、「高度外国人材活躍推進コーディネーターによる伴走型支援」を提供している。
高まる高度外国人材の採用ニーズの背景に、売り手市場や理系人材不足
日本企業が高度外国人材の採用に注目する背景には、日本の新卒採用事情や、理系人材の需給不均衡などがある。
まず、現在の日本は過去最高水準の「売り手市場」にある。リクルートの「就職プロセス調査(2025年卒)![]() 」(注3)によると、2025年3月卒業時点の日本の大学生(大学院生を除く)の就職内定率(内々定を含む)は98.8%となった。2017年卒(95.5%)以降で最高を記録した。近年の就職内定率は9割を超え、学生優位の「売り手市場」が続いており、その半面で企業の人材獲得競争は厳しさを増しているといえる。
」(注3)によると、2025年3月卒業時点の日本の大学生(大学院生を除く)の就職内定率(内々定を含む)は98.8%となった。2017年卒(95.5%)以降で最高を記録した。近年の就職内定率は9割を超え、学生優位の「売り手市場」が続いており、その半面で企業の人材獲得競争は厳しさを増しているといえる。
中でも、理系人材の確保は厳しさを増している。日本経済新聞が実施した「2025年度の採用状況調査![]() 」(注4)によると、企業の採用計画に対する理工系の内定者の充足率は過去17年間で最低の87.4%となり、理工系の採用が難しいと回答した企業は47.3%で、文系の18.6%を大きく上回った。
」(注4)によると、企業の採用計画に対する理工系の内定者の充足率は過去17年間で最低の87.4%となり、理工系の採用が難しいと回答した企業は47.3%で、文系の18.6%を大きく上回った。
こうした日本の新卒採用事情を受けて、日本の大学に留学している外国人学生に向けた採用活動に力を入れる企業も増えているのが実態だ。日本学生支援機構(JASSO)の「外国人留学生在籍状況調査![]() 」によると、2024年5月時点の外国人留学生数は33万6,708人と、前年から約20%増加し、過去最高を記録した。在籍段階別では、2024年時点で大学院留学生が約5万8,000人、学部留学生が約8万7,000人と、大学および大学院在籍者が全体の半数程度を占める(図)。
」によると、2024年5月時点の外国人留学生数は33万6,708人と、前年から約20%増加し、過去最高を記録した。在籍段階別では、2024年時点で大学院留学生が約5万8,000人、学部留学生が約8万7,000人と、大学および大学院在籍者が全体の半数程度を占める(図)。
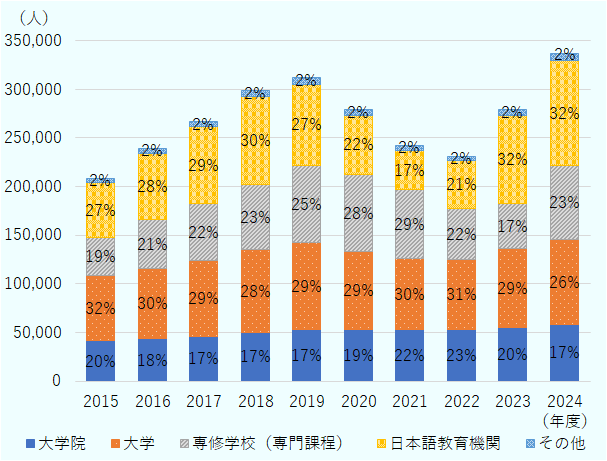
注1:その他には、短期大学、高専、準備教育課程を含む。
注2:図内のパーセンテージは、全体に占める各項目の割合。
出所:JASSO「外国人材留学生在籍状況調査」を基にジェトロ作成
しかし、キャリタスによる「外国人留学生の就職活動状況に関する調査![]() 」(注5)では、2024年7月時点での外国人留学生の内定率は49.3%で、日本人学生の内定率(89.7%)との差が大きい。要因として、外国人留学生に向けた就職活動情報の不足や就職活動の開始時期の遅れが挙げられる。日本企業の外国人材獲得ニーズと、留学生の就職活動の実態にミスマッチが生じている点が指摘できるだろう。
」(注5)では、2024年7月時点での外国人留学生の内定率は49.3%で、日本人学生の内定率(89.7%)との差が大きい。要因として、外国人留学生に向けた就職活動情報の不足や就職活動の開始時期の遅れが挙げられる。日本企業の外国人材獲得ニーズと、留学生の就職活動の実態にミスマッチが生じている点が指摘できるだろう。
また、専攻分野別の外国人留学生数(大学および大学院)では、人文科学・社会科学系が全体の70%を占める。工学系、理工系は合わせて13.8%と少数派で、文系偏重の傾向だ(表1参照)。また、日本人を含めた国内大学への2024年度入学者の専攻分野別内訳をみると、人文科学・社会科学系が全体の45.7%を占める。工学系、理工系は合わせて17.5%となっており、日本の大学生全般で理工系人材が少ないことが分かる(表2参照)。
外国人留学生の内定率の低さは、留学生の理系人材の割合の少なさだけでなく、理系人材であっても日本企業の理系人材への需要を満たすことが難しいという実情にも起因していると考えられる。
| 専攻分野 | 留学生数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 人文科学 | 158,505 | 47.1% |
| 社会科学 | 77,045 | 22.9% |
| 理学 | 4,600 | 1.4% |
| 工学 | 41,658 | 12.4% |
| 農学 | 4,036 | 1.2% |
| 保健 | 6,910 | 2.1% |
| 家政 | 4,119 | 1.2% |
| 教育 | 3,632 | 1.1% |
| 芸術 | 14,572 | 4.3% |
| その他 | 21,631 | 6.4% |
| 計 | 336,708 | 100% |
出所:JASSO「外国人材留学生在籍状況調査」![]() を基にジェトロ作成
を基にジェトロ作成
| 専攻分野 | 入学者数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 人文科学 | 83,725 | 13.3% |
| 社会科学 | 203,862 | 32.4% |
| 理学 | 18,981 | 3.0% |
| 工学 | 91,133 | 14.5% |
| 農学 | 18,604 | 3.0% |
| 保健 | 74,289 | 11.8% |
| 家政 | 14,854 | 2.4% |
| 教育 | 44,926 | 7.1% |
| 芸術 | 19,484 | 3.1% |
| その他 | 58,908 | 9.4% |
| 計 | 628,766 | 100% |
出所:ナレッジステーション![]() を基にジェトロ作成(原典は、文部科学省「学校基本調査」)
を基にジェトロ作成(原典は、文部科学省「学校基本調査」)
理系人材の需給不均衡の背景として、日本では博士人材と企業のマッチングに課題があることも指摘される。日本で博士課程への進学者が減少傾向にある中、留学生の博士課程進学者は増えており、専門性の高い人材確保には留学生の採用が有望とされる。しかし、日本の就職活動に関する情報不足や言語の壁などで、博士課程の留学生も、学部・修士レベルの留学生と同様、就職活動に困難を抱えている(経済産業省、「博士人材の産業界への入職経路の多様化に関する勉強会 議論の取りまとめ![]() 」、注6)。
」、注6)。
今後は、博士課程も含め、留学生に対するさらなる理解と支援が求められる。同時に、留学生だけでなく、日本企業に対しても、留学生のキャリア指向に関する理解促進や出会いの場の創出を含めた支援を行うことが重要だ。
海外大学の学生や英語トラック留学生など、新たな人材市場を模索
こうした現状を踏まえ、日本企業では、海外大学で学ぶ学生の直接採用や、日本の大学で増えつつある英語で授業を行うコース(英語トラック)で学ぶ留学生の採用を視野に入れる企業も増えている。例えば、東京都のソフトウェア開発を手掛けるトマトは、「日本語能力よりも専門性を重視し、内定後に日本語を習得してもらう方が質の高い人材を確保できる」として、海外大学からの直接採用に積極的だ(2025年2月27日付地域・分析レポート参照)。
他方、日本企業の採用担当者にとっては、海外大学や英語トラック留学生に関する情報不足で、効果的な採用戦略の構築ができていないことが大きな課題となっている。特に、大学へのコンタクトの際に提示する、海外大学の学生や英語トラックの留学生に対する採用要件について、専攻分野や日本語能力など、どう設けるべきか苦慮しているという。こうしたルートで高度外国人材の採用を行うに当たっては、大学の教育内容や学生の専門性、キャリア志向を理解することが非常に重要だ。
ジェトロでは2024年5月より、海外大学を紹介するイベント「JETRO Overseas University Connect」を開催し、海外大学の情報を日本企業に提供している。2025年8月までに15回開催し、特に、ホーチミン市工科大学(2024年8月28日付ビジネス短信参照)、日越大学(2025年3月19日付ビジネス短信参照)、ハノイ工科大学、泰日工業大学(2024年12月10日付地域・分析レポート参照)などが日本企業の関心を集めた。参加者満足度は平均97%と高く、日本企業の採用意欲の高さがうかがえた。
イベントに参加した海外大学も、日本企業との連携を通じた実践的な教育や、語学・キャリア支援の強化を進める。例えば、ベトナムの日越大学では、日本とベトナム両政府の支援の下、リベラルアーツとサステナビリティを軸に、日系企業とのインターンシップや共同研究を通じた人材育成を行っている。
また、日本国内の大学でも、同様に留学生の日本企業就職に力を入れる。京都先端科学大学では、工学部の授業を全て英語で行っている。企業課題に取り組むキャップストーンプロジェクト(注7)を通じて、留学生と日本人学生が協働しながら大学の学びを就職後も生かすべく実践力を磨いている。
本特集では、国内外大学の具体的な取り組みを紹介しながら、日本企業が海外大学や英語トラック留学生とどのように接点を持ち、共同研究といった連携、採用につなげていくかを探っていく。
- 注1:
- 英語トラック学生とは、英語で授業を履修し卒業できるカリキュラムで学ぶ学生のこと。
- 注2:
- 2024年11月上旬~12月上旬に、海外ビジネスに関心の高い日本企業(本社)9,441社を対象にアンケートを実施。有効回答数3,162社(有効回答率33.5%)。
- 注3:
- リクルートの研究機関である就職みらい研究所が実施。2025年3月25日公表。調査対象は、2025年卒業予定の大学生および大学院生のなかで、調査モニターに登録した学生3,810人。実施時期は、2025年3月12日~3月17日。
- 注4:
- 日本経済新聞社が実施。2024年10月22日公表。調査対象は、上場企業と日本経済新聞社が独自に選んだ非上場企業1,082社。2024年10月1日までの回答企業1,008社のうち、大卒については比較可能な984社をまとめた。
- 注5:
- キャリタスが実施。2024年8月22日公表。調査対象は、2025年3月卒業予定の外国人留学生(回答数は304人)。実施時期は、2024年7月1日~7月25日。
- 注6:
- 経済産業省で「博士人材の産業界への入職経路の多様化に関する勉強会」が主催され、2024年2月に議論のとりまとめが公表された。
- 注7:
- 本学工学部の3年生および4年生が、学びの集大成として、国内外の企業が抱えているグローバルな ビジネス課題と向き合い、解決に近づくための方法を探る、本学 工学部の正規科目。「キャップストーン」とは、ピラミッドの頂上に最後に乗せる石のこと。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ知的資産部高度外国人材課
斉藤 美沙季(さいとう みさき) - 2018年、ジェトロ入構。対日投資部地域連携課、ジェトロ岩手を経て、2023年10月から現職。






 閉じる
閉じる





