高度外国人材を輩出する大学、その最前線に迫るベトナムに築くリベラルアーツ:ベトナム国家大学ハノイ校日越大学
2025年10月16日
2014年に日本とベトナム、両国政府は協力の下、日越大学を設立した。目的は、アジアでトップクラスの大学を創ることだ。
きっかけは2009年、ベトナム政府が両国間の協力による大学設立を提案したことだった。翌2010年、両国政府が共同声明で、「日本の大学を模範とする質の高い大学の設立を、ベトナムで検討している」と発表。その後2014年7月、ベトナム国家大学ハノイ校の7番目のメンバー大学として日越大学を設立。2016年から、修士課程の学生の受け入れが始まった。
日本政府は2015年、「日越大学構想の推進に関する関係省庁会議![]() 」を立ち上げた。省庁間で連携しながら、本構想の推進に取り組んでいる。あわせて、国際協力機構(JICA)を通じ、政府開発援助(ODA)による技術協力を実施している。
」を立ち上げた。省庁間で連携しながら、本構想の推進に取り組んでいる。あわせて、国際協力機構(JICA)を通じ、政府開発援助(ODA)による技術協力を実施している。
すでに、開学から10年が経過した。卒業生の動きや産学連携の取り組み、今後の方向性について、日越大学の産学連携担当(JICA専門家)、根岸正実氏に聞いた(取材日:2025年2月5日。ただし、2月以降の追加取材で得た情報もあり))。
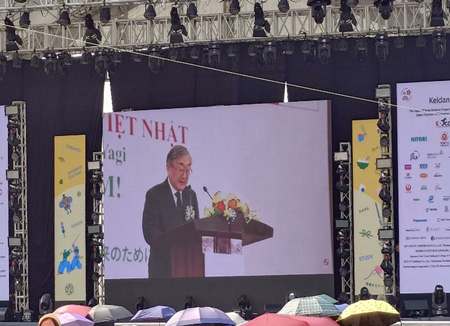
開学から10年を経て教育課程がそろう
- 質問:
- 大学の成り立ちや教育体系は。
- 答え:
- 本学の設立目的は、高度人材の育成である。ベトナム、日本、東南アジアをはじめ、世界で活躍できる次世代のリーダーやマネージャー、エキスパートを目指す人材を輩出していきたい。
- 学内には、FISS(Faculty of Interdisciplinary Social Sciences、学際社会科学学部・研究科)とFATE(Faculty of Advanced Technologies & Engineering、先端工学・技術学部・研究科)の2つの系統の学部・研究科がある。前者は文系、後者は理系に相当する。それぞれの系統に属する「プログラム」(専攻・学科)を設けている。2016年から修士課程の受け入れを開始。2020年からは学士課程・技師課程も設置した。また2025年からは、FISSの博士課程「日本学・日本語教育」を開設。日本学については、学士課程の「日本学」、修士課程の「地域研究」を経て博士課程の「日本学・日本語教育」に至るまで一貫した教育が可能になった。
- プログラムは、年々拡充してきた。2025年9月現在、学士課程・技師課程が9つ、修士課程9つ、博士課程1つから成る。それぞれ、連携する日本の大学からカリキュラムの立ち上げや改善、教員の派遣やオンラインでの講義・論文指導などの支援を受けている。
- プログラムは今後も、国のさまざまなニーズも踏まえて拡充が想定できる。例えば、2025年に新設した「半導体チップ技術」は、ベトナム政府の「2030年までのベトナム半導体産業の発展戦略と2050年のビジョン」(2024年9月の首相決定1017号、1018号)に関連して立ち上げた。
-
表:プログラムの一覧 課程 プログラム名 開設年 学士課程・技師課程 ●日本学 2020 ◇コンピュータサイエンス&エンジニアリング 2021 ◇シビルエンジニアリング 2022 ◇スマート農業とサステナビリティ 2022 ◇食品工学と健康 2023 ◇メカトロニクスと日本型ものづくり 2023 ●グローバル開発とイノベーション 2025 ◇インテリジェント制御とオートメーション 2025 ◇半導体チップ技術 2025 修士課程 ●地域研究 2016 ●企業管理 2016 ●公共政策 2016 ●グローバル・リーダーシップ 2019 ◇ナノテクノロジー 2016 ◇社会基盤 2016 ◇環境工学 2016 ◇気候変動・開発 2018 ◇コンピュータサイエンス&エンジニアリング 2025 博士課程 ●日本学・日本語教育 2025 注:●は、学際社会科学の学部・研究科(FISS)。◇は、先端工学・技術の学部・研究科(FATE)。
出所:日越大学の提供情報を基にジェトロ作成 - 質問:
- キャンパスの立地などは。
- 答え:
- キャンパスは、ホアラックハイテクパーク内(ハノイ中心部から西に35キロほど)とミーディン地区(ハノイ中心部)に位置する。 ホアラックキャンパスには学士課程・技師課程の1年生が、ミーディンキャンパスには2年生から4年生および修士課程の学生が、主に在学している。今後の学生数の増加や、ホアラックキャンパスの整備に伴い、体制を変更する可能性がある。
-

ホアラックキャンパスの様子(日越大学提供)
日系企業への就職などもサポート
- 質問:
- 教育の特色は。
- 答え:
- 日越大学が重視しているのは、「リベラルアーツ」と「サステナビリティ」の2つである。
- 「リベラルアーツ」は、クリエーティブシンキング(既成概念にとらわれず、幅広い知識や新しい視点で考える)や、クリティカルシンキング(批判的・論理的に物事を捉える)を重視している。一般的に、ベトナムの大学教育は職業に直結する専門志向が極めて強い。こうした状況で、リベラルアーツは当地大学で珍しい特色といえる。
- 「サステナビリティ」は、すべての研究プログラムが持続可能な開発に貢献することを目的にしている。すなわち、最新のテクノロジーと学際科学での研究成果、そして日本とベトナムの間の知識移転が社会に貢献することを目指している。「世界で活躍できる人材を輩出する」という本学のミッションにもつながる。
- プログラムは、拡充を経て多様化してきた。いずれのプログラムでも、これら2点が共通項になっている。
- 質問:
- 学生の人数・構成は。
- 答え:
- 全学生数は約1,700人(2025年9月時点)。(1)開設から年数が浅いプログラムでは上級生がいない場合があること、(2)定員を徐々に増やしていることから、低学年が多い。
- 募集定員はプログラムや年度によって異なる。学士課程の「日本学」「コンピュータサイエンス&エンジニアリング」がそれぞれ、定員120~150人。そのほかのプログラムの募集定員は、学部で各50人程度、大学院で各10~15人程度である。
- 質問:
- 学生の語学力は。
- 答え:
- 「コンピュータサイエンス&エンジニアリング」の学生は、必修の日本語授業を通じて、卒業時にはN5またはN4を大半が取得している。中にはN1やN2、N3まで取得する学生もいる。日系企業へ就職する学生もいるが、ビジネスレベルの英語を習得し、グローバル企業への就職を目指す学生も多い。
- 質問:
- 学生の就職動向や就職先の関心は。
- 答え:
- 「コンピュータサイエンス&エンジニアリング」を専攻する学生は、企業からの関心が高い。事実、有名なグローバル企業が関心を寄せている。しかし、学生側の日本で働きたいという意向は、2割程度にとどまる。グローバル企業のオファーや就職実績が、学生が専攻分野やキャリアを考える判断材料になるだろう。
- 質問:
- 大学としては、どのように就職を支援しているのか。
- 答え:
- 2025年の例を挙げると、まず3月14日、就職希望者を対象にワークショップを開催。日系企業への就職を目指す学生が、履歴書の書き方や日本のビジネス文化について学んだ。
- また4月21日から25日にかけて、「キャリアデザインウィーク2025」と題して企画を実施した。対象は、日越大学の在学生と卒業生。ジョブフェアや日本の大学院への進学説明会などを組み合わせ、キャリア形成に必要な情報を提供した。このイベントには、在ベトナム日系企業を含む日本企業16社と日本の大学7校が参加している。
- なお、こうした就職支援の取り組みにあたっては、日本からの参加も受け付けている。
-

3月14日に開催したワークショップの様子(日越大学提供) - 質問:
- 学生の就職の傾向や課題などは。
- 答え:
- ベトナムでは、学生が内定を持たずに卒業し、卒業後に就職活動を続けるケースも少なくない。学事暦では9月に年度が始まり、7月に卒業する。日越大学では、学部4年生の5月ごろから就職活動を始める学生が多い。卒業までに就職を決めるのは、7~8割ほどである。
- 学生側から「日本に渡航し、日本企業の本社に就職したい」という希望も聞く。しかし、大学に日本企業とのコネクションが十分ない。また、日本企業の採用スケジュールに合わせることも難しいのが現状だ。大学側は、こうしたことなどを課題視している。
インターンシップを中心に産学連携、今後は共同研究も
- 質問:
- 産学連携の現状は。
- 答え:
- 民間企業、公的機関、日本の大学や自治体と覚書を締結して連携している。そのほか、奨学金や寄付金を受け付けている。
- 民間企業と連携した例としては、(1)在ベトナム日系企業の工場見学や、(2)企業の方を講師に招いての特別講義、(3)インターンシップの実施などがある。
- インターンシップは、学部3年生の必修科目として設定している。夏に1カ月程度、無給で就労する。主にハノイ市周辺の日系企業が受け入れるケースが多い。他方で、日本の本社が受け入れるケースもある。その場合は、日本企業が滞在に係る費用(住居・滞在費など)を負担する。
- 修士課程では研究能力の向上を目的としたインターンシップが実施されており、主に連携先の日本の大学が学生を受け入れる。このほか、「産学連携コンテスト」を実施している。例えば、マーケティングリサーチや新商品開発、アプリ開発のコンテストなどである。
- 質問:
- 今後の産学連携の方針は。
- 答え:
- 今後注力したいのは、教育内容の充実と共同研究の拡大である。
- ベトナムの大学では、機材が充実した実践的な研究環境が限定的である。しかし、特に製造業に関連する工学系では、企業の現場を通じた経験を得ることが望ましい。そのため、連携可能な日本企業を探している。
- また日越大学は、トップレベルの研究大学を目指している。そのためには、研究開発機能の拡大・強化を希望する製造業企業や大学研究室と、共同研究などを推進する必要がある。今後は、そうした連携も深めていきたい。
-
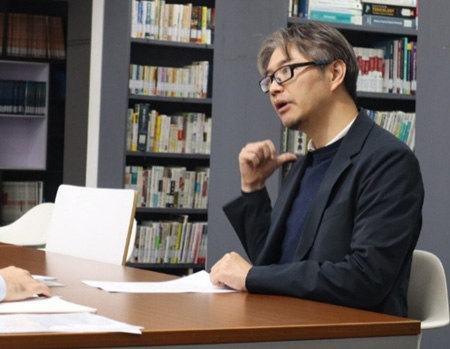
3月14日に開催したワークショップの様子(日越大学提供)
- 注:
-
日本語能力試験のレベルは、N5~N1まである。数字が小さいレベルの方が、難度が高い。
なおN2は、2番目の難度。「日常で使われる日本語が理解でき、それ以外の場面で使われる日本語もある程度理解できる」ことが認定の目安になる。
- 変更履歴
- 表に誤りがありましたので、次のように加筆・訂正いたしました。(2025年11月18日)
- 加筆箇所
- 修士課程:「◇コンピュータサイエンス&エンジニアリング」/開設年:2025年

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ハノイ事務所 ディレクター
河野 尭広(こうの たかひろ) - 2015年、ジェトロ入構。新興国進出支援課、国際ビジネス人材課にて高度外国人材活躍推進事業の立ち上げに従事。2021年ハノイでの語学研修(ベトナム語)、企画課を経て2024年8月から現職。






 閉じる
閉じる





