最恵国待遇のない世界
米国が挑む新たな国際通商システム(2)
2025年9月10日
米国による相互関税の賦課が、2025年8月7日から始まった。この高関税は、トランプ政権下の一過性ではなく、向こう10年という単位で継続する見通しだ。その背景には、WTOを基軸とした自由貿易体制を再構築しなければならないという米国の強い意志がある。米国が目指す、最恵国待遇(MFN)のない、新たな国際通商システムについて解説する。
米国が目指す、最恵国待遇のない新しい国際通商システム
前編で解説したように、米国による相互関税は長期間続く見通しだ。そして、長期間にわたって国・地域別に異なる関税率を設けることは、WTOを基軸とした自由貿易体制に大きな変化をもたらし得る。端的に言えば、最恵国待遇(MFN)の機能停止だ。MFNはWTOの基本的な原則の1つで、最も低い関税率を適用している国と同じ関税率を他の加盟国にも適用しなければならないと定めている。だが、米国の首都ワシントンでは、MFNをベースにした自由貿易体制は、持続可能でないとする考え方が根付きつつある。
J.D.バンス副大統領、マルコ・ルビオ国務長官といった「ニューライト」(注1)と呼ばれる指導者層と近いワシントンのシンクタンク、アメリカン・コンパスのポリシーアドバイザーであるマーク・ディプラシド氏は、「WTOが明らかに機能していない現状を踏まえ、貿易収支に焦点を据え直した枠組みを確立する必要がある」「市場経済と非市場経済の違いを認識し、同じルールに従わない市場によって貿易が歪(ゆが)められることがないように保護すれば、より良い、よりバランスの取れたシステムに到達できる」「新しいシステムは、MFNとは異なる機能を持つ可能性がある。新しい通商システムに参加する国々が、近年みられたような大規模な貿易赤字や黒字を回避するため、関税水準を調整する必要があるからだ。経済的にバランスの取れた国とそうでない国を区別することが必要になるだろう」との見解を示している。アメリカン・コンパスは2020年に設立された新興シンクタンクだが、こうした考え方は、ワシントンのいわゆるエスタブリッシュメントの間で、広く共有されている。バイデン政権下の国家安全保障会議(NSC)や国家経済会議(NEC)で要職を担った経験もある、新アメリカ安全保障センター(CNAS)のシニアフェローであるジェフリー・ガーツ氏は、「MFNに基づく関税を常に適用するとのコミットメントは、もはや各国の通商政策の決定要因とならない。特に、市場経済国と非市場経済国とで対応は分けるべきだ」「MFNを基にした制度から、敵対国からデリスキングできるシステムに調整しなければならない」「そもそも2018年以降、米国は実質的にMFNを支持していないし、MFNはもう機能していない」と述べている。ガーツ氏が指摘するように、対中追加関税はWTOの紛争解決機関のパネル裁定で、MFNを規定する「関税および貿易に関する一般協定(GATT)第1条」違反と判断されたが、米国は措置を継続している(注2)。また、伝統的な保守系シンクタンクとして知られているハドソン研究所のシニアフェローで日本部副部長を務めるウィリアム・チュー氏は、「現在の自由貿易体制の下で、中国の不公正な貿易慣行は広範に及んでおり、他の全ての参加国にとって公正でない競争環境を生み出している。このような不公正な状況下であるため、米国は貿易障壁を設け、競争環境の再均衡を図る取り組みを行っている」「これが、米国が現在2国間交渉を進めている理由であり、必要に応じて米国が影響力を発揮するための方法だ」と述べている(注3)。そのほか、バイデン前政権下で、WTO大使を務めたマリア・ペイガン氏は、トランプ政権による関税政策に疑問を呈しつつも、MFNは適用対象の国が比較的少なかった時代にのみ意味を成していたとして、「見直すべき唯一のルールはMFN」との見解を示している(注4)。
これらワシントンの有識者が、明示的、暗示的問わず指摘しているように、米国の問題意識は、WTO体制の下で中国のような非市場経済国の台頭を阻止できなかったことにある。米国通商代表部(USTR)は2025年3月に発表した「2025年の通商政策課題と2024年の年次報告」の中で、「WTOは、中国の非市場経済がもたらす課題に対処できていない」「米国は、中国の補助金プログラムや国営企業に対して、最低限の透明性を提供するように何度も対抗措置を講じざるを得なかった」と記している(注5)。また、USTRのジェミソン・グリア代表が2025年8月に、トランプ政権発足200日に合わせて発表した論説では、「WTOを基軸とした現在の通商システムの下で、米国は雇用と経済安全保障を喪失する一方、中国が最大の受益者となり、持続不可能な状態」だと非難した。また既存のシステムは、関税を「公共政策の正当な手段」として用いることを拒否していたと指摘した。裏を返せば、関税は「公共政策の正当な手段」だと主張していることになる。グリア氏はまた、生産拠点の米国外への移転が進んだことで、米国は中国、ベトナム、メキシコなどとの貿易赤字が拡大し、重要なサプライチェーンの敵対国への依存が高まったと指摘した。相互関税発表後に行われた、米国と各国・地域との交渉を「トランプ・ラウンド」と称し、米国の貿易相手国は「かつてないほど米国への市場開放を行い、経済的・国家安全保障上の課題で一致した」として、米国は「長年にわたる WTO 交渉では達成できなかった多くの市場アクセスを確保した」と評価した。特にEUとの関税措置を巡る合意は、多国間機関の曖昧な目標ではなく、具体的な国家利益を重視した公平でバランスの取れた内容だと賞賛した。グリア氏は、新たなシステムへの移行プロセスは必ずしもスムーズではないとしながらも、「米国の産業基盤を強化するためには、強固で断固とした行動が求められている」とし、この新しいシステムを、EUとの合意が行われたスコットランドのトランプ・ゴルフクラブにちなんで「ターンベリー・システム」と名付けて締めくくっている。
システム移行にはらむ危険、懸念される米国の孤立
米国が新たなシステムへの移行を目指す一方で、現在、世界中に網の目の様に張り巡らされているサプライチェーンは、WTO体制の下で構築された点に留意が必要だ。米国が志向する新たなシステムは高関税を容認するため、このサプライチェーンを破壊し得る。そのため、新たなシステムへ移行するのであれば、混乱を生まないよう慎重に行わなければならない。具体的には、米国が同盟国や有志国と連携しながら、非市場経済国への対応方針を明確なルールの下で行い、新しいシステムを採用する国を徐々に拡大していくことが重要だ(注6)。
しかし、トランプ政権には、新しいシステムへ移行する意志はみえても、それを実行する戦略の妥当性には疑念が示されている。対中政策を専門とする議会のスタッフは、中国の過剰生産などに関する課題は米国1カ国では解決できないとして、「各国が中国からの輸入を削減するなど、同盟国などとの協調が重要」と指摘するが、その協調相手となる日本やEUにも相互関税を課していることから、協調しづらい状況にあるという(注7)。戦略国際問題研究所(CSIS)のシニアアドバイザーであるウィリアム・ラインシュ氏も、中国の過剰生産に米国一国のみで対処しようとする試みは効果を生まないとして、他国との協力の重要性を指摘している(注8)。またCNASのガーツ氏は、「米国が今よりも高い関税を課すなどより孤立主義を貫いていけば、保護主義の連鎖を引き起こす危険性がある」と指摘している。
これらに加えて、一方的な措置の行使は、米国が国際通商システムの中で孤立する危険もはらむ。例えば米国は、中国製電気自動車(EV)に対して、追加関税率を100%に設定しているほか、車両接続システム(VCS)と自動運転システム(ADS)を搭載したコネクテッドカーの輸入・販売を禁止する情報通信技術サービス保護規則(注9)を導入するなどして、輸入拡大を防いでいる(注10)。しかし、それ以外の国・地域では、中国製EVの輸入は拡大傾向にある。特に、東南アジア、中南米、ロシアなどの旧ソ連圏、中東などで顕著だ(図1参照)。企業は2018年以降、米中対立に起因した米国による追加関税措置や輸出管理の強化といった規制の拡大を受け、中国向けサプライチェーンと米国を含むそれ以外のサプライチェーンへと再編していったが(注11)、米国による高関税や独自の強硬な規制が長期間続けば、将来的には米国だけがデカップリングしていく可能性もある。
図1:中国からの自動車の地域別輸出状況(2024年)
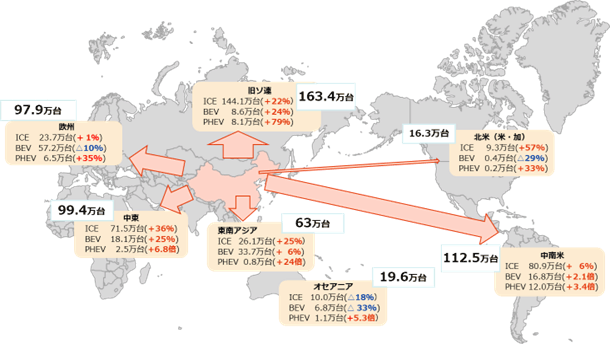
注1:カッコの中は2023年同期比、△はマイナス値。四角内の数字は自動車輸出全体の数字。
注2:ICE:内燃機関搭載車、BEV:バッテリー式電気自動車、PHEV:プラグインハイブリッド車。
出所:中国汽車販売協会汽車市場調査部(乗用車市場情報合同委員会)からジェトロ作成"
高関税で守られる世界最大の市場
ただ、こうした状況が企業の海外戦略にとって難しいのは、米国は依然として世界最大の市場であることだ。米国の2024年の名目GDPは29兆1,850億ドルで、2位の中国の18兆7,480億ドルを大きく上回る。さらに2030年にはその差はさらに拡大すると予測されている(図2参照)。仮に米国が、グローバルなサプライチェーンから孤立したとしても、日本企業にとって無視できない市場であり続ける。ピーターソン国際経済研究所(PIIE)のシニアフェローのアラン・ウォルフ氏は、米国の1人当たりの可処分所得は欧州やその他のどの国よりも少なくとも30%ほど高い水準にあるとし、各国・地域と「米国との貿易がなくなることはない」と指摘している(注12)。
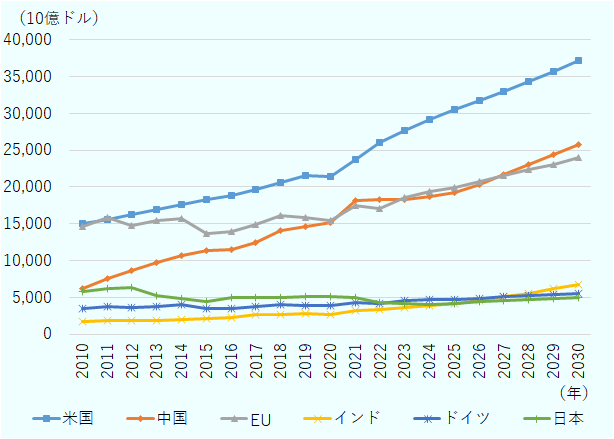
出所:IMF
岐路に立つ国際通商システム
米国はWTOへの分担金拠出を保留し、対応方針を検討しているが、その結果はまだ公になっていない(注13)。新しいシステムへの移行を志向している米国が、WTOから正式に脱退するのか、新しいシステムへの移行が成功するのかもわからない。例えばPIIEのウォルフ氏は、「米国は世界貿易の7分の1弱を占めるに過ぎない」「通商上の譲歩を伴う新たな要件を一方的に課すことを命じたに過ぎない」などとして、「米国が構築したのは、新たな世界の貿易秩序ではない」と指摘している(注14)。また、スイスのビジネススクールIMD教授のリチャード・ ボールドウィン氏は、米国の世界貿易におけるシェアは約15%であるため、残りの85%を占める国・地域が通商ルールを擁護すれば、自由貿易体制を維持できる可能性があると指摘している(注15)。オバマ政権下でUSTR代表を務め、現在は外交問題評議会(CFR)の会長であるマイケル・フロマン氏は、米国はWTOを基軸とした以前の体制には戻れないとしつつも、経済統合と経済効率を促進する貿易自由化に焦点を当てた、特定の分野で共通の利益を有する複数国による新たな連合が形成される可能性を指摘している(注16)。こうした指摘を踏まえ、ハドソン研究所のチュー氏は「問題は、米国がどのように2国間貿易協定を高次元化して、ワシントンの政策専門家が提言する貿易ブロックのようなものを構築し、中国の不公正な貿易慣行に対抗し、より秩序あるグローバルな貿易・投資システムを構築していくかにある」と指摘する。
このように、今後の国際通商システムに対しては、多用な見方が存在する。ただし、本稿でみたように、米国には、現在のシステムの変更を試みる「強い意志」がある。今後、米国がWTO体制を超えて、高関税を維持しながら新たな国際通商システムを構築するのか。あるいは、孤立主義を深め、その間隙を縫って中国のような非市場経済国が覇権を握るのか。それとも、WTO体制下のまま、米国のリーダーシップが回復不能な状態に陥るのか。米国の相互関税に端を発して、国際通商システムはまさにパラダイムシフトの入り口に立っている。
- 注1:
- ニューライトとは、従来の保守的な思想とは異なり、反グローバリズムなどを特徴とする近年の米国保守思想。
- 注2:
- 米国は、追加関税措置を「戦時その他の国際関係の緊急時」の例外に該当すると主張としていたが、2022年にパネルがそれを認定しないと判断したことや、WTO協定上は先例拘束性を有しないにもかかわらず、上級委員会の判断が事実上の先例となり協定解釈を拡大していることなどを問題視している。これらの理由から、米国は上級委の新委員の選任を拒否し、その結果、2019年12月に、上級委員会の委員数が審理に最低限必要な3人を割ったことで、WTOの紛争解決機能は機能停止に陥った。
- 注3:
- 筆者が2025年5~6月にかけて行ったインタビューによる。
- 注4:
- Maria L. Pagan, “Reflections on the angels on the head of Jamieson Greer's pin”, Hinrich Foundation, August 12, 2025.
- 注5:
- 2025年3月4日付ビジネス短信「米USTR、2025年の通商課題を報告、WTO体制に「我慢の限界」も改革に取り組む」参照。そのほか、2025年8月12日付ビジネス短信「グリア米USTR代表、WTO体制から脱却し、関税措置用いたサプライチェーン再編の必要性訴える論説発表」も参照。
- 注6:
- 例えばガーツ氏らは、トランプ政権は、親密な同盟国・パートナー国との間で深い経済的・安全保障面の統合などをすべきと提言している。Emily Kilcrease and Geoffrey Gertz, “Tell Me How This Trade War Ends. The Right Way to Build a New Global Economic Order”, Foreign Affairs, June 9, 2025.
- 注7:
- 筆者が2025年4月に行ったインタビューによる。
- 注8:
- ラインシュ氏は、トランプ政権は、他国が中国との貿易関係を低減させる手段として、相互関税を巡る各国・地域との合意に「積み替え品」に対する罰則を設けたと解説している。William Alan Reinsch, “A Short Primer on Transshipment”, CSIS, August 11, 2025.
- 注9:
- 2025年6月11日付地域・分析レポート「米国コネクテッドカー規則発効、求められるサプライチェーンの透明化」参照。
- 注10:
- 米国では、政府補助金を活用した安価な中国製EVが大量に流入し米国経済へ与える影響が大きくなるとの懸念が党派を超えて共有されている。本文で述べた措置のほか、2026年7月までに予定されている米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の見直しで、中国製部品を一定程度利用した車両をUSMCAの特恵関税の対象外とする原産地規則の強化が検討されているといわれている。詳しくは2024年12月12日付地域・分析レポート「トランプ次期政権下で取られ得る中国製EV流入への対抗措置」参照。
- 注11:
- 2025年3月19日付地域・分析レポート「トランプ政権下の米中サプライチェーン 少量でも製造に不可欠な製品の調達管理が今後の焦点」参照。
- 注12:
- Alan Wm. Wolff, “Are Trump's tariffs a path to a new world trade order?”, PIIE, August 11, 2025.
- 注13:
-
米国通商専門誌「インサイドUSトレード」によれば、米国によるWTOへの分担金の支払いは、8月13日時点でまだ行われていないという。Margaret Spiegelman, “U.S. still in arrears at the WTO following State funding review deadline”, Inside U.S. Trade, August 13, 2025.
その後ホワイトハウスは8月末に、WTOへの拠出を停止すると発表したものの、数日後にWTOに関する記述は削除され、現在も米国とWTOとの関係性は不透明なままとなっている。詳しくは、2025年9月3日付ビジネス短信「トランプ米政権、対外援助や国際機関への拠出50億ドル分を停止へ」参照。 - 注14:
- Wolff (2025).
- 注15:
- Richard Baldwin, “The Great Trade Hack: How Trump's trade war fails and global trade moves on”, Centre for Economic Policy Research, May 19, 2025.
- 注16:
- Michael B. G. Froman, “After the Trade War. Remaking Rules From the Ruins of the Rules-Based System”, Foreign Affairs, August 11, 2025.
米国が挑む新たな国際通商システム

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ニューヨーク事務所 調査担当ディレクター
赤平 大寿(あかひら ひろひさ) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部国際経済課、海外調査部米州課、企画部海外地域戦略班(北米・大洋州)、調査部米州課課長代理などを経て2023年12月から現職。その間、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)の日本部客員研究員(2015~2017年)。政策研究修士。




 閉じる
閉じる






