トランプ政権下の米中サプライチェーン
少量でも製造に不可欠な製品の調達管理が今後の焦点
2025年3月19日
米中対立は、トランプ政権1期目の2018年に顕在化した。当時実行された追加関税や輸出管理など、通商上の各種措置は、続くバイデン政権で維持・拡大された。米中関係の改善が短期的には見通せない中、企業は米中間のサプライチェーンを見直し、再編に着手した。米中対立の顕在化から7年が経ち、2期目となるトランプ政権が発足した今、米中間のサプライチェーンはどう変容していくのか。米国の対中輸入額の変遷、日系企業へのヒアリング、現時点で示されているトランプ政権2期目の対中政策を基に、今後の米中サプライチェーンを展望する。
米国の対中輸入の変遷
米国の2024年の中国からの輸入額(財)は、前年比2.8%増の4,389億ドルだった。米国の輸入総額が6.1%増加した中では、伸びは比較的小幅にとどまった。米国の対中輸入額は2000年代に入り急激に拡大し、中国は2007年にカナダを抜いて以降、15年以上にわたり国別で1位だった。だが、米中対立や、2020年以降の新型コロナウイルスのパンデミックにより、2018年をピークに対中輸入額は一度縮小した。その後、パンデミック後の需要回復などから2021~2022年にかけて再び拡大したものの、2023年に前年比20%超減少し、国別輸入額でメキシコに抜かれ2位となった。2024年も、メキシコに続き2位だった(図1参照)。
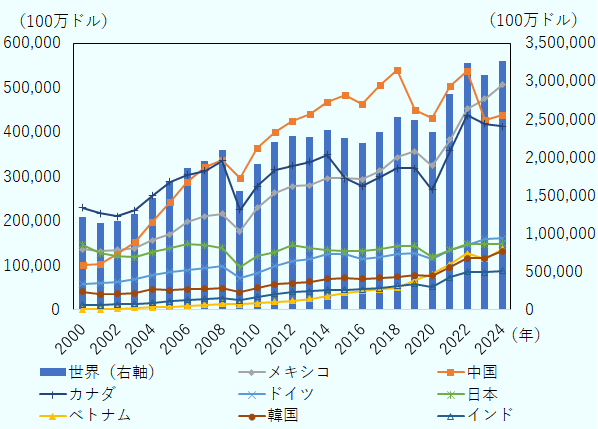
出所:米国際貿易委員会(USITC)から作成
2024年の米国の対中輸入を品目別にみると、HSコード8桁で輸入額の大きい上位10品目は2023年と同じだった(表1参照)。輸入額上位2品目のスマートフォン、ノートパソコン(PC)の輸入額減少のトレンドにも変化はなかった。米国のスマホの対中輸入額は前年比7.8%減の413億ドル、ノートPCは前年比8.1%減の326億ドルだった。対照的に、これら2品目のインドとベトナムからの輸入額は拡大した。この傾向も、これまでと同じだった。インドからのスマホの輸入額は前年比40.2%増の69億ドル、ベトナムからのノートPCの輸入額は前年比70.5%増の134億ドルとなった(表2、3参照)。これらの背景にあるのは、インドやベトナムでのスマホ、ノートPC生産増に向けた投資の拡大だ。米中対立や新型コロナウイルスのパンデミックの影響により、米国の巨大IT企業が生産拠点を中国からベトナムやインドなど周辺国に移管する戦略を策定し、それを受け、委託生産を行う台湾の大手企業がこれらの国で投資を拡大する構図となっている。ルーターの対中輸入額減少が一貫して続いている状況も変わらなかった。ルーターの2024年の輸入額は76億ドルで、前年比2.0%減の微減だったが、ピークの2018年と比較すると3分の1以下にまで減少した(表1参照、注1)。
|
HTS コード |
品目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入額 |
前年比 (%) |
輸入額 |
前年比 (%) |
2018年比 (%) |
|||||||
| 85171300 | スマートフォン | — | — | — | — | 50,297 | 44,789 | △ 11.0 | 41,312 | △ 7.8 | — |
| 84713001 | ノートPC | 37,358 | 37,298 | 46,963 | 55,688 | 49,207 | 35,482 | △ 27.9 | 32,611 | △ 8.1 | △ 12.7 |
| 85076000 | リチウムイオン電池 | 1,472 | 1,813 | 2,071 | 4,329 | 9,073 | 13,089 | 44.3 | 16,238 | 24.1 | 1003.2 |
| 95030000 | 三輪車など玩具 | 11,902 | 12,235 | 11,026 | 14,519 | 16,269 | 12,160 | △ 25.3 | 13,479 | 10.9 | 13.3 |
| 85176200 | スイッチング・ルーティング機器 | 23,478 | 16,245 | 11,765 | 10,138 | 9,491 | 7,798 | △ 17.8 | 7,639 | △ 2.0 | △ 67.5 |
| 95045000 | ゲーム用機器 | 5,368 | 3,460 | 4,996 | 8,718 | 10,201 | 9,320 | △ 8.6 | 5,649 | △ 39.4 | 5.2 |
| 30049092 | 医薬品(包装されたもの) | 394 | 456 | 635 | 812 | 6,943 | 4,101 | △ 40.9 | 5,607 | 36.7 | 1324.7 |
| 85285200 | PC用モニター | 4,696 | 5,109 | 4,783 | 6,340 | 6,871 | 4,741 | △ 31.0 | 4,916 | 3.7 | 4.7 |
| 84733011 | プリント基板 | 12,761 | 2,938 | 4,204 | 3,183 | 4,373 | 4,355 | △ 0.4 | 4,224 | △ 3.0 | △ 66.9 |
| 85183020 | マイク付きヘッドホン・イヤホン | 1,092 | 1,645 | 1,912 | 2,712 | 3,274 | 3,192 | △ 2.5 | 3,492 | 9.4 | 219.8 |
| — | 全品目 | 538,514 | 449,110 | 432,548 | 504,246 | 536,259 | 426,885 | △ 20.4 | 438,948 | 2.8 | △ 18.5 |
注:スマートフォンのHTS8517.13.00は2022年から新設されたため、2021年以前は値なし。
出所:米国際貿易委員会(USITC)から作成
| 国・地域名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 輸入額 |
前年比 (%) |
|||
| 世界 | 65,106 | 59,085 | 50,948 | △ 13.8 |
| 中国 | 50,297 | 44,789 | 41,312 | △ 7.8 |
| インド | 1,154 | 4,937 | 6,920 | 40.2 |
| ベトナム | 12,542 | 7,959 | 2,168 | △ 72.8 |
| 香港 | 119 | 110 | 150 | 36.6 |
| 韓国 | 728 | 1,137 | 108 | △ 90.5 |
注:HTS85171300。
出所:米国国際貿易委員会(USITC)から作成
| 国・地域名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入額 |
前年比 (%) |
2018年比 (%) |
|||||||
| 世界 | 39,594 | 40,268 | 50,813 | 59,760 | 53,651 | 45,793 | 49,349 | 7.8 | 24.6 |
| 中国 | 37,358 | 37,298 | 46,963 | 55,688 | 49,207 | 35,482 | 32,611 | △ 8.1 | △ 12.7 |
| ベトナム | 725 | 996 | 1,298 | 1,686 | 1,980 | 7,868 | 13,412 | 70.5 | 1751.1 |
| 台湾 | 1,081 | 1,424 | 1,847 | 1,943 | 2,197 | 2,073 | 1,989 | △ 4.1 | 84.0 |
| メキシコ | 69 | 154 | 367 | 115 | 13 | 108 | 767 | 609.0 | 1007.7 |
| タイ | 0 | 8 | 8 | 4 | 17 | 12 | 328 | 2694.6 | 156133.3 |
注:HTS84713001。
出所:米国国際貿易委員会(USITC)から作成
プリント基板(PCB)の対中輸入額も、ピーク時と比べ減少した。米中対立が顕在化した2018年の米国の対中輸入額は128億ドルだったが、翌2019年には29億ドルまで急減した。その後、2022年以降は40億ドル台で推移しており、2024年の輸入額は2018年比で66.9%減となった。米国の2024年のPCB輸入額上位10カ国のうち、中国以外は全て前年比増となっているのとは対象的だ。代わって輸入額が伸びているのが、台湾、ベトナム、韓国などのアジアの国だ(表4参照)。なお、バイデン前政権では、CHIPSおよび科学法(CHIPSプラス法)の下、先端半導体を中心に、サプライチェーンの強靭(きょうじん)化を図ってきた。他方で、ロジスティクスに関するインフラと政策について商務長官に助言をするサプライチェーン競争力諮問委員会(ACSCC)からは「工場から出荷されるチップのほとんどは、パッケージングとPCBへの搭載のためアジアに輸送される」として、PCBのサプライチェーン強靭化の必要性が指摘されている(注2)。
| 国・地域名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入額 |
前年比 (%) |
2018年比 (%) |
|||||||
| 世界 | 21,860 | 14,319 | 18,538 | 23,966 | 26,913 | 26,005 | 47,412 | 82.3 | 19.0 |
| 台湾 | 1,726 | 3,831 | 3,925 | 6,865 | 7,709 | 11,878 | 22,722 | 91.3 | 588.1 |
| 韓国 | 4,892 | 4,119 | 5,925 | 7,595 | 7,500 | 3,837 | 6,966 | 81.5 | △ 21.6 |
| ベトナム | 72 | 306 | 1,198 | 2,720 | 3,531 | 2,140 | 5,989 | 179.9 | 2875.5 |
| 中国 | 12,761 | 2,938 | 4,204 | 3,183 | 4,373 | 4,355 | 4,224 | △ 3.0 | △ 65.9 |
| マレーシア | 174 | 353 | 677 | 674 | 1,106 | 1,258 | 3,570 | 183.7 | 623.5 |
| メキシコ | 189 | 528 | 696 | 733 | 700 | 795 | 1,282 | 61.3 | 320.2 |
| フィリピン | 1,435 | 1,602 | 1,304 | 1,440 | 1,157 | 402 | 1,042 | 159.3 | △ 72.0 |
| タイ | 153 | 179 | 151 | 141 | 249 | 697 | 1,000 | 43.5 | 356.7 |
| カナダ | 177 | 172 | 173 | 156 | 159 | 203 | 216 | 6.4 | 15.2 |
| フランス | 12 | 30 | 32 | 53 | 67 | 103 | 104 | 0.6 | 770.2 |
注:HTS84733011。
出所:米国国際貿易委員会(USITC)から作成
これらを総合的に勘案すると、米国の対中輸入額は、2024年こそ前年比で微増したものの、米中対立発生直後の2019年と同程度にとどまり、スマホやノートPCなど輸入額が大きく戦略品目といわれている分野で輸入額減少が続いていることから、長期的な視点では下降トレンドにあると考えられるだろう。
トランプ政権下での日系企業の米中サプライチェーン
輸入額の減少傾向を裏付けるように、在米国・在メキシコの半導体や自動車関係の日系企業を対象に、2024年末~2025年初にジェトロが行ったヒアリングからは、企業が必要なサプライチェーンの移管を着々と行っている様子がうかがえた。サプライチェーンの移管には数年かかるといわれている中、短期的に米中対立が緩和する見通しが立たないことから、一定数の企業は2018年の米中対立の顕在化を契機に、サプライチェーンの移管を進めてきた。自動車産業を中心に、中国市場向けと米国を含むそれ以外の国向けのサプライチェーンの再構築は、おおむね完了したようだ(表5参照)。
| 産業 | コメント | ヒアリング時期 |
|---|---|---|
| 半導体 | 米国の顧客からは、明示的に中国や台湾で生産された製品を使わないようにとの指示も実際にある。現在、引き合いの相談は、4~5年後に生産する製品であるため、米中のいわゆるデカップリングは今後数年でさらに明示的にでてくるかもしれない。 | 2024年10月 |
| 自動車 | グローバルなサプライチェーンをみて中国は別扱いとなっており、中国部品は中国用、米国市場向けは中国製品を使わないようにするなど、デカップリングしている。 | 2024年10月 |
| 自動車 | 中国で生産された部品は、中国以外では使わないようにしている。現状、ほぼサプライチェーンは分けられている。これには3~4年かかった。ただし、今後米国で電気自動車(EV)需要がさらに伸びれば、中国製のバッテリーも使う可能性も検討しなければならない。バッテリーのみ、引き続き中国にサプライチェーンを依存している。 | 2024年11月 |
| 半導体 | 原料は基本的には日本で調達しているが、元をたどっていくと、中国由来のものもある。米国の顧客からは、米中対立の関係から、なるべく中国由来の原料を使わないでほしいといわれているが、供給地を変えると値段も変わるため、その辺りの商談の難しさがある。米国の顧客も中国から調達していたものを非中国産にしたく、当社に引き合いをもってくるが、結局、当社も最終的には中国から買っているので、変わらない結果となっている。 | 2025年2月 |
| 半導体 | 関税を理由に、原料の変更をしようと思っても、それだけで3年かかる。これから4年弱と決まっているトランプ政権下で、サプライチェーンが変わるとは思わない。 | 2025年2月 |
| 自動車 | 米中政治リスクを考慮し、コストは圧倒的に中国が安いが、中国からは調達しないという方にかじを切っている。ただし、レアメタルなど、必要な量はわずかでも中国から調達しなければいけない製品は残る。 | 2025年2月 |
出所:ジェトロによる在米国・メキシコ日系企業へのヒアリング
さらにヒアリングでは、米中対立による将来的な規制強化を懸念し、数年後に生産予定の製品に対する引き合いにおいて、米国の顧客から中国製の部品を利用しないよう要請されている企業が複数あることがわかった。トランプ政権による今後の対中政策は、依然として不透明な部分が多く、今後の「ディール」次第では、規制緩和など米中関係の改善もあり得る。だが、政権発足から1カ月超の3月上旬までに正式に発表された政策から判断する限りにおいては、トランプ政権は基本的には、中国に対して厳しい姿勢をとっていくと考えられる。
まず、ドナルド・トランプ大統領が1月20日の就任初日に発表した「米国第一の通商政策」では、「不公平かつ不均衡な貿易への対処」「中国との経済および通商関係」「経済安全保障に関する追加事項」と大きく3つに分けて、通商上の調査を指示した。この中で、「不公平かつ不均衡な貿易への対処」「経済安全保障に関する追加事項」は、そのほぼ全てが全世界を対象としているのに対し、「中国との経済および通商関係」では中国のみを対象としている(表6参照)。これら大項目の中で具体的な国名を指定されたのは、中国のみとなっている(注3)。
| 内容 | 対象国 |
報告 担当 |
報告 期限 |
|---|---|---|---|
| (a)中国が米国との第1段階の経済・貿易協定を順守しているか見直し、必要に応じて関税の賦課またはその他の措置を含む適切な措置を講じるよう勧告する | 中国 | USTR | 2025年4月1日 |
| (b)2024年5月に発表された1974年通商法301条に基づく追加関税措置の4年間の見直し報告書を評価し、必要に応じて追加関税率変更を検討する(特に、産業サプライチェーンや第三国を介した関税回避などの観点から) | 中国 | USTR | 2025年4月1日 |
| (c)不合理または差別的であり、米国の通商に負担をかけたり制限を加えたりする可能性のある、中国によるその他の行為、政策、慣行を調査し、適切な対応措置を勧告する | 中国 | USTR | 2025年4月1日 |
| (d)中国との恒久的正常貿易関係(PNTR)を評価し、必要な修正を提案する | 中国 | 商務長官 | 2025年4月1日 |
| (e)中国との間で知的財産権の相互的かつ均衡ある待遇を確保するための勧告する | 中国 | 商務長官 | 2025年4月1日 |
出所:米国政府発表資料から作成
また、トランプ氏が発表した複数の関税政策の中で、初めて実行に移されたのは、中国に対する追加関税の賦課だ。トランプ氏は2月1日に、不法移民やフェンタニルの流入を理由にメキシコ、カナダ、中国へ追加関税を賦課する大統領令を発表したが、メキシコとカナダに対しては、両国首脳との交渉を経て3月4日までの延期を決定した。一方で、中国に対しては当初の発表どおり、2月4日から現行の追加関税率にさらに10%を上乗せした。国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく、米国史上初めての関税賦課となった(注4)。その後3月3日には、中国に対するIEEPA追加関税を20%に引き上げる大統領令を発表している。そのほか、トランプ氏の大統領就任から1カ月超で発表した主な関税政策は、1962年通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミニウム製品への追加関税強化、相互関税制度の導入指示、銅・木材などに対する同232条調査などがあるが、いずれも2月には発動されていない。
これらに加え、2月21日に発表した「外国の敵対者」との対内・対外投資を規制する方針を示した覚書「米国第一の投資政策」は、米中間の投資をさらに規制することを念頭に置く内容となっている。具体的には「中国関係者による米国の技術、重要インフラ、医療、農業、エネルギー、原材料、その他戦略分野への投資の制限」「米国人による中国の軍事産業部門への投資をさらに抑制するため、IEEPAや、中国の軍産複合体と関係のある企業などへの証券投資を禁止する大統領令、対外投資規制など、必要なあらゆる法的手段の利用」などが規定されている(注5)。
また、トランプ氏が強い懸念を抱いている米国の貿易赤字額は、2024年に中国が2,954億ドルと国別で最大になっている。中国に対する貿易赤字額は減少傾向にはあるものの、2位のメキシコ(1,718億ドル)とは、依然として大きな差がある(図2参照)。こうしたことから、トランプ政権2期目においても、中国に対する厳しい規制環境が続けば、表5の日系企業のコメントのとおり、米中間のサプライチェーン上のデカップリングは進行すると予測される。
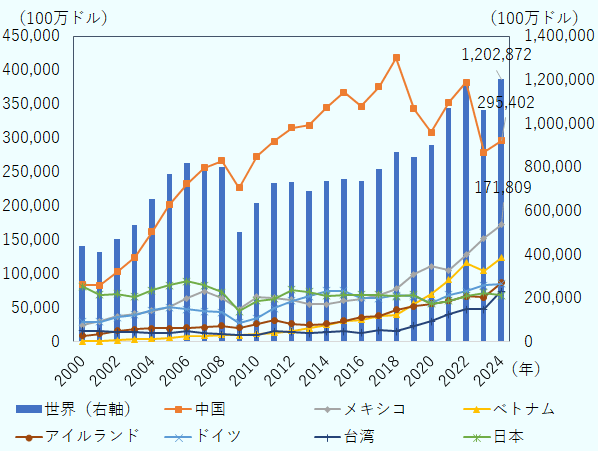
出所:米国際貿易委員会(USITC)から作成
対中追加関税がサプライチェーンに与えるインパクト
ジェトロが2025年1月のトランプ大統領の就任直前に実施した、在米日系企業へのアンケート調査によると、新政権の関税政策のうち、「サプライチェーンの変更を検討するほどの影響がある」と回答した割合が最も多かったのは「中国からの輸入に対する60%の関税」だった(図3参照)。これは、関税率の高さもさることながら、短期的に関係が改善される見通しが立ちづらい米中関係も影響していると考えられる。他方で、メキシコに対する追加関税によってサプライチェーンを変更するとの回答割合が比較的低いのは、たとえ賦課されたとしても短期的に終わる、あるいは長くてもトランプ政権下で終わるとのシナリオが十分あり得るからだと考えられる(表5参照、注6)。したがって今後、トランプ政権による中国との「ディール」が思うように進まず、関税率が60%などに高く設定された場合には、米中のサプライチェーン上のデカップリングは、今後一層、進行する可能性がある。
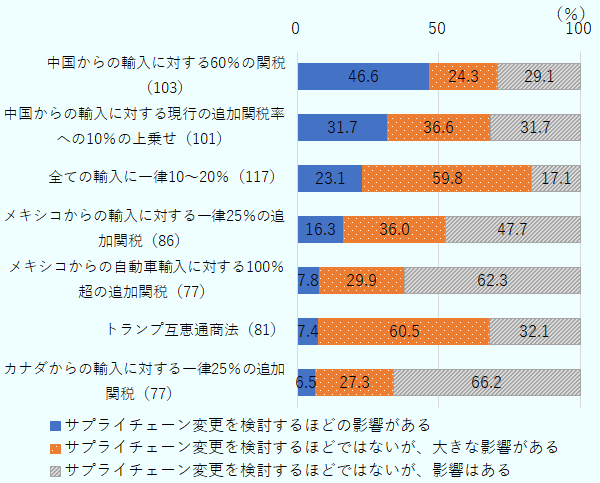
注:かっこ内の数値は関税措置の影響があると回答した企業数。
出所:ジェトロ「米国トランプ新政権の政策に関するクイック・アンケート調査」
バッテリーサプライチェーンは引き続き中国に依存
ただし、必ずしも全ての品目で米中デカップリングが進行しているわけではない点には留意が必要だ。例えば、リチウムイオンバッテリーの中国からの輸入額は、米国市場での電気自動車(EV)の需要拡大を背景に、米中対立が顕在化した2018年以降も、そして新型コロナウイルス禍の2020~2022年の間も、一貫して拡大している。2024年の輸入額は前年比24.1%増の162億ドル、2018年比でみると11倍以上で、スマホ、ノートPCに次ぐ3番目に大きい輸入品目となっている(表1参照)。中国産リチウムイオンバッテリーに対する、米国内でのビジネス環境は必ずしも良好ではなく、1974年通商法301条に基づく追加関税の対象となっているほか、中国から輸入したバッテリーを組み込んだEVは、インフレ削減法(IRA)による税額控除の対象外となっている。それでもなお、世界最大のバッテリーメーカーが中国の寧徳時代新能源科技(CATL)であるように、精錬などのバッテリーサプライチェーンは中国にいまだ依存している。実際に表6のとおり、米中間でサプライチェーンは分けたとする企業でも、「バッテリーのみ、引き続き中国にサプライチェーンを依存している」と述べている。加えて、バッテリーの原料となる黒鉛なども、米国はその調達の大部分を依然として中国に依存している。バイデン前政権のインフラ投資雇用法(IIJA)やIRAなどによる補助金や税額控除によって、米国では、黒鉛の生産のための複数のプロジェクトが立ち上がりつつあるが、需給ギャップはしばらく続くとみられている(注7)。そのほか、「必要な量はわずかでも中国から調達しなければいけない製品は残る」など、中国でしか調達できないレアメタルなどの原料の調達先変更の難しさが、ヒアリングでは複数聞かれた。
本稿でみてきたように、中国に対する追加関税は既に発動から7年が経過していることや、メキシコやカナダに対する追加関税と異なり、今後、短期的に改善される見通しが立たないことなどから、一定の企業は米中のサプライチェーンを分けるように既に再編している。ただしその中で、原料など中国に依存せざるを得ないサプライチェーンの再編の難しさが浮き彫りになった。こうした企業にとっては、追加関税の応酬そのものよりも、米国による一方的措置に対して、中国が輸出管理の強化などで特定の原料の輸出を認めなくなるリスクが顕在化した状態となっている。従って今後、トランプ政権下において、中国に対するビジネス環境が一層厳しくなれば、輸入する金額や量は大きくなくとも、特定の製品の生産に不可欠で、中国に依存する原料や材料の調達をどのように管理していくのかが、米国での事業運営の課題になってくるだろう。
- 注1:
- インドでのスマートフォン生産拡大、ベトナムでのノートPC生産拡大、ルーターの輸入額減少については、2023年10月16日付地域・分析レポート「米中対立が対米サプライチェーンに与えた影響」および、『グローバルサプライチェーン再考』(2024年9月、文眞堂)の第7章「米国」を参照。
- 注2:
- 2024年6月17日付ビジネス短信参照。
- 注3:
- 調査の報告期限は4月1日に設定されていることから、中国に対する通商上の措置は、当該報告書をもってより明確に示されていくと考えられる。「米国第一の通商政策」については、2025年1月22日付ビジネス短信参照。
- 注4:
- IEEPAについては、2024年12月10日付地域・分析レポート「トランプ次期政権下で取られ得る関税政策(米国)」参照。
- 注5:
- 「米国第一の投資政策」については、2025年2月25日付ビジネス短信参照。
- 注6:
- メキシコへの追加関税賦課に伴うサプライチェーンへの影響については、2025年2月21日付ビジネス短信参照。
- 注7:
- リチウムイオンバッテリーや同原料に関するサプライチェーンについては、2024年12月17日付地域・分析レポート「米国のEV市場における中国の存在」参照。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ニューヨーク事務所 調査担当ディレクター
赤平 大寿(あかひら ひろひさ) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部国際経済課、海外調査部米州課、企画部海外地域戦略班(北米・大洋州)、調査部米州課課長代理などを経て2023年12月から現職。その間、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)の日本部客員研究員(2015~2017年)。政策研究修士。






 閉じる
閉じる





