日本企業は対中投資に及び腰か?
データからみる各国の対中投資
2023年5月26日
米中関係の緊張や新型コロナウイルス感染防止措置により、日本を含む各国の対中ビジネスに影響が生じている。そうした状況の中、日本企業は対中投資に及び腰になっているが、「欧米企業」は積極的に対中投資を続けているとの見方がある。各種リスクを勘案し、個別の日本企業が対中投資に慎重になっている事例はあると思われるが、果たして日本企業全体として及び腰になっているのだろうか。
中国側の対内直接投資統計(注1)をみると、国・地域別の内訳がわかる2021年のデータでは香港からの投資が75.9%を占めている。いわゆる「香港企業」がこのように大きな比率を占めているとは考えづらく、世界各地の企業が香港を経由して中国に投資しているとみられる。しかし、香港経由の対中投資を示すデータはなく、中国側の統計のみでは各国・地域からの対中直接投資の実態をつかむことは難しい(注2)。また、香港の対内直接投資統計(2021年)をみても、投資元の1位は中国(3,516億香港ドル、約5兆9,772億円、1香港ドル=約17円)、2位は英領バージン諸島(3,110億香港ドル)、3位はケイマン諸島(1,209億香港ドル)となっており、香港の統計から資金の出し手を推測することも難しい。
そこで、本稿では、日米欧の対外直接投資統計および在中国商工会のアンケートなどから、それぞれの対中投資の現状および対中ビジネスに対する意欲を分析する。なお、本稿では米国、EU27カ国全体とそのうち最も対中投資に積極的なドイツ(注3)、そして英国を「欧米企業」として取り上げる。
中国への投資は日本では対外投資全体の3位
まず、それぞれの対中直接投資統計を確認する。日本の対外直接投資額(2022年)(注4)は23兆2,024億円。うち、対中直接投資額は1兆2,070億円だった。対中直接投資額は前年から減少したものの、投資先としては1位の米国(8兆527億円)、2位のオーストラリア(1兆3,025億円)に次いで、3位だった。4位はオランダ(1兆426億円)、5位は英国(9,627億円)だった。
米国の対外直接投資額(2022年)(注5)は3,729億9,600万ドル。うち、対中直接投資額は91億5,300万ドルで、国・地域別では10位だった。米国の投資先は1位が英国(858億ドル)、2位がオランダ(630億800万ドル)、3位がアイルランド(479億700万ドル)、4位がカナダ(421憶7,800万ドル)、5位がシンガポール(370億5,700万ドル)だった。
EUの対外直接投資額(2021年、注6)は、987億7,760万ユーロ。うち、対中直接投資額は69億7,210万ユーロと、国・地域別では18位となっている。EUの投資先は1位が米国(846億7,850万ユーロ)、2位が英国(492億1,030万ユーロ)、3位がオランダ(438億2,890万ユーロ)、4位がルクセンブルク(348億2,360万ユーロ)、5位がシンガポール(286億9,090万ユーロ)(注7)だった。
ドイツの対外直接投資額(2022年)(注8)は1,690億600万ユーロ、うち対中直接投資額は115億3,200万ユーロで、国・地域別では6位となった。ドイツの投資先は1位がルクセンブルク(296億100万ユーロ)、2位がオランダ(188億5,100万ユーロ)、3位が英国(188億4,100万ユーロ)、4位がフランス(149億4,400万ユーロ)、5位がスペイン(131億1,200万ユーロ)だった。
英国の対外直接投資額(2021年)(注9)は617億4,400万ポンドで、うち対中直接投資額は13億4,600万ポンドの引き揚げ超過だった。英国の投資先は1位が米国(490億200万ポンド、約8兆3,303億円、1ポンド=約170円)、2位が英国王室属領(130億1,000万ポンド)、3位がフィンランド(59億5,700万ポンド)、4位がアイルランド(44億7,400万ポンド)、5位が香港(36億7,100万ポンド)だった。
手元で確認できる時点までの統計比較にはなるが、対外直接投資は日米欧ともに欧州、米州への投資が主となっている。対中直接投資について、日本は全体の中で3位となっているが、欧米で最も上位に入っているドイツですら6位にとどまる(注10)。日米欧ともに、タックスヘイブン向け投資が多い(注11)点には注意が必要であるが、国・地域別でわかる範囲では、日本企業の対外直接投資において中国の占める比重は大きいものとなっている。
日本の対中直接投資は安定的に推移
経済規模からみても、日本にとって対中直接投資の比重は大きい。対中直接投資額の名目GDP比(注12)の推移をみると、2016年を除き、日本は一貫して0.2%以上の水準を維持している(図1参照)。欧米企業についてみると、ドイツは2014~2016年は日本よりも高い比率となっていたものの、2017年に日本を下回り、2020年まで減少を続けた。しかし、2021年に急増したことにより、その後は再び日本を上回っている。米国、EU27、英国は一貫して日本を下回っている。
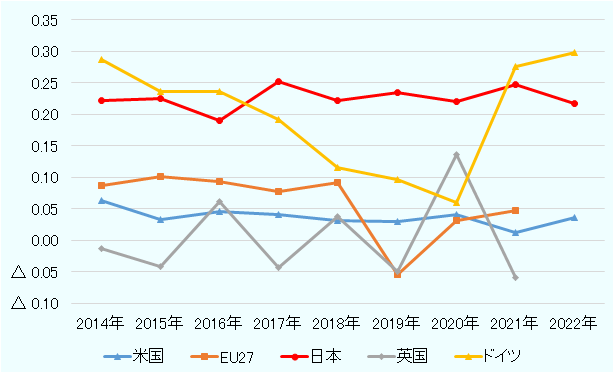
出所:内閣府、財務省(日本)、米商務省(米国)、EU統計局(EU27)、英国家統計局(英国)、ドイツ連邦銀行
また、日・米・EU27・ドイツ(注13)の対中直接投資額の推移について、2014年を100とした指数でみると、日本は2016年を除き、新型コロナウイルス感染拡大の時期も含めて100を上回っている(図2参照)。米国は2015年以降一貫して100を下回る状況が続いている。EUは2018年までは、2017年を除き100を上回っていたが、2019年に急減してからは100を下回っている。ドイツは2020年までは100を下回っていたが、2021年と2022年は大きく増加し100を上回った。日本企業は欧米企業に比べて、米中関係の緊張や新型コロナウイルス感染拡大の影響下においても、安定して対中直接投資を行っていることがわかる。
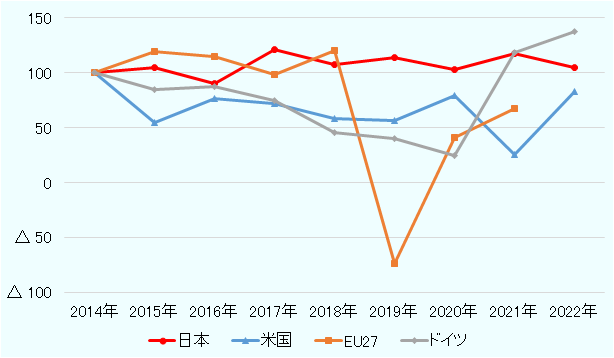
出所:財務省(日本)、米商務省(米国)、EU統計局(EU27)、ドイツ連邦銀行(ドイツ)
減速する欧米企業の対中投資意欲
続いて、企業の今後の対中投資意欲について、それぞれの企業に対するアンケート結果をもとに分析する。
ジェトロが中国を含む各国・地域の日本企業の現地法人を対象に実施した「2022年度 海外進出日系企業実態調査」(注14)によると、在中国日系企業のうち今後1~2年の中国での事業展開の方向性について「拡大」と回答した割合は33.4%だった。2021年度調査の40.9%から7.5ポイントと大きく低下し、比較可能な2007年度以降で最低となった。ただし、「縮小」は4.9%、「第三国(地域)へ移転・撤退」が1.4%と、両者を合わせた比率(6.3%)は2.5ポイントの上昇にとどまり、「現状維持」が5.1ポイント増の60.3%となっている。
また、ジェトロが海外ビジネスに関心が高い日本企業(本社)を対象に実施している「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」(注15)の2022年度の結果をみると、「今後海外で事業拡大を図る国・地域」(複数回答、最大3つ)は、1位が米国(29.6%)、2位がベトナム(26.5%)となり、中国は26.4%で3位にとどまった。なお、中国は2021年に、アンケートとして比較可能な2006年以来で初めて同項目で1位を譲った(注16)。また、2022年度の結果で「最も重視する輸出先」について中国と回答した企業は23.1%(前年比4.7ポイント減)と1位を保ったものの、2位米国の22.7%(1.2ポイント増)との差は0.4ポイントにまで縮小した。3位は西欧の11.6%(2.2ポイント増)、4位はベトナムの6.8%(0.2ポイント増)、5位はタイの5.9%(1.7ポイント増)となり、上位5位では中国のみ前年度比で割合が減少した。
現地拠点、本社いずれに対するアンケートでも、日本企業の中国での事業拡大意欲はこれまでにないほど低い水準になっている。また、輸出先としても他国と比べ重要性が薄れていることは確かである。
一方で、移転・撤退を考える企業はわずかであり、引き続き中国でビジネスを続ける企業がほとんどを占めている。この要因の1つとして、他国・地域に比べた中国での投資収益率の高さが挙げられる。2021年の対中直接投資の収益率は15.1%と主要投資対象国(注17)の中で最も高く、全体平均の6.9%を大きく上回っている(図3参照)。近年のデータでは、中国は2017年以降、一貫して主要投資国の中で1位を維持している。2位のタイとの差は年々拡大しており、2021年は4.7ポイント差となっている。
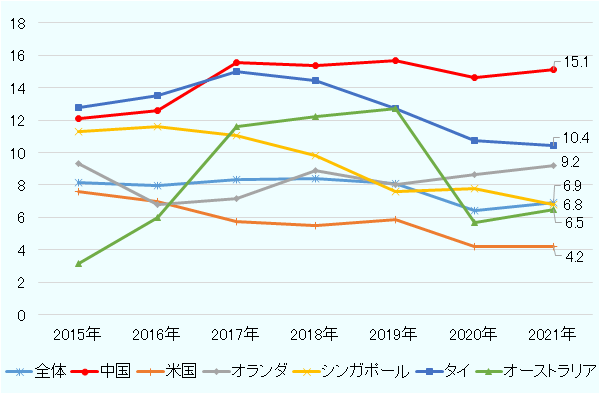
注:収益率は当年の直接投資収益受取÷((当年末の直接投資残高+前年末の 直接投資残高)÷ 2 )×100。
出所:財務省、日本銀行
欧米企業の対中投資意欲についても、アンケートからみてみる(2023年5月1日付地域・分析レポート参照)。中国米国商会のアンケート(注18)では、グローバルな投資計画での中国の重要性について、「第1の目的地」とした企業は14%(前年比8ポイント減)、「上位3位に入る目的地」は31%(7ポイント減)といずれも減少し、両者を合わせた割合は調査開始以来で初めて50%を下回った。
また、2023年の中国での投資計画について、「投資拡大計画なし」が46%(17ポイント増)と大幅に増加した。同時に、「投資を減少する」は9%(4ポイント増)となった。中国外への生産・調達の移転について、「計画はない」が74%(9ポイント減)で最大だったが、「検討しているがまだ具体的な行動は取っていない」が12%(5ポイント増)、「移転に向けたプロセスを開始済み」が12%(5ポイント増)と、合わせて約4分の1を占めた。
移転を検討、もしくは既に移転した理由については、「リスク管理」が60%(40ポイント増)、「新型コロナ防疫措置」が57%(40ポイント増)といずれも大幅に増加した。同時に、「米中貿易摩擦」が43%(14ポイント増)、「地政学的緊張の上昇」が20%(選択肢として初)と、米中関係を含む国際情勢の変化も大きく影響している。移転先については、「米国」が30%(6ポイント増)、「アジアの開発途上国」が29%(1ポイント増)、「アジアの先進国」が15%(2ポイント減)と、米国回帰の動きが強まっている。
EU企業の状況についてみると、中国EU商会のアンケート(注19)によれば、「新型コロナウイルス対策厳格化後に移転を検討している」と回答した企業は23.0%に達した。また、中国の投資目的地としての魅力は「明らかに減少した」が40%、「やや減少した」が37%と合わせて約8割を占めた。
ドイツ企業の状況についてみると、中国ドイツ商会のアンケート(注20)では、中国の追加投資の予定については「大幅に拡大する」が9%(9ポイント減)、「多少拡大する」が42%(11ポイント減)と合わせて20ポイントの大幅減となった。中国の投資目的地としての魅力は「減少した」が58%と5割を上回っている。今後2年以内に中国から移転・撤退するかという質問について、「はい」と回答したのは1%(1ポイント増)(注21)にとどまったが、「現時点で具体的な計画はないが検討中」が10%(6ポイント増)とやや増加している。
英国企業の状況についてみると、中国英国商会のアンケート(注22)では、グローバルな投資計画における中国の位置付けについて「優先度が高い」が31%(28ポイント減)と大幅に減少し、「優先度は低い」が27%(17ポイント増)と大幅増になっている。今後5年の投資計画については、「完全に中国から離れることを検討あるいは計画している」が7%、「一部機能を中国外へと移転するかあるいは現在移転している」が19%と、合わせて26%に達している。
また、この1年のビジネスの状況(複数回答)について、「困難になった」が89%(25ポイント増)と約9割に達している。困難になった要因については「新型コロナの影響」が95%に達したほか、監督・管理が46%、経済状況が46%、地政学的要因が42%と、新型コロナ以外の要因も半数に迫る状況となっている。
各商工会のアンケートをみる限り、日米欧いずれもマインドは以前と比べて中国ビジネスに消極的になっていることは間違いない。しかし、移転・撤退を検討している企業の比率について、日本企業は欧米企業に比べて比較的低い水準になっており、欧米企業の方がより米中関係や新型コロナの影響を受けているようにみえる。
大型投資が目立つ欧米企業
前述のとおり、統計をみる限りでは、日本企業は欧米企業と比べて安定的に対中直接投資を行っており、対外直接投資に占める比重も大きい。また、現地商工会アンケートの回答をみても、欧米企業に比べて中国で事業を続ける意欲は高い。それにもかかわらず、欧米企業の方が対中投資に積極的にみえる要因の1つとして、大型投資が活発で中国政府の重要プロジェクトとして優遇を受けている案件が多いことが考えられる。
中国政府は、外資系企業による投資のうち条件を満たしたものを「重要外資プロジェクト」として、重点的に支援を行っている(注23)。認定されたプロジェクトについては、土地やエネルギーの使用、法規制などで特別な支援が行われる。2022年2月時点で5期33プロジェクトが認定されており、総投資額は約1,380億ドルに達したという(「央視網」2022年2月11日)。認定プロジェクトのリストは発表されていないが、報道や記者会見などからみる限りでは、欧米企業が多く採用されている(表1参照)。
| No | 企業名 | 国 | 場所 | 投資金額 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | ドイツ | 遼寧省瀋陽市 | 150億元 | 自動車製造。 |
| 2 | テスラ | 米国 | 上海市 | 500億元 | EV生産。 |
| 3 | シェル | 英国 | 広東省恵州市 | 326億元 | スチレン、酸化プロピレンなどの製造。2022年には第3期520億元を投資。 |
| 4 | サムスン | 韓国 | 陝西省西安市 | 約80億ドル | 12インチフラッシュメモリー製造。陝西省最大の外商投資プロジェクト。 |
| 5 | Litium Werks | オランダ | 浙江省嘉興市 | 16億ユーロ | リチウムイオンバッテリー |
| 6 | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 米国 | 浙江省嘉興市 | 10億ドル | 水素エネルギー |
| 7 | BASF | ドイツ | 広東省湛江市 | 100億ユーロ | エチレン生産・加工。単独プロジェクトとしてドイツ企業による最大の投資。 |
| 8 | エクソンモービル | 米国 | 広東省恵州市 | 100億ドル | エチレン生産・加工。 |
| 9 | SABIC(サウジアラビア基礎産業公社) | サウジアラビア | 福建省漳州市 | 約420億元 | エチレン生産・加工。福建省で過去最大の中外合弁プロジェクト。 |
| 10 | VANDEWIELE | ベルギー | 江蘇省無錫市 | 1.6億ドル | 中国本部および紡織機械の研究開発・製造 |
出所:政府記者会見および報道から作成
2022年の欧米企業の対中投資案件について投資額1億ドル以上のものをみると(注24)、米国からはバイオ、半導体、自動車などの分野で大型投資がある(表2参照)。また、EUからはドイツの自動車や化学関連企業による大型投資が行われている(表3参照)。これらの分野はいずれも、中国政府が第14次5カ年(2021~2025年)規画において発展やレベルアップを目指している分野である。
| 順位 | 企業名 | 省 | 市/区 | 分野 | 業務 |
総投資額 (100万ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VectorBuilder | 広東省 | 広州市 | バイオ | 研究開発 | 500 |
| 2 | Flexible Circuit Technologies | 広東省 | 珠海市 | 半導体 | 製造 | 386.3 |
| 3 | Citigroup | ― | ― | 金融サービス | ビジネスサービス | 312.2 |
| 4 | Azenta | 江蘇省 | 蘇州市 | バイオ | 本社機能 | 173.2 |
| 5 | FedEx Express | 広東省 | 広州市 | 運輸・倉庫 | 物流・運輸 | 151.3 |
| 6 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 海南省 | 三亜市 | ビジネスサービス | 教育・研修 | 147.4 |
| 7 | Tesla Motors | 上海市 | ― | 自動車製造 | 研究開発 | 143.2 |
| 8 | SI Group (Schenectady International) | 上海市 | ― | 化学 | 製造 | 125.1 |
出所:fDi Markets
| 順位 | 企業名 | 国 | 省 | 市 | 分野 | 業務 |
総投資額 (100万ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayerische Motoren Werke (BMW) | ドイツ | 遼寧省 | 瀋陽市 | 電子部品 | 製造 | 1383.5 |
| 2 | BMW Brilliance Automotive | ドイツ | 遼寧省 | 瀋陽市 | 自動車製造拠点 | 製造 | 626.7 |
| 3 | Bollore Logistics China | フランス | 海南省 | 海口市 | 運輸・倉庫 | 物流・運輸 | 151.3 |
| 4 | cargo-partner | オーストリア | 広東省 | 深セン市 | 運輸・倉庫 | 物流・運輸 | 151.3 |
| 5 | cargo-partner | オーストリア | 江蘇省 | 昆山市 | 運輸・倉庫 | 物流・運輸 | 151.3 |
| 6 | Porsche Engineering Group | ドイツ | 北京市 | 広州市 | 自動車製造拠点 | 研究開発 | 143.2 |
| 7 | Mercedes-Benz Group (Daimler) | ドイツ | 上海市 | ― | 自動車製造拠点 | 研究開発 | 143.2 |
| 8 | Audi China | ドイツ | 北京市 | ― | 自動車製造拠点 | 研究開発 | 143.2 |
| 9 | Air Liquide | フランス | 江蘇省 | 淮安市 | 再生可能エネルギー | 製造 | 138.1 |
| 10 | RÖHM | ドイツ | 上海市 | ― | 化学 | 製造 | 125.1 |
| 11 | Evonik Industries | ドイツ | 上海市 | ― | 化学 | 製造 | 124.8 |
| 12 | Solvay | ベルギー | 四川省 | 成都市 | 化学 | 製造 | 124.8 |
| 13 | ASK Chemicals | ドイツ | 江蘇省 | 鎮江市 | 化学 | 製造 | 124.6 |
| 14 | Hanza AB | スウェーデン | 江蘇省 | 蘇州市 | 電子部品 | 製造 | 116.4 |
| 15 | L'Oreal | フランス | 江蘇省 | 蘇州市 | 消費財 | 物流・運輸 | 113.7 |
| 16 | Merck KGaA | ドイツ | 江蘇省 | 無錫市 | バイオ | 製造 | 110 |
| 17 | Gardner Aerospace | 英国 | 四川省 | 成都市 | 航空宇宙 | 製造 | 107.3 |
| 18 | CARIAD | ドイツ | ― | ― | ソフトウエア・ITサービス | 研究開発 | 107 |
出所:fDi Markets
一方で、欧米企業については、中小企業の投資は厳しい状況のようだ。中国EU商会関係者によれば、EUからの投資は大企業の大型投資に限られており、中小企業の投資はわずかなものにとどまっているとされる。中国EU商会のイェルク・ウトケ会長は「EUからの対中投資は減少しており、少数の大企業に限定されている」として、EUからの投資は特定の大企業のみに集中していることに言及している。英国商会のアンケートでも、中小企業では「完全に中国から離れることを検討あるいは計画している」が13%、「一部機能を中国外へと移転するかあるいは現在移転している」が23%と、いずれも大企業(それぞれ11%、6%)と比べて中国での事業展開に後ろ向きになっている。
日本企業をみると、大企業と比べ中小企業の中国での投資意欲が著しく低下しているわけではない。前述の「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」の「今後海外で事業拡大を図る国・地域」について、中小企業に限定すれば、中国を選んだ割合は26.3%となり、米国(29.4%)に次ぐ2位となっている。また、「2022年度 海外進出日系企業実態調査」でも、製造業における中小企業の事業拡大意欲は28.2%と大企業(35.1%)に比べて弱いものの、縮小は5.2%、移転撤退は0.6%と、いずれも大企業(それぞれ5.4%、2.3%)よりも低い割合となっている。
さらに、欧米商会関係者からは、中小企業の投資が消極的であることに加え、「欧米企業の対中投資は特定の業種に偏っており、日本企業のように幅広い分野での投資はみられない」との声も聞かれた。
チェーン店の進出も活発化
以上のように、対中直接投資統計および企業アンケートをみる限りでは、日本企業は欧米企業に比べて、少なくとも対中投資に及び腰であるとは言えないだろう。
日系企業の近年の特徴として、製造業と比べて非製造業の業績が堅調であることが挙げられる。日系企業調査で2022年度の営業利益(見込み)を「黒字」と回答した企業の割合は製造業が63.8%(前年比7.1ポイント低下)、非製造業が66.3%(7.8ポイント低下)となり、2年連続で非製造業が製造業を上回った。黒字比率は、2007年度を除き、製造業が非製造業を上回ってきたが、2019年と2021年に逆転した。
また、対中直接投資の収益率についても、2021年は製造業が14.5%、非製造業が16.3%と非製造業が製造業を上回っている。2015年以降では、2019年に初めて非製造業が製造業を上回り、2020年は0.1ポイント差で製造業が逆転したが、2021年には再び非製造業が上回った。
日本からの個別の投資案件をみると、消費市場の拡大を背景にした各種企業の進出が続いている。FOOD & LIFE COMPANIESは、すしチェーン店の「スシロー」の中国1号店を2021年9月に広東省広州市に開店、2022年11月には四川省成都市に12店舗目を開店した。家具・インテリア用品チェーン店のニトリは、2014年に武漢市に1号店を開店、2023年4月には福建省アモイ市に68店舗目を開店した。ニトリは2020年だけで30店舗以上をオープンしている。生活雑貨・書籍などを扱うカルチュア・コンビニエンス・クラブは、2020年10月に浙江省杭州市に「蔦屋書店」を開店、2022年12月には上海市で「TSUTAYA BOOKSTORE」を開店するなど全国で9店舗を運営している。アウトドア用品などを扱うスノーピークも、2022年10月に中国で合弁会社を設立している。
消費市場としての中国の重要性が増す中で、日本企業は引き続き幅広い分野での投資を行うものとみられる。
- 注1:
- 実際利用外商直接投資額。国際収支ベースの対内直接投資額とは異なる。
- 注2:
- なお、中国側統計では、日本は香港、シンガポール、英領バージン諸島、韓国に次いで5位となっている。また、香港の対内直接投資額(2021年)は、全体では1兆897億香港ドル、日本からは383億香港ドルで6位となっている。
- 注3:
- EU統計局(ユーロスタット)によれば、EU27カ国のうちドイツの対中直接投資額は2013年以降で2020年を除いて最大となっている。
- 注4:
- 特に記述のない場合、各国ともに国際収支ベース、フロー、ネットの数値。日本は2023年4月10日発表データ。なお、各国の統計はIMF基準によるものではあるが、全く同じ基準で集計されているわけではない点は留意する必要がある。
- 注5:
- 2023年3月23日更新データ。
- 注6:
- EU加盟国間の投資も含む。2023年3月1日更新データ。
- 注7:
- なお、EU域内への投資を除いた場合、シンガポールは3位、4位はマン島、5位はブラジルとなり、中国は10位。
- 注8:
- 2023年4月18日更新データ。
- 注9:
- 2023年3月23日更新データ。
- 注10:
- ただし、ドイツの対中直接投資額については2022年に過去最高を更新するなど、再び活発化している。なお、ドイツからの対中投資のほとんどは再投資となっている。
- 注11:
- 日本でも4位のオランダのほか、6位がケイマン諸島(7,933億円)、14位がルクセンブルク(3,709億円)となっている。
- 注12:
- 経年比較には、日・米・EU・英・独のすべてがIMF国際収支マニュアル第6版(BPM6)を採用している2014年を基準とする。英国については、2020年に国際収支の統計基準(IMF基準に沿った上で)が改定されている点に留意が必要。
- 注13:
- 英国については、引き揚げ超過の年が多く、振れ幅が大きいため除外。
- 注14:
- 2022年度は8月22日~9月21日実施。中国の有効回答企業数720社。
- 注15:
- 2022年11月中旬~12月中旬実施。3,118社が回答(有効回答率33.3%)。
- 注16:
- 2022年度は質問の仕方が異なるため、厳密な連続性はない点に留意が必要。
- 注17:
- 対外直接投資額ストック上位5カ国に、製造業の直接投資額ストックが4位のタイを加えたもの。
- 注18:
- 「チャイナ・ビジネス・クライメート・サーベイ・レポート(China Business Climate Survey Report)」2023年版。2022年10月中旬~11月中旬にかけて会員企業319社に対して行った調査を基にしており、25年連続で発表されている(2023年3月30日付ビジネス短信参照)。
- 注19:
- 「COVID-19 AND THE WAR IN UKRAINE: THE IMPACT ON EUROPEAN BUSINESS IN CHINA」。2022年4月21日から30日に実施。372社が回答(2022年5月11日付ビジネス短信参照)。
- 注20:
- 「ビジネス・コンフィデンス・サーベイ(Business Confidence Survey) 2022-2023」。2022年8月23日から9月21日に実施。589社が回答(2023年1月5日付ビジネス短信参照)。
- 注21:
- 2021年版では「12カ月以内に中国から移転・撤退するか」となっており期間が異なる。
- 注22:
- 「ブリティッシュ・ビジネス・イン・チャイナ:センチメント・サーベイ(British Business In China: Sentiment Survey)2022-2023」。2022年10月12日~11月4日実施、292社が回答。
- 注23:
- 具体的な認定基準は公表されていないが、主に投資額10億ドル以上で先端分野や研究開発センター、既存産業の高度化など中国が発展を促進している分野への投資を対象とするとされる。
- 注24:
- fDi Marketsのデータに基づく。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・北京事務所 経済分析部 部長
河野 円洋(かわの みつひろ) - 2007年、ジェトロ入構。在外企業支援・知的財産部知的財産課、ジェトロ岐阜、海外調査部中国北アジア課、ジェトロ・広州事務所、企画部企画課を経て2022年1月より現職。




 閉じる
閉じる






