知財の力で挑むグローバル市場:海外展開する日本企業の知財の取り組み総論:中小企業が抱える知的財産の課題と海外市場での知財保護の現状
2025年9月11日
中小企業は、国内外を問わず、イノベーションの源泉や経済活性化に重要な役割を果たす存在だ。近年、日本の中小企業がビジネス拡大のために海外進出を計画するケースも増えている。このような中小企業にとって、知的財産は重要な資産で、輸出においても自社の強みとなる。一方で、知的財産は模倣品などによって侵害されるリスクも伴っている。知的財産保護や知的財産戦略を活用して海外事業に成功した中小企業もあれば、知的財産対策が不十分のため、侵害被害を受けてからその重要性に気づいた企業も少なくない。特に海外市場では、模倣品や知的財産侵害のリスクが高く、事前に知的財産リスクに備えることは重要である。また、日本の中小企業が国内外での競争力を高め、円滑な海外事業を促進するには、中小企業の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、なおかつ、積極的に活用していくことが求められる。
本稿では、中小企業が抱える知的財産の課題とともに、海外市場での知的財産保護の状況や課題について説明する。
創作者の権利守る知的財産権制度
知的財産とはそもそも、人間の知的活動の結果生み出された無形資産の総称だ。知的財産には、特許(発明)や実用新案(アイデア)、意匠(デザイン)、商標、著作物、ノウハウなどが含まれている。その創作者に一定期間の権利保護を与え、独占的に実施・使用できるようにするのが知的財産権制度である。知的財産権はその種類に応じ、異なる法律で保護されている(図1)。
図1:知的財産権の種類
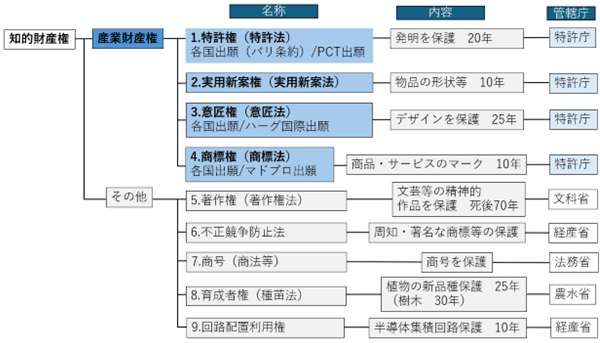
出所:特許庁ウェブサイト を基にジェトロが作成
を基にジェトロが作成
模倣品リスクはアジア中心に拡大、企業の「気づかぬ被害」も
前述の知的財産は、多くが模倣品による侵害リスクにさらされている。技術的なアイデアやデザインなどは、その創作者に独占的に創作を利用するための知的財産権が与えられる。そうした権利を侵害して、第三者が正規品のデザインや機能を不正にまねてつくられたものを模倣品という。安価につくられた模倣品が流通すると、正規品の販売機会の損失や、消費者の健康被害、安全性の低下、さらには、ブランドイメージの低下など、さまざまな影響が考えられる。
特許庁が実施した令和6年度知的財産活動調査![]() の日本企業へのアンケートでは、調査対象(有効回答数:3,158社)のうち18.3%が直近の会計年度に商品・サービスに対して国内外で「模倣被害にあった」と回答している(図2)。同調査では、模倣品被害に係る物品の販売提供国・地域の回答結果が掲載されており、模倣品被害があったと回答した企業のうち約40%が「中国(香港を除く)で製造された模倣品が、同国内で販売された」と回答した(注)。また、「中国(同)で製造された模倣品が、日本で販売された」と回答した企業は約2割、「日本で製造された模倣品が日本で販売された」と回答した企業も約2割だった。中国をはじめとしたアジアで製造・販売される物品による模倣被害が多く見て取れる。一方で、模倣品被害の有無について、「不明」と答えた割合は回答企業全体の約4割だった。また、模倣品の被害を受けたと回答した企業のうち、例えば日本で販売された模倣品では、1割の企業が製造国を把握していないと回答した。このように、そもそもの現状が把握できていないという企業も数多く存在しており、気づかずに模倣品が流通しているケースも少なくないようだ。
の日本企業へのアンケートでは、調査対象(有効回答数:3,158社)のうち18.3%が直近の会計年度に商品・サービスに対して国内外で「模倣被害にあった」と回答している(図2)。同調査では、模倣品被害に係る物品の販売提供国・地域の回答結果が掲載されており、模倣品被害があったと回答した企業のうち約40%が「中国(香港を除く)で製造された模倣品が、同国内で販売された」と回答した(注)。また、「中国(同)で製造された模倣品が、日本で販売された」と回答した企業は約2割、「日本で製造された模倣品が日本で販売された」と回答した企業も約2割だった。中国をはじめとしたアジアで製造・販売される物品による模倣被害が多く見て取れる。一方で、模倣品被害の有無について、「不明」と答えた割合は回答企業全体の約4割だった。また、模倣品の被害を受けたと回答した企業のうち、例えば日本で販売された模倣品では、1割の企業が製造国を把握していないと回答した。このように、そもそもの現状が把握できていないという企業も数多く存在しており、気づかずに模倣品が流通しているケースも少なくないようだ。
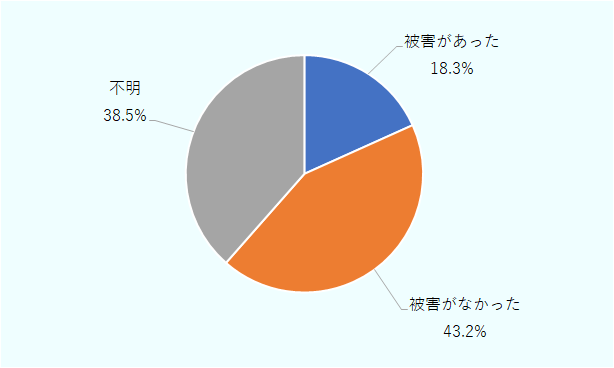
出所:特許庁資料「令和6年度知的財産活動調査 」を基にジェトロ作成
」を基にジェトロ作成
また、回答企業全体のうち60.1%は模倣品対策をしていないとしている。対策をしていない理由として、「模倣被害が発生していない、または被害を把握していない」が最大(71.8%)だった。被害が発生していなければ対策を取る必要がないと認識している企業も多いとみられる。一方で、被害はあるが「費用対効果が低い」(14.2%)、「対策をしたいが人員不足、資金不足から実施できない」(12.3%)、「対策をしたいが、対策の方法が分からない」(9.4%)と、悩みを抱える企業も少なくないことがうかがえる。
「人材・知識・資金」の三重苦に悩まされる中小企業の知財活動
特に中小企業では、知的財産活動の課題は大きい。特許庁による特許行政年次報告書2024年版![]() によると、日本企業の99.7%を中小企業が占めるにもかかわらず、中小企業の特許出願件数は全体の17.6%にとどまっている(図3)。中小企業による外国への出願数は近年少しずつ増加傾向にはあるものの、2023年の外国への出願率は大企業が39.3%に対して、中小企業では約半分の18.8%にとどまっている(図4、図5)。
によると、日本企業の99.7%を中小企業が占めるにもかかわらず、中小企業の特許出願件数は全体の17.6%にとどまっている(図3)。中小企業による外国への出願数は近年少しずつ増加傾向にはあるものの、2023年の外国への出願率は大企業が39.3%に対して、中小企業では約半分の18.8%にとどまっている(図4、図5)。
図3:企業数・特許出願件数に占める中小企業の割合
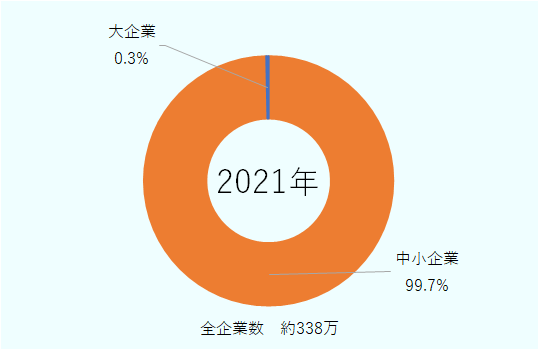
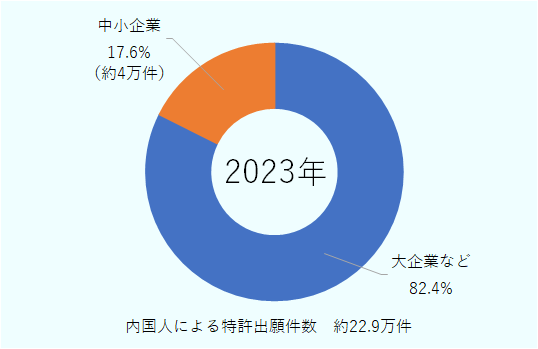
出所:特許庁資料「特許行政年次報告書2024年版 」を基にジェトロ作成
」を基にジェトロ作成
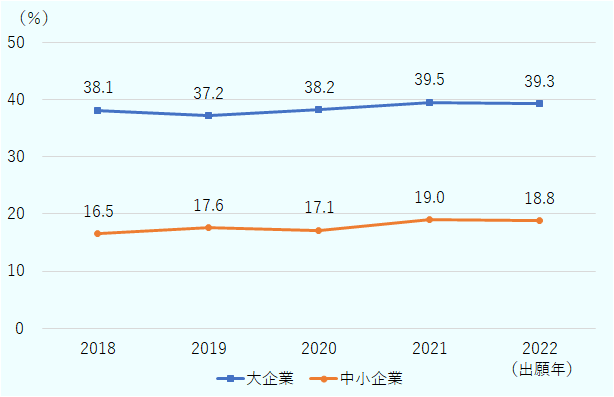
注:海外出願率=(優先権請求件数+PCT直接出願)/(国内出願+PCT直接出願)。
出所:特許庁資料「特許行政年次報告書2024年版 」を基にジェトロ作成
」を基にジェトロ作成
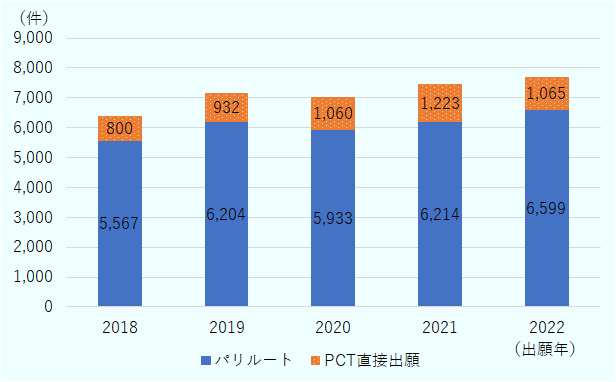
注1:国内へ出願される特許出願のうち外国にも出願される件数。
注2:特許庁で把握できない外国に直接出願された件数を含んだものではなく、日本企業による海外全ての出願件数を意味しない。
注3:パリルートは、パリ条約に基づく国際出願制度。最初に出願した国(基礎出願)から12か月以内に、各国に個別に出願する方法。
注4:PCTは特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願制度。1つの出願で最大150以上の加盟国に出願可能。PCT直接出願は、国際出願の受理官庁としての日本国特許庁に出願されたPCT出願のうち、国内出願に基づかない出願。 出所:特許庁資料「特許行政年次報告書2024年版 」を基にジェトロ作成
」を基にジェトロ作成
この背景には、資金不足のほかにも、主に2つの要因が挙げられる。まず1つは、人材不足だ。大企業の知的財産担当者は知的財産部を専任とし、特許や商標など、また出願や係争、ライセンス契約など、分野や業務によって担当が分かれていることが多いが、中小企業では、知的財産担当者は全ての知的財産業務を担うケースや、知的財産以外の業務と兼任しているケースが多い。中小企業では知的財産の総括責任者が経営トップや役員相当の場合も非常に多く、知的財産活動のみに時間やコストをかけることはやはり難しい。
2つめは、知識不足や意識の低さだ。大企業のようにノウハウが蓄積されていなかったり、知的財産活用のやり方が分からなかったりすると、知的財産は「コストがかかるだけのもの」として軽視されやすい。このような環境下では、知的財産侵害のリスクにさらされやすいと言える。また、都道府県別でみると、東京都の企業は出願数が圧倒的に多いが、その他の地域では、大阪府と京都府を除く全ての地域が全国平均を下回るなど、地域格差も顕著に表れている。
限られた資金の中で知的財産に取り組むことが必要
知的財産権は、保護したい国・地域ごとに権利を取得しなければならず、海外進出を目指す企業にとってコストがかかることは否めない。しかし、知的財産権を確実に取得し、模倣品などの権利侵害に対抗するすべを持つことは企業の責任として重要だ。また、知的財産の保護や活用に取り組むことで、例えば、通常は目に見えない情報の無形資産を権利として「見える化」し、明確に企業の「財産」にすることができるほか、社内の創意工夫や意欲の活性化をもたらす。
技術やデザインなどが企業の財産として見える形で保護されることで、競合他社との間での優位性や、取引者間で主導権を確保することができる。特に電子商取引(EC)が発展した近年、実際にこういった知的財産権の取得や模倣品対策を強化した中小企業の例もある(本特集「伊勢半の模倣品対策、「ものづくり」企業としてブランドと信頼を守る」参照)。加えて、知的財産を戦略的に用いることでブランドを広めていくことも可能になる(本特集「模倣品対策でキャラクターの価値を最大化 ―バンダイの知財戦略に迫る」参照)。これらの例のように、知的財産活動に積極的に取り組むことは、国内外でのブランド価値の向上や競争力の一助となる。
また、内閣府知的財産戦略推進事務局では、「知的財産推進計画2025」が新たに策定された。地方などの中堅・中小企業の知的財産活用や保護の促進のための支援策も打ち出され、今後さらに強化されるとみられる。ジェトロやその他の機関でも、中小企業をはじめとした企業の侵害対策支援の取り組みを行っている。ジェトロでは、自社製品の権利を侵害された中小企業などに対し、支援を行っている〔中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)〕。そのほかにも、工業所有権情報・研修館(INPIT)![]() や、各都道府県の機関では(各都道府県の機関は特許庁「地域実施機関」参照
や、各都道府県の機関では(各都道府県の機関は特許庁「地域実施機関」参照![]() )、海外での出願について一部費用を助成するプログラムを実施しており〔工業所有権情報・研修館(INPIT)「INPIT外国出願補助金」参照
)、海外での出願について一部費用を助成するプログラムを実施しており〔工業所有権情報・研修館(INPIT)「INPIT外国出願補助金」参照![]() 〕、こうした支援を活用して知的財産保護・活用の強化を進めていくことを勧めたい。
〕、こうした支援を活用して知的財産保護・活用の強化を進めていくことを勧めたい。
本特集では、海外展開を行う日本企業の模倣品対策を中心とした知的財産保護の取り組みや課題、知的財産戦略などについて取り上げる。先行して知的財産活動を行う大企業から、限られたリソースの中で工夫した取り組みを進める中小企業やスタートアップまで、幅広い事例を紹介していく。
- 注:
- 各割合は、模倣被害があったと回答した577社を母数とし、各国・地域の選択肢に回答した企業数を用いて計算した。母数には、この設問に無回答の企業も含む。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ知的資産部知的財産課
井上 真琴(いのうえ まこと) - 2024年、ジェトロ入構。知的財産課でASEANおよびオセアニア地域を担当。






 閉じる
閉じる





