新たなステージに入った世界のカーボンプライシングカーボンクレジット取引が拡大、炭素税導入の可能性も(タイ)
2024年5月21日
タイは2024年4月時点で、カーボンプライシング制度を導入していない。炭素税、キャップアンドトレード方式による排出量取引制度(ETS)のいずれもである。他方、タイで開発されたカーボンクレジット「T-VER」の取引が拡大している。背景には、2021年ごろからの気候変動対策に対する政財界の関心が急速に高まったことが挙げられる。
タイには企業の生産や輸出の拠点が集積している。EU向けに取引する事業者も少なくない。こうしたことから、EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)が意識されるようになっている。今後、CBAM対象品目が追加されたり、米国など他の主要輸出先でCBAMが導入されたりした場合、事業への懸念が生じかねない。そのため先手を打って、大手企業を中心に脱炭素化を進める動きが見られるが、中小企業の対応は遅れているのが実態だ。
低炭素社会へかじ切るタイ政府
タイのプラユット・チャンオーチャー首相(当時)は2021年1月、「バイオ・循環型・グリーン(BCG)経済モデル」を国家戦略に据えた。同戦略の下、タイ政府は持続可能な経済社会の実現や二酸化炭素(CO2)削減のため、電気自動車(EV)や工場のグリーン化、農業の効率化、バイオマスや廃棄物の利用を推進してきた(2023年10月27日地域・分析レポート参照)。
プラユット首相はその後、2021年の国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)の場で「2050年までのカーボンニュートラル(CN)達成」「2065年までに温室効果ガス(GHG)排出量を実質ゼロにする」という目標を発表した。2023年5月の総選挙を経てセター・タビシン新政権が発足してからも、これらの目標は変更されていない。パッチャラワート・ウォンスワン副首相兼天然資源・環境相はCOP28(同年11月~12月に開催)の席上、「2065年までに排出量ネットゼロ」の公約を再確認した。
当該分野での国際的なイニシアチブである、パリ協定の履行に向けた対応も進んでいる。タイ政府は、国別気候変動緩和行動(NAMA)に基づき、2020年時点でBAU比(注1)15.4%のGHG排出削減を達成したと発表した。また、2022年11月には「国が決定する貢献(NDC)」の第2改定版![]() (200KB)を国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に提出し、2030年までにGHG排出量をBAU比で30%(技術・財政支援を得られる場合、40%)削減することを目標に掲げた。
(200KB)を国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に提出し、2030年までにGHG排出量をBAU比で30%(技術・財政支援を得られる場合、40%)削減することを目標に掲げた。
なお、NDCには、カーボンプライシングに関する記述はないものの、同月に改定された長期低排出発展戦略(LT-LEDS)![]() には、将来的に制度導入することを想定した言及がある。タイでも、長期的に排出量ネットゼロを達成する方法の1つとして、カーボンプライシングを認識している。また、LT-LEDSでは、GHG削減を実現する上でカギになる取り組みを紹介している。例えば、炭素市場として「マーケットインフラストラクチャー」「再生可能エネルギー(再エネ)およびカーボンクレジット取引プラットフォーム」を構築することなどを挙げている。
には、将来的に制度導入することを想定した言及がある。タイでも、長期的に排出量ネットゼロを達成する方法の1つとして、カーボンプライシングを認識している。また、LT-LEDSでは、GHG削減を実現する上でカギになる取り組みを紹介している。例えば、炭素市場として「マーケットインフラストラクチャー」「再生可能エネルギー(再エネ)およびカーボンクレジット取引プラットフォーム」を構築することなどを挙げている。
カーボンクレジット「T-VER」取引が活発に
「マーケットインフラストラクチャー」としては、タイ国内で削減したGHGをボランタリークレジットとして取引できる「タイ自主的排出量削減プログラム(T-VER)」が具体的な取り組み例になる。T-VERは、タイ温暖化ガス管理機構(TGO)が運営している。2024年3月時点で164件のプロジェクトが認証され、約1,812万トン(CO2換算)のGHGがクレジット化されている。実際に取引されたのは約326万トン(CO2換算)で、金額としては2億9,200万バーツ(約12億2,640万円、1バーツ=約4.2円)相当になっている。
T-VERの取引高は、2022年に飛躍的に拡大した。取引量は前年比4.2倍の118万7,300トン、取引金額は13.2倍の1億2,800万バーツに上った。2023年は、量で前年比27.8%減の85万7,100トン、金額も6,832万バーツと縮小したが、それでも取引量は2021年比約3倍に当たる。市場として大きく成長したと評価して良いだろう(図1参照)。T-VERの平均取引価格も、2018年時点の1トン当たり21.36バーツが、2022年108.22バーツ、2023年は79.71バーツと上昇がみられる。
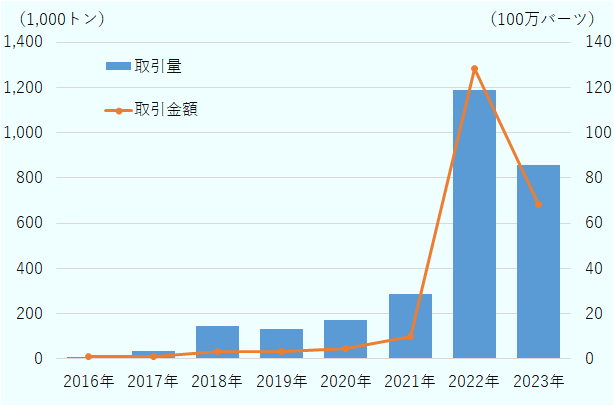
出所:TGOウェブサイトからジェトロ作成
T-VERの仕様や取引方式も、多様化している。仕様としては、2014年に開発された「スタンダードT-VER」に加え、2022年から「プレミアムT-VER」を導入した。これは外国企業などとの取引を念頭に、国際標準により適合するよう改良されたものである。また、2022年から、直接販売方式(OTC:Over the counter)だけでなく、「FTIX」を利用できるようになった。
FTIXとは、タイ工業連盟(FTI)がTGOと共同開発し、運営する新規取引プラットフォームだ。末尾のXは、エクスチェンジを意味する。LT-LEDSの中で言及された「再エネおよびカーボンクレジット取引プラットフォーム」は、このFTIXを指す。売り手と買い手が直接売買するOTC方式に比べ、需給バランスに応じてリアルタイムに売買できる点で優位性がある。なお、取引を想定している対象は、主に(1)カーボンクレジット(CC)、(2)再エネ(RE)、(3)再エネ証書(REC)だ。将来的には、名称どおりRECやREも取引可能になる予定だ。
炭素税導入に向けて進展
炭素税についても、導入の動きがある。タイ天然資源・環境省は2023年8月、気候変動対策の中核部局として気候変動環境局(CCE)を設立した。CCEは、「気候変動対策法」(CO2排出量削減に向けた包括的法令)の草案を作成している。同草案にはカーボンクレジット取引に関する規制や、炭素税の仕組みなどが盛り込まれる可能性があるという(4月2日付「バンコク・ポスト」紙)。
炭素税については、以前から財務省物品税局が導入を検討しているという現地報道がある。石油製品などを対象にCO2排出量に応じて税率を設定する案や、(2)製油所のCO2排出量が物品税局の規定を超えた場合に、超過分に課税する案、などが取り沙汰されている。
タイ開発研究所(TDRI)のソムキアット・タンキッワーニット所長は2023年10月31日付レポート「タイの低炭素経済・社会への転換」![]() で、GHG排出削減に向けタイが包括的戦略を欠いていると指摘している。その上で、GHG排出削減に最も有効な方法の1つとして、カーボンプライシングを紹介している。炭素税とETSの長所と短所を挙げた上で、制度的に取り組みやすいのは炭素税という結論を示している。その最大の理由は、物品税徴収という既存の仕組みを使えることだ。ETSを導入するには、炭素取引のための新たなインフラが必要になる。これは、炭素削減に取り組み始めたばかりの国にとって、簡単でないという。
で、GHG排出削減に向けタイが包括的戦略を欠いていると指摘している。その上で、GHG排出削減に最も有効な方法の1つとして、カーボンプライシングを紹介している。炭素税とETSの長所と短所を挙げた上で、制度的に取り組みやすいのは炭素税という結論を示している。その最大の理由は、物品税徴収という既存の仕組みを使えることだ。ETSを導入するには、炭素取引のための新たなインフラが必要になる。これは、炭素削減に取り組み始めたばかりの国にとって、簡単でないという。
同レポートで、ソムキアット所長は炭素税について、(1)輸出炭素税、(2)エネルギー炭素税の2つを提案した。前者は、EUなどCBAMを実施している国へ輸出する場合に、輸入国の炭素価格と同等の税金を課すものだ。狙いは、輸入国(EU側)に国境炭素価格を支払うのではなく、輸出国のタイ側で課税することにある。後者は、化石燃料を使う発電所や石油精製業者、輸入業者に課す炭素税だ。これは物品税局が既に提案している仕組みで、排出量削減を進める上での動機付けになる。
背景にEUのCBAM
タイ政府が低炭素化やカーボンプライシングへの取り組みを急ぐ背景には、EUのCBAM設置がある。EUは2022年末、CBAMに関する規則案をめぐって暫定的な政治合意に達した。この時点で商務省は、タイの事業者に対して早々にGHG排出量の算定などの対応を図るよう警鐘を鳴らした。
在タイ日本大使館とジェトロは2023年9月、バンコク都内でCBAMに関するセミナーを実施した。登壇したグリーン&ブループラネット・ソリューションズの梅山研一氏(ジェトロ・コーディネーター)と同社のレッジーナ・ルーテゴード氏によると、タイの対EU輸出(2022年)のうち、CBAM対象製品が占める割合はわずか0.8%、EU以外を含む輸出全体の中では0.07%にすぎないという。しかし、CBAMには将来的に、有機化合物やポリマーが対象製品に追加される可能性がある。レッジーナ氏は「プラスチック製品が含まれた場合、タイ企業への影響は必至」と述べた。
現状では、当地日系企業への影響は限定的と言える。在タイ工場からEU向けにCBAM対象製品を輸出している例は限られ、直接的に大きな影響を被るケースは聞かれない。ただし、将来的に、日本企業が多く輸出する市場で同様の措置が実施された場合には話が違ってくる。例えば、米国やオーストラリア、ASEAN域内などに波及すると、影響が大きい。目下、CBAMへの対応に一定の関心が集まっているのは、そうした理由からだ。
日系企業の取り組みは、まだ限定的
ジェトロが2023年8~9月に実施した「海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」によると、アンケートに回答した在タイ日系企業のうち、何らかの脱炭素化(GHG排出削減)に取り組んでいる企業は36.2%だった。これは、在マレーシア(45.4%)や在インドネシア(44.3%)の日系企業より低く、ASEAN平均(39.2%)をも下回った。
もっとも、企業規模(注2)や業種によって差があるのが実態だ。在タイ日系企業でも大企業は56.2%が取り組んでいるのに対し、中小企業は25.4%と低い(図2参照)。また、製造業の大企業は67.7%に上る一方、非製造業の中小企業は19.9%だ。製造業の「電気・電子機器」「輸送機器部品」「化学・医薬」は50%~60%に達する一方、商社・卸売業は26.1%と低い。
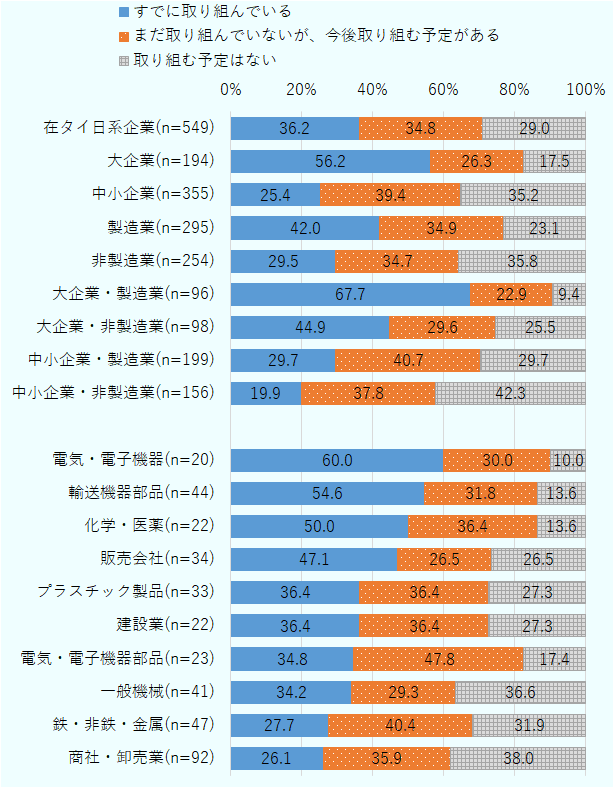
注:回答数が20社以上ある業種を抽出。
出所:ジェトロ「海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」
2022年の当該調査では、脱炭素化に関する具体的な取り組み内容に関する設問も盛り込まれた。その結果によると、「市場から排出削減のクレジットを購入」(または検討)している在タイ日系企業は、有効回答296社のうち4.1%にとどまった。「省エネ・省資源化」(65.5%)や「再エネ・新エネ電力の調達」(47.6%)といった比較的ポピュラーな取り組みに比べ、クレジットを活用する企業はまだ限られていることが分かる。
しかし昨今では、日系企業・タイ企業を問わず、脱炭素やCBAM対応は新たな競争力につながるという考え方が広まってきた。これに伴い、カーボンニュートラルに資する技術へのニーズが高まっている。例えば、ジェトロ・バンコク事務所が取りまとめた「カーボンニュートラル達成に向けたサステナブルビジネス集」掲載日系企業等が持つ技術への引き合いが増えている。当事務所は「サステナブル・ビジネスデスク![]() 」でのサポートを強化中だ。関連する企業ごとの課題に応じ、個別に支援したり情報提供したりしている。この取り組みは、2023年12月にタイ投資委員会(BOI)が東京で主催した日タイ投資フォーラム
」でのサポートを強化中だ。関連する企業ごとの課題に応じ、個別に支援したり情報提供したりしている。この取り組みは、2023年12月にタイ投資委員会(BOI)が東京で主催した日タイ投資フォーラム![]() でも紹介された。なお同フォーラムには、齋藤健経済産業相、セター首相、ナリット・タードサティーラックBOI長官などが出席し、タイ政府が日系企業に投資を期待する重要分野の1つがカーボンニュートラル分野ということも確認された。
でも紹介された。なお同フォーラムには、齋藤健経済産業相、セター首相、ナリット・タードサティーラックBOI長官などが出席し、タイ政府が日系企業に投資を期待する重要分野の1つがカーボンニュートラル分野ということも確認された。
- 注1:
- 2005年を基準年とし、追加的な対策を講じなかった場合のGHG排出量。
- 注2:
- 当該調査でいう企業規模(大企業、中小企業の別)は、日本本社(親法人)に基づく。日本の中小企業基本法の定めに該当する場合、「中小企業」とした。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・バンコク事務所
北見 創(きたみ そう) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部アジア大洋州課、大阪本部、ジェトロ・カラチ事務所、アジア大洋州課リサーチ・マネージャーを経て、2020年11月からジェトロ・バンコク事務所で広域調査員(アジア)として勤務。




 閉じる
閉じる






