トランプ政権下で「ビジネスと人権」政策はどう変わるのか(米国)
2025年5月9日
米国で2025年1月に発足した第2次トランプ政権は、気候変動対策、エネルギー政策、連邦政府職員の雇用・労働慣行をはじめとして、さまざまな分野でバイデン前政権からの方針転換を推進している。そのバイデン前政権が積極的に取り組んだ、いわゆる「ビジネスと人権」に関連する通商措置も、第2次トランプ政権下で方針転換があるのだろうか。第2次トランプ政権下では、バイデン前政権下よりも、人権関連の通商措置の優先順位が低くとどまるとの予想はあるが、中国に対抗して米国の経済的利益を確保する手段の1つとして、ウイグル強制労働防止法(UFLPA)を筆頭に、措置の執行は継続されるだろう。従って、在米日系企業や、米国に自社商品を輸出する日本企業は、引き続き適切な人権デューディリジェンス(DD)の実行が求められる。本稿では、過去8年間(第1次トランプ政権およびバイデン前政権)の人権関連の通商措置を振り返った上で、第2次トランプ政権発足後の3カ月弱の措置動向をまとめ、今後の方向性を見極める上での注目点を解説する。
第1次トランプ政権は、UFLPAやRRMの土台を整備
米国の過去8年間の人権関連の政策や措置を振り返ると、その目的は大まかに、(1)国際的に基本的人権の擁護を推進することで、米国の尊重する価値観に基づいた世界秩序を構築すること、(2)強制労働などを用いて生産された外国製品の米国への輸入の取り締まりを通じて、基本的人権を保障する米国の労働者・産業との競争条件を平準化し、米国の経済的利益を確保すること、の2点があると考えられる。
第1次トランプ政権(2017~2021年)の政策や措置をこれに照らせば、前者の国際的な人権の擁護の推進に関しては、消極的だったとは言い切れないまでも、限定的だったと評価できる。例えば、第1次トランプ政権は2018年6月に、国連人権理事会の組織改革に向けて取り組むことなく、脱退に踏み切った。ニッキー・ヘイリー元国連大使は当時、脱退の理由に、米国と価値観が異なる国が理事国を務める構造や、イスラエルに批判的な決議が多いことなどを挙げ、「国連人権理事会は人権侵害国の擁護者であり、政治的偏見の温床だ」などと厳しく非難していた。第1次トランプ政権は、気候変動対策の国際枠組みのパリ協定を脱退したことなどからも、人権分野に限らず、多国間連携の仕組みそのものを生産的と見なしていなかったことが伺える。
一方で、後者の目的を達成する上でのツールとして、第1次トランプ政権は人権関連の輸入規制措置を積極的に講じてきた実績もある。具体的には、1930年関税法307条に基づいて、強制労働の関与が疑われる外国製品に対して26件の「違反商品保留命令(Withhold Release Order:WRO)」または「認定(Finding)」を発令し、これら物品の米国への輸入を禁止した。関税法307条は、強制労働、児童労働、囚人労働などを用いて生産された物品の米国への輸入を原則禁止する法律だ。国土安全保障省(DHS)傘下の税関・国境警備局(CBP)が、強制労働などの関与が推定される物品についてWRO・認定を発令し、米国への輸入を差し止める(注1)。第1次トランプ政権が発動したWRO・認定26件のうち、13件(注2)が中国の企業・地域・製品を対象にしたものだ。第1次トランプ政権が「現状を変更する勢力(the revisionist powers)」の1つと位置付けた中国に対抗し、米国の経済的利益を確保する目的があったことも推定できる。政権交代直前の2021年1月には、中国・新疆ウイグル自治区が関与する全ての綿製品・トマト製品を対象にWROを発令した。これは、地理的区分に従って対象を広範に拡大した初めての措置で(2021年1月15日付ビジネス短信参照)、バイデン前政権下で成立したUFLPAの土台になる措置だったと言えよう(注3)。
また、第1次トランプ政権は「米国第一主義(America First Policy)」の経済・通商政策を掲げ、既存の通商協定の見直しも図った。具体的には、2017年1月に日本も締約国に加わっていた環太平洋パートナーシップ(TPP)協定から離脱した。また、北米自由貿易協定(NAFTA)を再交渉し、2020年7月に米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を締結・発効した。このうち、USMCAの人権に関連する文脈では、(1)関税法307条と同様に、強制労働が関与する物品の輸入を禁止する法令をカナダとメキシコが採用することを新たに規定した。この結果、カナダは2020年7月、メキシコは2023年5月に、強制労働が関与する物品の輸入を禁止する規制をそれぞれ導入した(注4)。また、(2) USMCA協定下に、労働問題の紛争解決制度「事業所特定の迅速な労働問題対応メカニズム(RRM)」を創設した。RRMは、締約国内に所在する企業の事業所単位で労働権侵害の有無を判定する手続きだ(注5)。労働権侵害の事実が確認されれば、当該事業所製品に対するUSMCA特恵措置の適用停止などの罰則が科され得る。RRM創設には当時野党だった民主党の働きかけが大きかったとされる。当時の議会構成は上院で共和党が多数派、下院は民主党が多数派のねじれ構造であり(注6)、協定批准法案の可決には民主党の同意が不可欠だった。伝統的にリベラル派で労働者の権利を重んじる民主党議員からの同意を取り付ける条件として、RRMを含む労働章や環境章を付属書ではなく協定本文に盛り込み、執行メカニズムを策定した経緯がある(注7)。なお、第1次トランプ政権がRRMを通じてメキシコ政府に労働権侵害の事実確認要請を行うことはなく、その最初の活用事例はバイデン前政権に持ち越されることになった。
このほか、輸入規制や通商協定以外の措置もある。例えば、人権侵害に加担した疑いのある企業・個人を、輸出管理規則(EAR)の対象になる事業体リスト(エンティティー・リスト)や、資産凍結や取引禁止など経済制裁の対象になる事業体リスト(SDNリスト)に追加することが、第1次トランプ政権、バイデン前政権下で随時行われた(注8)。
バイデン前政権はRRMとUFLPAを積極的に活用
バイデン前政権(2021~2025年)は、政権発足直後から国際的な人権の擁護の推進に向けて積極的な姿勢を打ち出し、2021年2月に国連人権理事会への復帰を表明した。また、ビジネスと人権の観点では、「労働者中心の通商政策(Worker-Centered Trade Policy)」を掲げ、国際的な労働者の権利や基本的人権の擁護に積極的に取り組んだ。米国通商代表部(USTR)はバイデン前政権の最終盤の2024年12月、労働者中心の通商政策の実績を振り返ったファクトシート![]() で、(1) RRMを通じたメキシコの労働問題の解決、(2) UFLPAに基づく輸入規制の執行、(3)関税法307条に基づく輸入規制の執行の3つの措置を強調している。各ツールの運用実績は次のとおりだ。
で、(1) RRMを通じたメキシコの労働問題の解決、(2) UFLPAに基づく輸入規制の執行、(3)関税法307条に基づく輸入規制の執行の3つの措置を強調している。各ツールの運用実績は次のとおりだ。
(1)RRM
RRMに基づく米国政府からメキシコ政府に対する労働問題の事実確認要請は、2021年5月のメキシコの自動車工場の案件を皮切りに、バイデン前政権下で延べ32件に及んだ。自動車・自動車部品工場における労働問題を対象にした案件が多かったが、金属採掘施設、加工食品工場、コールセンターまで、対象施設の産業分野は幅広く及んだ。また、メキシコに拠点を有する外国企業の施設も対象となり、日本企業がメキシコに出資・設立した施設に関連する案件も複数みられた。なお、バイデン前政権が発動したRRM全32件のうち、23件は是正措置が講じられるなどして解決したものの、3件は現在も事実確認や是正措置を履行中、6件は米国政府がメキシコ政府の事実確認結果や是正措置内容を不服としてRRMに基づく労働問題の紛争解決パネル(注9)に持ち込む結果となっている。このうち、1件は米国側の訴えを退ける裁定が下されたが、5件は現在も係争中だ。
(2)UFLPA
2021年12月に成立、2022年6月に施行した法律で、同法に基づいて、バイデン前政権は延べ約37億ドル相当、約1万5,000件の貨物の米国への輸入を差し止めた(2025年1月末時点、注10)。UFLPAでは、(1)新疆ウイグル自治区で物品を採掘・生産・製造した場合、または(2) UFLPAのエンティティー・リストで指定されている企業・団体が物品の生産などに関与した場合、強制労働の利用があるとみなし、関税法307条を根拠に米国への輸入を禁止する。日本を含めた第三国からの米国への輸入でも、これらに該当する中間財などを使用した物品は、同法に基づく輸入差し止めなどの取り締まりの対象となる。執行対象は全ての産業分野に及ぶが、DHSは、アパレル、綿・同製品、ポリシリコンを含むシリカベース製品、トマト・同製品、アルミニウム、ポリ塩化ビニル、水産品の7分野を優先執行分野と明示している。なお、バイデン前政権下で差し止められた貨物の39%は、輸入者の申し立てに基づいて輸入を許可されているものの、57%は否認、4%は保留(注11)となっている。
(3)関税法307条
バイデン前政権下の関税法307条に基づくWRO・認定の発令件数は16件で、このうち11件が、2022年6月のUFLPA施行前に発令した事案だ。2022年以降は、強制労働などを理由とした輸入規制措置全体の執行金額・件数のうち、UFLPAに基づく措置が大半を占めることから、UFLPA施行を境に、米国の人権関連の輸入規制は、関税法307条に基づく措置からUFLPAに基づく措置へと、執行の重点がシフトしたことがうかがえる。とはいえ、関税法307条に基づく措置の執行が停止したわけではなく、2024年4月の中国企業に対するWROの発令に当たって、CBPを所管するDHS高官は「今回のCBPの行動は、われわれが全ての強制労働に対処する法律を強力に執行することを示すもの」と述べており、UFLPAだけでなくWROも利用して強制労働に対処していく姿勢をあらためて示唆していた。
これら3つのツールに加えて、バイデン前政権はビジネスと人権に関する有志国連携のスキームの立ち上げにも取り組んだ。具体的には、2021年12月にバイデン前政権が主催した民主主義サミットで、「輸出管理と人権イニシアチブ(ECHRI)」の創設を発表した。ECHRIは、監視カメラなどの人権侵害に用いられる可能性のあるデュアルユース品目の輸出管理を有志国で協力する枠組みで、日本を含め24カ国が参加している(2023年3月31日付ビジネス短信参照)。2022年5月にバイデン前政権が主導して発足した、日本や米国など14カ国が参加する「インド太平洋経済枠組み(IPEF)」では、サプライチェーンへのリスクとなり得る労働権に関する課題を特定する労働諮問委員会を創設したほか、個別の労働権侵害事案に関する申立制度を構築することを決定している。
第2次トランプ政権は既存の路線をおおむね踏襲か
2025年1月に発足した第2次トランプ政権のこれまでの人権関連の外交・通商政策の動向を振り返れば、ドナルド・トランプ大統領は、米国国際開発庁(USAID)を通じた人道支援目的を含む対外援助プログラムへの資金拠出停止(2025年1月28日付ビジネス短信参照)や、国連人権理事会を再脱退する大統領令を発令しており(2025年2月6日付ビジネス短信参照、注12)、第1次政権に引き続き、人権擁護に向けた国際協調への取り組みは限定的なものにとどまりそうだ。
人権関連の通商措置に限定して政権発足後の3カ月弱の実績をみると、RRM、WRO、UFLPAの3ツールの執行は継続している様子がうかがえる(表参照)。このうち、2025年4月のWRO発動に際しては、CBP貿易局エグゼクティブ・アシスタント・コミッショナー代行のスーザン・トーマス氏が、「サプライチェーンでの強制労働と闘うことは、規則を順守する米国企業が公平に競争できる環境を確保する取り組みの1つだ」と述べており、WROを外国企業と米国企業の競争条件の平準化に向けたツールと捉える姿勢がみられる。
また、RRMを通じたメキシコへの労働権侵害の事実確認要請は、前述のとおり第1次トランプ政権下のUSMCA締結時に創設した制度ながら、第1次政権下での発動実績はなかった。そのため、2025年4月のメキシコの自動車部品工場に対するRRM発動は、トランプ政権で初めての事例ということになる。少なくともRRMに関しては、第1次政権に比べ第2次政権の方が前向きと言えよう。なお、バイデン前政権が設置した、自動車部品工場などでの労働問題を巡るRRMに基づく紛争解決パネルが、第2次トランプ政権への「置き土産」として5件残されている(注13)。これらの案件に対するパネル裁定結果に関して、第2次トランプ政権がどのような反応を見せるのか、同政権のビジネスと人権に関する一般的なスタンスを確かめる上で注目される。
|
通商 措置 |
執行 月日 |
措置内容 | 対象企業所在国・対象製品輸出元国 | 対象製品・産業分野 | 参考記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| RRM | 4月3日 | 対象施設の労働問題の事実確認要請 | メキシコ | 自動車部品 | 2025年4月4日付ビジネス短信参照 |
| 4月16日 | 対象施設の労働問題の事実確認要請 | メキシコ | アルミニウム | 2025年4月18日付ビジネス短信参照 | |
| WRO | 3月17日 | 対象製品の輸入差し止め命令の解除 | ドミニカ共和国 | 砂糖 | 2025年3月24日付ビジネス短信参照 |
| 4月2日 | 対象製品の輸入差し止め命令の発令 | 韓国 | 塩 | 2025年4月7日付ビジネス短信参照 | |
| UFLPA | 2月1日~3月31日 | 1,109万ドル相当の1,403件の貨物の輸入差し止め | 中国、マレーシア、ベトナムなど | 自動車・航空宇宙、衣料・履物・織物など | — |
出所:USTRおよびCBP公表資料からジェトロ作成
UFLPAの執行は今後も継続する可能性が高い。第2次トランプ政権は、政権発足初日の1月20日にジョー・バイデン前大統領が発表した78本の行政命令を撤回する大統領令![]() を発令した。3月14日には同様に18本の行政命令を撤回する大統領
を発令した。3月14日には同様に18本の行政命令を撤回する大統領![]() を発令した。国連人権理事会の再脱退なども含め、トランプ大統領はバイデン前大統領の「レガシー」の排除に執着する様子もうかがえる。しかし、UFLPAはバイデン前政権下で成立した法律にもかかわらず、第2次トランプ政権および連邦議会上下両院で多数派を占める共和党がUFLPAの存在を問題視する様子はこれまでにみられない。これは、前述のとおり、(1) UFLPAが第1次トランプ政権下で発令された新疆ウイグル自治区関連の製品に対するWROを通じて道筋が作られた法律であることや、(2) UFLPAが上下両院での全会一致により成立した経緯があること、(3)米国の対中強硬路線には、ワシントンで超党派の意見一致があること、などが背景にあるためと考えられる。特に、第2次トランプ政権のマルコ・ルビオ国務長官は、UFLPA成立を当時上院で主導した議員の1人だった(注14)。さらに、第2次トランプ政権は、UFLPAの執行戦略の改訂、UFLPAエンティティー・リストの追加、UFLPA優先執行分野の追加などの機能を担う省庁横断委員会の強制労働執行タスクフォース(FLETF)のトップに、DHSの高官を任命しており、UFLPAの運用体制は維持されているもようだ(注15)。
を発令した。国連人権理事会の再脱退なども含め、トランプ大統領はバイデン前大統領の「レガシー」の排除に執着する様子もうかがえる。しかし、UFLPAはバイデン前政権下で成立した法律にもかかわらず、第2次トランプ政権および連邦議会上下両院で多数派を占める共和党がUFLPAの存在を問題視する様子はこれまでにみられない。これは、前述のとおり、(1) UFLPAが第1次トランプ政権下で発令された新疆ウイグル自治区関連の製品に対するWROを通じて道筋が作られた法律であることや、(2) UFLPAが上下両院での全会一致により成立した経緯があること、(3)米国の対中強硬路線には、ワシントンで超党派の意見一致があること、などが背景にあるためと考えられる。特に、第2次トランプ政権のマルコ・ルビオ国務長官は、UFLPA成立を当時上院で主導した議員の1人だった(注14)。さらに、第2次トランプ政権は、UFLPAの執行戦略の改訂、UFLPAエンティティー・リストの追加、UFLPA優先執行分野の追加などの機能を担う省庁横断委員会の強制労働執行タスクフォース(FLETF)のトップに、DHSの高官を任命しており、UFLPAの運用体制は維持されているもようだ(注15)。
第2次トランプ政権でUFLPAの運用の変化に注目
UFLPAの実務に詳しい米国の法律事務所によると、CBPがUFLPAに基づいて輸入を差し止めた場合も、物品の原材料が同法に抵触するとみなされたのか、または、物品のサプライヤーが同法に抵触するとみなされたのかなど、当局が問題視した事項は輸入者に具体的には通知されないもようだ。また、差し止め後に輸入が許可されているのは、新疆ウイグル自治区が物品に関与しないとして、輸入者がCBPに「適法性審査」を申し立てた結果と推測されるが、具体的な事例は公表されていない。こうしたことから、企業の取り組みの拠り所となる情報が不透明で、法令順守を困難にしているという指摘がある(注16)。バイデン前政権下では、UFLPAの執行データ![]() の公表を通じて執行対象貨物の原産国・地域や産業分野を公表してきた。また、適法性審査に関するガイダンスの追加公表や、UFLPAエンティティー・リストの追加指定を通じた、米国政府が問題視するサプライヤー情報の更新などがみられた。第2次トランプ政権下で、執行の透明性や信頼性をより高める追加資料などが公開されるか、FLETFを中心とした当局の姿勢の変化も注目されよう。
の公表を通じて執行対象貨物の原産国・地域や産業分野を公表してきた。また、適法性審査に関するガイダンスの追加公表や、UFLPAエンティティー・リストの追加指定を通じた、米国政府が問題視するサプライヤー情報の更新などがみられた。第2次トランプ政権下で、執行の透明性や信頼性をより高める追加資料などが公開されるか、FLETFを中心とした当局の姿勢の変化も注目されよう。
第2次トランプ政権発足後の2025年2月~3月のUFLPAの執行データ(4月14日更新版)を見ると、CBPはUFLPAに基づいて、約1,109万ドル相当の1,403件の貨物の輸入を差し止めている。一方で、輸入を差し止めた貨物の月単位での金額と件数は、いずれもバイデン前政権の最終盤から減少している(図参照)。首都ワシントンにあるシンクタンクの米国の通商政策や人権政策に詳しい研究者は、トランプ政権が意図的にUFLPAの執行態度を緩めた兆候は見て取れないが、トランプ政権がバイデン前政権と同様の執行水準を維持したいと考えても、実際にはCBPの執行体制が維持できていない可能性を指摘する(注17)。実業家のイーロン・マスク氏の率いる「政府効率化省(DOGE)」が推し進める連邦政府機関の予算・人員削減の取り組みにより、執行体制が縮小した可能性や、トランプ政権が優先課題に掲げる不法移民対策強化に向けて、CBPのリソースが税関業務から国境管理業務に移行した可能性があるというのがその理由だ。
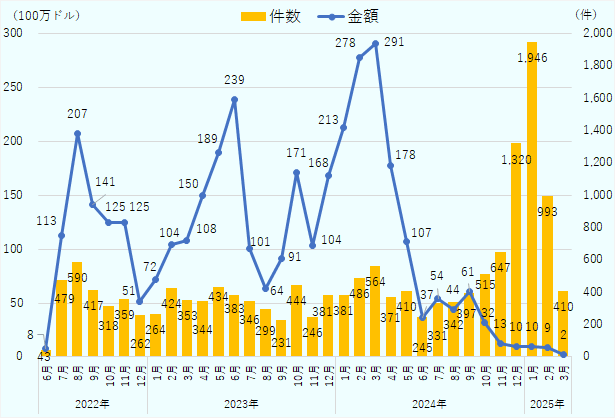
出所:CBP公表資料からジェトロ作成
なお、UFLPAの執行データの数値は毎月更新されている。第2次トランプ政権下での執行金額と件数の減少傾向が今後も持続するか要注目だ。同時に、第2次政権下でどの国・地域のどの産業分野の貨物に対して重点的に執行が及ぶかにも要注目だ。ジェトロの在米日系企業に対するアンケート調査「2023年度 海外進出日系企業実態調査(北米編)」(2023年9月実施)では、社内の人手や資金が不足していることなどが、企業が人権DDを実施する際の課題として多く挙げられた。人権DDの実施に当たっては、人的・経済的リソースの制約があること、また、人権リスクは膨大にあり得ることなどを踏まえ、サプライチェーンにおけるリスクが最も深刻と想定される部分などから優先的に取り組むことが肝要になる(注18)。この優先度を考慮するに当たっては、同執行データを通じた最新の動向の把握は、米国政府が優先度を高く位置付ける国・地域や産業分野を推し量るために、重要な参考資料になるだろう。
- 注1:
- WROが発令された物品が差し止められた場合、輸入者は当該物品を米国へ輸入せずにそのまま他国へ輸出するか、WROの発令に異議を申し立てることができる。当該物品に強制労働などの関与が正式に認定(Finding)された場合、当該製品は押収・没収される。2025年4月3日時点で51件のWROが発令され、9件が認定されている。
- 注2:
- ただし、台湾の4件を含まない。
- 注3:
- なお、第1次トランプ政権の関税法307条に基づくWRO・認定の発令の積極的な発動に先立って、執行強化に向けた規則面・体制面の整備が進められてきた。具体的には、2016年2月に成立した「貿易円滑化・貿易執行法(TFTEA)」で、以前は強制労働などが関与する物品でも、同等の物品が国内で生産されていない、または国内での生産能力が国内需要を満たしていない場合には執行対象外とするとしていた同条の例外規定が削除された。また、2016年4月にCBPに強制労働などが関与する物品の輸入規制の措置執行などに取り組む貿易執行作業部会(Trade Enforcement Taskforce)が設立され、2018年1月に同作業部会がCBP貿易局内の強制労働部(Forced Labor Division)に再編された。
- 注4:
- ジェトロ調査レポート「サプライチェーンと人権」に関する法制化動向(全世界編)を参照。
- 注5:
- ただし、米国・メキシコ間およびカナダ・メキシコ間のみで、米国・カナダ間にはRRMは設けられていない。
- 注6:
-
議席構成は、次のとおり。
- 上院:共和党53議席、民主党47議席(民主党会派の未所属2議席含む)。
- 下院:共和党197議席、民主党233議席、無所属1議席、欠員4議席。
- 注7:
- 第1次トランプ政権が離脱したTPPでは、オバマ元政権の主導で労働章が協定本文に盛り込まれていた。なお、米国の離脱後、日本を含む11カ国によりTPPを基礎として2018年12月に発効した「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)」でも、労働省は協定本文に引き継がれている。
- 注8:
- ジェトロ調査レポート「サプライチェーンと人権」に関する法制化動向(米国編)を参照。
- 注9:
-
USMCAの紛争解決パネル、RRMに基づく労働問題の紛争解決パネルの概要は、ジェトロ「USMCA紛争解決制度の運用状況
 (444KB)」参照。
(444KB)」参照。
- 注10:
- 第2次トランプ政権下の2025年1月20~31日の執行実績を含む。
- 注11:
- 輸入者は、CBPの差し止め通知から30日以内に異議申し立てが可能。差し止め後に輸入が許可された物品は、新疆ウイグル自治区が関与しないとして「適法性審査」を申し立てた結果と推測される。適法性審査については、ジェトロ調査レポート「ウイグル強制労働防止法『適法性審査』の追加ガイダンス(暫定仮訳)」を参照。
- 注12:
-
国連人権理事会の再脱退の理由には、「国連人権理事会の反ユダヤ主義の推進や人権侵害の加害者の擁護」などを挙げており、おおむね第1次トランプ政権での脱退理由と同様だった。なお、同大統領令の発令と同日の2月4日、トランプ大統領はイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と首脳会談を実施している。
また、トランプ大統領は、2月7日に南アフリカ共和国における人権状況への対応措置を関係閣僚に指示する大統領令 を発令した。発令理由には、同国政府による同国内少数民族の財産収用に関する措置に加えて、同国政府が国際司法裁判所でイスラエルを非難したことを挙げた。
を発令した。発令理由には、同国政府による同国内少数民族の財産収用に関する措置に加えて、同国政府が国際司法裁判所でイスラエルを非難したことを挙げた。
- 注13:
- (1)メキシコのコールセンターに関する事案(2024年4月17日付ビジネス短信参照)、(2)メキシコの金属採掘施設に関する事案(2024年12月16日付ビジネス短信参照)、(3)~(5)メキシコの自動車部品施設などに関する事案(2024年12月20日付ビジネス短信参照)。
- 注14:
-
ルビオ国務長官は2025年3月に、タイ政府高官らに対してビザ制限措置
 を発表した。これは、タイ政府が2025年2月、同国に滞在していたウイグル族の40人を中国に強制送還したことを受けた措置だった。
を発表した。これは、タイ政府が2025年2月、同国に滞在していたウイグル族の40人を中国に強制送還したことを受けた措置だった。
- 注15:
- DHS次官補(通商・経済安全保障担当)のソハン・ダスグプタ氏がFLETFトップに任命されていたが、ダスグプタ氏は2025年4月にDHS次官補を解任された(米国政治専門誌「ポリティコ」4月23日)。記事執筆時点で、DHS次官補(国際問題担当)のクリストファー・プラット氏がFLETFトップに任命されている。
- 注16:
- ジェトロのヒアリングに基づく(2025年3月)。
- 注17:
- ジェトロのヒアリングに基づく(2025年3月)。
- 注18:
-
人権DDの実施に関して、日本政府は2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
 」を公表している。また、2023年4月に同ガイドラインの実務参照資料
」を公表している。また、2023年4月に同ガイドラインの実務参照資料 を公表している。
を公表している。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ニューヨーク事務所〔戦略国際問題研究所(CSIS)日本部客員研究員〕
葛西 泰介(かっさい たいすけ) - 2017年、ジェトロ入構。対日投資部、ジェトロ北九州事務所、調査部米州課を経て、2024年2月から現職。






 閉じる
閉じる





