台湾企業の生産能力配置の展望
ICT産業のサプライチェーン(2)
2025年5月14日
2025年1月の米国のトランプ第2次政権発足以降、米国と中国、あるいは米国とカナダ、メキシコなどとの間で、矢継ぎ早に追加関税賦課措置の応酬が発生している。これにより、日本企業は自社に関わるサプライチェーンに対する影響の分析と、その調整の検討の必要性に迫られている。
地域・分析レポート「ICT産業のサプライチェーン(1)台湾企業の動向」では、米トランプ第1次政権以降、パソコン、スマートフォン、サーバーなどを含む情報通信技術(ICT)産業では、HP、DELLといったブランド企業の戦略と、それに応じた台湾系EMS(電子機器製造受託)の生産拠点立地のメカニズムが、関連のサプライチェーンの変化に主要な役割を果たしていることを明らかにした。
本稿では、こういった観点から、台湾の公的シンクタンクの資訊工業策進会(台湾資策会)産業情報研究所(MIC)の台湾企業のサプライチェーン動向に関するデータから、パソコン、スマートフォン、サーバーのサプライチェーンの中期的動向を展望する(注1)。
脱中国が進むPCブランド企業の生産能力配置
まず、ノートパソコンのサプライチェーンの変化についてみていく。図1では、台湾系ノートPC製造企業の生産能力の配置比重の予測を示している。このデータは、前述の台湾資策会産業情報研究所(MIC)が算出した。MICが個別のブランド企業のサプライチェーンやEMSのロードマップ、各企業へのヒアリングによって、中国、非中国への生産拠点の配置方針、米国の追加関税の影響、現地政府の現地生産の要求の状況などを踏まえて算出(生産数量ベース)したものとなる。
2018年、2024年、2028年の3時点で中国、台湾、その他地域での台湾系ノートPC製造企業の生産能力の配置比重をみると、2018年まで台湾系ODM企業のノートPC生産は中国に集中しており、その生産能力(数量ベース)の配置比重は98%を超過していた(注2)。2018年に米中の追加関税賦課が激化したが、それ以前の段階では、ノートPC産業は、規模の経済による競争優位が重要なことから、中国が生産地として選ばれていたことが分かる。
その後、トランプ第1次政権が2018年以降、一部のICT関連部品を含む幅広い品目に追加関税を賦課したこともきっかけとなり、米系ブランドの中国プラスワンの生産拠点の新設が進んだ(注3)。
一方、ノートPC(完成品)については、最終的に米国側の追加関税が発動されず、生産拠点移転は限定的となった(注4)。そのため、2024年時点でも中国以外の生産能力はなお10%未満となっている。
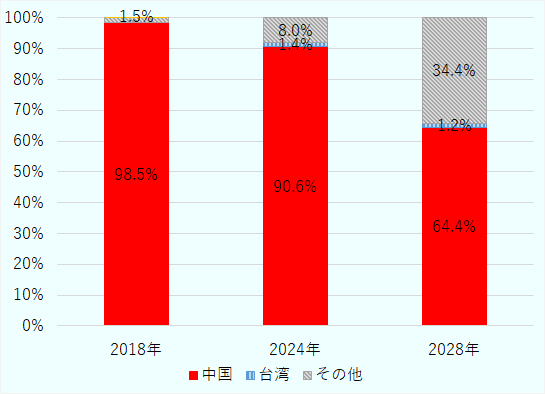
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析からジェトロ作成
MICの専門家は、2025年以降のトランプ第2次政権期では、地政学リスクが増大する中で、米系ブランド企業は自社のサプライチェーン上の企業に対し、生産拠点分散の要求を強めていると指摘する。一部企業は北米市場輸出用生産ラインの移動を先行して開始しているほか、米国系以外のブランド企業も積極的に中国以外の生産拠点を検討している状況とされる。一般的に、ブランド企業は自社のサプライチェーンの方針について、プレスリリースのようなかたちで公開はしていない。脱中国といった受け止められ方をした場合、レピュテーションリスクになるといった配慮があるものと考えられる。そのため、ブランド企業の方針については、報道やMICによる調査を基にひもといていく。
米デル・テクノロジーズ(DELL)については、2024年までに中国製半導体の使用を取りやめることを目指し、2025年にはノートPC生産量の50%を中国から移転する方針であることを複数メディアが報道している(注5)。さらに、「工商時報」(2023年3月14日付)によると、DELLは早ければ2025年から米国内市場向けノートPC製品で、中国本土での生産委託・調達を段階的に停止する。さらに、2025年末までに米国内で販売する同製品の60%、2027年までに米国内で販売する製品の100%の「脱中国化」を関連企業に要求しているとされる。
HPについては、2026年前後をめどにPC生産の過半を中国から移管すると報道されている(「日本経済新聞」2024年8月31日)。また、同社はシンガポールに、東南アジア市場を管理する「バックアップ」設計センターを設置している。これは、中国と台湾を巡る地政学リスクの低減を目指す取り組みと目されている。
EMSは、こういったブランド企業の方針を受け、ベトナム、タイ、メキシコ、インドでの生産能力増強のための投資を続々と実施している。さらに、2025年から2026年にかけてもさらなる量産が見込まれている(表1参照)。
| 国・地域 | 企業 | ノートパソコンの生産能力配置状況 |
|---|---|---|
| ベトナム | ウィストロン |
2021年Q4 第1工場生産開始。 2023年Q3ハナム第2工場計画を発表、2025年1月生産開始予定。第1工場を拡張中、2025年4月に生産開始予定。 |
| コンパル | 2022年Q4第2工場完成、生産開始。 | |
| クアンタ |
2024年Q3 生産・輸出開始。 2024年Q4 増資による生産能力拡大を発表。2025年に生産能力が年間260万台、2028年には900万台に達する見込み。 |
|
| ペガトロン | 2022年 ハイフォン工場が生産開始。 | |
| ホンハイ |
2024年Q3 借地委託建設により工場を建設、生産能力を拡大。 2024年Q4 ホンハイ傘下の富康科技がクアンチャウ工業団地にMacBookの生産ラインを新設。 |
|
| タイ | クアンタ | 既存の組み立てラインにより、2024Q1から量産。 |
| インベンテック |
タイのリース工場で量産。 2023年Q4に新工場設立発表、2025年Q1に量産開始予定。 |
|
| メキシコ | インベンテック | 生産を開始、2025年Q2はさらに量産を予定。 |
| インド | ウィストロン | 既存の拠点付近にノートパソコン生産ラインを設置、2026年1月に生産開始を予定。 |
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析、各社情報、報道からジェトロ作成
台湾系EMSのスマートフォン生産、インドとベトナムに注力
2018年前後からの米中摩擦の以前には、スマートフォン産業はその性質として、関連産業クラスター、安価な人件費、規模の経済に依存することから、スマートフォンの約9割が中国大陸で生産されていた。トランプ第1次政権では、スマートフォン(完成品)には最終的に追加関税を発動せず、生産拠点移転は限定的となっていた。一方、Appleなど一部のブランド企業がインドへの生産能力の移転目標を設定する動きが、限定的ではあるものの、出始めていた。こういった背景下、2024年現在、スマートフォンは約7割が中国で生産されている。
MICの専門家は2025年以降の見通しについて、トランプ第2次政権の政策による関税コスト増加を受け、主要ブランド企業は短期的には価格引き上げの対応をとると予想する。
ブランド企業の動向について、自社公表している情報はほとんど見当たらないが、アップルについては、全世界のスマートフォンの生産のうち、インドでの生産比率を25%まで引き上げる方針と伝えられている(「ロイター」2023年1月23日)。
こういった方針なども踏まえ、MICは2028年時点の台湾系スマートフォン企業の生産能力配置について、中国が53%(2024年比で18ポイント減)、インドが27%(同14ポイント増)、その他が20%(同4ポイント増)になると予測する(図2参照)。
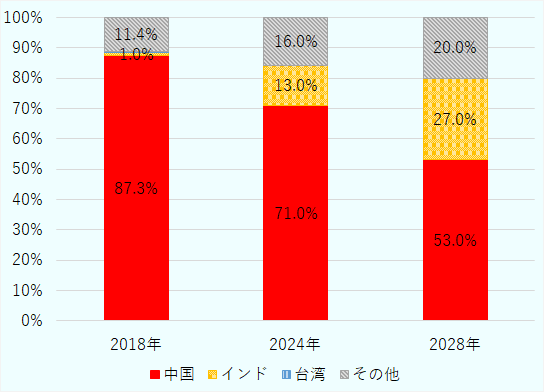
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析からジェトロ作成
報道ベースの投資事例からは、台湾系EMSがインド、ベトナムでの生産能力の強化を進めている状況がわかる(表2参照)。
一方、一部の米系ブランドは、ラックスシェア(中国)、タタ(インド)など非台湾系企業とも取引を拡大している。MICの専門家は、これまでのブランド企業はEMS間の競争を促進する、あるいは調達を分散してリスクを低減するという観点で、主要取引先のEMS以外の第2、第3のEMSを新規取引先として発掘し、提携の切り替えを断続的に行ってきたと指摘した。その上で、ラックスシェアなど非台湾系企業との取引拡大はこういった文脈の延長線上にあるとの見方を示した。
| 国・地域名 | 企業 | スマートフォンの生産能力配置状況 |
|---|---|---|
| インド | ホンハイ | カルナータカ州工場を拡張。2025年にiPhoneのインドでの組み立ての生産高比重を25%に増加させる見込み。 |
| ペガトロン | 2024年Q4に、タタグループとの合弁会社設立を決定。タタグループとペガトロンの持ち株比率はそれぞれ60%と40%。共同でiPhoneの組み立てを受注。 | |
| コンパル | コンパルとインドDixonが提携し、2024年Q4にノイダでGoogle Pixelのハイエンドバージョンのスマートフォンの生産開始を発表。Google Pixelの月生産量10万台を見込む。 | |
| ベトナム | ホンハイ |
2024年Q2に1.2億ドルを投資してバクザン省に新工場を建設。2025年Q2に生産を開始する予定。 5.5億ドルを投資してクアンニン省に新工場を2つ建設中。2027年の量産開始を予定。 |
| コンパル | タイビン省リエンハータイ工業団地に工場を建設。2.6億ドルを投資した、第1期工事が2024年末に完了。 | |
| 中国 | ホンハイ |
2024年Q3、鄭州市での新事業本部設立への投資を発表。研究開発などの機能を担う。 2025年Q2に竣工する予定、投資額は約1.4億ドル。 |
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析、各社情報、報道からジェトロ作成
2024年前後のインドへの投資事例について、ホンハイは、カルナータカ州工場を拡張し、2025年にiPhoneのインドでの組み立て生産高比重を25%に増加させる見込みとされている。ペガトロンは、2024年第4四半期(10~12月)に、タタグループとの合弁会社設立を決定し、共同でiPhoneの組み立てを受注する。コンパルは、インドDixonと提携し、2024年第4四半期に、ノイダでのGoogle Pixelのハイエンドバージョンのスマートフォンの生産開始を発表した。
ベトナムについては、ホンハイが2024年第2四半期(4~6月)に、1億2,000万ドルを投資してバクザン省に新工場を建設し、2025年第2四半期に生産を開始する予定とされる。また、コンパルはタイビン省リエンハータイ工業団地に工場を建設し、2億6,000万ドルを投資した第1期工事が2024年末に完了したとされる。
このように、2024年前後にインドとベトナムへの投資事例が目立つ一方、ホンハイが2024年第3四半期(7~9月)に、中国河南省鄭州市での研究開発などの機能を担う新事業本部設立への1億4000万ドルの投資を発表するなど、中国での新たな動きもみられた。
AIサーバーでは米国での組み立ても視野に
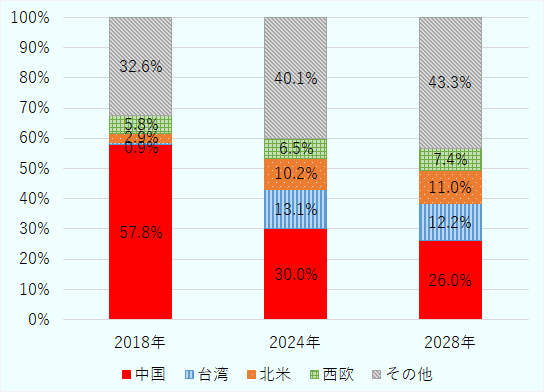
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析からジェトロ作成
トランプ第1次政権期には、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)が締結され、台湾のEMSは米国市場向けの製品ラインをメキシコに移転し、関税負担を削減してきた。その結果、メキシコは関税優遇、最終顧客までの距離の近さ、優良な労働力などの条件を具えた、台湾企業にとって重要なサーバーの生産地となった。
また、米国がクリーンネットワークプログラム(アメリカの通信ネットワークから中国の影響力を排除する仕組み)などで中国企業製品を規制したことに加え、新型コロナウイルス禍でも台湾では生産が比較的安定的にできたことで、台湾での生産も大きく増加した。その結果、2018年時点で中国での生産比率が57.8%、台湾が0.9%、北米が2.9%だったものが、2024年時点では中国が30.0%(2018年比で27.8ポイント減)、台湾が13.1%(同12.2ポイント増)、北米が10.2%(同7.3%増)と大きく変化した(図3参照)。
2025年以降のAIサーバーのサプライチェーンの見通しについて、MICの専門家は、米国系顧客がサプライチェーンのリスクを低減するために、中国以外の国・地域での生産を要求していく見込みと指摘する。なお、2028年時点の予測では、中国での生産比率が26.0%(2024年比で4ポイント減)まで減少するとしている。
一方で、同専門家は、第三国での生産や迂回輸出への米国の監視・管理が強化される流れになっていることを踏まえ、生産地が米国以外の場合、相互関税などのさらに高い関税が課されることになれば、台湾系EMSは米国国内で生産(組み立て)能力を拡充することが見込まれるとのシナリオも示した(注6)。
| 企業 | サーバーの生産能力配置状況 |
|---|---|
| クアンタ |
カリフォルニア州、テネシー州に生産拠点がある。カリフォルニア州フリーモント工場はサーバー後工程組み立ての主力工場。テネシー州ナッシュビル工場もサーバー組み立てを受託する。 2024年Q2、米国テネシー州の子会社QMNに10億米ドルを増資。段階的に生産能力拡大に投資し、顧客のAIインフラに対するニーズ増大に対応。 |
|
ウィストロン (ウィウィン) |
テキサス州マッキニー、テキサス州ダラスに工場を設立。マッキニー工場は主にリチウムイオン電池、プリント基板などのリサイクル拠点。テキサス州ダラスはアフターサービス提供用の工場。 2024年Q3、ウィストロンは約84億元規模の資金の投資を決定。台湾、米国、メキシコ、インドの4カ国・地域で、AIサーバーの生産能力を大幅に拡大。 うち米国は、ウィストロンが株式の100%を保有する北米のアフターサービス担当子会社WTXが7,200万米ドルで、米国テキサス州に位置する用地と工場を取得することを決定。主にサーバーとAIサーバーの米国でのアフターサービスのニーズに対応する。 |
| ホンハイ |
ウィスコンシン州、テキサス州ヒューストン、オハイオ州などにAIサーバーなどの生産拠点がある。 2024年Q2、81億台湾ドルを投資し、ヒューストン工場のAIサーバーの生産能力を増強。同年Q3には、さらに11億台湾ドルを追加投資。 |
| ペガトロン | インディアナ州、カリフォルニア州にサービスセンターを設立。現在主に保守サービスに使用。後工程の組み立ても可能。 |
| インベンテック | 製造工場なし。シリコンバレー、ヒューストン、オースティンに所在する運営拠点のみ。 |
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析、各社情報、報道からジェトロ作成
台湾系EMSの一部はトランプ第2次政権発足以前から、米国でのAIサーバー生産能力の設置を進めてきた(表3参照)。鴻海はウィスコンシン州、テキサス州ヒューストン、オハイオ州などにAIサーバーなどの生産拠点を持っているが、2024年第2四半期に81億台湾ドル(約364億5,000万円、1台湾ドル=約4.5円)を投資し、ヒューストン工場のAIサーバーの生産能力を増強することを発表した。同年第3四半期にはさらに11億台湾ドルを追加投資している。クアンタは2024年第2四半期に、米国テネシー州の子会社QMNへの10億ドルの増資を発表した。段階的に生産能力拡大に投資して、顧客のAIインフラに対するニーズ増大に対応するとしている。
| 国・地域名 | 企業 | サーバーの生産能力配置状況 |
|---|---|---|
| タイ | クアンタ | 2024年Q3に、タイでのサーバーの新工場の設置を発表。 |
| インベンテック | 2024年Q2に、8億台湾ドルを追加投資し、サーバーとノートパソコンの生産能力を拡充。 | |
| メキシコ | ウィストロン | 2024年Q2に、26億台湾ドルを投資し、AIサーバー工場を建設。 |
| インベンテック | 2024年Q4 に、6億台湾ドルを投資し、メキシコ工場に高圧変電所を建設し、顧客の注文に対応する電力を確保することを発表。将来のAIサーバー生産に向けた用電量にも対応。 | |
| ホンハイ |
2024年8月、AIサーバー生産ライン建設(シウダー・フアレス市)のため、77億台湾ドルを増資。 2024年2月、8億台湾ドルを投資し、工場用地を取得(ハリスコ州)。AIサーバーの生産能力を増強。 |
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析、各社情報、報道からジェトロ作成
なお、台湾系EMSは米国以外にも、タイやメキシコでも生産能力の増強を進めている(表4参照)。2024年にはウィストロン、インベンテック、ホンハイがメキシコに工場関連投資を実施している。
MICの専門家は今後の動きとして、トランプ政権の関税政策次第では、メキシコに地理的にも近い米テキサス州などが生産拠点として注目されると指摘する。
サプライチェーン主要プレーヤーの動向を前広に把握することがカギ
第1次トランプ政権下では、ブランド主導でEMSを主役としたICTサプライチェーンの変化が進展した。日本企業もEMSの移転に伴い、供給体制を変更するなどの対応が求められてきた。
第2次トランプ政権では、中国に対して2025年2月4日からより広い範囲で追加関税を課す政策が発動された。第1次トランプ政権は、PC、スマートフォンに最終製品としては追加関税を発動しておらず、生産拠点移転が限定的だった。しかし、今後は、米国の追加関税の対象となり、さらなる高関税を賦課される可能性もあるため、EMSを中心に、本格的な生産拠点移転の加速を迫られるだろう。
台湾系EMSは、第1次トランプ政権期から顧客(ブランド企業)の方針に基づき、生産拠点の分散を進めてきた。MICの予測によると、PCとスマートフォンについては、2028年に向けて生産能力の脱中国化が大幅に起きると見込まれている。
日本企業としては、自社が関わるサプライチェーンで、主要プレーヤーのブランド企業の戦略や、それを踏まえたEMSの生産能力配置の変化を把握することがカギとなる。また、それを基に自社の戦略に落とし込むというサイクルを政策動向の変化に応じて素早く実施することが一層求められる局面を迎えている。
- 注1:
- ジェトロが資訊工業策進会(台湾資策会)産業情報研究所(MIC)に委託し、調査を実施した。
- 注2:
- ODM企業とは、Original Design Manufacturingの略で、委託者のブランドで製品を設計・製造する企業のことを指す。
- 注3:
- 詳細は2023年10月16日付地域・分析レポート「米中対立が対米サプライチェーンに与えた影響」を参照。
- 注4:
- 詳細は2019年12月16日付ビジネス短信「米中が第1段階の貿易交渉で合意、対中追加関税リスト4B発動は見送り」を参照。
- 注5:
- 「デル、半導体で『脱中国』24年までに使用取りやめ」(2023年1月5日付「日本経済新聞」)、「US computer giant Dell to replace all China-made chips in its products by 2024 amid tensions between Beijing and Washington」(2023年1月5日付「サウスチャイナ・モーニングポスト」)など。
- 注6:
- 第三国経由での米国への迂回輸出の問題については、2025年03月14日付ビジネス短信「米下院公聴会、米国のインド太平洋政策を検証、対東南アジア戦略転換と対外投資審査強化を提言」、2025年3月7日付ビジネス短信「マレーシア政府、米半導体の迂回輸出疑惑受け声明発表、監視強化へ」を参照。
ICT産業のサプライチェーン
シリーズの前の記事も読む

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部中国北アジア課 課長代理
藤原 智生(ふじはら ともき) -
2009年にジェトロ入構後、海外調査部中国北アジア課、企画部企画課、北京事務所などでの業務に従事。
現在は中国大陸、香港、台湾関連の調査を担当。ジェトロの媒体などで経済動向や制度情報などについて、情報発信を行う。




 閉じる
閉じる






