台湾企業の動向
ICT産業のサプライチェーン(1)
2025年5月14日
2025年1月の米国のトランプ第2次政権発足以降、米国と中国、あるいは米国とカナダ、メキシコとの間で、矢継ぎ早に追加関税の応酬が発生している。これにより、日本企業は自社に関わるサプライチェーンに対する影響の分析とともに、その調整の必要性の検討を迫られている。2025年4月以降も相互関税など新たな国境措置の実施が見込まれる中、日本企業はいかにサプライチェーンの予見性を確保したらよいのだろうか。
本稿では、トランプ第1次政権下の2018年前後から本格化したサプライチェーンの変化で主要プレーヤーとなった、米国系電気・電子ブランド企業と台湾系電子機器製造受託(EMS)の動向を振り返る。また、Appleの事例から、米系ブランド企業と台湾系EMSの動向とその行動原理をひもとくことにより、コンピュータ、スマートフォン、サーバーなどの情報通信技術(ICT)産業について、今後のサプライチェーンの変化をみる上でのポイントを考察する。
半導体の用途はPC、スマホ向けが5割超
米国半導体工業会(SIA)の報告書によると、2023年のデバイス別の半導体マーケットシェアは、スマートフォンなど通信向けが32%、コンピュータ向けが25%だった。この2種のデバイスで5割を超える量の半導体が使用されていることが分かる(図1参照)。このほか、電気自動車(EV)化の進展に伴って、インフォテインメント機器(IVI、注1)や先進運転補助システム(ADAS)などの搭載が急速に進む自動車向け(車載電子)が17%、産業用が14%などとなっている。
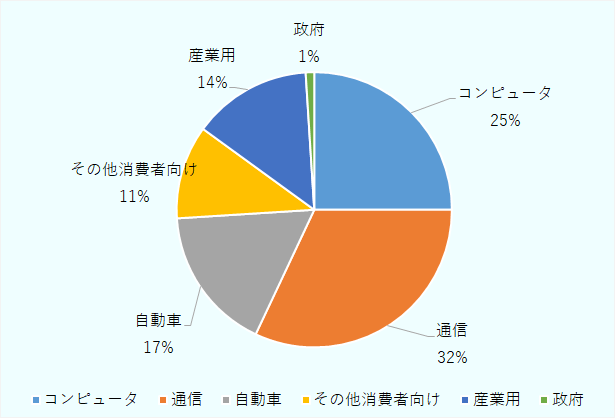
出所:米国半導体工業会(SIA)FACTBOOK2024、世界半導体市場統計(WSTS)
半導体が最終的に組み込まれるこういったデバイスについて、どのような企業が製造を担い、そのサプライチェーンの動向を決める意思決定権は誰が握っているのだろうか。
カギ握るブランド企業と台湾系EMS
この問いに対するヒントを探るために、消費者向け電子機器を例として、そのサプライチェーンをみていく。まず、サプライチェーンの最上流には、半導体材料メーカーや半導体装置メーカーが位置付けられる。これらの分野では日本企業が強みを持っており、主要なプレーヤーにも日本企業が多く位置付けられている(図2参照)。半導体製造の前工程を担う台湾積体電路製造(TSMC)などのファウンドリー、後工程を担うOSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)は、ファブレス企業から委託を受け、上述の川上企業が生産した材料や装置を用いて半導体の生産を行う。その後、主に組み立て工程を担う電子機器製造受託(EMS)が半導体に加え、その他の部品を組み立てて製品として完成させる。完成品となった製品は、パソコンならばHPやDell、スマートフォンならばAppleなどのブランド製品として、これら企業の販売ルートを通して消費者に供給される。
図2:消費者向け電子機器のサプライチェーン
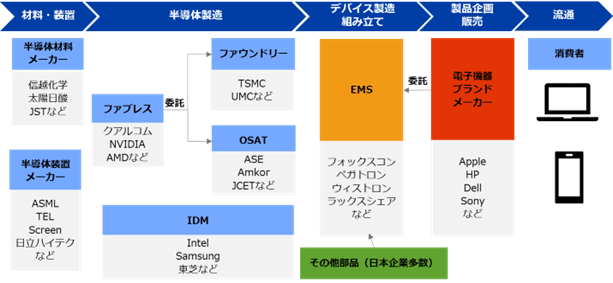
出所:経済産業省「令和3年度重要技術管理体制強化事業 (マイクロエレクトロニクスに係る 産業基盤実態等調査)調査報告書」からジェトロ作成
これらのプレーヤーの中で、TSMCに代表されるファウンドリーは、その存在がなくては先端半導体の供給が成り立たないという意味において重要なことは論をまたない。一方で、サプライチェーン全体の意思決定の観点では、HPやAppleといったブランド企業の戦略や発注量といったものが、ファウンドリーやEMSを含めた川中から川上の企業に大きな影響を与えているという点も見逃すことができない重要な事実だ。
また、最終製品を組み立てるEMSの立地は、製品の最終製造工程で多数の部品を輸入し、完成品を最終消費地に輸出するという役割からも、各国の関税政策や経済安全保障上の影響を最も受けやすいといえる。
こういった背景を踏まえると、ブランド企業のサプライチェーン戦略と、それを踏まえたEMS生産拠点の動向を分析し、サプライチェーン全体の動向メカニズムを把握することが、今後の予見性向上に資するのではないだろうか。
貿易摩擦からデカップリング、そしてデリスキングへ
台湾資策会産業情報研究所(MIC)の分析によると、トランプ第1次政権期の2018年前後からのICT産業のサプライチェーンの変化は、貿易摩擦やデカップリング、デリスキングという潮流に応じて、段階的に調達・生産拠点の移転・調整を進めてきた流れだった(図3参照)。
図3:ICTサプライチェーン移転の流れ
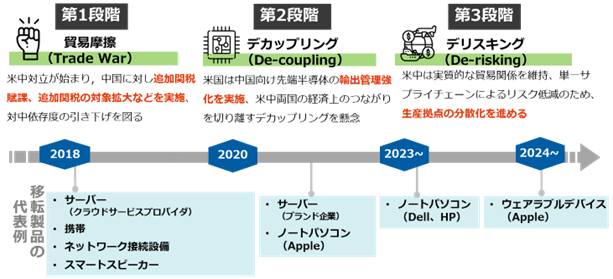
出所:台湾資策会産業情報研究所(MIC)からジェトロ作成
第1段階の貿易摩擦期(2018年前後~)では、米中対立が始まり、米国が中国に対して追加関税を賦課した。さらには、米国が段階的に対中追加関税の対象拡大などを実施したころから、対中依存度の引き下げを図る企業の動きがみられるようになった。それに続く第2段階のデカップリング期(2020年前後~)では、米国が中国向け先端半導体の輸出管理の強化を実施した。これに伴い、米中両国の経済上のつながりを切り離すデカップリング進行の懸念が高まり、さらに、広範な企業が米国を中心としたサプライチェーンと中国を中心としたサプライチェーンの2つを念頭に置き始めた。2023年前後からは、同年5月開催のG7での首脳声明に象徴される第3段階のデリスキング期と位置づけられる(注2)。デリスキング期に、米中は実質的な貿易関係を維持しつつ、サプライチェーンの過度な中国依存からの脱却や、先端技術の管理などを進めて行くかたちとなった。こういった流れの中で、日本企業も、中国のみに依存していた原材料などのサプライチェーンの複線化や、先端技術流出対策などに注力することになった。
この一連の流れをデバイスのレベルでみると、2018年に中国に対し、対米追加関税が課されたスイッチングルーター関連などのネットワーク接続設備関係などから移転が始まった。デカップリング期には、米国がサイバーセキュリティー面の規制強化をしたことなどもあり、サーバーや一部ブランド企業のノートパソコンの調達・生産拠点の移転が始まった。その後、米中それぞれの輸出管理、データ管理などが強化される中で、2023年ごろからは米国系ノートパソコンブランド企業が明確にサプライチェーンを変化させる方針を打ち出してきた。
このように、ICT産業のサプライチェーンでは、ブランド企業の戦略に主導され、台湾系を主とするEMSが主役となって移転が進展してきたという経緯がみてとれる。
大きな影響力持つ台湾系EMS
さて、ここでは、EMSについてあらためてその役割をみていく。主要なEMSを営業収益別でみると、フォックスコンというブランド名でも有名な鴻海精密工業(以下、ホンハイ)が最も大きい。ホンハイを筆頭に、ペガトロン、クアンタ、ウィストロンといった台湾系EMSがある。このほか、中国大陸系としては、ラックスシェアが台頭してきている。こういったEMSがパソコン、スマートフォン、サーバーなどをブランド企業から受託し、生産するという構造になっている。
| 企業名 | 本社 | 営業収益 | 営業収益中の米国(米州)比率 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
|
ホンハイ (フォックスコン) |
台湾 | 188,475 | 34.30% |
電子機器製造(EMS)では世界第1位、市場シェアは40%を超える。 主要製品分野は、家電、スマートフォン、クラウド・ネットワーキング製品(サーバー)、コンピュータ、電子部品。 EV製造プラットフォームMIHを主導。 |
| ペガトロン | 台湾 | 38,427 |
37.77% ※米州 |
台湾のパソコン大手、華碩電脳(エイスース)の生産部門が独立して設立。パソコンやスマートフォン、サーバーなどの受託生産を行う。 |
| クアンタ | 台湾 | 33,195 | 57.15% | ノートパソコンの受託生産に加え、情報通信、家電、クラウドコンピューティング、スマートホームソリューション、スマート自動車ソリューション、スマートヘルスケア、AIoTなどさまざまな分野を手掛ける。 |
| ウィストロン | 台湾 | 26,517 |
49.19% ※米州 |
台湾のパソコン大手宏碁(エイサー)の設計製造部門が独立して設立。 ノートパソコン、サーバー、ストレージ製品などを製造。 |
| ラックスシェア | 中国 | 31,970 | 不明 | 自動車、クラウドなど用のケーブルアセンブリおよびコネクターシステムソリューションの設計・製造に加え、コンピュータ、スマートフォンなども製造。 |
注:ペガトロンとウィストロンは米州の比率。
出所:各社の年報、HPからジェトロ作成、売上高は2023年度のもの。1台湾ドル=0.0306ドル、1人民元=0.1379ドルで換算した。
なお、各EMSの年報から、営業収益中の米国あるいは米州の比率をみると、ホンハイが34.30%(米国の比率)、クアンタが57.15%(米国の比率)で、ラックスシェアは「不明」だが、いずれも高い割合となっている。台湾系EMSにとっては、米国あるいは米州の市場が非常に重要なことが分かる。
一方で、台湾系EMSにとって、中国は販売先というよりも、生産拠点として重要との位置づけだ。中国対外経済貿易統計学会が2019年に発表した「2020年中国対外貿易500強総合排行榜」で、中国大陸の企業別輸出額ランキングを見ると、上位にホンハイ、富士康(フォックスコン)、広達(クアンタ)など、多くの台湾系EMSが並んでいる(表2参照、注3)。これら企業は、世界の工場としての中国大陸に向けて長年投資を続け、生産を維持しているという面も忘れてはならない。なお、政府の公式統計ではないものの、このような企業別の輸出額ランキングの上位20社のうち、台湾系企業が半数の10社を占める状況になっている。中国のマクロ経済レベルでも、これらEMSを含む台湾系企業の動向が影響を与え得る可能性が指摘できる。
| 順位 | 企業名 | 親会社/英語名称など |
輸出額 (億ドル) |
分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻富錦精密電子(鄭州) |
鴻海 (Hon Hai) |
316.4 | 台湾系 |
| 2 | 達豊(上海)電脳 | 広達(Quanta) | 171.5 | 台湾系 |
| 3 | 華為終端 | 華為(huawei) | 159.7 | 中国系(民間) |
| 4 | 深圳富士康 | 富士康(Foxconn) | 150.5 | 台湾系 |
| 5 | 鴻富錦精密電子(成都) | 鴻海(Hon Hai) | 146.1 | 台湾系 |
| 6 | 中国石油化工股份 | Sinopec | 127.5 | 中国系(中央国有) |
| 7 | 昌硯科技(上海) | 和碩(pegatron) | 127.4 | 台湾系 |
| 8 | 深圳華為 | 華為(huawei) | 127.1 | 中国系(民間) |
| 9 | 名硯電脳(蘇州) | 和碩(pegatron) | 124.7 | 台湾系 |
| 10 | 中国石油天然気集団 | CNPC | 115.5 | 中国系(中央国有) |
| 11 | 英特尔貿易(上海) | インテル(Intel) | 114.5 | 米国系 |
| 12 | 達豊(重慶)電脳 | 広達(Quanta) | 107.8 | 台湾系 |
| 13 | 美光半導体(西安) | マイクロン(Micron) | 99.6 | 米国系 |
| 14 | 世硯電子(崑山) | 和碩(pegatron) | 84.6 | 台湾系 |
| 15 | 載尔貿易(崑山) | デル(Dell) | 78.8 | 米国系 |
| 16 | 東莞市欧珀精密電子 | OPPO広東移動通信 | 75.2 | 中国系(民間) |
| 17 | 英業達(重慶) | 英業達(Inventec) | 72.5 | 台湾系 |
| 18 | 鴻富錦精密電子(太原) | 鴻海(Hon Hai) | 68.8 | 台湾系 |
| 19 | 美的集団 | Midea | 64.7 | 中国系(民間) |
| 20 | 小米通訊技術 | Xiaomi | 61.2 | 中国系(民間) |
注:ランキングは2019年の輸出実績に基づく。
出所:中国対外経済貿易統計学会「2020年中国対外貿易500強総合排行榜」
主要EMSのApple向けサプライチェーンの変化
個別企業のサプライチェーン変化の動向を把握するのは、データの入手可能性という点で限界がある。ここでは、サプライヤーリストをほぼ毎年公開しているAppleを例に、そのリストを手掛かりとして、EMSがどのように同社向けの生産拠点を変化させてきたのか分析する。Apple社製品の主要サプライヤーリストによると、2018年時点で同社の主要調達先200社の事業所所在地のうち、中国を所在地とする事業所の数が約5割となっており、米国の制裁関税の影響を大きく受ける構造となっていた(表3参照、注4)。
2019年には同社が主要サプライヤーに対し、「中国に集中する生産能力の15~30%を他の国・地域に移すことを検討するように求めた」との報道があるなど、米中貿易摩擦の影響を踏まえたサプライチェーン調整の動きがみられた。
実際、Appleがサプライヤーリストを公表していない2019年度を除くと、2018年以降に主要EMSがインドやインドネシア、オーストラリア、米国、タイ、ベトナムなどに調達先を変化した動きがみられる。
| 項目 | 国・地域名 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フォックスコン (ホンハイ) |
中国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ベトナム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ブラジル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 米国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 台湾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| インド | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 香港 | ● | ||||||||||||
| ペガトロン | 中国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| チェコ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 日本 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| シンガポール | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 韓国 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 台湾 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 米国 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| オーストラリア | ● | ● | |||||||||||
| インド | ● | ● | ● | ||||||||||
| インドネシア | ● |
注:Appleが調達先とする主要EMSの生産・調達拠点を●で示した。2019年度のSupplier list は公表されていない。
出所:Apple Supplier list 各年度版、報道からジェトロ作成
| 項目 | 国・地域名 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィストロン | 中国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 米国 | ● | ● | |||||||||||
| インド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| クアンタ | 中国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 米国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| タイ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ベトナム | ● | ||||||||||||
| ラックスシェア | 中国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ベトナム | ● | ● | ● | ● | ● |
注:Appleが調達先とする主要EMSの生産・調達拠点を●で示した。2019年度のSupplier list は公表されていない。
出所:Apple Supplier list 各年度版からジェトロ作成
一方で、各EMSとも中国からの供給(生産)は継続しており、Appleとしては、中国での生産は引き続き維持しつつ、調達先の多元化を図るかたちとなっている。
このようなAppleの方針に応じたEMSの供給拠点の変化の事例は、どのようなメカニズムによって説明し得るのだろうか。
MICの専門家は、スマートフォン、PCなど電子機器製造のサプライチェーンでは「ブランドを持つ委託元企業がEMSの生産や調達活動に介入するかたちの『従属型』の構造が強い」と指摘する(図4参照)。つまり、AppleやHPといった世界的ブランド企業に対し、EMSは委託を受ける立場にあり、意思決定ではいわば顧客と下請けのような関係性となる。そのため、EMSはブランド企業が定めたサプライチェーン移転の方針に従う側面が強いといえる。
一方で、ICT産業のサプライチェーンには、EMS以外にも、ファウンドリーなど様々なプレーヤーが存在する。前述のMICの専門家は「サプライチェーンの川上では、製造装置や材料など一部の企業しか供給できない、あるいは、高額かつ顧客ごとに調整やメンテナンスが必要であり、顧客とサプライヤーが『相互依存型」となるケースが多く見受けられる」と指摘する。
なお、EMSに部品を供給する企業の中には、多数の同業者が存在する。そのため、市場を介して顧客とサプライヤーがほぼ対等な取引関係を有する「市場型」の取引も存在する。この場合は、サプライヤーが特定顧客のサプライチェーンの方針にのみ従う状況は少ない。
図4:サプライチェーンの変化と企業間のパワーバランス
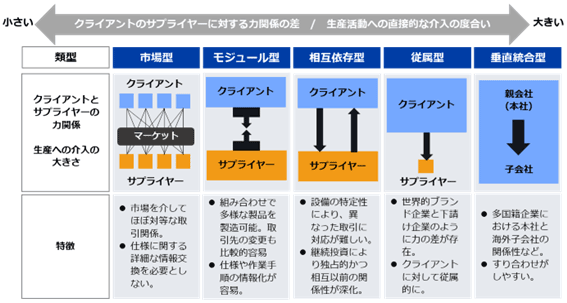
出所:猪俣哲史 著「グローバル・バリューチェーン―新・南北問題へのまなざし―」から作成
このように、サプライチェーンの中でも、製品の性質やそれによる顧客とサプライヤー間の関係性の違いによって、EMSがブランド企業などの方針の影響を受ける程度が異なる可能性が指摘できる。
ポイントはブランド企業の方針と企業間の関係性
これまで見てきたとおり、2018年前後からの米中摩擦をきっかけとしたICT産業のサプライチェーンの変化には、米系を中心としたブランド企業の方針が大きな影響を与えていることが分かる。また、Appleの事例からは、そういった方針を踏まえて、EMSがサプライチェーンを大きく変化させたことが指摘できる。なお、EMSがこのようにブランド企業の方針に大きく左右される要因としては、顧客とサプライヤーの力関係に大きな差がある点が浮き彫りとなった。ただし、企業間のパワーバランスが相互依存型や市場型などのケースではこの限りではない。
日本企業がICT産業のサプライチェーンで自社の拠点の調整を考慮する場合、ブランド企業の方針とそれを受けたEMSの移転に関する情報をいち早く把握することが重要だ。また、自社とサプライチェーン上の他の顧客との関係性を見極めておくことが、来るべき変化に対応する上での予見性向上に資するのではないだろうか。
- 注1:
- 「インフォメーション」と「エンターテインメント」を組み合わせた造語。車載システムでは、カーナビゲーションシステムやカーオーディオ、TVチューナーなどの各機能を統合したシステムを指すとされる。
- 注2:
- 「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」(2023年5月20日)では、「デカップリング(de-coupling=分断)」ではなく、「デリスキング(de-risking=リスク低減)」に基づいて対処する方針を盛り込んだ。
- 注3:
- 同ランキングは2019年を最後に、その後発表されていない。
- 注4:
- 2019年度Appleサプライヤーリストは発表されていない。
ICT産業のサプライチェーン
シリーズの次の記事も読む

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部中国北アジア課 課長代理
藤原 智生(ふじはら ともき) -
2009年にジェトロ入構後、海外調査部中国北アジア課、企画部企画課、北京事務所などでの業務に従事。
現在は中国大陸、香港、台湾関連の調査を担当。ジェトロの媒体などで経済動向や制度情報などについて、情報発信を行う。




 閉じる
閉じる






