トランプ関税の米国輸出への影響
米国の付加価値貿易統計からの考察
2025年7月31日
米国商務省経済分析局(BEA)は2025年6月30日、米国独自の付加価値貿易統計の最新データを公開した。本稿では、付加価値貿易統計を基に、貿易統計だけでは測りきれない、米国の輸出額に占める米国外で付加された価値を分析し、米国による追加関税が米国の輸出にも影響を与える可能性を検証する。
米国独自の付加価値貿易統計
インターネットの普及など技術革新により経済はグローバル化し、企業は効率化を求めてサプライチェーンを世界中に広げ、国際分業体制が形成された。一方で、モノの流れは複雑になり、特に機械製品は最終製品になるまで複数回、国境をまたぐようになった。北米で生産される自動車は、完成車として輸出されるまでに、平均で8回、国境を越えるといわれている。
米国による追加関税は(注1)、こうした状況下で賦課されており、その影響を測ることは容易ではない。貿易統計はその性格上、輸出あるいは輸入される製品の価格が全て、製品の原産国に計上されるため、例えば日本から中国に輸出された部材が、その後、最終製品となって米国に輸出される場合、米国の統計では日本の部材の価値は無視される。また、日本の部材の価値が中国と米国で二重に計上される問題もあり、複雑化したサプライチェーンを捉えきれていない。そこで、輸出入された製品に含まれる価値がどの国で付加されたかに注目する、付加価値貿易の考え方が重要となる(注2)。
現在、WTO![]() やOECD
やOECD![]() などが、付加価値貿易に関する統計を公開している。米国の商務省経済分析局(BEA)はこれら国際機関による統計について、米国の直接的および間接的な貿易相手国を通じてサプライチェーンを追跡できること、米国から輸出された価値が「帰国」する形で米国への輸入に組み込まれている部分を捕捉できること、国境を複数回越える中間財の二重計上を排除できること、などをメリットとして挙げている。一方でBEAは、国際機関による付加価値貿易の統計について、高度な国際協調が必要なこと、各国の統計公開スケジュールによって即時性が制限されること、他国のデータの利用可能性に制限があること、他国との不一致を調整するため米国のデータの変更が必要なこと、などをデメリットに挙げている。そこでBEAは、より迅速かつ詳細で、米国の公式統計と高い整合性が取れる、米国独自の付加価値貿易統計の整備に努めてきた。
などが、付加価値貿易に関する統計を公開している。米国の商務省経済分析局(BEA)はこれら国際機関による統計について、米国の直接的および間接的な貿易相手国を通じてサプライチェーンを追跡できること、米国から輸出された価値が「帰国」する形で米国への輸入に組み込まれている部分を捕捉できること、国境を複数回越える中間財の二重計上を排除できること、などをメリットとして挙げている。一方でBEAは、国際機関による付加価値貿易の統計について、高度な国際協調が必要なこと、各国の統計公開スケジュールによって即時性が制限されること、他国のデータの利用可能性に制限があること、他国との不一致を調整するため米国のデータの変更が必要なこと、などをデメリットに挙げている。そこでBEAは、より迅速かつ詳細で、米国の公式統計と高い整合性が取れる、米国独自の付加価値貿易統計の整備に努めてきた。
BEAは2021年12月、米国独自の付加価値貿易統計(BEA TiVA)のプロトタイプを公開した(注3)。2023年には、産業別および国・地域別の内訳を追加した。そして2025年6月に、ユーザーがデータベースをカスタマイズしてデータをダウンロードできる機能を公開した。BEA TiVAでは、米国の財・サービス輸出に占める、米国内および米国外で付加された価値を分析できる。トランプ政権の追加関税措置の目的の1つには米国への製造業回帰や貿易赤字の削減があるが、関税によって輸入材のコストが上がれば、米国内での生産コストが高くなり、販売価格が上昇するのみならず、米国からの輸出にも影響する可能性がある。そのため本稿では、米国からの輸出に、米国外で付加された価値がどれだけあるのかを検証する。
米国の輸出の1割強は米国外で付加された価値
BEAが2025年6月に公開したデータによると、米国の財・サービスの輸出額に占める米国内で付加された価値は、2007年の1兆2,910億ドルから2023年には2兆3,637億ドルとなり、2倍近くに拡大した。比較可能な2007年以降で、過去最大となった。米国外で付加された価値は同期間中、2,161億ドルから2,759億ドルに拡大した。ただし、最大だったのは2022年の3,151億ドルだった。米国外からの付加価値は、2014年にも3,000億ドルを超えていたが、2009年のリーマン・ショック時や2020年の新型コロナウイルスのパンデミックの際には2,000億ドルを下回るなど、増減を繰り返している(図1参照)。
割合でみると、2007年に米国の輸出額に占める米国内で付加された価値は85.7%で、2023年には89.5%に上昇した。一方で、米国外で付加された価値は、14.3%から10.5%に低下した(図2参照)。
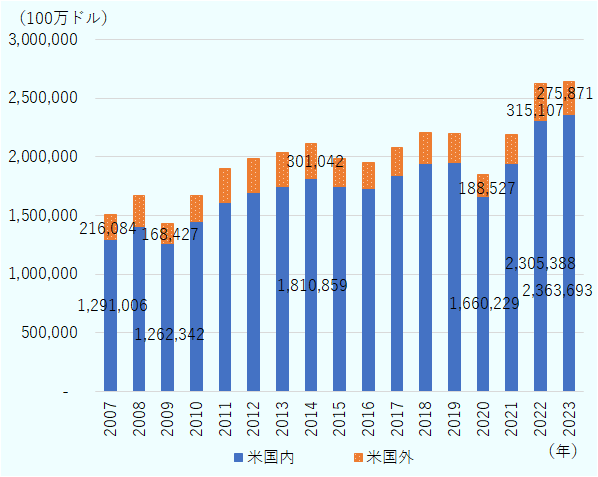
出所:BEA TiVA
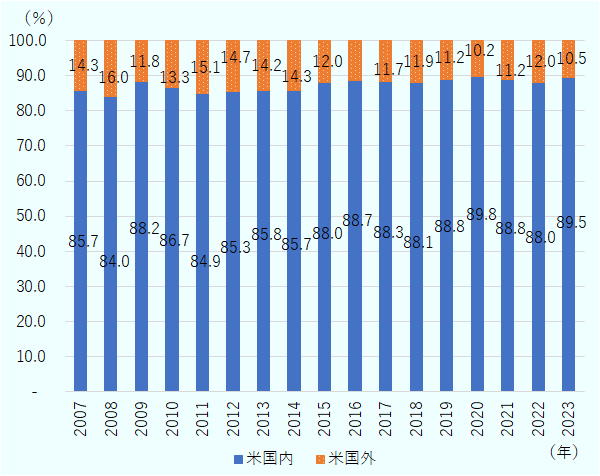
出所:BEA TiVA
米国外で付加された価値を国・地域別にみると、2023年に最大だったのは欧州で、653億ドルだった。米国外で付加された価値全体の23.7%を占めた。欧州は2007~2023年の間、全ての年で20%を超えた。欧州の後は、カナダの539憶ドル(19.5%)、日本・中国を除くアジア太平洋の477億ドル(17.3%)、メキシコの304億ドル(11.0%)、中国の246億ドル(8.9%)、日本の130億ドル(4.7%)が続いた(注4)。米国外で付加された価値は2022年に過去最高を記録したことから、2023年はほぼ全てで前年比減となったが、メキシコのみ微増したため、同国が占める割合は2022年から1.4ポイント増加した。これまでメキシコが占める割合はおおむね9%台で推移してきたため、割合の面では大きく増加した(図3、4参照)。
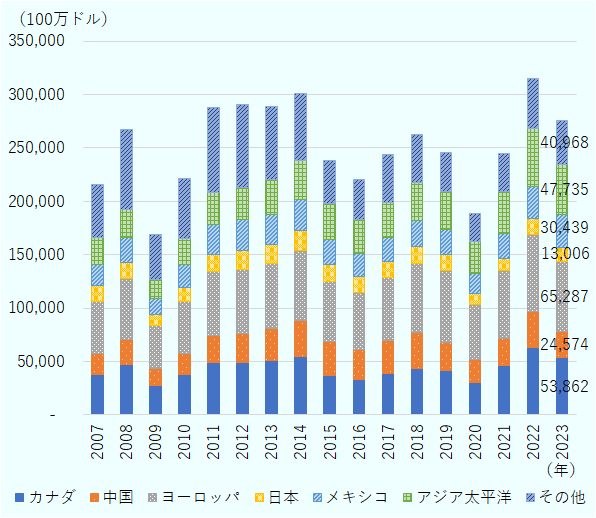
注:アジア太平洋は、日本と中国を除く。
出所:BEA TiVA
付加価値の減少傾向が続く中国と日本
付加価値の割合でみて、2007年との比較で減少したのは中国と日本のみだった。中国は2007年の9%から徐々に割合が拡大し、2018年に13.1%と最大となったが、その後は減少傾向が続き、2023年は2010年前後の水準にとどまった。2018年は、1期目のトランプ政権が、1974年通商法301条に基づき対中追加関税の賦課を開始した年であり、これをもって米中対立が始まった年とされる。一方でその間、日本・中国を除くアジア太平洋の付加価値の割合が拡大した。米中対立が激化・長期化し、米国による対中追加関税などの影響回避や、新型コロナのパンデミックであらわになったサプライチェーンの一極集中を解消する観点から、企業は改めて中国からASEANなど他国に生産拠点を移した(注5)。米国から輸出される製品の部材を生産している拠点が、中国に代わりASEANなどで拡大していることを示している可能性がある(注6)。日本は2007年に6.8%で、2019年まではおおむね6%台を推移していたが、2020年から低下し2021年以降は4%台にとどまっている。日本は絶対値でもみても、2023年の値が2007年よりも減少した唯一の国となった。
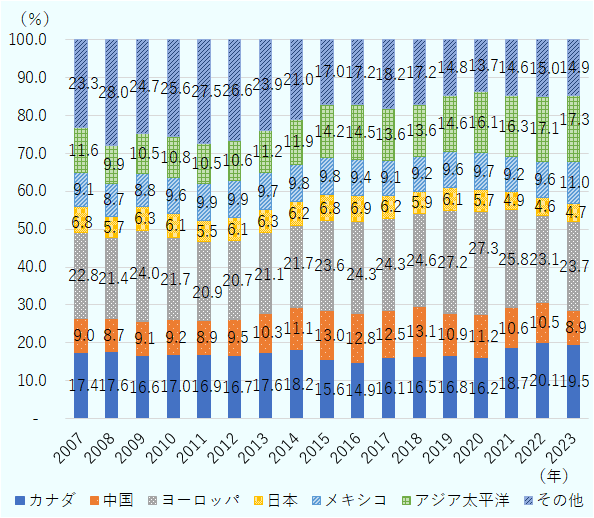
注:アジア太平洋は、日本と中国を除く。
出所:BEA TiVA
日本からの付加価値は減るも、対米投資は最大
以上を総括すれば、次のとおりとなる。米国の輸出における米国内で付加された価値は現在、約90%で過去15年ほどの間、上昇傾向にある。米国外で付加された価値は約10%程度で、その中では欧州が大きい。従って、トランプ政権による追加関税のような諸外国からの価値流入を妨げる措置は、米国の輸出の10%程度に影響を与えると考えられ(注7)、特に欧州に対する措置が最も影響が大きいといえる。また近年は、中国からの付加価値が減少傾向にあり、代わって日本と中国を除くアジア太平洋からの付加価値が拡大している。これには、長期化する米中対立などが影響している可能性がある。
なお、日本からの付加価値は減少傾向にあるものの、米国の輸出におけるプレゼンスが縮小しているとの考えには、慎重な判断が必要だ。在米の外国企業による付加価値は、米国内で付加された価値として計上されるからだ。BEA TiVAで日本の割合が減少傾向にあるのと反対に、日本の対米投資額は拡大しており、日本の対米投資残高は2023年末で7,934億ドル、2024年末で8,192億ドルだ。日本は2019年以降、最も米国に投資している国であるうえ(図5参照)、日本企業が創出する製造業の雇用数は52万9,200人、在米の日系企業による米国からの財輸出額は823億ドルで、いずれも国別で首位となっている。BEA TiVAには表れないかたちで、在米日系企業が米国からの輸出に一定程度貢献していることには留意が必要だ。
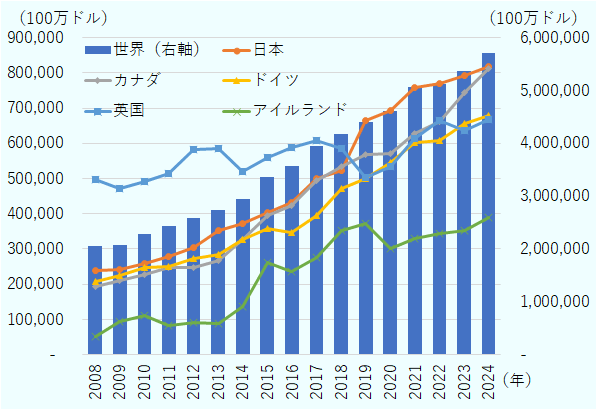
注:投資主体を最終的に所有またはコントロールしている事業体である最終的な実質所有者(UBO:Ultimate Beneficial Owner)が所在する国を基準とした集計値。
出所:BEA
付加価値貿易統計はその複雑さ故に、貿易統計と異なり、統計整備はまだ発展途上にある。例えば即時性の観点では、付加価値貿易統計のデータは、BEA TiVAでは2023年、WTOでは2018年、OECDでは2020年が最新年となっている。付加価値貿易統計は、関税などの影響について貿易統計よりも実態に即して分析できる。サプライチェーンが世界中に網の目のように敷かれる中で、経済安全保障の観点も踏まえた政策立案や経営戦略の策定が求められる現代において、一層の統計整備が期待される。
- 注1:
- 米国による追加関税措置は、トランプ政権1期目の2018年に発動されて以降、続くバイデン政権でも維持され、現在のトランプ政権2期目で強化された。トランプ政権1期目の関税措置については、2024年12月10日付地域・分析レポート「トランプ次期政権下で取られ得る関税政策(米国)」参照。トランプ政権2期目の関税措置の実績と見通しについては、2025年6月24日付地域・分析レポート「米トランプ関税の行方(1)変遷する関税措置と在米日系企業の対応方針」、「米トランプ関税の行方(2)関税措置の今後の見通しと不確実性への備え」参照。
- 注2:
-
付加価値貿易の考え方については、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)のウェブサイト
 が簡潔で分かりやすい。
が簡潔で分かりやすい。
- 注3:
- BEAの発表では単にTiVAとして記載されているが、TiVAは単に付加価値貿易を指す場合や、他機関によるTiVAデータベースもあることから、本稿ではそれらと区別するため、BEAによるTiVAのデータベースを、BEA TiVAと記載する。
- 注4:
- BEA TiVAで現在確認できる国・地域は、欧州、カナダ、日本・中国を除くアジア太平洋、メキシコ、中国、日本となっている。
- 注5:
- 2023年10月16日付地域・分析レポート「米中対立が対米サプライチェーンに与えた影響-通信機器で変化の兆し-」、2025年3月19日付地域・分析レポート「トランプ政権下の米中サプライチェーン-少量でも製造に不可欠な製品の調達管理が今後の焦点-」参照。
- 注6:
- BEA TiVAは、これら因果関係を証明しているものではないことに注意が必要。
- 注7:
- BEA TiVAには財だけでなく、サービスも含まれている。追加関税は財の輸入にのみ課される。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ニューヨーク事務所 調査担当ディレクター
赤平 大寿(あかひら ひろひさ) - 2009年、ジェトロ入構。海外調査部国際経済課、海外調査部米州課、企画部海外地域戦略班(北米・大洋州)、調査部米州課課長代理などを経て2023年12月から現職。その間、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)の日本部客員研究員(2015~2017年)。政策研究修士。






 閉じる
閉じる





