人件費高騰が筆頭経営課題に
ジェトロ在米日系企業実態調査(後編)
2023年3月6日
ジェトロは、 2022年度海外進出日系企業実態調査(北米編)を実施した(注1)。その結果から、2022年に黒字を見込む在米日系企業の割合が6割台半ばと、前年調査から増加した一方で、景況感を示すDI値は17.5と前年調査(34.7)から大幅に悪化していることがわかった。同時に、在米日系企業が(1)急速なインフレによる原材料・部品調達コスト上昇や、(2)人件費上昇などの経済的圧力を受けているといった実態も見えてきた。
本連載の後編では、労働市場に関する主要経済指標(注2)などからみえる米国経済の現況とともに、在米日系企業の今後について展望する。
「従業員の賃金上昇」が経営課題の筆頭に
ジェトロは当該調査で、在米日系企業が抱える経営上の課題についても問いを設けた。その結果によると、「従業員の賃金上昇」(67.5%)が筆頭課題に挙がった。そのほか、「従業員(一般社員)の確保」(51.4%)や「従業員の定着率」(40.2%)、「従業員(技術者)の確保」(39.4%)など、人員不足を挙げる企業が多くみられた。
その裏返しとして、従業員の維持や確保のためには、賃金を引き上げざるを得ない。そうした事情もあり、経営上の課題への対応策としても、「賃金の引き上げ」(59.3%)が筆頭に挙げられた。ほかにも、「人件費以外の経費削減」(35.1%)や「就業規則・雇用条件の見直し」(29.5%)など、雇用・労務面の対応が上位に食い込んだ。在米日系企業が、人件費の上昇や人員確保に苦慮している姿がうかがえる。
表:経営上の課題と対応策
|
課題となっている 事項 |
分類 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 従業員の賃金上昇 | 雇用・労務面 | 67.5 |
| 物流コストの上昇 | 原材料・部品調達面 | 56.9 |
| 新規顧客の開拓 | 販売・営業面 | 52.5 |
| 従業員(一般社員)の確保 | 雇用・労務面 | 51.4 |
| 調達コストの上昇 | 原材料・部品調達面 | 50.7 |
| 従業員の質 | 雇用・労務面 | 42.7 |
| 従業員の定着率 | 雇用・労務面 | 40.2 |
| 従業員(技術者)の確保 | 雇用・労務面 | 39.4 |
| 物流遅延 | 原材料・部品調達面 | 37.5 |
| 納期管理 | 原材料・部品調達面 | 32.5 |
| 原材料・部品供給不足 | 原材料・部品調達面 | 26.0 |
| 取引先からの発注量の減少 | 販売・営業面 | 22.8 |
注1:回答企業数:766社。
注2:上位項目のみ抜粋、50%以上は太字。
出所:ジェトロ調査を基に作成
| 対応策 | 分類 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 賃金の引き上げ | 雇用・労務面 | 59.3 |
| 調達先・調達内容の見直し | 原材料・部品調達面 | 40.5 |
| 競合製品との差別化 | 販売・営業面 | 36.7 |
| 販売方法の見直し・強化 | 販売・営業面 | 35.8 |
| 人件費以外の経費削減 | 雇用・労務面 | 35.1 |
| 新製品の開発 | 販売・営業面 | 33.8 |
| 社内コミュニケーションの活発化 | 雇用・労務面 | 33.1 |
| 在庫の積み増し | 原材料・部品調達面 | 32.1 |
| 労働環境の改善 | 雇用・労務面 | 32.0 |
| 配送契約・配送方法の見直し | 原材料・部品調達面 | 31.0 |
| 就業規則・雇用条件の見直し | 雇用・労務面 | 29.5 |
| 各種規制への対応 | 規制面 | 26.5 |
| 自動化・省力化の推進 | 雇用・労務面 | 24.5 |
| リモートワーク・WEB会議の活用 | 雇用・労務面 | 23.4 |
| 製品(サービス)価格の見直し | 販売・営業面 | 23.1 |
| カスタマーサービスの強化 | 販売・営業面 | 21.7 |
注1:回答企業数:713社。
注2:上位項目のみ抜粋、30%以上は太字。
出所:ジェトロ調査を基に作成
もちろん、労働市場の逼迫は、在米日系企業にとどまる問題ではない。
まず、米国の失業率は目下、かなり低下している。新型コロナの感染が拡大した2020年4月には実に14.8%に及び、ピークを記録した。しかし、そこから徐々に回復し、2021年12月は3.9%。3%台は、2020年2月以来のことになる(図1参照)。
また、米国労働省の雇用動態調査(JOLTS)![]() (634KB)によると、ジェトロがアンケートを実施した2022年9月時点で求人件数は1,070万件だったのに対し、採用人数は610万人。充足率は57.0%となった。新型コロナ禍前の2019年の平均充足率は約80%だったことから、20ポイント以上も低下しており、企業が求める労働力を充足できていないことがうかがえる。すなわち、労働市場が逼迫状態にありそうだ。
(634KB)によると、ジェトロがアンケートを実施した2022年9月時点で求人件数は1,070万件だったのに対し、採用人数は610万人。充足率は57.0%となった。新型コロナ禍前の2019年の平均充足率は約80%だったことから、20ポイント以上も低下しており、企業が求める労働力を充足できていないことがうかがえる。すなわち、労働市場が逼迫状態にありそうだ。
タイトな労働需給を反映して、米国の平均賃金(時給)はほぼ一貫して上昇を続けてきた(図1参照、注3)。在米日系企業についても、基本的に同様だ。ジェトロの調査結果では、2022年度の基本給昇給率(ベースアップ率)の中央値が4.0%。加えて、2023年度(見込み)も、3.5%だった。賃金上昇圧力が高止まりしていることが見て取れる。
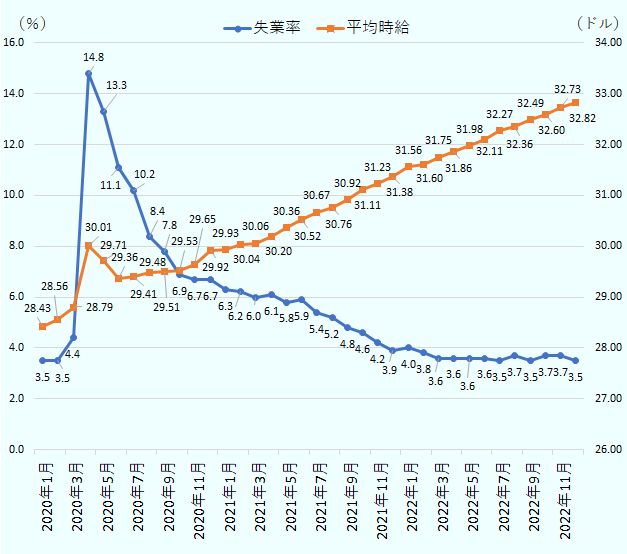
出所:労働省労働統計局(BLS)公表数値に基づきジェトロ作成
また、人件費の上昇は、在米日系企業のサプライチェーンにも影響を及ぼしている。生産を今後見直す予定の企業は、3割を超えた(30.5%)。そうした企業が生産を見直す理由としては、「人件費の高騰」(63.0%)が最多。特に製造業に限っては、約7割(70.4%)に上った。「労働市場のタイト化により採用・雇用維持が困難なため、生産設備の自動化を進める」(化学・医薬)といった声も聞かれる。その主な見直し内容としては、「新規投資/設備投資の増強」(31.2%)が筆頭に挙がった。さらに、今後「生産地の見直し」を予定する企業は2割強(23.9%)を占めた。
さらに、今後の生産地の変更内容を国・地域別にみると、主な変更対象としては、米国(38件)、日本(16件)、中国(14件)が多かった。また、変更後の生産地としては、米国(20件)、ASEAN(17件)、メキシコ(16件)が上位に挙がった。中でも、米国からメキシコ(11件)への変更が最多。在米日系企業がコスト削減に向けて生産拠点の一部を移転している可能性もうかがえる。
今後の「事業拡大」回答が5割近くに
この調査では、米国での事業拡大を継続するという前向きな姿勢も見えてくる。在米日系企業は、米国を成長市場と捉えていると言えそうだ。
今後1~2年の事業を「拡大する」企業は、前回調査(48.1%)に続いて5割近くに上った(48.7%)。これは、新型コロナ禍拡大前の2019年(47.5%)を上回る水準だ。事業拡大の理由としては、米国市場の「成長性、潜在性の高さ」(49.2%)が筆頭に挙がった。これに、「現地市場での購買力増加に伴う売り上げ増加」(36.2%)が続いた。具体的に拡大する機能は「販売機能」が6割弱(59.1%)。販売増を見込んだ「生産(高付加価値品)」(37.4%)、「生産(汎用品)」(22.2%)が続いた。
また、在米日系企業の製品の販売先は、2022年も製造業・非製造業ともに米国内(それぞれ77.8%、77.3%)が最大だった。メキシコとカナダを加えた北米市場向けは8割を超えた(86.2%、84.8%)。今後の販売方針でも、販売を拡大するという企業数は米国(84社、65社)、メキシコ(44社、30社)、カナダ(29社、21社)の順に多い。在米日系企業が需要増を見込んで、北米での販路拡大を目指す方向性がうかがえる。
円安ドル高によるマイナスの影響は限定的
既に見たように、米国は目下、かなり急激なインフレ下にある。その抑制を目的に、米国連邦準備制度理事会(FRB)は大幅な利上げを続けてきた。その結果、日本との金利差が広がった。その結果として、金利が高い米国の資金需要が高まり、2022年には急速に円安ドル高が進行した。
当該調査では、その状況を踏まえ円安ドル高(注4)が在米日系企業の経営に与える影響について聞いた。その回答としては、「全体としてプラスの影響がある」企業が、最多の32.1%を占めた。「影響がない」(26.2%)、「マイナスとプラスの影響が同程度」(18.5%)が続き、「全体としてマイナスの影響がある」は14.9%にとどまった。
プラスの影響があると回答した企業からは、「日本から輸入する原材料の価格が下落した」(食料品)、「日本本社で製造された製品・システムの価格が下落した」(一般機械)など、日本からの輸入コストの減少につながったという声が聞かれた。影響がないとした企業からは、「米国法人の決済はドル建てで行っている」(販売会社、化学・医薬品)など、為替変動の影響を受けない仕組み・取引環境が要因として挙げられた。一方で、マイナスの影響があるとした企業からは、「新規投資にあたっての投資額の増加」(鉱業・エネルギー)、「駐在員の人件費の高騰」(プラスチック製品、情報通信業)など、為替差損による負担増が理由に挙がった。
また、円安ドル高への対応策では、「為替予約」(プラスチック製品、ゴム・窯業・土石)のほか、「取引や借り入れの円建てからドル建てへの変更による為替リスクの低減」(鉄・非鉄・金属、自動車部品)や、「在庫調整」「発注調整」などが挙げられた。
2023年は弱含みの個人消費、日系企業はどう向き合うのか
米国経済は、新型コロナ禍からの経済再開に伴い、個人消費や雇用状況などのファンダメンタルズが改善した。一方で、労働市場や需給の逼迫から急速にインフレが進行している。ジェトロがアンケート調査を実施した2022年9月は、米国経済が底を打ってわずかに回復基調に入った時期に当たる。一方で、インフレ率は依然として高止まりし、FRBが急速に金融を引き締めていた。当該調査で営業利益見込みや景況感などに悲観的な数値が現れたのは、こうした動きがあってこそだろう。その帰結として、主に調達と雇用、2つのコスト上昇に伴う負担増が在米日系企業の調達・生産・販売方針を見直す要因につながった可能性がある。一方で、在米日系企業が米国を引き続き成長市場と捉え、北米地域でサプライチェーンの現地化を進めている実態もみえてきた。
2022年の実質GDP成長率(速報値)は、前年比2.1%。プラス成長になった。一方で、米国経済はGDP総額の7割を占める個人消費の動向に大きく左右されている。その個人消費は、依然として高止まりするインフレが強い逆風になっている。米民間調査会社コンファレンスボードの公表する米国の消費者マインドを示す消費者信頼感指数(1985年=100)を見ると、2022年6月に98.4。新型コロナ感染拡大の影響が色濃かった2021年2月以降で、初めて100を割り込んでしまった。その後、同年12月に至っても、109.0にとどまる。新型コロナ禍前の2019年(121.7~135.8)には遠い水準だ。
こうしてみると、2022年度の実態調査の結果は、米国経済全体の動きと軌を同じくしているところが見られる。一方で、2023年の経済は、弱含みな個人消費などを理由に緩やかな景気後退も予想される状況にある(2023年1月10日付地域・分析レポート参照)。そうした中、日系企業がどのようにかじ取りしていくのか、注目だ。
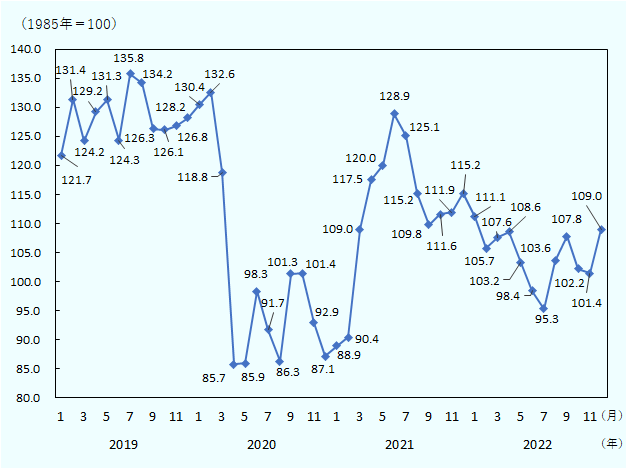
出所:コンファレンスボード
- 注1:
-
調査実施期間は2022年9月8~30日。調査対象は、(1)在米日系企業(製造業・非製造業)のうち、直接出資や間接出資を含めて、日本の親会社の出資比率が10%以上の企業、および(2)日本企業の支店、1,841社・支店。有効回答数は787社・支店42.7%)。本調査は北米、中南米、欧州、アジア大洋州などの主要地域別に、原則として年1回、ビジネスの最前線にいる進出日系企業の活動実態を把握するために実施している。米国では、1981年以降これが41回目。
なお、「2022年度海外進出日系企業実態調査(全世界編)」では、全地域で共通して立てた設問について、地域横断的に比較して結果を参照することができる。 - 注2:
- 詳細は、ジェトロが作成する基礎的経済指標を参照。
- 注3:
- 平均時給は、2020年4月に一旦、急激な上昇を記録した(前月比4.2%増の30.01ドル)。もっとも、この時の状況は、現在とかなり異なる。この時点では、まず(1)雇用情勢が悪化、(2)それに伴い、低賃金労働者の失業が急増、(3)その結果、平均賃金が押し上げられた、とされている。
- 注4:
- 2022年6月の為替水準(1ドル=134円程度)が経営に与える影響について、問いを設けた。
ジェトロ在米日系企業実態調査
- 調達の現地化は今後も進展
- 人件費高騰が筆頭経営課題に

- 執筆者紹介
-
ジェトロ海外調査部米州課
葛西 泰介(かっさい たいすけ) - 2017年、ジェトロ入構。対日投資部、ジェトロ北九州を経て、2022年5月から現職。




 閉じる
閉じる






