調達の現地化は今後も進展
ジェトロ在米日系企業実態調査(前編)
2023年3月2日
ジェトロは2022年9月、米国に進出する日系企業を対象にアンケート調査(注1)を実施した。当該調査では、現地での活動実態を定点観測するのが目的の1つだ。1981年以降、原則毎年1回の頻度実施し、今回で41回目になる。
最新の調査結果〔2022年度海外進出日系企業実態調査(北米編)〕では、2022年に黒字を見込む在米日系企業の割合が6割台半ばだった。前年調査から増加したかたちだ。その一方で、在米日系企業が急速なインフレによる原材料・部品調達コスト上昇や人件費上昇の圧力を受けている実態も明らかになった。
当連載前編では、第41回調査のポイントを概観する。あわせて、GDPや景況感に関する主要経済指標(注2)も交え、米国経済の現況を考察する。
黒字割合が回復しながらも、景況感が大幅悪化
ジェトロの調査結果をみると、2022年に営業利益の黒字を見込む在米日系企業の割合が64.3%になった。前年の59.2%から5.1ポイント上昇したことになる。ただし、2019年は66.1%だった。新型コロナ禍前の水準までには及ばなかったかたちだ(図1参照)。
営業利益の黒字割合は、非製造業で71.5%に上った一方、製造業では58.6%にとどまった。非製造業について細分化した業種別にみると、運輸業(95.7%)が好調だった。サプライチェーンの混乱に伴う運賃高騰が高収益につながった可能性ある。対照的に、旅行需要の回復が遅れている旅行・娯楽業(37.5%)は低調だった。製造業では、一般機械(81.7%)や電気・電子機器(75.9%)などが好調だった。逆に低かったのが、自動車等部品(17.1)。半導体供給不足による自動車生産台数減少などが響いた。
ここまでみたとおり、営業利益の黒字割合は前年比で増加した。しかし、先行きは不透明だ。営業利益見込みが前年から「改善」を見込む企業の割合(41.9%)は前年比9.7ポイント減だったのに対し、「悪化」(24.4%)が7.5ポイント増になった。景況感を示すDI(注3)は17.5。前年の34.7からほぼ半減と、大幅に悪化した(図2参照)。なお、非製造業では25.7、製造業で11.0だった。特に製造業で不透明感が高い様相がうかがえる。
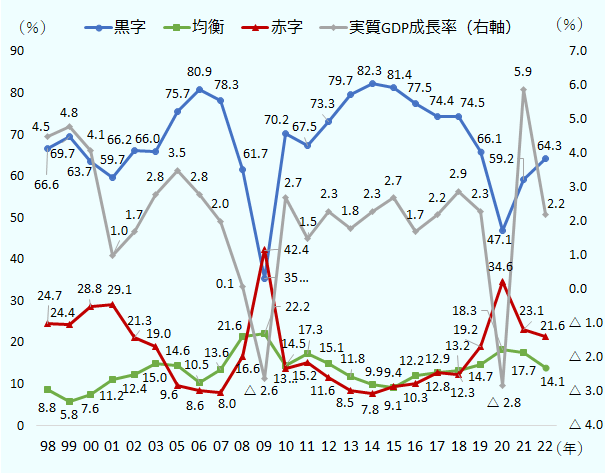
注:2004年度は調査を実施せず。
出所:ジェトロ調査、実質GDP成長率は米国商務省経済分析局(BEA)公表数値を基にジェトロ作成
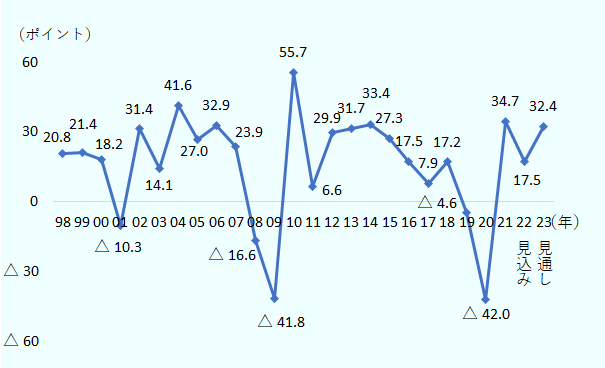
注:2004年度は調査を実施しなかったため、2003年度調査時点の見通しの数値。
出所:ジェトロ調査を基に作成
米国の実質GDP成長率をみると、2022年第1四半期(1~3月)に前期比年率マイナス1.6%、第2四半期(4~6月)にマイナス0.6%。2期連続でマイナス成長が続いていた。第3四半期(7~9月)には3.2%と、3期ぶりにプラス成長へと持ち直してはいる。しかし、その内訳をみると、財消費が前期比0.4%減と落ち込んだ。そのほか輸入も、7.3%減と縮小に転じた。ジェトロがアンケートを実施した2022年9月は、内需の落ち込みが顕在化していた時期に当たる(ただし、第3四半期統計は、アンケート期間後の2022年10月27日に発表された)。
日系企業に限らず、米国企業の景況感をみても特に製造業で不振が目立つ。例えば、米国製造業購買担当者景気指数(PMI、注4)は2022年9月、52.0(図3参照)。また、米サプライマネジメント協会(ISM)の景況感指数は、やはり9月時点で、製造業については50.9、非製造56.7だった(図4参照)。これら景況感指数では、好景気・不景気の境目は50になる。製造業に関する両指数で、その境目近くまで落ち込んでいたことがわかる。
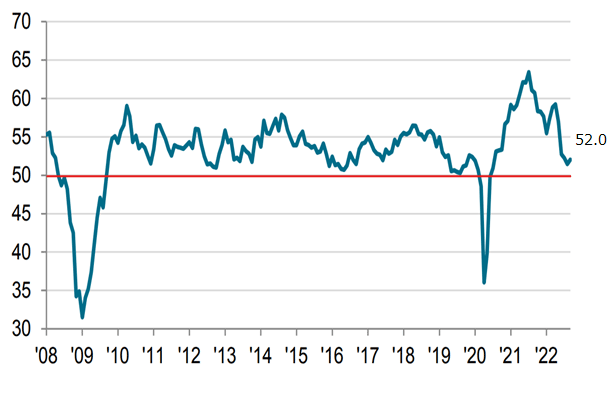
出所:S&Pグローバル
図4:米サプライマネジメント協会(ISM)景況感指数(2022年9月時点)
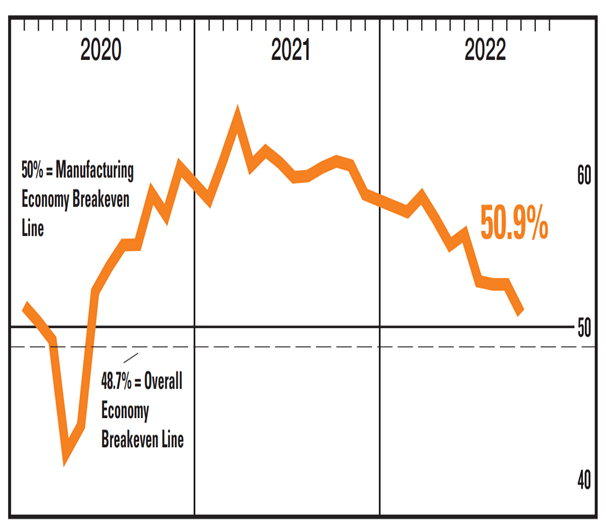
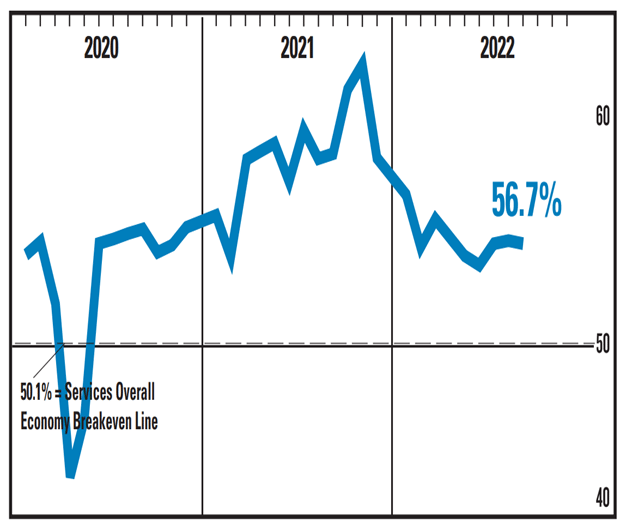
出所:米サプライマネジメント協会(ISM)
景況感下押し要因はインフレ圧力
ジェトロは在米日系企業調査で、2022年の営業利益見込みが改善または悪化する要因についても設問を設けた。その結果、改善する企業の場合、その主因は「新型コロナに起因する反動増」(20.1%)が筆頭に挙がった。当地日系企業が米国経済の回復に伴う需要増を捉えている様子がうかがえる。一方で、新型コロナ禍に起因する消費抑制から大きく反動したことに伴う副作用もある。サプライチェーンの混乱による供給不足なども相まって、需要と供給のバランスを崩したのだ。すなわち、米国での急速なインフレを招いた一因となった。
反対に、悪化する企業がその主因に挙げたのは、「原材料・部品調達コストの上昇」(25.3%)が筆頭だった。急速に進行したインフレが在米日系企業の景況感を下押しした実態がみえてくる。
実際、米国の企業間取引価格の上昇率を測る生産者物価指数(PPI)は急上昇していた。上昇率でみると、2021年1月には前年同月比1.6%増に過ぎなかった。それが、同年12月には10.0%増と急上昇。さらに2022年3月に、11.7%増を記録した。これは、2010年11月に同数値が公表されて以降最大の上昇率となった。
また、いわゆる「物価上昇率」を示す際にしばしば利用されるのが、消費者物価指数(CPI)だ。その上昇率は2021年4月に前年同月比4.2%増と2008年9月以来(4.9%増)の上昇幅を記録した。その後、翌5月に5%台、10月6%台、12月7%台と、歯止めがかからない。さらに、2022年に入ると、2月のロシアによるウクライナ侵攻などを契機に、エネルギー・食料価格の高騰がインフレの進行に拍車。3月に8%台。6月には、9.1%増に達した。これは、1981年以来約40年ぶりの歴史的な上昇幅ということになる(図5参照)。同月は、とりわけエネルギー価格の伸びが急速だった。エネルギー全体では41.6%増、さらにその中でガソリンは59.9%増と伸びを牽引した。これらは、生産や物流など幅広い分野に影響を与えるだけに、深刻だ。
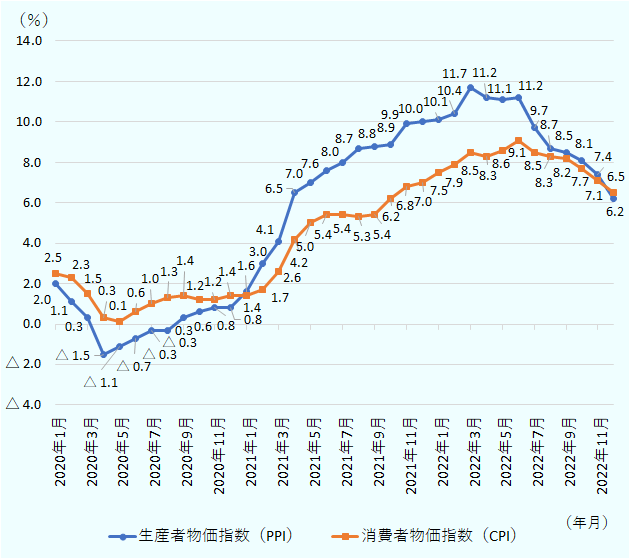
出所:労働省労働統計局(BLS)公表数値に基づきジェトロ作成
調達先が米国・メキシコにシフトの動き
調達コストの上昇は、供給途絶リスクへの対応なども相まって、在米日系企業のサプライチェーンにも影響を及ぼしている。ジェトロの調査結果では、新型コロナ感染拡大以降、調査時点までに「サプライチェーンを見直した」企業は、5割弱(49.2%)に上る。また、「今後サプライチェーンを見直す予定」の企業も、5割を超えた(54.9%)。その主な見直し内容としては、「販売価格の引き上げ」や「調達先の見直し」が上位に挙がった。
ジェトロが調査した時点の在米日系企業の国・地域別の調達比率は、製造業では米国が最大(49.5%)だった。非製造業でも、米国に相当の比重が確認できた〔38.8%と、日本(43.0%)に次ぐ高さ〕。この存在感がさらに進展していく可能性がある。今後の調達方針として「米国内から調達を拡大する」企業数は、製造業で83社、非製造業でも48社あった。ともに、国・地域別で最大だ。在米日系企業が米国での現地化戦略を進めていることがうかがえる。
さらに、調達先の見直し対象となる国・地域をみると、「日本から米国」(28件)、「中国から米国」(15件)、「中国からメキシコ」(7件)へ変更を企図する件数が多かった。製造業を中心に日本から米国や、中国から米国・メキシコへと調達先をシフトする志向が確認できたことになる(表参照)。2023年度の第42回調査(予定)では、実際にこの調達先のシフトがどこまで進展したかがポイントの1つになろう。
|
変更前の調達先 (国・地域名) |
変更後の調達先(国・地域名) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 日本 | メキシコ | ASEAN | 中国 |
メキシコを除く 中南米 |
欧州 | 韓国 | その他 | 無回答 | 総計 | |
| 米国 | 29 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 69 |
| 日本 | 28 | 6 | 2 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 44 |
| 中国 | 15 | 4 | 7 | 5 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 41 |
| 欧州 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 9 |
| ASEAN | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 7 |
| メキシコ | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
| 韓国 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 |
| その他 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 |
| 新たに調達を開始 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 総計 | 84 | 26 | 18 | 14 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 16 | 188 |
出所:ジェトロ調査を基に作成
また、今回の調査では、通商環境の変化が在米日系企業の業績に与える影響についても聞いた。回答した割合が最も高かったのは、「影響はない」(34.5%)だった。しかし、「マイナスの影響」(26.6%)も相当数みられる。「マイナスの影響」を受ける具体的な政策としては、トランプ前政権下で2018年7月から発動した「通商法301条に基づく追加関税」(52.4%)が最多。「中国の米国に対する報復関税」(34.0%)が続いた。米中対立が在米日系企業の活動に影響を与えている実態も浮かび上がったかたちだ。今後の方針として、米国やメキシコで調達が拡大する結果も読み取れた。対照的に、中国については、製造業、非製造業ともに縮小(それぞれ30社、16社)が拡大(7社、7社)を上回っている。米中対立が在米日系企業による中国依存を弱めた可能性もある。
これまで、ジェトロの調査を基に、在米日系企業が調達コスト上昇の課題に直面していることを解説した。後編では、人件費コストの上昇を中心に論じる。
- 注1:
-
調査実施期間は2022年9月8~30日。調査対象は、(1)在米日系企業(製造業・非製造業)のうち、直接出資や間接出資を含めて、日本の親会社の出資比率が10%以上の企業、および(2)日本企業の在米支店、1,841社・支店。有効回答数は787社・支店(有効回答率42.7%)。
本調査は北米、中南米、欧州、アジア大洋州などの主要地域別に、原則として年1回、ビジネスの最前線にいる進出日系企業の活動実態を把握するために実施している。米国では、1981年以降これが41回目。
なお、「2022年度海外進出日系企業実態調査(全世界編)」では、全地域で共通して立てた設問について、地域横断して結果を参照することができる。 - 注2:
- 詳細は、ジェトロが作成する基礎的経済指標を参照。
- 注3:
- Diffusion Indexの略。ここで示したDIは、営業利益が「改善」する企業の割合から、「悪化」する割合を差し引いて計上した。
- 注4:
- 米国製造業購買担当者景気指数(PMI)を公表するのは、米金融機関のJPモルガンと米金融情報会社S&Pグローバル。
ジェトロ在米日系企業実態調査
- 調達の現地化は今後も進展
- 人件費高騰が筆頭経営課題に

- 執筆者紹介
-
ジェトロ海外調査部米州課
葛西 泰介(かっさい たいすけ) - 2017年、ジェトロ入構。対日投資部、ジェトロ北九州を経て、2022年5月から現職。






 閉じる
閉じる





