スタートアップを生んで育てる。最前線の取り組み(欧州編)オーストリア進出第1号日系スタートアップ・Godot
2024年5月24日
2022年7月に、行動科学と機械学習による社会課題解決を目指して設立されたディープテック・スタートアップのGodot(ゴドー)![]() 。人々の意思決定を研究し、行動変容を助ける人工知能(AI)を開発・提供する。自治体との連携から始まった取り組みは、海外との連携も急速に進んでおり、2023年5月にはウィーンに研究開発拠点としてGodot GmbHを設立。日系スタートアップ初のオーストリア進出企業である同社が、オーストリア進出をきっかけに、今後達成していきたい未来を、共同創業者兼最高技術責任者(CTO)の鈴井豪氏に聞いた(取材日:2024年4月19日)。
。人々の意思決定を研究し、行動変容を助ける人工知能(AI)を開発・提供する。自治体との連携から始まった取り組みは、海外との連携も急速に進んでおり、2023年5月にはウィーンに研究開発拠点としてGodot GmbHを設立。日系スタートアップ初のオーストリア進出企業である同社が、オーストリア進出をきっかけに、今後達成していきたい未来を、共同創業者兼最高技術責任者(CTO)の鈴井豪氏に聞いた(取材日:2024年4月19日)。

- 質問:
- 解決したい社会課題とは?
- 答え:
- 人は、意思決定をする際に、難しい課題であることや他の事象に気を取られることで、決断を後回しにする傾向がある。決断が遅れることで個人や社会に及ぼす悪影響を軽減させるため、超個別化AIエンジンを開発した。現在は、特に「心と体の健康」に関わる領域などに注力している。
- 弊社のビジネスモデルはBtoBtoCやBtoGtoC(Business to Government to Citizen)となるため、自治体や保険会社がクライアントであり、予防の文脈で弊社プロダクトを活用してもらっている。例えば、自治体との連携では、健康診断受診を促すため、まずはショートメールを送ってもらう。そのメッセージに対するリンククリック有無などの市民の反応の積み重ねたデータを基に、次のアクションを判断する。結果、早期のがん発見につながることもあり、人々にとって健康面で、国にとっては医療費適正化の面で貢献をすることができている。保険会社と連携をした際には、メーリングリストでの配信をしてもらうなど、消費者へのリーチ方法は各社が持ち合わせているコミュニケーションチャネルに合わせて変更している。今後は文章のみならず、画像や音声など、チャンネルそのものも一人一人に合わせられるようマルチモーダル(複合)化を進めるとともに、脳波の反応を見る実験を行い、準備を進めている。
-
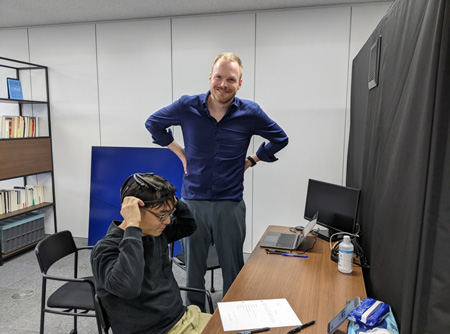
Godot GmbH社員と日本親会社の研究交流の様子(Godot提供) - 質問:
- なぜ海外進出を考え始めたのか?
- 答え:
- 経営者3人全員が海外での留学や業務経験があり、創業時から海外進出は意識していた。また、日本法人設立前に世界保健機関(WHO)の西太平洋地域事務局(WPRO)が行っていた健康保険分野に資するイノベーションを表彰するコンペで優勝したことをきっかけに、東南アジア地域での感染症対策分野にも取り組んでいる。そうした折、代表が参加した「SDGsチャレンジ」という兵庫県と神戸市が主催するアクセラレータープログラムに、オーストリアの政府機関がスタートアップの国際化を目的として運営するイニチアチブGIN(Global Incubator Network)が登壇しており、「Go Austria」プログラムを知った(2024年5月21日付地域・分析レポート参照)。経営者3人は米国や英国での経験があったため、進出先として欧州という考えが元よりあったことから、このプログラムへ応募することに決めた。
- 2022年春のGo Austriaグループプログラムに採択されることとなり、渡航前よりGINからビジネス文化やピッチの講習などが受講できるオンラインプログラムが提供されたほか、個別メンターからは会いたい人リストの提出が求められ、作成したリストを基にアポイントメントがセットされた。プログラム自体は自由時間も多く、メンターによるアポイントメント取得サービスを活用しないと観光で終わってしまうケースもある。我々はアポイントメントがあったため、滞在期間の自由時間には、個別でリンツ市のアート・イノベーション機関であるアルスエレクトロニカの担当者や、ウィーン大学でAI倫理を専門とするマーク・クーケルバーク教授と直接面談する機会を得ることができ、両者との共同プロジェクト開始への合意を得るという成果にもつながった。
- 両プロジェクトについて、日本を拠点としたまま国際プロジェクトとして進めることも考えたが、日本国内のみで新しく技術開発に取り組むことに、将来的には限界があるのではないかと考え、2022年秋のグループプログラムに再度参加し、同時に、子会社設立に向けた具体的な調査を行った。例えば、オーストリア研究推進機構(FFG)やウィーン経済振興公社(VBA)などの政府機関と助成金について議論をしたほか、在日オーストリア大使館商務部の紹介により弁護士事務所と子会社設立を行うべきかの相談もでき、進出を決断する上での重要な情報収集機会となった。その後、進出準備段階企業が対象となる3回目の渡航支援プログラムであるGo Austria PLUSにも参加をし、2022年12月には登記に向けた申請を開始することができた。
- 質問:
- オーストリアへの進出を決めた理由、また進出のメリットは何か?
- 答え:
- 進出理由は3つある。 1つ目は、政府からの充実した補助金などの支援。FFGやオーストリア経済サービス(AWS)、VBAなどが助成金プログラムを用意している。特に研究開発については、多くの種類の助成金が提供されている印象がある。
- 2つ目は、進行中のプロジェクトがすでにあったこと。1回目の渡航ですでにアルスエレクトロニカやウィーン大学との共同プロジェクトを開始することで合意が取れていたため、欧州の中でもウィーンという土地を選択することは、自然な流れであった。
- 3つ目は、当社特有の利点とはなるが、ウィーンという土地がフロイトやアドラーといった心理分析分野研究者の本拠地であり、弊社の研究と深いつながりがあること。オーストリアは多くの方がご存知の通り、文化面での成熟度も高く、合理的側面と非合理的側面を包括的に研究することができ、意思決定研究をする我々にとって最適な環境だと感じている。
- メリットは2つある。
- 1つ目は、ウィーンは非常にコンパクトであり、キーパーソンに会いやすい環境であること。国として、研究やテクノロジー、イノベーション分野に力を入れているため、イベントに大臣などの出席があるなど、主要人物と直接会う機会があることは他国にはないメリットであった。
- 2つ目は、個人情報の取り扱いやAIの社会実装などの問題について、産業界と対話が持てる環境が整っていること。EU一般データ保護規則(GDPR)やAIの包括的な規制枠組み規則案(AI法案、AI Act)について、オーストリア連邦産業院(WKO)が主催するセミナーなどに参加することで、スタートアップ同士や大学研究者と議論ができ、1スタートアップとして声を上げることができる環境にある。
- ただ、法律とは関係なく、市民が感じる心理的なハードルについては、実際に現地に進出し、出展などを通じて市民と交流してみないことには分からない。アルスエレクトロニカ・フェスティバルに出展した際、自らのスマートフォンを使用して体験する出展物に対し、最先端技術の祭典に来ている来場者であっても、拒否反応があったことは新たな発見であった。コンプライアンス順守だけでなく、当社技術と市民の間の信頼関係構築のために、情報発信の仕方も重要であると学べた機会となった。
- 質問:
- オーストリア政府からはどのような支援を得られたか?
- 答え:
- FFGからは、GINプログラムの一環として3度のオーストリア渡航に係る費用の助成が得られた。費用負担だけでなく、関係者とのネットワーク機会も作ってもらえたことで、進行するプロジェクトがある状態で進出することができた。GIN以外のFFGの助成プログラムについても、どの助成金が適切かどうかのアドバイスも得られ、現在はオーストリア企業として応募ができる助成金2種類の申請を終え、結果待ちをしているところ。GINプログラムのアルムナイ(卒業)企業としても、スタートアップイベントなどがある際には声をかけてくれ、登壇機会を得られることもありがたい。
- オーストリア経済振興会社(ABA)には、2022年に行われたマルティン・コッハー労働・経済相の日本へのビジネスデリゲーション派遣中に行われた投資セミナーなどへ招待してもらえ、オーストリアへの理解を深める大きな手助けとなった。また、彼らの日本での窓口である在日オーストリア大使館商務部の担当者紹介や、設立準備に係る各種質問への回答、法律事務所紹介など、ソフト面での支援も手厚かった。ABAのホームページにはインタビュー記事も掲載してもらえ、広報面での支援にもなっている。
- 質問:
- 進出準備段階、進出後の困難は?
- 答え:
- 準備段階では、(1)ビザと会社設立でそれぞれの書類が必要となったこと、(2)非常に多様な書類が求められるほか、途中で追加書類の提出が求められることもあり、一筋縄ではいかないこと、(3)書類提出後の待ち時間が長いこと、に苦労をした。会社用銀行口座を開設するためには銀行との面談や公証人面前での署名もあり、審査で数カ月かかるなど、最終的に設立に至るまで約150日を要した。
- 進出後には、(1)語学面での壁、(2)助成金選び、の困難があった。英語での情報も用意されてはいるものの、詳細についてはドイツ語のみのページとなっていることがあるなど、自ら言語を習得するか、早急に現地採用を行うことが求められると感じた。また、助成金の種類は多い一方、条件や内容が整えられておらず、個別に担当者へ問い合わせる必要があった。
- 質問:
- 今後ウィーンでの展望や課題は?
- 答え:
- ウィーンは研究開発拠点として設立しているが、欧州の人の反応と日本の人の反応は、文化的な差異も相まって異なる。まずは日本の顧客、その次に欧州の顧客をターゲットにするつもりだが、オーストリアでのデータが日本に合うかは判然としていないため、どちらでもデータを集め、比較研究を進めていく予定。
- そもそも行動変容を促すことは、その手前に人の意思決定を変えていることから始まっている。他方、意思決定時に何が起きているのかは不明な点が多い。行動変容を促せても、意思決定時に余計な負荷をかけていたのでは本末転倒となりかねないため、技術の透明性を上げるためにも、そうしたポイントに留意しつつ、今後の研究開発を進めていきたい。
- また、研究拠点としての機能を加速化するために、研究開発要員の積極的採用を行う予定。ウィーンでは少人数体制となるため、別途、日本親会社にも還元できるようなAIエージェントを社内ツールとして開発し、効率化を推進していく。
- 質問:
- これから進出を検討するスタートアップへのアドバイスは?
- 答え:
- 進出にあたり立ちはだかる困難は、基本的には他社も経験してきている「解答のある課題」である。やるべきことが多く、苦労もあるが、解答はあるため、粘り強く取り組めば必ず解決できる。特に肌感覚としてオーストリアは、日本企業への寛容さを感じる。他方、担当者によって対応は異なるため、先人たちとのコネクション作りは大切になるかと思われる。
- スタートアップの進出に際しては、会社のことばかりに注力しがちであるが、自身のケアや、帯同家族のケアなどが非常に肝要である。オーストリアは比較的生活がしやすい国ではあるが、家族も併せて心身ともに健康であることが進出において重要なポイントとなるのではないかと思う。
-

Godot入居オフィスのカフェテリアスペース(Talent Garden Vienna Campus)
(ジェトロ撮影)

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ウィーン事務所
神谷 真由(かみや まゆ) - 2021年、ジェトロ入構。企画部企画課を経て2023年7月から現職。




 閉じる
閉じる






