越境ECの課題と克服ポイント(日本)
JAPAN STORE参加企業に見る米英アマゾン出品の実態と工夫
2025年11月18日
新型コロナ禍を機に生活に根付いた電子商取引(EC)は、今や海外の消費者に直接商品を販売する手段として有効な手段の1つといえる。
本稿では、越境EC(BtoC)の中でも、特に欧米で高いシェアを持つアマゾンを通じた販売において、日本企業が直面する課題と取り組みのポイントを取り上げる。
はじめに:越境ECで海外消費者に直接販売するには
越境EC販売の主な手順は図1のとおりである。越境EC販売においてもBtoB販売と同じく、現地の輸入規制や、食品や衛生品などに関する認証、税制などへの対応が必要で、手続きをあらかじめ確認しておきたい。
図1:EC販売を行う際の主な取り組み事項
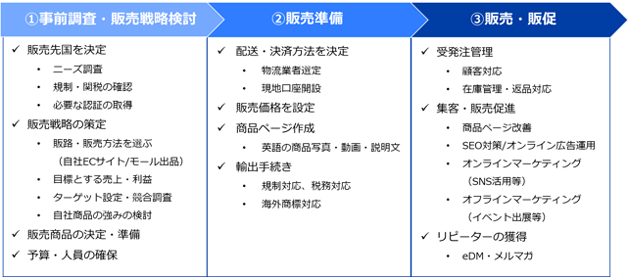
出所:ジェトロ作成
なお、販売先国がある程度想定されている場合は、事前の市場調査として、現地大手プラットフォームなどで、検索ボリューム、商品ラインナップ、競合商品の価格やレビューなど、消費者ニーズや市場環境の確認を行っておくことが望ましい。
越境ECアマゾンで販売する企業が抱える課題と対応策
越境ECプラットフォームの中で、アマゾンは北米、中南米、欧州をはじめ18カ国で展開、35カ国で利用可能であり、多国展開も視野に入れると比較的取り組みやすいプラットフォームといえる。なお、初めて海外アマゾン販売に取り組む企業は、市場が大きく規制面からもハードルが低いといわれている米国から挑戦する場合が多い。
ジェトロは、アマゾンと連携し「JAPAN STOREプログラム」(米英アマゾン出品販売) を実施している。本事業参加者を対象としたアンケート(2023、2024年度)およびヒアリング結果をもとに分析を行ったので以下で紹介する。
出品から売り上げ拡大の段階で、取り組むべき課題が変化
初めて越境ECに取り組む場合は、出品手続きが最初の関門である。一方で、出品をクリアし、ECサイトに商品を掲載さえすれば自動的に売れるわけではない。出品後に売上高を伸ばすためには、自社商品への消費者からの認知度の向上、関心喚起、そして購入につなげる取り組みを行うことが重要だ。
アマゾン出品販売において取り組むべき課題を出品・販売状況別に見ると(図2参照)、(1)出品、(2)最初の売り上げ創出、(3)売り上げ拡大、とステップごとに課題が移行していることがうかがえる。まず、出品手続きの段階では「物流手続き」や「予算の確保」、次に、出品後の売り上げ創出の段階では「商品認知度の向上、アクセス数の増加」が加わり、そして、売り上げ拡大、売り上げ上位(注1)の段階では「SEO(検索エンジン最適化)対策・広告運用」が課題として挙げられる。また、売り上げが安定してからも、「規制や関税(FDA、VAT)」、「Amazonのテクニカルな問題」など、当局やアマゾンの制度変更、トラブル対応が継続して発生することが見てとれる。
図2:売り上げ状況別の課題
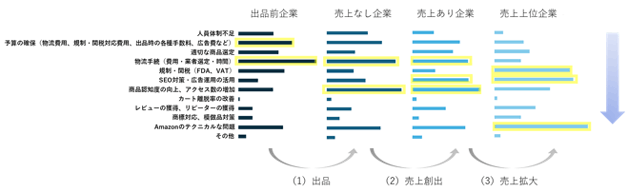
注:「売り上げ上位」とは、JAPAN STORE参加企業向けアンケート実施時点の当該企業のAmazon.comにおける売上高と企業の回答をクロス集計した上位1割の企業を指す。
出所:2023年度JAPAN STORE参加企業向け第4四半期アンケートを基にジェトロ作成(2024年3月実施)
出品前に準備しておきたいこと
1.最初のハードル「出品準備」
アマゾンでの販売において大きな関門は出品だ。出品者はプラットフォーム上に商品情報を公開し消費者が購入できる状態にするまでに、規制対応や関税対応、物流手続き、現地口座開設、商品ページ作成などを行う必要がある。
アンケート時点で、プログラム参加企業のうち未出品企業が米国では約3割、英国では約7割と、少なくない企業が出品に至っていない状況であった。
未出品の理由(複数回答可)としては、米国と英国いずれも約半数が「商品準備に時間がかかっているため」と回答した(図3参照)。商品準備内容は、ラベルやパッケージの海外対応、現地の規制やニーズに合わせた商品の選定・作成、商品ページ掲載写真や英語説明文の準備などが挙げられる。
次いで、米国では「配送業者を手配中のため」、英国では「認証取得中のため」という理由が多かった。とくに食品や医薬品の場合、米国、英国ともに規制や認証取得の必要性がある品目が多く、準備に時間を要する。加えて英国では、品目に関わらず付加価値税(VAT)登録などが必要であり(調査レポート「英国VAT登録手続きガイドブック」参照![]() (1.46MB))、3カ月から6カ月程度の時間を要すると言われている。
(1.46MB))、3カ月から6カ月程度の時間を要すると言われている。
なお、アマゾン販売における配送方法としては、(1)注文ごとに輸送する自社出荷、(2)海外現地のアマゾン倉庫にあらかじめ配送し、アマゾンが都度配送を行うFBA(Fulfilment by Amazon)(注2)という仕組みがある。すぐに配送されるFBA活用商品は検索結果の上位に掲載されやすいというアマゾンの仕組みにより、FBAを使う事業者は多い。
図3:出品が開始できていない理由
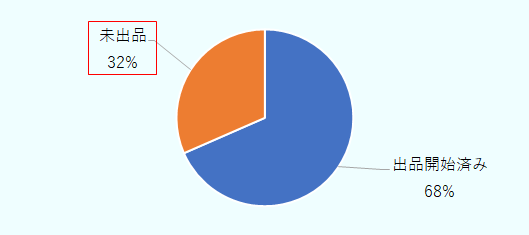
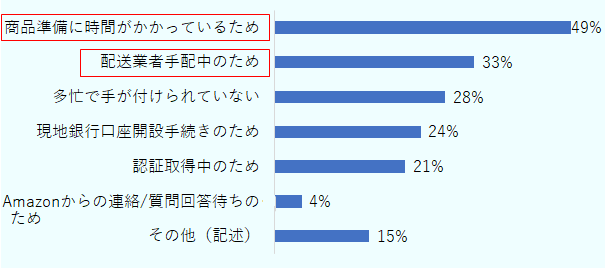
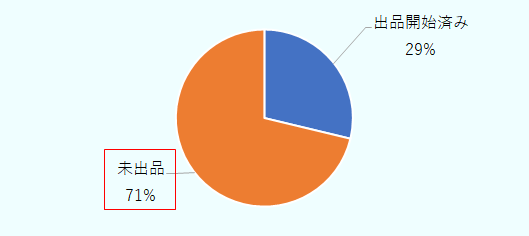
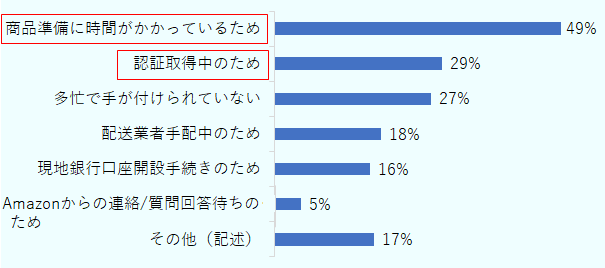
出所:2024年度JAPAN STORE参加企業向け第1四半期アンケートを基にジェトロ作成(2024年7月実施)
2.社内の課題「予算確保」
「予算の確保」を課題として挙げる事業者も多い。海外アマゾン販売には、アマゾンに対し支払う出品・販売手数料、規制や関税関連費用〔例えば米国食品医薬品局(FDA)認証の取得、英国の付加価値税(VAT)登録など〕、配送費用、広告費用などのコストが発生する。
米国アマゾン販売における予算投下額(上位3項目)としては、「配送・物流」が全体で最も多く、売り上げのある企業では次いで「広告予算」の割合が高かった(図4参照)。出品後の広告費用なども考慮し、長期的な視点で予算を検討しておきたい。
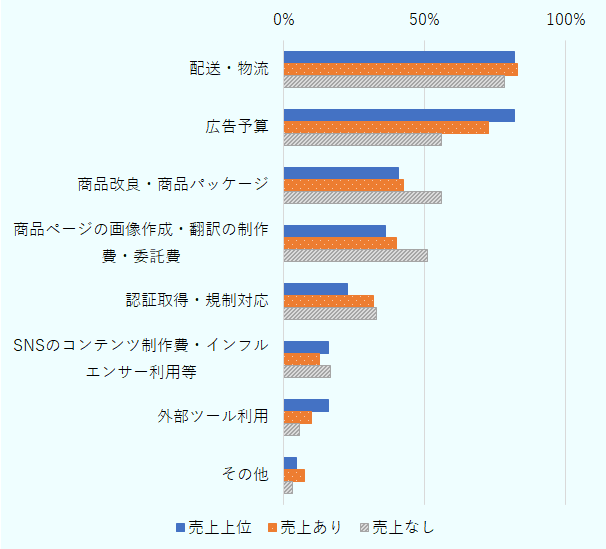
注:「売り上げ上位」の定義は図2と同じ。
出所:2024年度JAPAN STORE参加企業向け第1四半期アンケートを基にジェトロ作成(2024年7月実施)
3.商品を売るための「市場調査」
さらに、EC販売を始める前に取り組んでおきたいのが市場分析だ。米国向け販売者のうち、売り上げ上位企業ほど市場分析を実施していた(図5参照)。特に類似商品のレビューの確認や自社商品との比較、販売数や損益分岐点のシミュレーションなどは、売り上げの有無により差が大きく出ていた。
商品選定時の検討事項(図6参照)として、売り上げ上位企業とそれ以外の企業で、「現地消費者のニーズがあると思われる商品」と「日本国内で売れている商品」が逆転しているように、市場や消費者ニーズの分析は商品選定に生かされているといえる。日本で売れている商品でも、米国向け販売に適しているかどうか検討する必要がある。
現地ニーズに合った商品を選び、競合と差別化できるポイントや商品の魅力の伝え方を考慮した商品ページを整えて、出品開始ができるようにしておきたい。
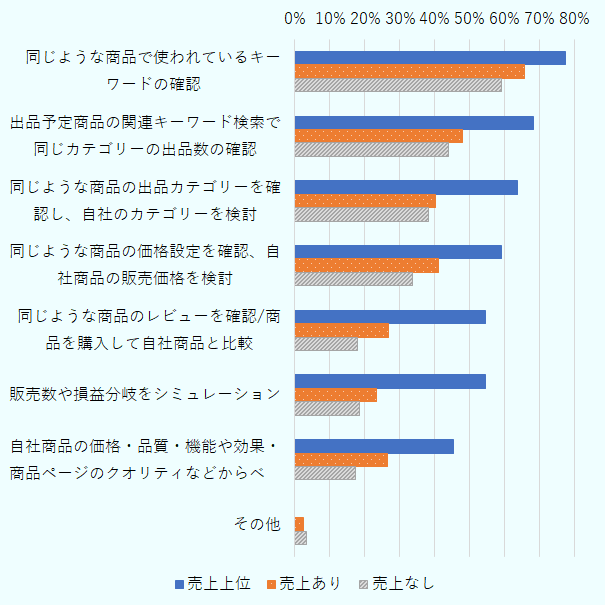
注:「売り上げ上位」の定義は図2と同じ。
出所:2024年度JAPAN STORE参加企業向け第1四半期アンケートを基にジェトロ作成(2024年7月実施)
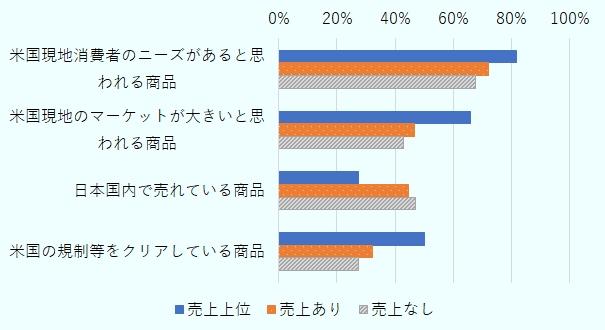
注:「売り上げ上位」の定義は図2と同じ。
出所:2024年度JAPAN STORE参加企業向け第1四半期アンケートを基にジェトロ作成(2024年7月実施)
出品後の取り組み:消費者を呼び込み、商品の魅力を伝える
出品が開始できても、「出品しているだけでは売れず、在庫が残ってしまう」「年間の売上高が伸びず、物流費がかさみ採算が合わない」といった声は多い。アマゾン内にはさまざまな販売促進ツールがあるが、全体として売り上げにつながっていない企業はツールの活用度が低く、販売促進ツール活用と売り上げ有無には相関が見られる。
1. アマゾン販売における販売促進ツール
売り上げ上位の企業が活用しているツールとしては、「A+コンテンツ(商品紹介コンテンツ)」「クーポン・タイムセール」「ブランドストア」「VINE」が多かった(図7参照)(注3)。また、今後活用を検討しているツールは、「クーポン・タイムセール」「ブランドストア」「SEO改善を含む商品ページ改善」が多かった。
小売店におきかえると、店舗の外装・内装が「ブランドストア」、購入者レビューを促すのが「VINE」、看板や販売員が「SEO改善を含む商品ページ改善」や「A+コンテンツ(商品紹介コンテンツ)」、セールでの集客などが「クーポン・タイムセール」、といったイメージを持つとわかりやすいだろう。
図7:米国アマゾン販売で活用している販売促進ツール、
今後活用を検討している販売促進ツール
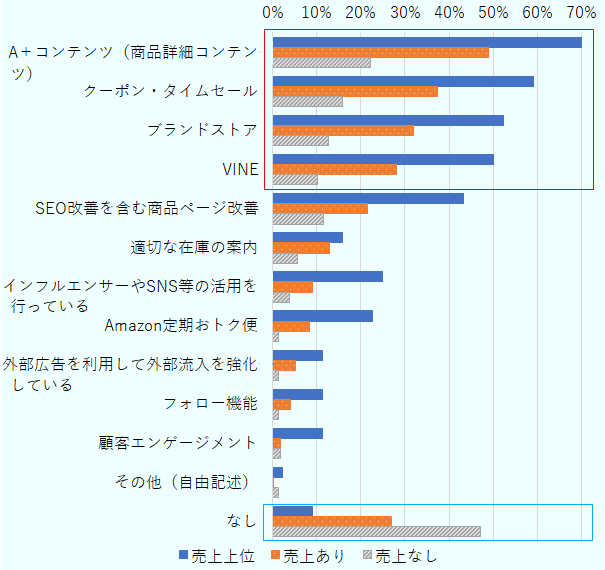
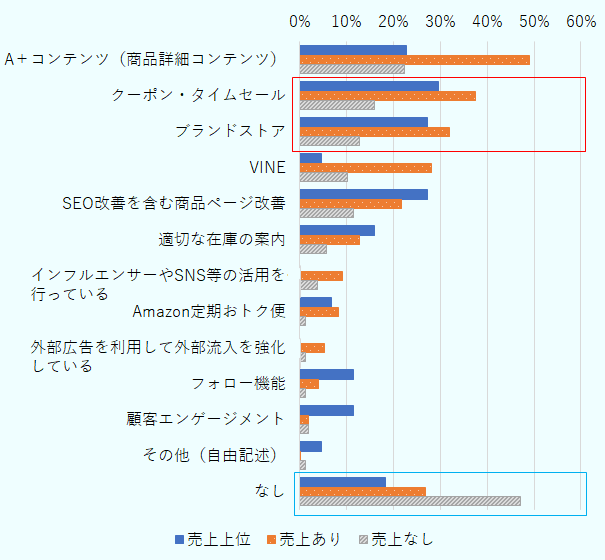
注:「売り上げ上位」の定義は図2と同じ。
出所:2024年度JAPAN STORE参加企業向け第1四半期アンケートを基にジェトロ作成(2024年7月実施)
2. 消費者の目線で、効果的に訴求する工夫を
売り上げを出している企業へのヒアリングによると、販売促進ツールを使うだけでなく、いかに消費者目線で魅力的な商品提案ができるかもポイントであった。
例えばSEO改善では、消費者がほしい商品を検索した時に自社商品が上位に表示されるよう、「検索キーワード」を商品ごとに設定する。その際には、消費者に刺さりやすく自社商品の購入につながりやすいキーワードを探して設定することが重要である。また商品ページでは、画面だけで魅力や強みが伝わるような商品説明文、写真、動画コンテンツ、他社商品との比較コンテンツなどが活用できる。
実際にアマゾンで販売し、売り上げを伸ばしている企業へのヒアリングでは、販売促進の取り組みとして以下が挙げられた。各社がさまざまな工夫により売り上げ向上やブランド構築に努めていることがわかる(注4)。
- 商品ページは営業パーソンの役割を果たすため、ChatGPTを活用した説明文作成や、十分なリソース投入をしている。
- ブランドの見え方を重視し、高級感が伝わるよう、色や質感を意識した画像や動画を入れている。ブランドページでは商品のラインナップやスマートフォンでの見え方も意識したページ設計にしている。
- 競合商品のレビューや商品ページを見て現地消費者のニーズをつかみ、自社商品の訴求方法の参考にしている。レビューを踏まえて説明文も修正している。
まとめ
ここまで見てきたように、越境EC販売は取り組み方法にかなり幅があると言える。常に新しいツールや情報が出る分野でもあるため、越境ECにこれから取り組む、または取り組んでいる事業者は、さまざまな情報源にあたりながら戦略を練るとよいだろう。
- 注1:
- JAPAN STORE参加企業向けアンケート実施時点の当該企業のAmazon.comにおける売上高と、企業の回答をクロス集計した上位1割の企業を指す。
- 注2:
- FBA(Fulfilment by Amazon)は、アマゾンが商品の保管・発送・カスタマー対応を代行する仕組み。米国アマゾンで販売する場合、事前に米国のアマゾンの倉庫に商品を送っておく必要がある。
- 注3:
-
各用語の意味は以下のとおり。
- 「A+コンテンツ」は、商品ページに写真や説明文を追加できる機能。商品の魅力を詳細に伝える際に活用される。
- 「クーポン・タイムセール」は、一定期間だけ割引を行う販促手法。消費者の購入意欲を高めるために活用される。
- 「ブランドストア」は、アマゾン内に自社専用のページを作成できる機能。ブランドの世界観を伝える場として活用される。
- 「VINE」は、アマゾンが選んだレビュアーに商品を提供し、レビューを書いてもらう仕組み。
- 注4:
- 各社の工夫など、「JAPAN STOREプログラム」参加企業の具体的な活用事例を参照されたい。

- 執筆者紹介
-
ジェトロデジタルマーケティング部ECビジネス課
松田 かなえ(まつだ かなえ) - 2020年、ジェトロ入構。企画部、ジェトロ・ベンガルール事務所を経て、2023年9月から現職。




 閉じる
閉じる






