スピードが重要
インドの財閥・ビジネスリーダーに聞く協業(1)
2025年9月17日
中長期的なビジネス展開先として注目が続くインド。2024年のインド進出日系企業数は1,434社、5,205拠点でインド国内の拠点拡大の動きは顕著だが、新規進出企業数は近年、横ばいとなっている。国際協力銀行(JBIC)による日本の製造業企業の海外事業展開に関するアンケート調査(2024年度)でも、インドは今後3年程度の有望な事業展開先国として3年連続で首位となるなど進出への関心は高いが、実際の進出には課題も多いことが見て取れる。こうした中、インドビジネスを検討する際、地場企業との様々な形での協業を検討することもできるだろう。インドのビジネスリーダーたちは日本企業をどう捉えており、どういった協業が検討できるのか。インドを代表する多様な業界のビジネスリーダーたちに聞いた。
世界的鍛造メーカー:バーラト・フォージ
インド西部マハーラーシュトラ州プネに本社を置き、海外にも製造拠点を有する世界的な鍛造メーカーであるバーラト・フォージ![]() 。自動車・産業分野向けの高性能製品の供給で知られているが、近年は航空宇宙・防衛製品の製造・供給など事業の多角化を進め、人工知能(AI)や先進ロボティクスなどの新興分野への投資も急拡大している。インドを代表する実業家であり、日印ビジネス・リーダーズ・フォーラム共同議長を長く務めるなど、日本にも造詣が深いババ・カリヤニ会長に、インド市場の魅力などについて聞いた(インタビュー日:2025年7月8日)。
。自動車・産業分野向けの高性能製品の供給で知られているが、近年は航空宇宙・防衛製品の製造・供給など事業の多角化を進め、人工知能(AI)や先進ロボティクスなどの新興分野への投資も急拡大している。インドを代表する実業家であり、日印ビジネス・リーダーズ・フォーラム共同議長を長く務めるなど、日本にも造詣が深いババ・カリヤニ会長に、インド市場の魅力などについて聞いた(インタビュー日:2025年7月8日)。

- 質問:
- インド市場の魅力と日本企業の機会は。
- 答え:
- 世界でもっとも急速に成長している大規模経済国のインドは、世界で最後の大市場だ。若くて豊富な人的資源、優秀な技術者も多く、様々なビジネス機会に溢れ、世界中の企業と協業している。世界各国で活発に活動している中国企業の影響が少ない点も、好材料だろう。米国アップルがiPhoneの委託製造をインドに移管するなど、サプライチェーン多角化の観点からも世界からの注目度は増している。インド政府が積極誘致する電子産業においては、中国、台湾、韓国などの東アジア諸国・地域と共に日本にも大きな強みがある。
- 質問:
- インド人材の活用については。
- 答え:
- 先進国の人口は減少傾向にある。日本、韓国、米国、中国、ロシア、欧州などの各国が低出生率に直面する中、日本の出生率低下と高齢化は加速している。一方、インドは、今世紀中は最大の社会となる見込みで、今後25~30年間、毎年数十万人の高度なスキルと教育を受けた人材を輩出する大規模な労働者層を擁している。日本とインドは、共通の価値観を有し、お互いの社会を尊重している。日本は、インドが持つ豊富な人材プールを活用すべきだ。そのために、才能ある人材を発掘し、魅力を感じてもらうためのマーケティングをする必要がある。インドの教育機関ではインド工科大学(IIT)がよく知られているが、地域ごとに高いレベルの人材を輩出する他の機関も多く存在するため、他の機関にも積極的にアプローチすべきだ。
インドの変化のスピードは速い
- 質問:
- 日本企業に対するアドバイスは。
- 答え:
- 日本企業は、よりオープンになるべきだ。今後、日本の人口減少は加速し、経済も縮小していくので、行動にスピードが必要だ。特に日本の中小企業は、インド企業と組み、様々な協業を模索すべきだ。
- 信頼感の高い日本企業との協業への関心・評価は高いが、協業におけるロードマップが必要で、それが5年前と同じものではいけない。インドはとても速いスピードで変わり続けていることを理解する必要がある。研究開発への共同投資や世界市場向け製品の共同開発・生産などで、大きな可能性があるだろう。
- 質問:
- 貴社の現在の協業の関心事項は。
- 答え:
- 当グループとしての関心は様々ある。一方で、当面の重要な焦点としては、造船事業を開始するにあたり、協業先を検討している。通信システム・コントロール分野では米企業と協力の予定だが、エンジンやタービンなどの分野の協業先を探している。
トヨタとの合弁でも有名なコングロマリット:キルロスカ・グループ
銑鉄鋳物、発電機、冷却装置、コンプレッサーなどの製造や、ノンバンクなどの金融、不動産分野などにも参入するキルロスカ・グループ。135年以上の歴史があり、グループ全体で、70カ国超でビジネスを展開している。同グループの自動車部門では、トヨタ自動車との合弁事業も有する。銑鉄鋳物を扱うキルロスカ・フェラス![]() のラフール・キルロスカ会長には、日本企業との協業可能性について尋ねた(インタビュー日:2025年7月8日)。
のラフール・キルロスカ会長には、日本企業との協業可能性について尋ねた(インタビュー日:2025年7月8日)。
- 質問:
- 日本企業との協業への関心は。
- 答え:
- 検討可能だ。まずは販売、アッセンブリーなどから検討を開始し、ビジネスになるかどうかを検証する必要がある。
- 質問:
- どのような分野での協業に関心があるか。
- 答え:
- 主に特殊鋼、エレベーター、モーターなどのエンジニアリング製品に関心を持っている。
- 質問:
- 海外企業との協業に求めることは。
- 答え:
- 当社は基本的に、製品のライセンス供与、または両社の利益が保護されるような合弁事業への参画を検討している。
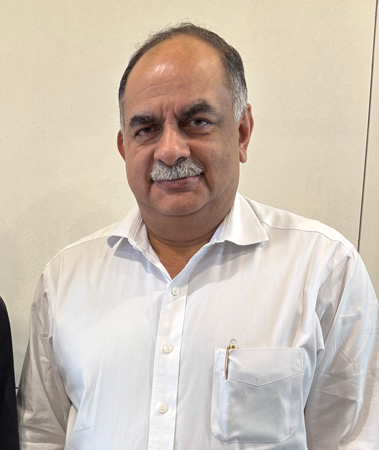
デジタル界のリーダー:TVモハンダス・パイ氏
大手IT企業インフォシスの元取締役兼最高財務責任者(CFO)でインドのデジタル分野の第一人者であるTVモハンダス·パイ氏(Aarinキャピタル![]() 共同創業者兼会長、3one4キャピタル
共同創業者兼会長、3one4キャピタル![]() 会長)には、デジタルおよびその他の分野も含めた日本企業のインドビジネスについて聞いた(インタビュー日:2025年7月9日)。
会長)には、デジタルおよびその他の分野も含めた日本企業のインドビジネスについて聞いた(インタビュー日:2025年7月9日)。

- 質問:
- 日本企業のインドビジネスに対する期待は。
- 答え:
- インド経済は大きく発展しており、IT、鉄鋼、自動車、生命科学、デジタル、住宅など、多くの分野で、世界有数の市場に成長している。また人材の宝庫でもあり、現在、中国を除いた世界のエンジニアの半分はインド人だと言われている。米国はIT技術者の多くをインドに頼っているとともに、グローバル企業のトップをはじめ、銀行、病院、大学など、多くの分野でインド人が活躍している。
- 日本は、インドでより存在感の強いビジネスプレーヤーとなることを目指すべきだ。日印で協力し、インド国内のみならず、アジアを変えていきたい。インドビジネスは難しいといった意見を聞くことがあるが、昔の苦労話やメディアによるネガティブな側面が伝わっている様子もあり、インドの古くなったイメージを持っている人も多いのではないか、と感じる。
- 質問:
- 日本企業のインドビジネスにおけるハードルは。
- 答え:
- 日本企業は自分たちのことをオープンにしない、クローズドな文化だと感じる。また日本がインドでのビジネスになじまない背景としては、英語を話す人が限られること、内向き志向であること、インド拠点の運営を日本人が担うことが多い点などが挙げられる。インド拠点では、日本人の代表が日本本社との連絡や対応を担当し、インドのビジネス自体はインド人の代表が監督するべきだ。
日本企業は「大胆な発想力」を持つべき
- 質問:
- 日本企業へのアドバイスは。
- 答え:
- パートナーとしての日本は、関係構築に時間がかかるが、一度親しくなるとそこからの物事の進みはとても速いという印象がある。しかし、インドが急速に変化し続ける中、準備にあまり長い時間はかけられないので、日本企業は動きを速くし、インドで良いパートナーを探す必要がある。そして日印ビジネスでは、日本を知っているインド人などのブリッジ人材の活用が効果的だと感じる。
- 日本企業は、小さなことに時間を費やすべきではなく、ぜひ「Think Big(大胆に発想)」すべきだ。
- 質問:
- デジタル分野での日印企業の協業を促進する上で重要な点は。
- 答え:
- 日印間には、安倍政権時代に署名された「日印デジタル・パートナーシップ」が締結されており、この基盤をさらに強化する必要がある。日本の大手企業を中心に、米国企業のように、インドにグローバル・ケイパビリティー・センター(GCC、注)を設立すべきだ。そして、インドの世界トップクラスの人材を集め、AIを活用したデジタル変革を実現し、ビジネスの利益率と柔軟性を高めるべきだ。
- また、日印のスタートアップ企業が、定期的に相互の国を訪問し合い、関係性を強化することが望まれる。ベンガルールに日本のインキュベーターを、東京にインドのインキュベーターを置く必要がある。日本の大手ファンドや銀行による、インドの銀行、ベンチャーキャピタルファンド、テック企業への投資拡大も重要だろう。インドのベンチャーキャピタル(VC)とスタートアップへの投資を促進するため、50億ドル規模の日印デジタルファンドの設立が望まれる。日本のディープテック製造企業がインドに進出し、委託製造を進め、拡大するインド市場を捉えることも重要だ。同分野の成長促進のための、「ベンガルール・東京デジタル・パートナーシップ」の設立も検討してもらいたい。
- メディアの役割も重要だと考えている。日本のメディアに訪印してもらい、インドの成長する経済、産業、デジタルイノベーションについて伝えてほしい。古い社会問題やインドをおとしめるような話題ではなく、インドのポジティブで正しい姿を伝えるべきだ。長きにわたり、メディアがインドの否定的なイメージを植え付けてきた側面は感じられ、そうした状況は改められるべきだ。
- 日本は大規模投資を行うことで、インドのような成長国の主要な経済パートナーとなるために5年ほどの猶予がある。この機会を逃せば、アジアは中国とインドに支配されることになり、中国、インド、日本という構図は崩れるだろう。時間は待ってくれない。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 リサーチ・マネージャー
古屋 礼子(ふるや れいこ) - 2009年、ジェトロ入構。在外企業支援課、ジェトロ・ニューデリー事務所実務研修(2012~2013年)、海外調査部アジア大洋州課、 ジェトロ・ニューデリー事務所(2015~2019年)を経て、2019年11月から現職。






 閉じる
閉じる





