自動車など、製造業の比重が引き続き拡大(メキシコ)
国立統計地理情報院(INEGI)が経済センサス2024発表
2025年9月3日
メキシコの国立統計地理情報院(INEGI)は7月24日、「経済センサス2024」の確定値を発表した。
この発表によると、製造業の事業所数は顕著に増加している。5年前の9.3%増、10年前の32.6%増、20年前の67.0%増だ。雇用も、同11.6%増、41.8%増、66.6%増と伸びている。経済活動で、製造業の重要性が高まっていることがわかる。
牽引しているのは、輸送機器(自動車など)製造業だ。この分類だけで、製造業全体が生む付加価値の30%超を占める。
他方で過去5年間は、全業種平均で、事業所の伸びと比較して雇用の伸びが低調になっている。非金融サービス業のように、むしろ減少した業種もある(当該業種では2000~2021年の新型コロナウイルス禍の影響が大きく、事業所数に比べて雇用の回復が遅れているのが一因)。過去5年間で規模が小さいインフォーマルな事業所が増え、全事業所の65%近くに及んだ。操業上の課題についてみると、インフレ進行による部材・商品価格の上昇、需要の低迷、光熱費の高さなどを問題視する事業所の比率が高まっている。
全体的に雇用の伸びが緩慢
INEGIは2024年2~8月、「2024年経済センサス(Censo Económico 2024、注1)」を実施。2025年7月24日に確定値を発表した。
当該調査によると、2024年時点でメキシコの事業所総数は709万3,631カ所。前回調査(2019年)から11.3%増、10年前の調査時(2014年)から25.5%増になった。一方、雇用総数は3,659万人。前回調査時から1.5%増、2014年比では23.4%増になる(図1参照)。
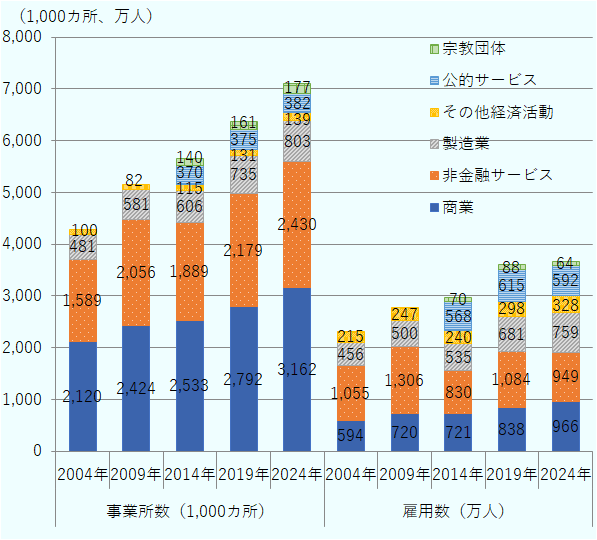
注:2009年までは、公的サービスが非金融サービスに含まれていた。
出所:国立統計地理情報院(INEGI)「経済センサス」(2004/2009/2014/2019/2024)からジェトロ作成
事業所数の増加に比して、雇用数が伸びていないのはなぜか。その背景には、零細な規模の事業所、特にインフォーマル(注2)な事業所が増加していることがある。今回の調査結果から要約すると、次のとおり。
- 全事業所の95.4%が従業員10人以下の零細事業者で、構成比が5年前から0.5ポイント拡大した。 これに対し、従業員11~50人の小規模企業が全体の3.7%、51~250人の中規模企業0.7%、250人超の大企業0.2%。5年前と比べ、それぞれ、0.3ポイント、0.1ポイント、0.04ポイント縮小した。中規模企業は、絶対数でも4.2%減少している。
- 1事業所当たりの平均従業員数は、5.2人。5年前の5.9人から、0.7人減少した。
- 零細事業者は、特に商業に多い。商業の1事業所当たりの雇用数は3.1人。
- 製造業では、雇用規模が大きくなる。それでも、平均9.5人。「町工場」のような工場が多いのが現状だ。
メキシコ経済は、2020年に新型コロナウイルス感染拡大の影響を強く受けた。当年、8.3%のマイナス成長を記録している。2021年以降は、経済が回復に転じた。しかし正規雇用の回復は緩慢で、失業者の多くがその後インフォーマルな事業所での就労に流れた。関連する指標は、次のとおり。
- 総事業所数に占めるインフォーマル比率は、過去5年間で62.6%から64.3%に高まった。
- 同様に、雇用に占める比率も18.9%から21.4%(注3)へ、粗付加価値に占める比率も3.0%から3.6%へ拡大した(図2参照)。
被雇用者全体の41.4%を雇用するのが、零細企業だ。当該規模の企業は、インフォーマル比率が高い。ちなみに、小規模企業は15.1%、中規模企業14.8%、大企業28.7%になっている。
小規模企業、中規模企業、大企業の雇用比率が前回調査時(それぞれ17.0%、16.1%、29.1%)から縮小した。これに対し、零細企業の比率は37.0%から4.4ポイント拡大し、零細企業の雇用に占めるウエートがさらに高まっている。
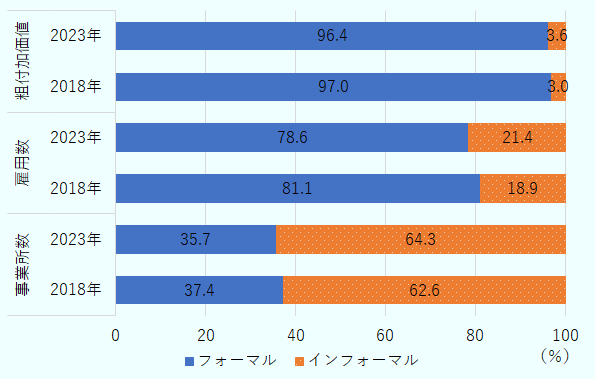
注:5人以下の従業員で社会保険負担金を支払わず、会計システムの利用や会計帳簿の整備などを行っていない事業所を「インフォーマル」な事業所と定義。
出所:INEGI「経済センサス」(2019,2024年)からジェトロ作成
産業分野別に事業所・雇用データについてみると、以下のとおり。
- 事業所数では、商業が約316万カ所(構成比44.6%)で最も多い。前回調査から13.3%増え、構成比も0.8ポイント拡大した。
- 商業の雇用数は966万人。前回調査時から15.4%増、構成比も3.2%ポイント拡大した。
前回調査で雇用数は、非金融サービスが1,084万人で最多だった。しかし今回は12.5%減少して949万人。商業を下回った。 - 非金融サービスの事業所数は、243万カ所。11.5%増になる。
- 製造業は、事業所数で全体の11.3%、雇用数で同20.8%を占めた(前回調査から、それぞれ9.3%増、11.6%増)。
事業所数でウエートが0.2ポイント縮小した一方、雇用数は1.9ポイント拡大した。
自動車産業を中心に重要性増す製造業
調査対象の事業所が2023年に生み出した付加価値を産業分野別構成比でみると、製造業が34.3%を占めて最大。小売業(13.4%)、卸売業(10.2%)、金融・保険業(9.4%)、鉱業(7.0%)が続く(表1参照)。
付加価値の構成比を前回、前々回調査と比較すると、鉱業が10年間で大きく縮小した(16.8%→7.0%)。その原因としては、(1)石油公社(PEMEX)の非効率経営により、原油・天然ガスの生産が低迷したこと、(2)アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール(AMLO)前政権が、鉱業分野の投資を減退させる数々の政策を導入したこと(注4)などを挙げることができる。
一方で製造業は、2018年比で2.35ポイント、2013年比で5.33ポイント拡大している。(1)自動車産業が成長したことに加え、(2)米中貿易摩擦を背景に近年、ニアショアリングが進展したことが奏功した(2024年10月17日付地域・分析レポート参照)。特に輸送機器(自動車や航空機を含む)製造業の粗付加価値をみると、2023年時点で全体の10.8%に達した。
| 産業分野 | 粗付加価値(A) | 総固定資本形成(B) | 増減 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年-2018年 | 2023年-2013年 | |||||||||
| 2013年 | 2018年 | 2023年 | 2013年 | 2018年 | 2023年 | (A) | (B) | (A) | (B) | |
| 漁業・養殖業 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 鉱業 | 16.8 | 9.5 | 7.0 | 36.3 | 15.1 | 41.6 | △ 2.43 | 26.51 | △ 9.77 | 5.31 |
| 電気・ガス・水道 | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 8.0 | 20.8 | 0.08 | 12.76 | △ 2.06 | 16.29 |
| 建設業 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.20 | 1.20 | 0.25 | 0.70 |
| 製造業 | 29.0 | 32.0 | 34.3 | 26.6 | 26.5 | 48.1 | 2.35 | 21.53 | 5.33 | 21.41 |
 輸送機器製造業 輸送機器製造業
|
6.3 | 10.0 | 10.8 | 6.3 | 7.1 | 31.8 | 0.73 | 24.62 | 4.47 | 25.48 |
| 卸売業 | 6.4 | 8.8 | 10.2 | 2.6 | 13.6 | 0.3 | 1.38 | △ 13.36 | 3.73 | △ 2.36 |
| 小売業 | 9.1 | 12.6 | 13.4 | 4.4 | 3.8 | 9.1 | 0.80 | 5.36 | 4.28 | 4.74 |
| 運輸・郵便・倉庫 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 3.2 | 8.1 | 0.15 | 4.92 | 0.50 | 2.43 |
| 通信・マスメディア | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 4.0 | 18.7 | 3.2 | △ 0.25 | △ 15.45 | △ 1.01 | △ 0.73 |
| 金融・保険 | 9.5 | 8.6 | 9.4 | 3.1 | 3.0 | 6.5 | 0.79 | 3.49 | △ 0.08 | 3.33 |
| 不動産・賃貸 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | △ 0.28 | 0.74 | 0.17 | 1.02 |
| 専門・科学・技術サービス | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | △ 0.61 | △ 0.37 | △ 0.09 | △ 0.36 |
| 関連会社統括・経営 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | △ 0.36 | 0.72 | △ 0.64 | 0.43 |
| 経営・廃棄物関連サービス | 4.0 | 4.7 | 1.7 | 4.7 | 0.8 | 2.1 | △ 2.94 | 1.34 | △ 2.27 | △ 2.62 |
| 教育(私立) | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | △ 0.13 | 1.13 | △ 0.21 | 0.91 |
| 健康・医療・福祉 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.33 | 0.72 | 0.33 | 0.39 |
| 娯楽・スポーツ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.05 | 0.57 | 0.12 | 0.27 |
| ホテル・レストラン | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | 0.74 | 1.12 | 1.49 | 1.75 |
| その他サービス | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | △ 52.2 | 0.05 | — | △ 0.14 | — |
| 合計(注) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:「経済センサス」の調査対象には農業関連の事業所が含まれていない。
出所:INEGI「経済センサス」データ(2014/2019/2024年版)からジェトロ作成
総固定資本形成(設備投資や建設投資など)の構成比でも、最大が製造業だった(48.1%)。これに、鉱業(41.6%)、電気・ガス・水道(20.8%)が続く。
製造業の総固定資本形成は、過去5年間で21.5ポイント拡大した。中でも輸送機器製造業は、24.6ポイント拡大している。また2023年は、輸送機器製造業の総固定資本形成だけで、全産業の31.8%に達した。
「粗付加価値」「総固定資本形成」「雇用」の3項目で、製造業の内訳をみると次のとおりになる。
- 粗付加価値:
輸送機器(自動車など)が、31.3%で最大。これに、加工食品(15.4%)、化学(7.2%)、プラスチック・ゴム(5.1%)、飲料・たばこ(5.1%)が続く(図3参照)。 - 総固定資本形成:
輸送機器が、52.6%と過半。プラスチック・ゴム(6.4%)、卑金属(6.3%)が続く。 - 雇用:
輸送機器が、20.7%と2割を超えた。
ちなみに10年前には、加工食品が最大の雇用を生み出していた。現時点では、輸送機器が同産業(内訳16.9%)を大きく上回る。そのほか、金属製品(7.0%)、プラスチック・ゴム(6.4%)の雇用規模が大きい。
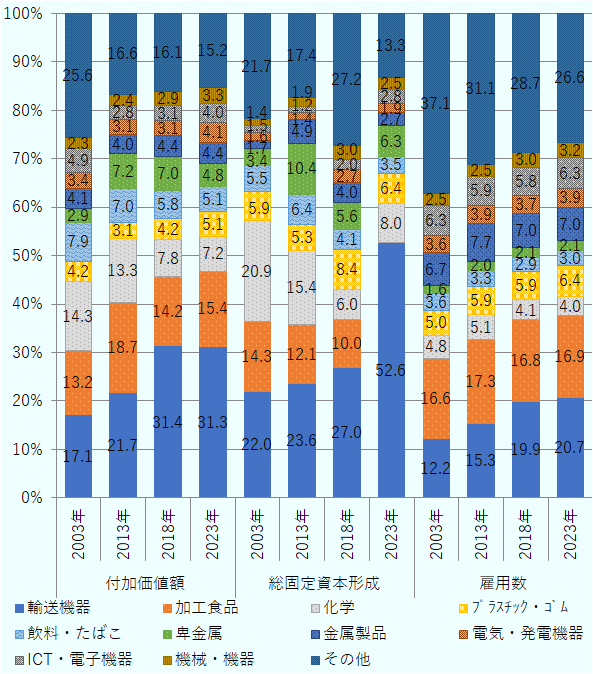
注:総固定資本形成は償還超過分を除く。
出所:INEGI「経済センサス」データ(2009/2014/2019/2024年版)からジェトロ作成
輸送機器製造業の粗付加価値、総固定資本形成、雇用を10年前と比較すると、構成比がそれぞれ9.64ポイント、29.00ポイント、5.41ポイント拡大した。メキシコを代表する基幹産業に成長したことを、ここからも読み取れる。
自動車産業の大半は大企業
事業所の特徴は、産業や製品分野別で大きく異なる。
- 雇用規模:
全業種の全国平均で、1事業所当たり5.1人になる(2023年に事業を実施した事業所に限り、行政機関と宗教団体を除く/表2参照)。
しかし、輸送機器製造業(同409.4人)では、大半が大企業になる。特に完成車メーカー(同2,044.5人)の雇用規模が大きい。また自動車部品メーカー(同575.7人)も、500人を超える。
そのほか、情報通信技術(ICT)・電子機器製造(同504.8人)など、外資系企業が多い業種の雇用規模は総じて大きい。
| 産業分野 |
事業所数(注1) (箇所) |
雇用規模 (人/箇所) |
従業員 平均年収 (ペソ/年) |
固定資産/従業員 (ペソ/人) |
付加価値/従業員 (ペソ/人) |
付加価値/固定資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁業・養殖業 | 24,984 | 9.7 | 82,055 | 211,765 | 183,587 | 86.7 |
| 鉱業 | 3,123 | 53.5 | 337,945 | 6,453,797 | 6,609,653 | 102.4 |
| 電気・ガス・水道 | 2,961 | 78.1 | 299,948 | 10,914,703 | 1,534,929 | 14.1 |
| 建設業 | 19,501 | 36.5 | 148,107 | 235,615 | 452,799 | 192.2 |
| 製造業 | 579,828 | 12.4 | 206,150 | 534,545 | 749,753 | 140.3 |
 輸送機器製造 輸送機器製造
|
3,644 | 409.4 | 212,258 | 765,698 | 1,132,799 | 147.9 |
 自動車・トラック製造 自動車・トラック製造
|
67 | 2,044.5 | 263,848 | 2,785,430 | 5,935,230 | 213.1 |
 自動車部品製造 自動車部品製造
|
2,091 | 575.7 | 202,326 | 577,833 | 650,908 | 112.6 |
 航空機・同部品 航空機・同部品
|
131 | 350.5 | 269,195 | 482,819 | 547,610 | 113.4 |
 加工食品 加工食品
|
223,412 | 5.4 | 176,336 | 372,332 | 684,024 | 183.7 |
 飲料・タバコ 飲料・タバコ
|
33,008 | 6.5 | 200,609 | 399,963 | 1,271,056 | 317.8 |
 化学 化学
|
6,809 | 42.0 | 268,245 | 1,077,202 | 1,364,600 | 126.7 |
 プラスチック・ゴム製品 プラスチック・ゴム製品
|
7,065 | 64.9 | 214,957 | 536,475 | 598,809 | 111.6 |
 卑金属 卑金属
|
1,605 | 92.9 | 249,616 | 2,011,152 | 1,740,684 | 86.6 |
 金属製品 金属製品
|
76,721 | 6.5 | 187,046 | 494,764 | 473,562 | 95.7 |
 ICT・電子機器 ICT・電子機器
|
898 | 504.8 | 245,131 | 207,705 | 477,983 | 230.1 |
| 卸売業 | 155,545 | 11.6 | 154,900 | 610,168 | 884,636 | 145.0 |
| 小売業 | 2,092,770 | 3.3 | 125,704 | 157,457 | 306,859 | 194.9 |
| 運輸・郵便・倉庫 | 22,245 | 57.2 | 173,719 | 717,176 | 458,195 | 63.9 |
| 通信・マスメディア | 8,828 | 34.9 | 292,877 | 2,569,560 | 876,796 | 34.1 |
| 金融・保険 | 26,593 | 24.3 | 457,711 | 402,519 | 2,284,758 | 567.6 |
| 不動産・賃貸 | 68,010 | 4.9 | 119,888 | 534,254 | 397,667 | 74.4 |
| 専門・科学・技術サービス | 100,098 | 6.8 | 110,027 | 86,136 | 282,684 | 328.2 |
| 関連会社統括・経営 | 366 | 340.4 | 663,517 | 577,586 | 4,608,593 | 797.9 |
| 経営・廃棄物関連サービス | 76,059 | 10.5 | 129,132 | 203,575 | 340,422 | 167.2 |
| 教育(私立) | 53,524 | 14.5 | 161,151 | 248,152 | 249,712 | 100.6 |
| 健康・医療・福祉 | 196,089 | 4.4 | 126,732 | 186,384 | 209,817 | 112.6 |
| 娯楽・スポーツ | 51,352 | 5.3 | 143,364 | 398,309 | 331,417 | 83.2 |
| ホテル・レストラン | 637,124 | 4.7 | 99,305 | 187,291 | 195,143 | 104.2 |
| その他サービス | 681,769 | 2.5 | 86,177 | 120,239 | 136,553 | 113.6 |
| 全産業計または平均 | 5,468,180 | 5.1 | 169,961 | 482,965 | 561,348 | 116.2 |
注1:民間企業および国営企業。ただし2023年に営業した事業所に限る。また、行政機関と宗教団体を除く。
注2:1ペソ=約7.8円。
出所:INEGI「経済センサス」(2024)からジェトロ作成
- 従業員の平均年収:
(1)鉱業、(2)関連会社統括・経営、(3)電気・ガス・水道、(4)通信・マスメディア、(5)化学、(6)卑金属、(7)金融・保険、(8) ICT・電子機器、(9)輸送機器製造などで高い(順不同)。
(1)~(6)は国営企業や財閥系企業の、(7)~(9)は外資系企業の、影響力が強いのが特徴だ。 - 従業員1人当たりの固定資産・付加価値額:
このいずれも、資本集約的な産業で高い。
ただし付加価値額は、資本集約産業だけでなく、金融・保険や関連会社統括・経営でも高くなっている。 - 事業所が支払う人件費の内訳:
全業種平均では、直接部門(開発や製造、営業など、事業所の売り上げに直接貢献する部門)の賃金・給与(ボーナスや休暇手当てなどの現金給付を含む)が59.0%。間接部門(総務、経理、人事、労務など、事業所の売り上げに直接貢献しない部門)が22.4%になっている。しかしこの割合は、業種によってかなり異なる(表3参照)。金融・保険や鉱業などでは、間接部門の給与総額の方が直接部門より大きい。
また、社会保険の雇用主負担は、大半の産業でおおむね人件費の10%前後になっている。
一方、福利厚生費は業種によって大きな差がある。一般的に、国営企業や大企業が多い業種、労働組合の活動が活発な業種で、福利厚生費の比率が高くなっている。 - 賃金・給与水準:
直接部門の事業所平均年間賃金・給与は、2023年の全業種平均で11万9,466ペソ(約94万3,781円、1ペソ=約7.9円:2023年平均レートで換算)。また、間接部門では同23万7,166ペソだった。ただし、業種別に開きが大きい。
直接部門の平均賃金・給与が最も高かったのは、(1)関連会社統括・経営で28万5,028ペソ、(2)鉱業(25万7,997ペソ)、(3)金融・保険(23万2,207ペソ)と続く。(1)は財閥が、(2)は国営企業や財閥が、(3)は外資系企業が、それぞれ多いのが特徴だ。
間接部門の平均賃金・給与では、(1)金融・保険(58万2,423ペソ)、(2)関連会社統括・経営(38万7,661ペソ)、(3)電気・ガス・水道(32万5,917ペソ)と続いた。 - 自動車産業の賃金・給与水準:
この産業では、進出日系企業も多い。
直接部門(当該産業では直接工)の平均賃金・給与は、(1)自動車・トラック製造(完成車メーカー)で16万881ペソ、(2)自動車部品製造13万9,178ペソ。このように、直接工については、(1)と(2)で開きがあった。
他方、間接部門では、(1)28万9,477ペソ、(2) 29万2,355ペソ。直接部門と異なり、あまり差がないことになる。
| 産業分野 | 構成比 | 平均賃金(年収) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接部門給与 | 間接部門給与 | 社会保険負担 | 福利厚生 | PTU | 人件費合計 | 直接部門 | 間接部門 | |
| 漁業・養殖業 | 86.3 | 7.9 | 4.5 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | 74,480 | 130,291 |
| 鉱業 | 64.7 | 12.4 | 7.7 | 13.4 | 1.8 | 100.0 | 257,997 | 275,047 |
| 電気・ガス・水道 | 48.9 | 37.4 | 9.6 | 3.4 | 0.6 | 100.0 | 223,806 | 325,917 |
| 建設業 | 61.7 | 21.1 | 12.8 | 1.9 | 2.4 | 100.0 | 109,747 | 186,717 |
| 製造業 | 58.0 | 21.4 | 11.5 | 4.9 | 4.2 | 100.0 | 141,533 | 285,081 |
 輸送機器製造 輸送機器製造
|
57.9 | 20.0 | 12.2 | 5.1 | 4.8 | 100.0 | 143,769 | 293,026 |
 完成車製造 完成車製造
|
50.9 | 18.1 | 11.7 | 6.2 | 13.1 | 100.0 | 160,881 | 289,477 |
 自動車部品製造 自動車部品製造
|
59.3 | 20.0 | 12.3 | 4.7 | 3.8 | 100.0 | 139,178 | 292,355 |
| 卸売業 | 54.7 | 26.2 | 11.6 | 2.6 | 4.8 | 100.0 | 108,269 | 186,672 |
| 小売業 | 68.3 | 15.2 | 10.0 | 3.1 | 3.5 | 100.0 | 96,835 | 167,825 |
| 運輸・郵便・倉庫 | 64.6 | 19.2 | 11.6 | 2.1 | 2.5 | 100.0 | 139,297 | 171,766 |
| 通信・マスメディア | 52.3 | 29.9 | 11.1 | 2.9 | 3.8 | 100.0 | 209,960 | 324,572 |
| 金融・保険 | 31.4 | 48.6 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 100.0 | 232,207 | 582,423 |
| 不動産・賃貸 | 59.3 | 26.3 | 9.4 | 1.4 | 3.6 | 100.0 | 94,455 | 127,758 |
| 専門・科学・技術サービス | 55.7 | 27.6 | 10.0 | 2.1 | 4.7 | 100.0 | 82,633 | 117,213 |
| 関連会社統括・経営 | 29.2 | 18.7 | 11.3 | 40.0 | 0.7 | 100.0 | 285,028 | 387,661 |
| 経営・廃棄物関連サービス | 62.9 | 19.8 | 11.8 | 2.2 | 3.2 | 100.0 | 98,628 | 145,334 |
| 教育(私立) | 58.5 | 25.1 | 10.8 | 3.5 | 2.1 | 100.0 | 121,012 | 183,510 |
| 健康・医療・福祉 | 70.8 | 18.3 | 8.4 | 1.3 | 1.2 | 100.0 | 106,275 | 149,276 |
| 娯楽・スポーツ | 68.2 | 17.8 | 10.2 | 2.7 | 1.2 | 100.0 | 110,041 | 228,669 |
| ホテル・レストラン | 79.2 | 12.2 | 5.7 | 1.0 | 1.8 | 100.0 | 84,514 | 175,206 |
| その他サービス | 79.9 | 11.9 | 6.4 | 0.7 | 1.1 | 100.0 | 77,113 | 95,624 |
| 全産業平均(注1) | 59.0 | 22.4 | 10.7 | 4.4 | 3.6 | 100.0 | 119,466 | 237,166 |
注1:民間企業および国営企業。ただし2023年に営業した事業所に限る。また、行政機関と宗教団体を除く。
注2:憲法123条IX項及び労働法117条に基づき雇用主が支払う利益分配金。現行制度では税務上の利益の10%分を役員以外の被雇用者に労働日数と給与水準に応じて機械的に分配する。
出所:INEGI「経済センサス」(2024)からジェトロ作成
調達コスト高が最大の懸念、治安も引き続き問題視
今回の経済センサスには、前回調査(2019年)に引き続き、事業所の操業環境について調査項目がある(図4参照)。
事業所が抱えている操業上の課題(複数回答)としては、(1)「高い部材・商品の調達コスト」を挙げる比率が最も高かった。何らかの操業上の問題を抱えている事業所の35.5%が同問題を指摘したかたちだ。この比率は、前回調査時(17.8%)から大きく上昇した。
そのほか、(2)「治安」(34.4%)、(3)「需要低迷」(27.7%)、(4)「高い光熱費」(24.5%)、(5)「不当競争」(23.6%)、(6)「高い税負担」(16.7%)を問題視する事業所が多い。このうち、(2)を問題視する比率は、前回調査(35.4%)からわずかに低下した。しかし、そのほかの問題を挙げる企業の比率は、軒並み上昇している。
回答率の上昇は、先述した(1)のほか、(3)(9.2ポイント増)、(6)(5.9ポイント増)、さらに(7)「インフォーマル部門との競合」(6.4ポイント増)、(8)「腐敗・汚職」(5.6ポイント増)などで、特に目立った。それぞれ5ポイント以上、上昇している。
こうしてみると、企業の操業環境が5年前より厳しくなっていることがうかがえる。その背景には、(1)新型コロナ禍に伴ってサプライチェーンが分断したこと、(2)その後の需要回復が緩慢だったこと、などがある。そのような中で多くの事業所を悩ますのは、重い税負担だ。そうした事業所は、税や社会保険を負担していないインフォーマル部門との不当な競合を問題視する。一方、AMLO前政権下では、抜本的なインフォーマル対策が欠如していた。
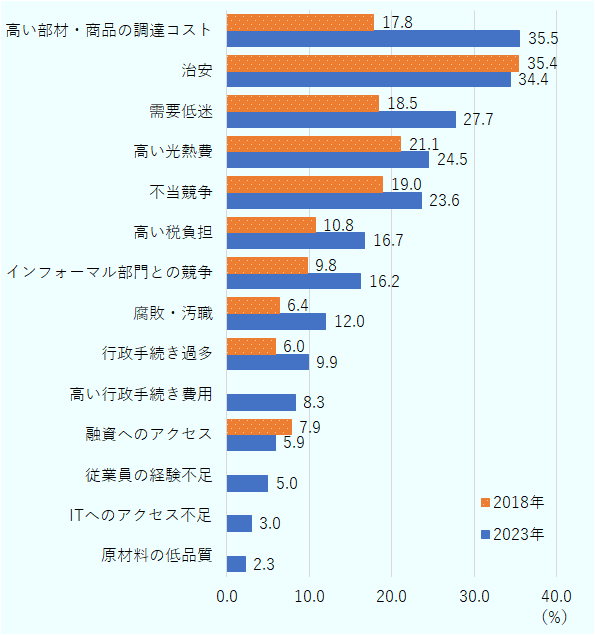
注:操業上で何らかの問題に直面していると回答した事業所が分母。
出所:INEGI「経済センサス」(2019/2024年版)からジェトロ作成
進出日系企業が多い輸送機器製造業に限ると、やはり(1)「高い部材・商品の調達コスト」が42.8%で最多。(2)「治安」(39.2%)、(3)「高い税負担」(38.7%)、(4)「高い光熱費」(36.1%)、(5)「行政手続き過多」(23.6%)と続く(図5参照)。
「需要低迷」(20.9%)以外は、おおむね全体より比率が高い。特に、(3)や(4)の比率が全体を大きく上回る。人件費以外のコストが総じて割高なメキシコの現状を表している。また、治安が近年悪化している自動車産業集積地(グアナファト州など)もあるため、(2)を問題視する事業所の比率も全体より高い。
「従業員の経験不足」を問題視する比率も高い。重要保安部品が多く、製造工程で技術と経験を要する。そのために必要な人材の確保に苦慮している事業所が多いことがうかがえる。
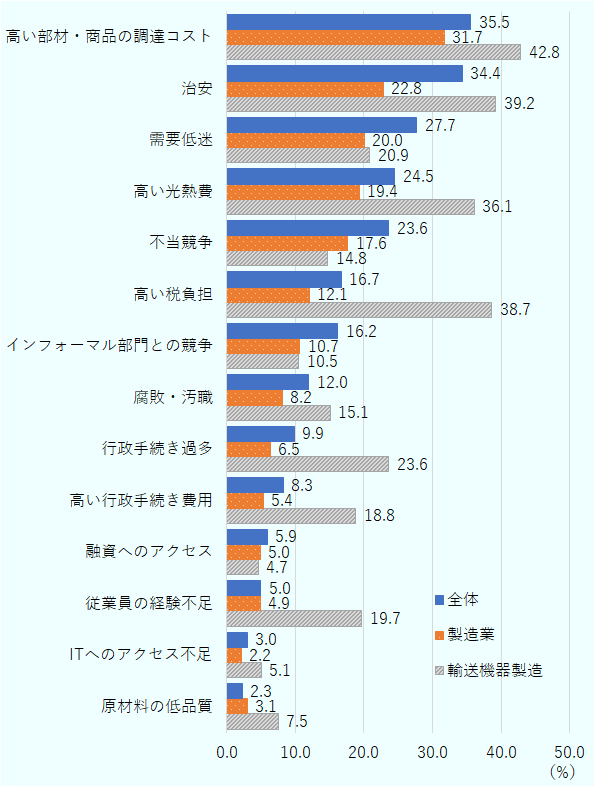
注:操業上で何らかの問題に直面していると回答した事業所が分母。
出所:INEGI「経済センサス」(2024年版)からジェトロ作成
操業上の問題点については、州別に比較することもできる(表4参照)。
主要州別にみると、「治安」を問題視する事業所は、グアナファト州、メキシコ市、ケレタロ州でかなり多くなっている。「高い光熱費」は、特にバハカリフォルニア州で多い。
「不当競争」は、首都メキシコ市で目立つ。同市では「インフォーマル部門との競争」を問題視する声も多いことからすると、インフォーマルとの不当競争に悩まされていることがうかがえる。なおメキシコ市では、「腐敗・汚職」も問題になっている。
「高い税負担」を指摘する比率は、ケレタロ州、ハリスコ州、バハカリフォルニア州で高い。ケレタロ州とバハカリフォルニア州では、「行政手続き過多」「高い行政手続き費用」を問題視する比率も高い。
日本企業進出数で最多なのが、グアナファト州だ。同州では、他の問題と比べ「治安」が際立つ。治安改善が喫緊の課題だろう。同州では主要幹線道路の国道45号線で車両強盗被害が相次ぐ。進出日系企業の被害もあるため、注意が必要だ。
| 問題の種類 | 全国 | メキシコ市 | グアナファト | ケレタロ | アグアスカリエンテス |
ヌエボ レオン |
サンルイスポトシ | ハリスコ | バハカリフォルニア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高い部材・商品の調達コスト | 35.5 | 39.6 | 28.8 | 35.5 | 38.4 | 23.8 | 34.4 | 30.2 | 28.3 |
| 治安 | 34.4 | 41.7 | 46.9 | 39.6 | 33.7 | 38.6 | 38.3 | 37.5 | 38.5 |
| 需要低迷 | 27.7 | 30.9 | 27.9 | 29.8 | 28.6 | 16.2 | 32.5 | 22.5 | 22.6 |
| 高い光熱費 | 24.5 | 21.5 | 20.9 | 27.4 | 26.9 | 27.1 | 25.4 | 29.0 | 31.0 |
| 不当競争 | 23.6 | 32.7 | 20.8 | 26.3 | 22.3 | 15.4 | 20.0 | 19.9 | 17.3 |
| 高い税負担 | 16.7 | 17.4 | 15.4 | 25.4 | 19.2 | 17.7 | 16.4 | 24.0 | 29.9 |
| インフォーマル部門との競争 | 16.2 | 25.0 | 14.1 | 20.4 | 15.7 | 14.3 | 13.5 | 14.8 | 15.4 |
| 腐敗・汚職 | 12.0 | 18.4 | 13.3 | 12.0 | 10.6 | 11.1 | 9.8 | 13.3 | 15.8 |
| 行政手続き過多 | 9.9 | 10.3 | 7.7 | 24.2 | 11.5 | 10.5 | 11.8 | 13.5 | 25.5 |
| 高い行政手続き費用 | 8.3 | 7.6 | 5.9 | 19.5 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 12.0 | 22.1 |
| 融資へのアクセス | 5.9 | 7.8 | 4.7 | 6.1 | 7.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.0 |
| 従業員の経験不足 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 9.0 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 6.8 | 7.6 |
| ITへのアクセス不足 | 3.0 | 4.6 | 2.7 | 4.4 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
| 原材料の低品質 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注1:操業上で何らかの問題に直面していると回答した事業所が分母(n=3,923,147)。
注2:太字は全国平均を5ポイント以上上回ることを示す。
出所:INEGI「経済センサス」(2024年版)からジェトロ作成
今回の経済センサスでは、前回に引き続きコンピュータやインターネットの利用についての調査項目を設定した。
- コンピュータ・タブレットの利用:
利用率は全体で25.4%。全事業所の9割以上を占める零細企業(従業員10人以下)で利用率が低いこと(22.4%)が影響している。小規模企業(同11~50人)で86.0%、中規模企業(51~250人)92.4%、大企業(251人以上)では95.1%に達するのと対照的だ。 - インターネットを事業で活用している企業:
全体では25.4%。規模別には、零細企業で23.6%、小規模企業83.1%、中規模企業90.6%、大企業93.1%だった。
最後に、金融機関の融資を受ける企業について。利用企業の比率は、大企業でも32.2%にとどまる。中小企業(11~250人)では23.9%、零細企業では10.1%に過ぎない。しかも2019年調査と比べると、利用比率がそれぞれ2.1%ポイント、4.3%ポイント、1.5%ポイント縮小した。すなわち、メキシコでは依然として企業向け金融サービスの普及が不十分で(2022年10月13日付地域・分析レポート参照)、状況に改善がみられていない。
- 注1:
- 農牧業以外の事業所を対象とする5年に1回の全数調査。事業所数や雇用数は2024年調査時点のデータを用い、出荷額(生産額)などの金額データは2023年時点のデータを用いている。2014年調査からは、行政機関の事業所や宗教団体の数も計上している。
- 注2:
- (1)従業員数5人以下、(2)社会保険負担金を支払っていない、(3)会計システムの利用がなく、会計帳簿を整備するなどしていない、すべての要件を満たす場合、「インフォーマル」な事業所と定義。
- 注3:
-
INEGIの全国就業雇用調査(ENOE)によると、就業人口に占めるインフォーマル就労比率は2023年平均で55.0%。経済センサスのデータよりも高くなっている。
これは、経済センサスが事業所を調査対象にしている〔特定の事業所を持たない個人労働者(行商人など)を対象にしない〕ことに起因する。他方、ENOEは、行商人や露天商なども対象にするため、インフォーマル就労比率がさらに高くなる。 - 注4:
-
AMLO政権下では、リチウムの開発を国が独占するかたちで、法改正した(2022年4月21日付ビジネス短信参照)。
加えて鉱業法を改正。(1)鉱区開発コンセッションを付与する手法を公共入札に限り、(2)資源探査の主体を国営メキシコ地質調査所(SGM)と明記した。つまり、SGMによる資源発見後でなければ、経済省が鉱区開発について入札機会を企画できないことになる。そのため、緊縮予算などを理由にSGMの資源探査が滞ると、鉱区入札案件そのものがなくなる可能性が生じる(2023年5月10日付ビジネス短信参照)。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部米州課主幹(中南米)
中畑 貴雄(なかはた たかお) - 1998年、ジェトロ入構。貿易開発部、海外調査部中南米課、ジェトロ・メキシコ事務所、海外調査部米州課を経て、2018年3月からジェトロ・メキシコ事務所次長、2021年3月からジェトロ・メキシコ事務所長、2024年5月から調査部主任調査研究員、2025年4月から現職。単著『メキシコ経済の基礎知識』、共著『グローバルサプライチェーン再考: 経済安保、ビジネスと人権、脱炭素が迫る変革』、『NAFTAからUSMCAへ-USMCAガイドブック』など。




 閉じる
閉じる






